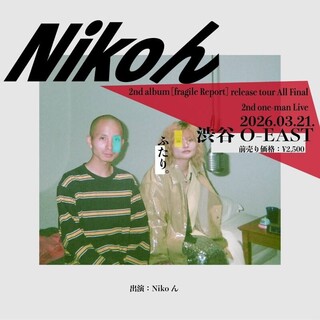1988年5月、アンジーのボーカリストとしてシングル『天井裏から愛を込めて』とアルバム『溢れる人々』でメジャー・デビューを果たしてから今年で30周年を迎える水戸華之介。毎年秋に行なわれる、彼のライフワークとも言うべき恒例のアコースティックライブ・ツアーのなかから特に評判の良かった歌を精選したセルフカバー・アルバム『ウタノコリ』を聴けば、水戸華之介という不世出の歌手は50代半ばにしていま最も脂が乗っていることがよくわかるはずだ。程よく雑味が取れてコクとまろみを増した歌声、大胆かつ繊細で緩急のついた唄い回し、歌によって器用にキャラクターを使い分ける熟練さ。アンジー時代から近年まで普遍性の高い歌を意表を突くお色直しで見事に蘇生させる手腕も含め、この『ウタノコリ』は日本語のビート・ロックを出発点とした男がジャンルレスの"いい歌"を変幻自在に唄いこなす円熟の域に達したことを如実に伝える作品である。個人的には"ポンポコピー"という呼称を知っているアンジーのファンだった人ほど聴いてほしい。その当時との差異こそ彼の30年にわたる進化の証だし、末恐ろしいのは才気煥発の伸びしろがまだまだありそうなこと。浅い傷を負い続けた満身創痍の男の歌は伊達じゃないのだ。(interview:椎名宗之)
『ウタノコリ』は空気感が命のライブ
──デビュー30周年の節目に『ウタノコリ』と題したアルバムをつくろうと以前から密かに決めていたそうですね。
水戸:5年前に出した『不死鳥Rec.』のときにはもう考えてたね。25周年の節目はゲストを呼んでのセルフカバー、30周年のときは『ウタノコリ』だろうなと自然と思ってた。
──『ウタノコリ』の過去のライブ音源からベストテイクを集めるということではなく?
水戸:そういう発想はなかったね。スタジオに入って『ウタノコリ』仕様のアルバムをちゃんと形に残すことを30周年でやりたかったので。ライブってそもそもその場限りで消えるものだけど、『ウタノコリ』でやるライブはその感じがより強いんだよね。同じセットリストでやってもハコの雰囲気やお客さんのテンションやこっちのコンディションで全然違うものになるし、その振れ幅がバンドでやるライブよりもアコースティックでやるライブのほうが大きい。
── 一期一会の感覚がバンド形式よりも大きいと。
水戸:うん。瞬間芸みたいなところがあるしね。仮に『ウタノコリ』をDVDとしてフルパッケージしたところで絶対に何かがスポイルされてしまうし、現場の空気をちゃんと伝えられないんだよ。『ウタノコリ』は空気感が命のライブだから。それにMCの調子がいいかどうかだけでもすごく違うし、MCで喋っている言葉と演奏が始まって唄っている言葉が地続きなんだよね。バンドのライブはワン、ツー、スリー、フォー、バーン! って音を鳴らした瞬間に別世界に行くし、MCの言葉との関連性をそんなに考えなくてもいいけど、アコースティックのライブは曲間の喋りも一本のライブ全体のグルーヴとして機能しているからね。
──以前、桂歌蔵さんによるインタビューで、アコースティック・ライブのMCは落語で、バンドのライブのMCは相方のいない漫才だと水戸さんが喩えていたのが言い得て妙だなと思って。
水戸:どっちのライブのMCでもその場のひらめきみたいなものがあるんだけど、そのひらめき方がちょっと違う。ベーシックの部分は同じなんだけど、ポーン! とひらめいて降りてくる部分が違う気がする。
──本作はこれまでの『ウタノコリ』で特に評判の良かった曲をレコーディングしたそうですが、膨大なレパートリーのなかから選曲するのは至難のわざだったのでは?
水戸:それほどでもなかったかな。アコースティック・ライブでやってみて良かったものっていうのが基準としてあったし、レコーディングしてCDにしたときにも面白さが伝わるってところに限定すると、まぁこんなところかなと思うし。ここで選ばなかった曲が面白くないってことじゃなくて、アルバムにしても面白いことをやっているのが伝わるのか? っていう考え方で選曲するのがわかりやすいかなと思って。
──3-10 chainにも名曲はたくさんあるはずなのに、潔いくらいにアンジーの曲が多いのが意外だったんですけど。
水戸:メジャー時代をカウントすれば、アンジーって4年くらいしかないのにね(笑)。でもそれはさっき話した選曲理由とも絡んでくるんだけど、近年の曲はいまの自分とそんなに変わってないんだよ。自分がある程度納得のいくやり方ができるようになってからレコーディングしたものだから。それよりも「あの歌はもっと良くなったはずだ」とか「もっと面白くやれたな」といまの自分が感じる若いときにつくった曲、自分がまだ経験も知恵も足らなかった時代の曲を中心に取り上げてみたかった。アンジーだからどうこうっていうのが選曲理由でもないんだよね。
──たとえば「雑草ワンダーランド」のような直近のレパートリーを再調理するのは難易度が高くないものなんですか。
水戸:あれは今回の選曲理由でいくと例外で、ちょっとやってみようかって軽い気持ちでやったら「そもそもこっちのほうが良かったんじゃない?」って思うくらいの仕上がりになってね。この歌にとってはオリジナルのバンド・バージョンよりもこっちのアレンジのほうが本当はハマってたんじゃないか? って。
バンドとアコースティックの発声法の違い
──アコースティック・バージョンとバンド・バージョンの2種類があった「マグマの人よ」で本作の幕が開くのが象徴的だなと思ったのですが。
水戸:これで3回目のレコーディングだね。30年以上唄ってくると、それなりに唄えるようになったなと思えるし、「マグマの人よ」もライブでだいぶ唄い込んできたし、いまなら『ヒソカ』のバージョンよりも『窓の口笛吹き』のバージョンよりも上手に唄えるという思いがあってね。
──アコースティック・スタイルでバンドをやるという『ヒソカ』のときに技術的にやりきれなかったことを、28年の歳月を経てリベンジするみたいなところもあったんですか。
水戸:いや、それはないかな。むしろ原点は変わってないね。『ヒソカ』の前後にアンジーでやり始めたアコースティック・スタイルに比べて経験値の積み上げはあるけど、根っこはそこからずっと変わってない。アコースティックの形でどこまでバンドに近いテンションまで持っていけるかっていうのがそもそものテーマでね。演奏的にではなく、お客さんのテンションをどこまで上げられるかっていう意味で。アコースティック形式で全曲バラードに落とし込んでしっとりやるなんてむしろイヤだったし、アコースティックでも通常のバンド形態と同じくらい盛り上がるライブをやりたかった。それを最初から目指していたけど、アンジーの頃は経験値が足りなかったからどこまでやれていたのかはわからない。ただそれから『ウタノコリ』を20年近くやるなかで現場でスキルが磨かれてきたし、いまならできると思ってね。
──バンドとアコースティックでは発声法が違うものなんですか。
水戸:全然違うね。バンドは直球主体で、手元でちっちゃく曲がる変化球を投げてもあまり意味がないし、パワーピッチで行くしかない。力押しで唄わないとバンドのパワーと拮抗できないしね。それはもう無意識のうちに染みついちゃってるし、頭で考えてもどうにもならない。俺たちがバンドを始めた頃ってPA事情がめちゃくちゃ悪くてね。意外と注目されないことなんだけど、音響設備がすごく発達したことで音楽に与えた影響は計り知れないと思う。たとえばいまの若いバンドはキーの幅がすごく広くて、1オクターブ半とかの幅で曲をつくったりする。Aメロが1オクターブ下くらいの低く潜るようなところで唄っていて、サビでポーン! と1オクターブ上がるみたいな曲を平気でつくるけど、それだと80年代のPA設備じゃお客さんには届かなかったはずだよ。お客さんに届かないから俺たちはそういう曲をつくらなかったし、当時はドレミファソラシドのなかの4音くらいしかちゃんと届けられなかったんじゃないかな。だからその4音がサビの部分でドン! と来るような曲ばかりをつくっていた事情があるんだよね。むかしは高音も低音もバンドのガシャッとした音に埋もれていたし、いまはそれが埋もれないのはPAの力なんだよ。
──なるほど。20年近く『ウタノコリ』をやっているとアレンジのフォーマットも固まってきたでしょうし、レコーディングでもそれほど悩まずに済んだんじゃないですか?
水戸:それがそうでもなくて、50歳を過ぎると忘れることが多くてね(笑)。年一で『ウタノコリ』をやってはいるものの、ほとんどの曲は披露するのが4、5年ぶりとかでね。「天井裏から愛を込めて」とか必ずやる曲もあるけど、そういうのは稀でさ。4、5年も空くと、前にやったアレンジをほとんど忘れちゃうわけ。もちろん大枠は覚えているけど、「たしかラテンっぽくやったよね」くらいで細かいことまでは覚えていない。歳をとると面倒くさくなるから過去のライブ音源を探して確認したりもしない。4、5年のあいだに積んだスキルもあるから、大枠だけ覚えていれば充分なんだよ。ギターとピアノだけの編成だからバンドよりもアレンジが臨機応変で柔軟だしね。だからどっちみちアレンジはいつも違うんだよ。
──ということは、今回はアルバムに即したアレンジというわけですね。
水戸:うん。たとえば「腹々時計」をブギーでやろうという大枠はライブと同じで、それも去年の秋のツアーでブギー・スタイルでやったんだけど、細かいことはもう覚えていない(笑)。