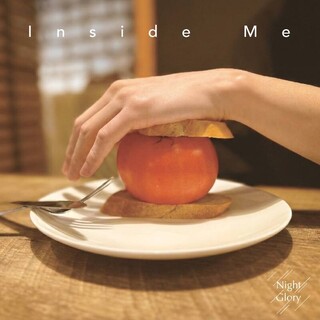劇的なサウンドに赤裸々な歌詞をのせて聴き手に叩きつけ、ポスト・ハードコア/エモ・シーンで異彩を放ってきたカーシヴが、6年ぶりの最新アルバム『ヴィトリオーラ』を発表した。
昨年設立した自らのレーベル=15パッセンジャーからのリリースとなる今作では、オリジナル・ドラマーだったクリント・シュイネスが復帰。また、USインディ史上に残るマスターピース『ザ・アグリー・オルガン』以来、ひさびさにチェロをフィーチャーしている。2014年にその『ザ・アグリー・オルガン』のデラックス・エディション、昨年には15パッセンジャーから初期2作品をリイシューしたこともあり、端々に原点回帰の意識も感じられるが、決して単なる懐古的な内容にはなっていない。
実際、中心メンバーのティム・ケイシャーはこの6年間にソロで2枚、別バンドのザ・グッド・ライフで1枚アルバムを作っており、さらには映画も1本完成させている。それ以前にカーシヴでも、クリント不在時に、各々優秀なドラマーであるコーンブレッド・コンプトン(ex.エンジンダウン)とカリィ・シミングトン(ex.アフガン・ウィグス/オッカーヴィル・リヴァー/スパルタほか)を迎えて2枚のアルバムを作り上げた経験を含め、ここまでのキャリアの集大成と呼びたくなるような、過去最高にヘヴィで、ドラマティックな音が『ヴィトリオーラ』では展開されているのだ。
パーソナルな狂気を吐き出してきた歌詞も、今作では現在のアメリカの社会情勢を反映し、銃撃事件、格差社会、拝金主義といった問題に真っ向から向き合った内容になっていることにも注目したい。以下に、ティムとのメール・インタビューを掲載する。(interview:鈴木喜之)
『ザ・アグリー・オルガン』のリイシュー・プロジェクトがもたらしたもの
──6年ぶりのニュー・アルバム『ヴィトリオーラ』完成、心から嬉しいです。前作『アイ・アム・ジェミニ』以降、『ザ・アグリー・オルガン』のリイシューや、自分たちのレーベル=15パッセンジャーの設立、さらにあなた個人はソロ名義やザ・グッド・ライフでのアルバム制作、映画関連のプロジェクトなどで多忙にしていたわけですが、そろそろカーシヴとしての新作にとりかかろうという気持ちは、いつ頃からどんなふうに固まっていったのですか。
ティム:マット(・マギン)とテッド(・スティーヴンス)と僕の3人で15パッセンジャーについてのプランを練っていたとき、出したい作品をなんでも出せるんだと思ってね。カーシヴの新作をこのレーベルから出すのは筋が通っていることだし、可能性を検討し始めたんだ。そのあとクリント(・シュイネス)から《またカーシヴのアルバムを一緒に作りたい》と連絡があって。それで自分たちの考えが固まったんだ。カーシヴの新作にとりかかるときが来たってね。
──オリジナル・ドラマーのクリントが復帰したわけですが、ひさしぶりの彼とのレコーディングはいかがでしたか。クリントの復帰は新作に何をもたらしてくれたと思いますか。
ティム:僕たちは力を合わせて、この新しい作品に取り組んだよ。クリントは曲作りでもレコーディングでも存在感を発揮してくれた。彼はカーシヴをやめてからも地元オマハでいろいろバンドをやっていて、ずっとプレイはしていたんだよ。クリントにとってドラムを叩くのは、生まれつきの才能であるかのように自然なことなんだ。彼がアルバムにもたらしたものといえば、一体感かな。昔のフィーリングを思い出させてくれたし、強い気持ちや自信を持って曲作りをするのを手助けしてくれたと思う。あと、いつものことだけど、最高のドラム・パートを考えてくれた。クリントとマットは本当にいいリズムセクションなんだよ。
──新メンバーのミーガン・シーブさんは、どういう経緯で加入に至ったのでしょうか。
ティム:ミーガンはオマハで活動しているミュージシャン仲間で、いい友達でもあるんだ。一緒に演奏し始めたのはここ数年のことで、ごく最近、レコーディングやツアーにもかなり参加してもらうようになった。彼女とツアーを回るのはとても楽しいし、うまくやっているよ。
──『ザ・アグリー・オルガン』をリイシューし、再びあの作品の収録曲を演奏するツアーを行なったことは、あなたにとってどんな経験となりましたか。その経験が、最新アルバムにも何らかの形で反映しているでしょうか。
ティム:ツアーをまわったことが今回のアルバムに影響を与えたかどうか、自分ではよくわからないんだけど、影響しているのかもね。影響っていうのはあらゆるところから受けるわけだから。でも、それがどこから来たのか特定するのはそれほど簡単ではないね。あのツアー自体については、本当に楽しかった。最初は、新しい作品を作るべきなのに昔のアルバムのお祝いをするなんてベストなことなのか、あまり自信がなかったんだけど、いろいろな作品を作ってきた流れで考えると、やってもいいのかなと思ったんだ。あのアルバムに影響を受けたたくさんのリスナーに、喜びと懐かしさを届けることができたのはいい経験だったし、やってよかったよ。
──古くからの仲間や新顔を迎えた最新作について、個人的には「ヘヴィなサウンドのアルバムになった」という印象を抱いています。このことは本作で唄われている内容にも関連してくるかと思いますが、現在の世界を覆っている状況と、そこに暮らす人間の暗い心情をテーマにしたことが、歌詞だけでなくサウンド面において、どれだけ反映されたと感じていますか。
ティム:メンバーの誰も、どんなアルバムを作るべきかという決まった考えは持ってなかったんだけど、新曲のアイデアに取りかかるにつれて、生々しく、もろくて傷つきやすく、カタルシスを感じさせたり、超越するようなものを表現したいと思うようになった。それはたぶん、リイシューのプロジェクトに関連して、自分たちの最初の2枚のアルバムをよく聴いた経験から、かなり影響されたんだと思う。初期の2作を聴きながら、心に疼きを抱え、何かを探し求め、宇宙全体に向けて疑問を叫んでいるような、昔の自分を思い出したんだ。そういう表現をまた経験したかったんだよ。
人間の存在を正しいものだと証明しようとしている
──アルバム冒頭に置かれた「Free to Be or Not to Be You and Me」のイントロから、激しく叩きつけるような音で始まりますが、作品全体でも、バンドが一丸となって打ち鳴らす衝撃音のような演奏を多く使っている印象を持ちました。これはやはり作曲/アレンジ段階から意図的なものだったのでしょうか。
ティム:そうだと思うよ(笑)。ヘヴィなパートをいくつか書いて、そこでは可能なだけ強く激しく叩きつけたかった。エンジニアのマイク・モギスには、そうしたパートでは想像できうる限りの激しさと重さを表現したい、と伝えたんだ。メタルやハードコアのバンドのようには聴こえるほどではないけれど、少なくともそのくらいの音を作ろうとしたっていうのは面白かったよ。
──たとえば1曲目と2曲目「Pick Up the Pieces」の間には銃の撃鉄をおこしている音、4曲目「Under The Rainbow」の前には何かチャントのような声、さらに先行公開された「Life Savings」の後にも不思議な加工音など、いろんなノイズをくっつけていますね。それぞれには何か意味が持たされているのでしょうか。
ティム:銃弾が装填され撃鉄を起こす音に続いてはじまる「Pick Up the Pieces」は、アメリカでの銃社会の悲劇について唄っている。「Under The Rainbow」の直前に入っているのはアーミッシュのチャントで、《虹の下》という表現はアーミッシュの言葉で《具合が悪い》っていう意味なんだ。「Life Savings」の後の音は、アルバム中の歌詞を使った抽象的なサウンド・コラージュで、漂っているような感じにしている。解釈としては、このアルバムの残り滓を使って、硫酸のようなやっかいな物質、つまりタイトルのヴィトリオーラ=毒、を象徴していると取ることもできるかな。
──『ハッピー・ホロウ』以降、あなたの書く歌詞は、架空の物語を通じて精神の闇を描くような方向へ進んできたと思います。しかし今作では、1曲目から「What I sing right now / Someone's screamed before / Time to take a bow / Before the stage is taken over」と、今まさに感じていることをそのまま唄っているようなスタイルになっているようにも思いました。これは歌詞の題材から自然にそうなったのでしょうか、それとも意図的なものですか。
ティム:カーシヴのアルバムについては、作品自体や、その作品の前に発表したものによって、パーソナルな内容に寄るか、意図的にパーソナルなものから離れるかを決める傾向があるんだ。自分にとって、アルバムを作るごとに同じことを繰り返さず、新しいコンセプトやアプローチに挑戦していると感じるための、ささやかな手法なんだよ。今回のアルバムについては、パーソナルなアプローチのほうがしっくり来たんだと思う。前のアルバムから6年経っているし、『アイ・アム・ジェミニ』はパーソナルな要素があまりない、フィクションの物語だったからね。
──アルバム全体として、現代にはびこる拝金主義へ怒りを表したりする一方、最後の曲は「Dystopian Lament」だったりして、「もうおしまいなんだ」という諦念も唄われていると感じます。しかし落ち込んで塞ぎこむには、音楽自体が(悲愴ではあっても)力強い生命力に満ちています。そのあたりのバランスを制作中どう考えていましたか。
ティム:このバランスはかなり重視した。だって、ニヒリズムと諦念だけを表現して、しかもそういうことを表現しようと全力でアルバムを作るなんて、論理的に破綻しているだろう? つまり、諦めますって言うために全身全霊を込めるなんて話はありえないんだよ。だって、1枚のアルバムを作るなんて、明らかに諦めてないわけだから。「Free To Be Or Not To Be You And Me」の最後の歌詞では、このパラドックスを表現しようとしてる。“もちろん、私はありのままでいたいと叫ぶ/こんなことに意味がないと知っている/それでも私は声を上げ、超越していこうと求め続ける”。ここで言おうとしているのは、すべてに意味がないと感じてしまう自分自身の傾向にもかかわらず、これらの曲を作り、世に問うことで、僕は人間の存在を正しいものだと証明しようとしているってことなんだ。