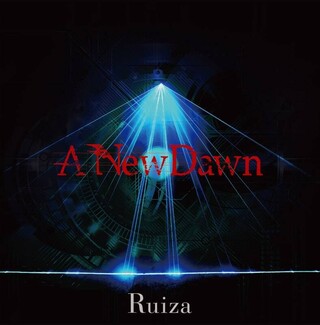音楽のすごいところは踊れること
──パブロックの趣きもある「NEW1」はくだけた言葉で朝の始まりが唄われているコミカルな曲で、アルバム全体の緩急をつけるバランスとしても良いアクセントになっていますね。
杉本:「NEW1」の歌詞はメンバーやスタッフもウケてくれて、俺のアルバムには必ず入ってる面白担当の曲でもあるね(笑)。
──ザクザクと斬り刻むビートが心地好い「電撃」は岡本太郎の同名の油彩画がモチーフとなっていて、“アート”がキーワードである本作に相応しい一曲と言えますね。
杉本:今年の春に岡本太郎の『電撃』(2006年に約60年ぶりに発見された油彩画)を初めて見た時の衝撃をそのまま音にしてみた。「無敵になって挑みぶち壊す 覚悟の様なキツイ一発だ」という歌詞があるけど、あの絵を見た時にまさにそんなことを感じたんだよね。岡本太郎の芸術と人となりにはいまだに憧れるし、青山の記念館と川崎の美術館はいまも両方合わせて年に4、5回は行ってるかな。あと、去年の夏から奥村大(wash?)っていうギタリストと一緒にライブをやるようになったんだけど、「電撃」はヤツのギターからインスパイアを受けた部分もある。『7↓8↑』の時は中畑大樹(syrup16g、VOLA & THE ORIENTAL MACHINE)っていうドラマーと新たに組んでライブをやっていくなかで「天国ロックショー」みたいな曲が生まれたように、「電撃」は俺のなかで大のファズギターと岡本太郎の絵がリンクして出来たんだよね。
──奥村さんのギターはラウドでひりひりとして異様に歪んでますけど、ちゃんと血の通った音なんですよね。
杉本:うん。ちゃんと感情が入ってるし、「電撃」で大が弾いてくれたギター・ソロのちょっと泣きのあるメロディがすごく好き。大が入ってくれたおかげでギターを振り分けられるようになったし、純然たるギタリストと一緒にバンドをやるのも歴史的に初めてなんだよね。いままで弾いてくれた(宮崎)洋一もすごく頑張ってくれたけど、彼はもともとボーカリストだからさ。大のおかげで音色を含めたギター・アンサンブルもいろんな可能性が広がったし、俺も歌に専念できる部分が増えたね。
──有江嘉典さん(VOLA & THE ORIENTAL MACHINE)はもう12年ほど恭一さんをサポートしているし、有江さんと中畑さんという鉄壁のリズム・セクションもかなり長いじゃないですか。だからよほどウマの合う面子なんだなと思って。
杉本:いままでサポートしてくれた人たちももちろん素晴らしかったんだけど、ある種のバンドの到達点ということで言えば、大を入れたいまの3人は非常に強烈だと思ってる。せっかくそれだけのミュージシャンたちと出会えて恵まれた環境にあるんだから、彼らの音が活きるアルバムにしたいと思ったね。
──恭一さんくらいのキャリアになると、自身のギターに対するこだわりはそれほど強くはないものなんですか。
杉本:その辺はもうあまりガツガツしてないのかもしれない。どう弾いても俺の音はもう分かるやろ? って感じだから。今回、録る時やミックスの前にはギターの音に関して注文はつけなかったし、ミックスやマスタリングでエンジニアとやり合うことが多かったのはリズムのことだったしさ。
──“音楽とアートの融合”というテーマがあって、序盤、中盤、終盤にインストを配して、前半はノリの良い攻めの曲、後半はじっくり聴かせる曲を並べるのはかなり緻密な構成だと思うし、とてもコンセプチュアルな作品と言えるのでは?
杉本:結果的に『STOWAWAY』というアートと音楽を融合させた展覧会から広がっていったアルバムという意味ではコンセプチュアルなのかもしれない。サウンドから浮かぶ映像のイメージとかもあらかじめあったしね。
──音楽以外のアートとがっぷり四つに組んでみたことで改めて見えてきた音楽の特性とはどんなものでしょう?
杉本:やっぱり、音楽のすごいところは踊れることだろうね。どんなに素晴らしい絵画でも、それを見て踊ることはないじゃない? ホントは踊りたいくらいの気持ちだったり、暴れてたり、泣いてたり、言葉にならない気持ちが見た人のなかにはあるんだろうけど、音楽ならその気持ちをストレートに出せる。『STOWAWAY』でも終わる最後の30分はPAを通さずに、生声と生ギターで見に来てたお客さんと一緒にギャラリーで唄ったんだけど、あれも音楽のなせるわざだったと思う。展覧会だからと言ってかしこまって終わらせたくないというエネルギーが充満していて、アートに囲まれたスペースのなかで俺がやれるのは音楽を鳴らすことだった。そこでみんなが体感したアートの素晴らしさを、俺の鳴らすリズムや音符が煽ってくれたんだよ。
いまはギタリストよりも唄い手という意識が強い
──今回のレコーディングは、自身を含めたバンド・サウンドのありのままの音を録れればOK、みたいな感じだったんですか。
杉本:俺はデモテープの段階で仕上がりの音色まで作り込んでおくタイプでさ、そうするとメンバーのほうが理解してくれる。とは言え、作ってるこっちはメンバーの個性を欲しがるから、彼ららしいプレイや音色を出してもらうようにはしたけどね。
──「Byway」も「Doorway」も細部まで緻密に作り込まれた宅録が基本じゃないですか。恭一さんは肉感的なバンド・サウンドで本領を発揮するタイプのミュージシャンだと思っていたので、そこまで作り込んでいたのが意外だったんですよね。
杉本:そういうイメージないやろ? 実は相当前からそんなことをやってるんだよ。何なんだろうね、そうやって細かくデモを作るのが好きな性分みたい。
──油絵で丹念に色を重ねていくよりも、水墨画でサーッと一筆書きするのが恭一さんのパブリックイメージだから意外なんでしょうね。
杉本:舞台のキャラは水墨画でサーッ、だからね(笑)。エンジニアにもミュージシャンにも「そこまで作り込まなくても…」っていつも言われるんだけど、結局やっちゃうんだよ。
──でも、当然のことながら良い意味で予想を裏切るプレイも現場では出てくるわけですよね。
杉本:もちろん、そういうのはほぼOK。その人のかっこいい個性が出たほうがこっちも得だしね。大はスタジオの仕事もしてるから気をつかうし、俺とのレコーディングは今回が初めてだったから最初は遠慮がちだったけど、「いつものお前になってくれ」みたいなことは言ったかな。結果的には「自分のバンド以外でこれだけ全力を出したのは初めてです」って言ってたけどね(笑)。
──有江さんと中畑さん、そこに奥村さんが加わる編成ですが、ソロ名義だけどれっきとしたバンドという形態がいまの恭一さんには一番しっくりきているんですか。
杉本:バンド名がないことで救われることがあるとしたら、悪いほうの責任は俺が全部一人で取れることなんだよ。これが名前のあるバンドなら、良くないことでもメンバー全員で共有していなければバランスがおかしくなるけど、ソロのバンドはその辺がラクだね。楽しいことはみんなでシェアして、良くないことは俺が被ればいいだけの話だから。それに、根本的に俺はバンドマンだから、バンドとしての楽しみ方しか分からない。弾き語りで一人でやっても、それは極めてバンド的なんだと思う。
──そうですよね。たとえそれがソロの弾き語りだとしても、恭一さんの場合はシンガー・ソングライターと言うよりもあくまでバンドマンらしいパフォーマンスだと思うんです。
杉本:俺がレピッシュで世に出た時はMAGUMIの横でギターを弾いてただけだし、やっぱり根はバンドマンなんだよ。まさか自分が唄うなんて想像もしてなかったからさ。真ん中に立って目立ちたい発想も全然なかったし。その割には両サイドで(上田)現ちゃんと目立ち合いを散々してたけどね(笑)。
──ソロで20年間唄い続けてきて、唄うことに快感を覚えることも出てきましたか。
杉本:いまは快感を超えて、自分が唄い手であるという気持ちがすごく強い。弾き語りをやるようになってから特にそう感じる。もちろん始まりはギタリストだからギターも大事にしてるけど、いまはギタリストと言うよりも唄い手なんだって意識が強いね。
──恭一さんほどの名うてのギタリストなら、全曲インストのアルバムを作ってもファンは納得すると思うんですけど、決してそうはならないじゃないですか。歌詞で悪戦苦闘しながらも、鼻歌で口ずさめるいい歌の詰まったアルバムをコンスタントに発表し続けている。僕はその闘っている感じがすごく好きなんですよね。
杉本:楽器出身だからこそ、言葉には勝てないと逆に思うのかもしれない。言葉を持っているのは楽器には勝てない部分だから、どうしても言葉は使いたい。それは思うかな。今回はインストを3曲も入れたくらいだから、もちろんインストも好きは好きなんだよ。ただ、俺にとって言葉は音楽をパワーアップさせてくれるものなんだよね。俺の使う言葉なんて、景色や色を見せる程度のものだけどさ。
──アコギ一本でむき出しになるライブは特に言葉が大きな武器になりますよね。
杉本:うん、もろにね。歌詞が屁みたいなものだったら、そこで終わりだから。
──その恭一さんの歌詞も言文一致体と言うか、どこかからの借り物じゃない平易な言葉なのがいいんでしょうね。
杉本:ミュージシャンでもよく詩人を気取った感じの歌詞を書く人がいるけど、ああいうのを見るとバカじゃねぇかと思うよね(笑)。だって、あくまで音楽のなかで使う言葉なんだから、詩人になられても困るって言うかさ。