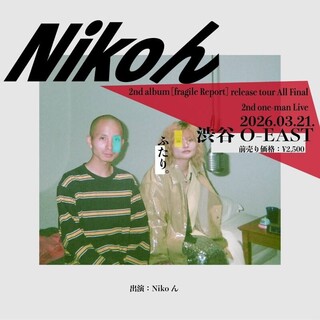グルーヴァーズらしさをそのまま出せば新鮮な音になる
──だから今回のアルバムは、音も楽曲もプリミティヴな趣きが増しているように感じるのかもしれませんね。
K:アレンジがガラッと変わった曲もあるんだけど、どの曲も試運転的にライブで最低一度は披露した上でレコーディングしたんだよ。その意味ではデビュー・アルバムっぽいところがあるね。プリミティヴさっていうのはそういう部分に出ているのかもしれない。
──アレンジがガラッと変わったのはどの曲なんですか。
K:「空白」とかね。いろんなリズム・パターンを試して仕上げたからさ。あと、「UNDER THE FOGGY MOON」もテンポが完成形より遅い時もあれば速い時もあった。
──アレンジのことで言えば、キーボードが絶妙な隠し味になっている曲が多いですよね。「PERFECT DAY」や「遠吠え彼方に」然り、「ANOTHER VIRTUE BLUES」然り。
K:今回は自分で弾いちゃったんだよね。エマーソン北村さんやリクオ先輩、ミッキー(伊東ミキオ)に頼むこともなく。何と言うか、今回の鍵盤はホントに必要最低限の隠し味で良かったから、わざわざプロに弾いていただくまでもなかったんだよね。セルフサービスでいいや、と。
──じゃあ、ゲスト・ミュージシャンは「YES or NO」の女性コラースくらいですか?
K:あのコーラスは、実はフリーのサンプル音源なんだよ。ネットで「female」「soul」「shout」とかで検索して(笑)。
──そうなんですか!? ということは、本作は徹頭徹尾、3人だけで作り上げたものであると。
K:最初から3人だけでやろうと決めていたわけじゃないけど、結果的にそうなった。「ANOTHER VIRTUE BLUES」のピアノなんか左手は弾いてなかったりもするけど、別にいいじゃん、と。ピアノの低音ってベースと被るしね。プロを呼んで本格的に弾いてもらうのもアリだけど、別に拙いピアノでもいいじゃん、っていう。今回求めていたのはそこじゃなかったし。そういう細かい部分も直感の通りに動いて結果オーライだったね。
──直感を頼りにするのもプリミティヴさの表れですよね。
K:ミックスとか歌詞とか、推敲する作業はいっぱいあるんだけど、楽曲を作り始める原石の段階ではヘンにこねくり回すよりもひらめきを最優先したほうが絶対にいいよね。あれこれ考えまくったのにダメだったら後悔も大きいだろうしさ(笑)。
──今回のような良質なオリジナル・アルバムを、なるべくタームを空けずにリリースしていくのが今後の理想ですか。
K:まぁ、欲を言えばね。でもたとえば狂乱の90年代のように、毎年アルバムとシングルを1枚ずつリリースして、創作期間もたっぷり設けてもらって、ともすればプリプロ期間まで設けてもらって、宣伝もガッチリとやってもらって…みたいな時代にはこの先もう戻ることがないでしょ? パッケージ商品としてのアルバムの概念さえも考え直されているこのご時世に、何年に一度アルバムを出すのが適正なのかはよく分からない。さすがに10年は空けたくないけど、無理のないペースでやりたいとは思ってるよ。
──狂乱の90年代と比べると、今の音楽産業の動向はやはり寂しく思えるものですか。
K:今は全体的にあまりにもしょっぱいよね。簡単に比較はできないけど、90年代は今よりもバンドマンやアーティストにとって甘すぎる環境だったとは思う。あの時代にぬるま湯に浸かっていた人たちは、業界全体が急激に落ち込んだ時はキツかったと思うよ。俺たちはその90年代ですら贅沢ができたわけじゃなかったけど、まあ飢え死にしない程度にはやっていけたし、そもそもこんなバンドに長年契約があったこと自体がバブル期最大の恩恵だった気がする(笑)。
──でも、ベスト・アルバムを2枚も出せるバンドってなかなかいないと思いますよ。
K:そうだよね。しかもオリジナル・アルバムのリマスター盤も2回出てるし、そういう面はラッキーだったと思う。仮に今のノウハウを持って潤沢な予算と時間を使えた90年代にタイムスリップできたら、もっといいサウンドを生み出せるのかもしれないけど、歴史に“if”はないからさ。今置かれた環境の中で、自分たちらしさ全開でやりたい音楽を精一杯やるだけだよね。新しく台頭してくる音楽に負けないためにはどうしたらいいのか考えていた時期もあったけど、そんなことはもう関係ない。自分たちの核となる部分をより濃くして、グルーヴァーズらしさをそのまま出せば新鮮な音になる自負があるから。今回のアルバムがそれを証明できていれば嬉しいね。