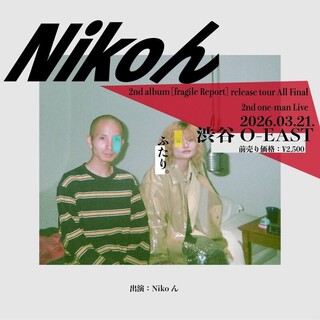先月13日、自身が参加した『スタンリー・クラーク・バンド・フィーチャリング 上原ひろみ』が第53回グラミー賞の最優秀コンテンポラリー・ジャズ・アルバム賞に輝き、世界中にその名を轟かせたジャズ・ピアニスト、上原ひろみ。その吉報を追い風とするかの如く、絶好のタイミングで日本先行発売されるのが"上原ひろみ ザ・トリオ・プロジェクト"名義の作品『VOICE』だ。
6弦ベースがトレードマークのアンソニー・ジャクソン、TOTOの2代目ドラマーとして知られるサイモン・フィリップスという辣腕ミュージシャンと共にトリオ編成の新たな可能性に極限まで挑んだ本作は、人の心の中にある真実の声に耳を傾け、溢れ出す感情のうねりを瑞々しい音に昇華させた渾身の一枚。エネルギッシュかつスリリングで有機的なアンサンブルは時にダイナミズムに満ち、時にハートウォーミングな響きを奏で、トリオという最少編成で何処まで生の実感を音に託せるかを実践している。
ライヴとは文字通り生きることだと言わんばかりにグローバルな活動を続ける彼女の表現意欲の源泉を知るべく、本人を直撃した。(interview:椎名宗之)
ライヴでできないことを音にしないのが信条
──今回発表される『VOICE』はサード・アルバム『SPIRAL』以来のトリオ編成による作品ですが、このタイミングで再びトリオに挑んだのはどんな理由からなんですか。
上原:もう一度トリオで同じことをやろうという気持ちはなかったんです。戻る気持ちは微塵もないし、常に進む気持ちしかありませんから。ただ単純に、アンソニー・ジャクソンとサイモン・フィリップスと一緒にトリオでやりたいという発想がまず最初にあったんですよね。自分としては極々自然な流れだったんです。
──今トリオでやるなら、その2人以外に考えられなかったと?
上原:最初はまずアンソニーと一緒にトリオをやりたいと思っていたんです。『ANOTHER MIND』と『BRAIN』で彼とご一緒した時からずっと「フル・アルバムを作りたいね」と話していて、今回ようやくその機会を得たんですよ。アンソニーとのトリオを念頭に曲を書き進めていくうちにドラムの音が明確になってきて、自分が欲する音はサイモン・フィリップスだなと思ったんです。
──サイモン・フィリップスと言えば、ジェフ・ポーカロ亡き後のTOTOの2代目ドラマーとして名を馳せた方ですが。
上原:私が彼のドラムを最初に聴いたのはジェフ・ベックの作品(『THERE AND BACK』)だったんです。ジェフ・ベックがスタンリー・クラークとツアーを回った時のドラマーがサイモン・フィリップスだったんですよね。私もスタンリーとツアーをしていて、その時にサイモンの話をよく聞いていたんですよ。そんなこともあって、今回はどうしてもサイモンのあのパワフルな音が欲しかったんです。
──スタンリー・クラークのトリオやバンドの一員としてレコーディングやツアーに参加した経験が本作に活かされている部分もありますか。
上原:ずっと第一線で活躍し続けている年輪の凄さをスタンリーからは感じました。それはチック・コリアもそうだし、レニー・ホワイトもそうだし、とにかく年輪が凄いんですよ。
──アンソニー、サイモンと初めて音合わせをした時は予想以上の手応えを感じました?
上原:もう、スタジオ中を走り回りたい気持ちになりましたよ(笑)。それくらい興奮しましたね。
──上原さんの録りはいつも早いのに驚かされますね。今回もニュージャージーのスタジオで3日間で録り終えるという早技で。
上原:そこで初めて音を合わせているわけではありませんからね。レコーディングの3ヶ月くらい前からリハーサルを重ねて、個人練習をしてから臨んでいますから。
──アンソニーとサイモンは実際どんな方なんですか。
上原:2人とも凄く優しいんですけど、サイモンのほうがちょっとやんちゃと言いますか、あの演奏の通りなんです(笑)。アンソニーは縁の下の力持ちとして常に全体を見ていて、「大丈夫かい?」と温かい眼差しで見守ってくれますね。アンソニーもサイモンも、とても素敵な大人たちなんです。彼らの存在があったからこそ存分にプレイに打ち込めたし、私は2人に活かされているなと思いました。
──上原さんにとって、トリオ編成の醍醐味とはどんなところですか。
上原:すでにやり尽くされた感のある編成だからこそチャレンジのし甲斐もあるし、そのメンバーにしか出せない音もあるし、トリオだと自分の曲でしか伝えることのできない思いが明確に出るんですよ。
──特典DVDのインタビューで、お互いの役割を交換し合うという話がとても興味深かったんです。ピアノがリズムをキープすることもあれば、ベースやドラムがメロディを奏でることもあるという。
上原:だから、集中力が凄く必要なんです。3人というバランスがまた面白いんですよね。3人ならバランスが取りやすいですし。
──特典DVDには『NOW OR NEVER』の演奏シーンが収録されていますが、上原さんがピアノの上にシンセサイザーを弾いて忙しなく同時演奏しているじゃないですか。
上原:ああ、ノードリードですね。
──重ね録りではなく、同時進行で弾くのが凄いなと思って。
上原:ライヴでできないことを音にしないのが私の信条なんですよ。今までもキーボードがフィーチャーされた曲は全部ピアノとキーボードを行ったり来たりで、てんてこ舞いなんです。「別録りすればいいのに…」なんて言われながらやってますけど(笑)。
思いを曲にしたくなる欲求が強い
──インストゥルメンタルでありながら『VOICE』というタイトルなのがまずユニークだと思ったんですが、本作は“人の心の中にある真実の声や感情”がテーマとのこと。上原さんはこれまでも自身の内なる声を音に託してきたと思うし、こうしたテーマを今回敢えて据えたのはどんな意図があったのでしょうか。
上原:突き詰めたいテーマだったんですね。人間の真の声というのはなかなか言葉にしづらいものだし、内に秘めている場合が多いじゃないですか。その内なる声に際限まで耳を傾けて、それをすくい取って音にしてみたかった。特に言わなくても何かが伝わってきそうなくらいの思いって、言葉にしないという意味でインストと同じなんですよね。そこで繋がるなと思って。…間違って買う人いますかね? 私が唄っているんじゃないかって(笑)。
──それはそれで結果オーライでしょう(笑)。内なる声を思うように吐露できない、鬱屈した感情があったがゆえのテーマだったんでしょうか。
上原:何と言うか、ツアーを凄くやるようになってから感情の起伏が激しい生活になったんですよね。人からワーッと求められて、ライヴが終わると人がサーッといなくなっていく。次の公演地に移動すると、昨日のことはまるでなかったかのように振り出しに戻ってリセットされる。そういう激しい起伏のある生活を送っていると、人の感情にも敏感になってくるんですよ。
──特典DVDで上原さん自身が語っている通り、それでも創造のインスピレーションはあくまで人であるというのが僕は上原さんらしいと思うんです。日々の生活の中で人から得た思いが蓄積されて、それが一篇の曲として昇華されるわけですよね。
上原:作曲しようと思って譜面に向かうこともあるんですけど、作曲したい欲求に駆られることが多いんですよ。思いを曲にしたくなる欲求が強いんですね。
──タイトル・トラックの『VOICE』は、憂いを帯びた序奏から躍動感に満ちたアンサンブルに発展した後に再び憂いのある終幕を迎えるという緩急の付いた構成が見事で、9分を超える大作ですが一気に聴かせますね。
上原:『VOICE』の導入部分に関して言うと、人の心の声に耳を傾けるのには集中力が要るので、集中力を研ぎ澄ませているイメージなんです。目を閉じると聴こえてくるたくさんの“VOICE”を音にしたかったんですよね。
──上原さんが抱く感情を音で具象化する上で、なかなか思い通りに行かないジレンマも絶えずあるものですか。
上原:“こうじゃない、もっと違うイメージなんだ!”とか“なんで降りてこないんだろう?”というのは毎回ありますね。今回も曲作りの段階で書いては止まっての繰り返しでしたから。
──文字通り“迷宮”に迷い込んだかのような音像の『LABYRINTH』はベースの太い音が心地好いし、歯切れの良いテンポが魅力の『DESIRE』は否応なしに感情が鼓舞されるし、各人の特性を活かした楽曲が揃っていると思います。
上原:それはやっぱり、アンソニーとサイモンありきで曲のアレンジを施したからでしょうね。
──流麗でいて透明感のある『HAZE』だけが本作の中で唯一のピアノ・ソロ楽曲ですね。
上原:ソロでやってみようと言うよりも、『HAZE』は最初からソロ曲として書いたものなので、それを形にしてみたまでなんですよね。
──ベートーヴェンのピアノソナタ第8番『PATHETIQUE』をカヴァーしたのは?
上原:とてもドラマティックな展開のアルバムなので、聴くほうも凄くエネルギーが要ると思うんですよ。いろんな感情がうごめいてきて、音楽というフィルターを通してその感情を浄化させるような曲を最後に置きたかったんです。「大丈夫だよ」ってギュッと抱きしめてあげられるような曲と言うか。私としては9曲目の『DELUSION』が本編のエンディングで、エンドロールとして『PATHETIQUE』を置く流れにしたつもりなんですよ。
──“指から耳へ”ではなく“心から心へ”思いを届けること、感情をそのまま注ぎ込むことに腐心する上で一番気に留めたのはどんなところでしたか。
上原:とにかく気持ちを集中させることに尽きますね。幸いなことに、集中力が凄く長く持続する3人だったんですよ。
──エンジニアもその集中力に追い付かなくてはいけないから大変ですね。
上原:私のレコーディングは激務ですよ。労働基準法を無視するようなワーカホリックぶりですから(笑)。ミックスも2日間で全部終わらせたんですよ。朝の9時から深夜0時まで働き通しで、エンジニアの人は“もう当分音楽を聴きたくない”みたいな感じだったと思います(笑)。エンジニアの人と私のマンツーマンでしたからね。
新宿ロフトでジャケット撮影をした理由
──今回のジャケットは我が新宿ロフトのフロアで撮影されていますが、これはどんな理由で?
上原:ライヴハウスという空間にはいろんな人たちの感情が渦巻いているじゃないですか。ライヴが終わって帰る時に、誰もいなくなったライヴハウスに一人佇むことがあるんです。もう誰もいないんだけど、その場にいた人たちの感情がもやりもやりと残っている感じがするんですね。そんな場所で写真を撮りたいと思って、いろんなライヴハウスを頭に思い描いたんですけど、私はロフトのあの雰囲気が好きなんです。あと、ロフトの床はピアノの色でもあるし、絶対にあの床を入れたいとカメラマンの方と話していたんですよ。
──白と黒の市松模様の床ですね。
上原:そういう床が白黒のライヴハウスは他にないなと思って。
──ロフトのオーナーである平野 悠によると、最初は黒のタイルを敷き詰める予定だったそうなんです。それが工事中に黒のタイルが足りなくなったために、余っていた白のタイルを交互に貼ることになったらしいんですよ。
上原:そうだったんですか。黒のタイルが足りなくて良かったです(笑)。
──言われてみれば、ライヴハウスは感情=心の声が交錯する象徴的な場所ですよね。
上原:誰もいないライヴハウスには感情の残り香みたいなものがあるんですよ。そんな状況に身を置くと、この瞬間はもう今しかないんだなと思うんです。ライヴハウスはそういう刹那を感じる場所なんですよね。そもそもライヴ自体がその瞬間で終わってしまうものだし、そこを出たら二度と出会えない感情たちが入り混じっているんですよ。ロフトのように老舗のライヴハウスであればあるほどそうなんじゃないですかね。数々の伝説のライヴがそこで繰り広げられて、いろんな人たちが泣いて笑って、その感情が充満しているのを感じるので。
──こうしてロフトでの撮影も済まされたわけですから、今後は撮影だけではなく是非ライヴをやって頂きたいですね。
上原:そうですね。ピアノが入らない問題は解決されたんですか?
──はい。グランドピアノはちゃんと搬入できるようになりました。
上原:良かったです。それなら是非出演させて頂きたいですね。