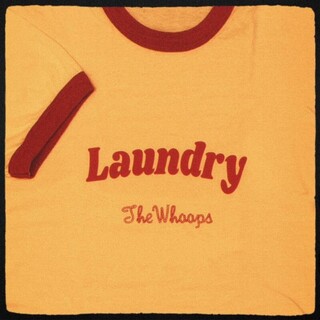2003年のデビュー以来、世界中で年間150本近いガチンコのライヴを続けてゆく。この事実にはどんなジャンルのミュージシャンでも一目置くしかない。ピアニスト、上原ひろみ。もはや日本のジャズ・シーンにおけるゼロ年代最大の超新星〈スーパー・ノヴァ〉であるだけでなく、ボーダレスに絡み合う世界の音楽シーンに確実に影響を与えるキーパーソンの一人である。自身初となるピアノ・ソロ・アルバム『PLACE TO BE』を、期待の新世代インスト・バンド、openingのキーボーディストにして新宿ロフトの制作に携わる佐藤 統と共に読み解いてゆく。彼女の技術の凄さ、鋭敏な思考、そして何よりも人生を懸けて音楽に生きる意志の強さが一端でも伝わることを願いながら。(interview:吉留大貴)
ピアノ・ソロ・アルバムの概念を変えたかったんです
──今回6枚目のオリジナル・アルバム、そして初のピアノ・ソロ・アルバムですが、デビューの頃に今回のようなアルバムを作るのは可能だったのかをまず訊きたいのですが。
上原:テクニック的なことや楽想的なことも含めて、当時ではできなかったと思います。それとデビュー当時には、ミュージシャンであり続けるのがこれほど体力的にも精神的にも根性を要するとは考えてもいませんでした。そんな中、毎年世界中でツアー生活を送るようになって、ピアノが戦友というか、世界のどんな場所に行っても助けられてきたことを実感したんです。今まで以上にピアノが大好きになって、もっとピアノの可能性を引き出したアルバムを作りたい気持ちが強くなったことが今回の作品の背景にはあると思います。
──そのピアノの可能性という点ですが、今回の楽曲『シュー・ア・ラ・クレーム』や『パッヘルベルのカノン』のカヴァーでは通常のピアニストならまずやらないようなかなりトリッキーな奏法をやっていますけど、不思議なことに全体を通して聴くと奇を衒っているようには感じられないんですよね。
上原:私の中でアルバムを作る際に一番大きな要素はライヴなんです。バンドの場合、たとえば4人なら4人分の音の変化がある。それに4人で弾く場合や、ソロ、1対3になったりとかのコンビネーションの変化もある。そういういろんな変化があるから、ライヴでお客さんが聴いていても飽きにくいですよね? ところがピアノ・ソロの場合、基本的にピアノ1台の音しかないので、それで1時間半から2時間のライヴを成立させるのは凄く難しいんです。それを観客に「ピアノだけでもこれだけ楽しめるんだ」と満足させるには、「ピアノ1台でこれだけのことができるんだ」というのをライヴで証明する楽曲が必要だというのを考えてアルバムを作るという発想が出てくる。そこでピアノだけでもライヴができるという確信がないとアルバムは作れない。だから相当、いろいろとこれまで以上にピアノについて研究したとは自分でも言えますよね。
──今回、その研究成果を一番証明しているのが、恐らく上原楽曲の中でも超A級難度であるのが誰でも一聴すれば判る1曲目の『BQE』です。アルバムのコンヴェンションでこの曲を弾かれた時もかなり近くで観ていたのに、正直何も判りませんでした(笑)。
上原:この曲は私もかなり練習してようやく弾けるようになった、とっても難しい曲なんですよ(笑)。この曲を最初に置いたのは、私はこれまでバンドでアルバムを発表してきたじゃないですか。「やっぱりソロ・ピアノだとこうなるんだね」と言われないようにするにはどうするべきなのか。今まで私の音楽を聴いてきた人に、今回は私がドラムであり、ベースであり、メロディを奏でるというすべての役割を担っているというのを判らせないといけない。その点を一番表現できている曲だと思ったので、アルバムの頭にすると私の意図が伝わるかなと考えたんですよ。それと個人的にですけど、私は今ニューヨークに住んでいて、一番戦っている場所のイメージがこの曲には込められているというのもあるんです。
──それと光と影、軽やかさと重厚さといった相反する要素が計算されて構成されていますよね。全体の曲順もこれまで以上に熟慮して、ピアノ1台で表現できる世界を押し広げてゆきたいとする意志を感じます。
上原:何というか、アルバムの70分近い時間をライヴとして聴いて欲しいんですよ。私にとってライヴは、その時間の中で人を旅のように何処かへ連れて行ってゆくものなんですね。ピアノ1台で人を旅にいざなうのは、1曲1曲似ないようにする必要性があります。金属音を出したりとか、低音弦を直に手で押さえたりとかの他に、何も細工をしなくても音色だけで微妙な風合いを出さないといけないんですね。打弦のレヴェルも楽曲ごとに変えていますし。その意味において、音色的に暖色系の次は寒色系といった組み合わせはこれまで以上に考え抜いた部分はありましたね。
──『ケープコッド・チップス』から『アイランド・アゾレス』への世界観の変化は今回のアルバムの聴き所ですけど、プロデューサーとしての上原さんの意図が最も明確に出ているのが興味深いです。
上原:厳密に言うと、ピアノを弾かない人ならどれを聴いてもピアノの音かもしれないですけど、面白いのは、人は潜在的に訴えかける音のニュアンスを感じ取ることができるんです。実際にそれを伝えるにはかなりのニュアンスを込めた弾き方が必要なんですけど、ピアノを聴いて人が優しい気持ちになるのも事実としてありますよね? 実は人の心を揺り動かすメッセージって、言葉で伝えるよりも音で伝えるほうが伝わりやすいので、何度か聴いた時に判るようなサブリミナルな要素を上手く入れてはいるんですよね(笑)。

私はピアニストとしてまだまだ"未熟"だと思っています
──今回特筆すべき点として、上原さんのデビュー以来日本でのピアノの調律を担当してきた小沼則仁さんが参加されています。これまで上原さんのオリジナル・アルバムは、アメリカ録音でアメリカの調律師が担当してきましたよね。アメリカにも優れた調律師は多いだろうし、わざわざ日本から調律師を呼ぶのはかなり異例なことじゃないですか。先のアルバム・コンヴェンションのスタッフとの乾杯に同席させてもらった時も、「このアルバムは小沼さんなしでは絶対にできなかった。私のことよりも小沼さんの技術を伝えてほしいんです!」とまで仰っていましたよね。本誌はライヴハウスが発行するフリー・マガジンでもあり、全国の生ピアノがあるライヴハウスにも届けられます。是非そのことを充分に語ってもらいたいです。
上原:今回のアルバムはピアノ1台で作るので、変化を付けるには"音色"が非常に大切なんです。ただ、そういったカラフルな音色を出すピアノを調律することは本当に難しい。その私が望む音色を作ってくれる調律師として、小沼さんには絶大な信頼を置いています。小沼さんの調律したピアノの一番の魅力は、何よりも音色の幅を広く作ってくれることなんですよ。もちろん、自分でその音色の幅を弾く能力がなければ望んだ音は出ないし、私自身、音色の幅を全部使い切ったかと訊かれればその自信はないです。だけど、「もうちょっとこんな音が出ればいいのにな...」という音は存在しないわけですよね。だからこそ今回のピアノ・ソロ・アルバムにはどうしても小沼さんの力が必要だった。確かにアメリカまで調律師を呼ぶのは異例なんですけど、今回は私だけのアルバムじゃないですか。実質、小沼さんをバンド・メンバー扱いすることで実現したというのもあるんですよね。だから私と小沼さん、そしてエンジニアでコ・プロデューサーのマイケル・ビショップのトリオで今回のアルバムを作った気持ちが強いです。普通、調律師やエンジニアのクレジットはアルバムの冊子の中にしか載らないじゃないですか? でも今回は、アルバムの裏ジャケットにもバンド・メンバーのように小沼さんとマイケルの名前が出ているんです。
──これまでエンジニアという職業にも、ミュージシャン同様にアーティストとして接するべきだと個人的には考えていたんです。でも、このアルバムを聴いてピアノ1台でも限りない音色があるんだと知って、調律師も完全にアーティストだったんだと改めて思い知らされました。
上原:本当にその通りで、調律師はアーティストなんですよ。ただ、調律師という職業にもいろんな人がいますよね。調律はピアノに対する研究がないと成立しないし、その研究はピアノに対する愛情から生まれてくるんです。愛情のない人の調律では、音に限界があるんですよね。「とりあえず調律だけ合えばいいじゃん」という人のピアノでは、人を感動させる演奏はできないですよ。小沼さんの調律は音には何の関係もないかもしれないけど、ピアノをピカピカに磨くことから始まるんです。自分は完全にピアノに屈している、常にピアノのご機嫌を取っていると本気で語る姿勢には感動します。デビュー当時からピアノについてたくさん教えられたし、もっと小沼さんが調律するピアノを弾きたいという気持ちが増していますね。
──こう話すと小沼さんはストイックな職人タイプだと読者は思われるかもしれない。実際、何度か上原さんのライヴでお見かけしていますが、見た目も凄くジェントルな方です。しかしここで忘れていけないのは、上原さんが平気で流血しながらピアノにエルボー連打を叩き込む演奏スタイルです(笑)。今回のアルバムでもかなり掟破りの奏法が披露されていますよね? 今まで上原さんのピアノの奏法は過激だとずっと言われてきましたけど、今回のアルバムを聴いて、実は本当に過激なのは上原さんの奏法を許している小沼さんのほうじゃないのかと感じてしまいました。だって、普通の調律師だったら絶対に嫌がることばかり演っているじゃないですか(笑)。
上原:確かに嫌がるでしょうね(笑)。小沼さんは調律師としての技術も一流なんですけど、私のやりたいアイディアにNOを言わずにオープンに考えてくれる思考性の人なので、本当に有り難いです。先ほど『BQE』を近くで観ていたのにどう弾いたか判らないと仰ったじゃないですか? あの曲にはあるトリックがあるんですけど、ライヴのリハ中に小沼さんが調律をしていて、今まで聴いたことのない音がピアノから鳴ったんです! 私が大興奮して「こんなサウンド聴いたことない! この音を録音したい! どうやったらこの音が出せるか教えて下さい!」とお願いして小沼さんに教えてもらったんですよ。でも、最近はマズイことを教えてしまったという気持ちからなのか、「あれは自分自身で発見した音で、俺が教えたんじゃない」と事実とは違う発言をするようになりました(笑)。普通の調律師だったら絶対に教えたらいけないことなのかもしれません(笑)。
──言い換えると、2人の作る音にダブーがないということにもなりますよね。そうやってデビュー以来6年間、2人が作り出してきた音に対する成長の過程が判るような気にさせられますよね。
上原:ただ、成長と仰いましたけど、小沼さんの調律するピアノを弾くたびにピアニストとしての自分の未熟さを思い知らされることも多いんですよね。
──未熟さ?
上原:改めてピアニストとしての自分の未熟さを実感するんです。たとえば欲しい音が出ないのは自分のテクニックに問題があるのではなくて、このピアノのここに限界があるというケースは私にもあるんですけど、余りにも古いピアノという場合を除いては、小沼さんの調律したピアノを弾くと欲しい音が出せないのをピアノが理由だとは言えないんです。小沼さんが調律する幅の広い表現力豊かな音色を持つピアノに対して、欲しい音が出せないのは単に自分が表現力不足なだけですから。だからいつも自分はまだまだだぞと教えてくれる、常に初心に戻らせてくれる小沼さんが調律するピアノの音色と小沼さんの存在が私には必要なんです。
──そこで上原さんにお訊きしますけど、本誌はプロのロック・ミュージシャンも数多く読んでいるんですが、彼らが生ピアノの録音で小沼さんを起用すれば確実に音が変わると言えますか?
上原:それは言えますけど、小沼さんはピアノの幅は広げてくれますけど、ピアニストの幅は広げてくれませんから。小沼さんを起用すればいきなりピアニストとしての腕が上がるとかではないので、そこはやはり努力が必要ですからね(笑)。それでも小沼さんの調律したピアノを弾くともっとこういった音を出してみたいという気には絶対になるから、結果として小沼さんを起用することでピアニストとしての向上には繋がるかもしれないですよ。



"変態"なミュージシャンが大好き! でも自分が言われると......
佐藤:僕は自分のバンドでキーボードを弾いて活動しているのですが、新宿ロフトでステージの設営やドリンクを作ったりもしています。そんな中、後輩から上原さんの『スパイラル』というアルバムを教えてもらって聴いたんです。僕も上原さんと同じで小さい頃からヤマハ音楽教室にレッスンへ通っていたのに影響を受けたピアニストもいなかったし、特にジャズも詳しくないんです。でも上原さんの音楽にはとても感動してしまい、実はロフトのバー・スペースで勝手にヘヴィ・ローテーションしていたんです(笑)。それが最近、上原さんの音源を流しているとやたら反応するハードコア・パンクのバンドマンとかが多くなっているんです。ハードコアでもヒップホップをやっていても聴ける音楽として上原さんの音楽がさらに広がっているのを実感するし、多分上原さんが自分に影響を与えた初めてのピアニストだと思っています。
上原:素直に嬉しいです(笑)。
佐藤:そこでお訊きしたいのは、今はニューヨークにお住まいですけど、新しい音楽を知るためにCDショップやライヴハウスに行ったりするかということと、日本の音楽とかを聴く機会があるのかということなんです。
上原:音楽に対する興味本位な好奇心は、アマチュアの頃から今日に至るまで何も変わっていないので何でも聴きます。ジャズに限らず、CDショップに行ったら店頭プッシュされている音源は聴いてみて、心に引っかかったら買ってみます。日本のミュージシャンに関してはそんなに知る機会がないですけど、去年『スウィート・ラヴ・シャワー』というイヴェントでBRAHMANを観て猛烈に感動したのを今でもはっきりと覚えています。雨が降っていたけど、傘を差すのも忘れるほどの衝撃がありました。フェスとかで凄いミュージシャンを観た時って、自分が出演者だったことも忘れるんですよ。いつ何処でどんな音楽が待っているか判らないから、ニューヨークでも東京でもこんなにライヴハウスに来るアーティストはいないと言われるほど人のライヴも観ます。あと、海外では野外のフリー・ライヴが多くて、バンドとしてはピンと来なくても「あのドラマーは凄いな」と思えば、後でグーグルで検索して別のバンドを観に行ったりはしますね。そういう点では自分でも貪欲だと思うし、ニューヨークにいる時はほぼ毎日ライヴに行っています。
──最近観て良かったライヴって何ですか?
上原:ミッシェル・ンデグオチェロがアントニー・パークスというドラムと演っていて、相当変態で良かったです。私の中では"変態"という言葉がとても重要なんです(笑)。今まで聴いたことのない、また観たことのないものって気持ち悪くて怖いじゃないですか? その気持ち悪い怖さのような変態さがないと、私はマニアックに好きになれないんですよ。アントニー・パークスのドラムは本当に変態で、逆にそこを突き抜けると聴いていて凄く気持ち良くなってくるんですよ。あと、スティーリー・ダンのドラムでスティングのツアーにも参加したキース・カーロックも本当にいい意味で変態だから大好きです。彼とアンソニー・ジャクソンがベースで、ウェイン・クランツというギタリストでトリオを組んでニューヨークで演奏するのを観ますけど、これも全員が変態ですね(笑)。でも、そういう人たちじゃないと聴いていてパワーが伝わってこないんですよ。
佐藤:じゃあ、僕がロフトのバー・カウンターで上原さんの音楽を流して若いバンドマンが反応するのは、今上原さんが挙げた人たちと同様の変態性があるからかもしれませんね?
上原:自分がそうなのかは、客観的になれないからよく判りませんね。
──いや、上原さんは音楽的に立派な変態じゃないですか(笑)。
佐藤:僕も初めて変態って褒め言葉なんだと知りました。考え方を改めないと......。
上原:でも、変態って自分が言われると何だか微妙な気がする(笑)。
──上原さんが好きなフランク・ザッパやジェフ・ベックも変態と呼ばれることが多いミュージシャンですよね?
上原:確かに"格好いい"や"素敵"という日本語じゃ足りないんですよ。海外でも凄いものを観たら"クレイジー"とか"ナッツ"と言うから、"グレイト"レヴェルじゃ人は感動しないんですよね。
佐藤:仲の良い友達に「あいつは凄い馬鹿だ」って言う時はありますよね?
上原:うん、その感覚に近いかもしれないです。
──なら、"変態"で何の問題もないでしょう(笑)。
上原:何か犯罪者っぽいからダメなのかもしれない(笑)。
──それこそ過剰反応ですよ(笑)。
椎名編集長:"異物感"とかはどうですか?
上原:それです! 私、自分のライヴでも人のライヴを観ても思うんですけど、強烈な異物感を覚えた人たちの音楽を何度も聴くうちに心地良さに変わる瞬間があるから好きになるわけですよね。ところが、そういった人たちはさらなる異物感を求めるから、彼らに対するハードルって一生高くなる一方なんです。そこは私にとってのチャンレジだと思うところがありますね。
──しかもその異物感が、大衆に対しては何処かでポップにならなきゃいけない。
上原:その通りで、ただの異物感なら結局は異物のままで終わっちゃうから(笑)。ヨーロッパのほうはちょっと変わった人しか呼ばれないアンダーグラウンドなフェスって多くて、私もよく呼ばれるんですけど(笑)、そういったドイツのフェスでハムクラッシュという北欧のバンドを観たんですよ。キーボードとドラムの2人組で、音楽的には一体何がどうなっているのか判らないけど最高でしたよ。「異物感をポップに変えるマジックってまさにこれなんだ!」と思って、とても参考になりましたね。
佐藤:今回のアルバムって凄く上原さんの息遣いが生々しく入っていますけど、ご自身では気にならないんですか?
上原:私、普通の人よりも呼吸が大きいんですよ。もうちょっと格好良かったらいいんだけど、時々うめき声みたいに聴こえます(笑)。だけど、レコーディングでそこを気をつけたテイクって絶対良くないの(笑)。エンジニアのマイケルも「これはこれでいい」と言っているので、プラスに取って頂けるといいんですが(笑)。
──ただ、そこがアクセントになっているのも事実で、上原さんがピアノを弾く上での独自な呼吸法と言えなくもないですよね。
上原:そこはメロディを活かすということに関係してくるんですけど、ピアノは管楽器とは違って何十分でも弾き続けていられますよね。人って音を受け入れる受動レヴェルに限界があるから、ある程度呼吸を一定にして話しかけるように弾くのが人には伝わりやすいんですよ。ただ、弾いていて自分でも息が続かなくなるような時は、やはりメロディに切迫感が出てくるんです。そういった点を上手く組み合わせるとメロディが活きてくるし、実はここがけっこう重要なポイントなんですよね。


いつだって"死にもの狂い"です! だって......
──今回のアルバムは上原さんの20代を総括する一面もありますが、ご自身ではどんな時代だったと考えているんでしょうか。
上原:絶えず責任感を問われ続けた日々でした。自分がベストを尽くしてもいい演奏ができるとは限らないけれど、お客さんが喜んでもらえる最低限のレヴェルをクリアするためには絶えず準備が必要になる。だから、ミュージシャンという職業にオフがないことを痛感しました。結局、格闘家が試合をしている時だけが仕事じゃなくて、身体作りから練習までが仕事なのと全く変わりませんよね。
佐藤:そんな中で、上原さんが音楽をやり続けるために何かを犠牲にしたことはあるんですか?
上原:犠牲って凄く難しくて、自分が自分に対してやっていることは、何かを得るための自己満足だから大変でもどうでもいいんです。ただ、私も結婚しているから、何処かで相手に対して苦労を掛けているのが判るから、そこにお互いの理解があるかどうか。そこには当然感謝の気持ちがないとダメだし、逆にそれを犠牲だと思うと後ろ髪を引かれて関係がおかしくなってゆくんですよ。私は主人が「自分はライヴに行ってくれて嬉しい」と言ってくれるのを本当に有り難いと思うし、その分良いライヴをやるプラスの理由になっています。将来的に家族が増えた時も、何かあれば家族全員で話し合って進んでゆくしかないですからね。あとは根性と日々の努力あるのみです(笑)。
──そして秋からは初のソロ・ピアノでの日本ツアーが始まるわけですよね。
上原:今回は音の良い会場を選んでいますので、ピアノの可能性を伝えられる文字通りの真剣勝負が見せられると思います。ただ今回は自分一人なんで、バンドで演るよりも4、5倍は疲れるんです。もちろん日本全国を回りたいし、前回よりも本数を増やしていますけど、スケジュールや身体のメンテナンスも考えると今はこれ以上は無理なんですよ。私も一応、人間なので(笑)。
──でも、上原さんは本質的に格闘家だから(笑)。
上原:格闘家だって365日試合をし続けているわけじゃないですよ(笑)。
──ツアーの移動中に地方のライヴハウスへストリート・ファイトのように乱入したり、上原さんにはそんな期待をついしてしまうんですよね(笑)。
上原:確かに格闘家に近いと言われるのは否定できませんよね(笑)。でも、今回は思い切った演出もアリかな? テーマ曲付きでガウンを着ながら入場して、それをピアノの前で脱ぐ...もちろんライヴ開始はゴングを鳴らします(笑)。時々お客さんがタオルを投げても絶対に拾わない(笑)。
──それを全国でやったら、いろんな意味で伝説になりますよ(笑)。あと佐藤さん、何かあります?
佐藤:最後に、上原さんは"死にもの狂い"という言葉がご自身に似合うと思いますか?
上原:凄く似合うと思います。そうじゃないと、こんな生活は絶対に送れませんから(笑)。