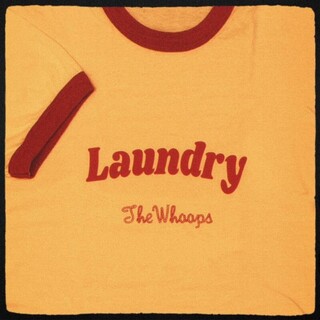「ジャズやクラシックは現実を見ない鑑賞用音楽に成り下がってしまった」──平野悠席亭対談を何度か読まれた方なら目にしたであろう席亭の自論である。ならばもしジャズやクラシックの現役トップ・ミュージシャンと対談した際にその自論で本当に論破出来るのか? 今回の対談の企画意図はこの一点に集約出来る。そしてその意味合いにおいてこの人以外の起用はあり得なかった。上原ひろみ。アメリカの有名音楽大学バークリー音楽院在学中の'03年にデビュー、以後人気と実力を合わせ持つ女性ジャズ・ピアニストとしての評価を確立。2月に新作『TIME CONTROL』を発表し、この4月には日本人で初となる3年連続NYブルーノート公演が決定しているジャズの新世代を代表する存在である。本文を読めば席亭のジャズに対するアンビバレンツな感情は判ると思うが、通常のインタビュー・モードと異なる席亭の思考回路が作動、恐らく上原ファンも読んだことがないような生々しい発言を引き出すことに成功している。だが同時に「現実を見ろ!」と言い続けてきた席亭に対して、現在のジャズや世界情勢、彼女が体験した9.11の真実(今後席亭対談でこれ以上のリアリティある発言は出ないのではないか?)、そして現在最も重要なジェンダーの問題等の現実を彼女が鋭く突き付けているのも見逃せない。席亭対談史上最もハードコアな内容ですが、是非とも大いに楽しんで下さい!(プロデュース&構成:吉留大貴)
音楽のジャンル分けには疑問があるかもしれない
平野:まず、僕は上原さんの音楽に対して凄く“違和感”があるんです。僕は現在62歳の全共闘世代、政治の季節を過ごす中で、ジョン・コルトレーンを神様だと思い、そこから第三世代の苦しみや貧困や戦争と平和の問題を引き摺りながら存在していたような4ビート・ジャズが凄く好きだった。だからそれらの問題を全部なかったことにして、ただ気持ちいいイージー・リスニングであればいいというようなCTI系フュージョンが台頭したことでジャズから離れてしまった。僕はずっとジャズにはマイナーであって欲しかったんだけどね。もうひとつ、僕は昔荻窪ロフトというライヴハウスを経営していて、そこはジャズもロックもフォークも演っていたんだけど、赤字続きでジャズ系の出演をやめたトラウマがある。もっと言うと、僕はそれからジャズを封印していたのかもしれない。
上原:今までのお話を聞いていると、私の音楽お好きじゃないですよね(笑)。
平野:いや、あなたのやっている音楽は僕の主張するジャズじゃないから理解できないと言うほうが大きいんだよ。それはあなたの本(『サマーレインの彼方』)の中に出てくる、生ピアノの上にシンセサイザーを乗せたら怒り出したヨーロッパのジャズクラブのマスターと同じですよ(笑)。上原さんの全アルバムを聴いて確かに心地良くは聴ける、でも半分以上はイージー・リスニングとしての心地良さとして感じられてならない。ところがあなたの音楽の中には色々な要素や可能性も不思議なことに感じられる。だから僕はあなたがジャズともロックとも呼びたくない新しい世界を作ろうとしているのかなとも考えるんですけどね。ちょっと難しいか(笑)。
上原:まず凄く嬉しいのが、好きの反対は無関心だと思うんですよ。だからこうして言いに来てくれること自体有難く思っています。それで私自身昔からずっと考えていたことがあるんです。例えばマイルス・デイヴィスは彼の本や資料や映像とかを見ていると、その当時彼はジャズというジャンルをやっていたと思っていなかったんじゃないでしょうか?
平野:「マイルストーン」なんて正にその通りの音だよね。
上原:それはジャズだけじゃなくて、クラシックだったらドビッシーでもラベルでもベートーヴェンでもいいけど、彼らはクラシックを作ろうと思っていたわけではないですよね。バッハの時代まで行くと宮廷音楽家の問題も出てくるわけだけど、基本的には後付けでバロックと呼ばれ、ロマン派と呼ばれたに過ぎない。じゃあジャズにしても、モダン・ジャズとは、ハード・バップとは誰が名付けたのか? 恐らく演っている本人ではないですよね。多分リスナーがカテゴリーとして何かに当てはめたほうが聴きやすいとか、CD屋さんがジャンルがないとお店の何処に置いていいか判らないとか理由はあるんだろうけど、そういったことが凄く不思議だったんです。私がコルトレーンを聴くのは、ジャズが聴きたいからではなく、コルトレーンの生命に触れたいからです。言い換えると生命体が宿っている音楽に触れていたいだけなので、確かにいつもジャンル分けには疑問を持っているかもしれないですね。
平野:そこで難しいことがひとつあって、僕はマイルスの音楽に生命体が宿ったのは、単に音だけが原因じゃないと思うんだ。彼はブラックパンサーに寄付したり、マルコムXと関係があったり、ジャズが持っていたアメリカの反抗の歴史を体現していた存在だったわけじゃないですか。そういった現実を認識して現在のジャズやクラシックの人は音楽を奏でているのかと考えてしまうわけ。むしろそういった意識を捨て去った鑑賞用音楽、飲み屋のBGMが一番ふさわしいみたいなね。それはそれで問題はない。でも僕にとって音楽は、現実をしっかり見つめて挑戦し問いかけるものであって欲しい。ライヴハウスの経営者として、そんな音楽をもっともっと育ててゆきたい。もしそれが出来ないのなら、僕はもう音楽を仕事としてはやらないだろうね。
私には“毒”のあるジャズを演奏することは出来ません

上原:さっき凄く気になったんですけど、「ジャズはマイナーであって欲しい」とおっしゃってたじゃないですか。そういうジャズ好きの方って、たくさんいますよね。
平野:笑っちゃうぐらいいるよね(笑)。
上原:どうしてなんですか?
平野:結局、僕らの高校時代とかに坂本九とかみんな歌っている時に、クラスで4、5人いるわけよ、あんなの聴けないって言ってジャズを聴くのが。昔の僕はそれが恰好良いと思ってたの。そのマイナーな状況の時に、皆が知らない、大衆受けしない時に、この音楽は俺達だけが知っているのが嬉しかったというかさ。
上原:でもそれって、本当に良い音楽は万人に判るわけはないということになりません?
平野:そう! 本音としてはある(笑)。それは俺達世代の美学なんだよ。メジャーになると興味なくなるから売れて欲しくないというぐらいの意味ですよ。そんな価値観が今通用するとまでは思ってないからね(笑)。でも正直言って若いバンドの追っかけの女の子も、僕達とそんなにメンタリティは違わないよ。マンガ家でも相撲でも頂点に行くプロセスが好きな層っていつの時代もあるわけ。それは粋がっているだけかもしれないけど、でも否定までは出来ないでしょう。
上原:その音楽自体が繁栄して欲しいとは思わないんですか?
平野:いや、繁栄するところまでは支持するんだ。
上原:繁栄したら興味ない?
平野:それは僕らにとっては“堕落”だから、そこでリアリティは失くなるよね。
上原:いや、私いつも思うんですけど、ジャズだけじゃなくて、インディーズの時代のほうが良かったよねみたいなことってよく言われるじゃないですか。ロック・バンドが、小さいライヴハウスから日本武道館でやっただけで、本当に音楽が面白くなくなることってあるんでしょうか?
平野:そこはあなたもこれから絶対ぶち当たる壁なんだけど、例えばレコード会社の意向があったりするでしょう。
上原:私の場合はそれは全くないです。私はアメリカのテラークという会社に所属していますけど、制作のイニシアティヴは私が全て取るということを前提にした契約しか結んでいませんから。だからレコード会社はレコーディングが終わるまで私が何を作るか全く判らずに、終わって音楽を聴いてビックリするんですよ。確かに大きな会場にバンドが移行すると、ライヴハウス時代を観ていた人にとっては近い距離感が失くなって淋しく感じるのは判るけど、それだけで本当に世の中に迎合して売れたのかなって思うんです。それはマイルスだってやろうとしていたことじゃないですか。マイルスはジャズをもっともっと広げて、大衆に聴いて欲しかったからこそ、当時のジャズマンからは想像出来ないような派手な格好をしていたわけですよ。彼が音楽だけのことを考えていたら、それこそボロボロのシャツでジーンズでも何でもいいはずです。あそこまで自分自身をトータル・プロデュースしたということは、マイルスはかなりビジネスのことを考えていなければあり得ないですよね。ジャズという素晴らしい音楽を、一般大衆にとりあえず聴く興味を持って欲しい。その為には何が必要かを常に考えていたんじゃないかな。音楽的にロックの方向に進出したことも含めてですよ。でもマイルスは絶対に迎合しなかった。自分のアートを曲げなかった。私はその考えには凄く共感します。
平野:…ところが、僕らの世代はそうなった後期マイルスは駄目なんだ(笑)。“広げたい”という気持ちがいつしか“受けたい”に変わったというかさ。彼を最後に観た筑波万博のライヴで、上原さんの言う“生命体”が彼の音楽には感じられなかったから、僕は離れてしまったんだ。音楽って何か害があったり、毒があったりするから面白いってところがあるじゃないですか。例えばセロニアス・モンクのぶっ飛んだ和音なんて毒そのものですよ。でもそれを俺のスタイルはこれだと決めて、自分の信念を貫いたようなことは僕にとってただ受けるということなんかよりも、ずっと尊いことに感じてしまうんだ。
上原:私は人にイージーに聴けるものとして音楽を作ったことは全くないです。偶然に自分の中から聴こえてきたメロディが聴きやすかったかもしれない。でもこれを聴いたら人が納得するだろうなとか、受けるだろうなと思って曲を作ったことはないですよね。そうやって音楽を作り続ける先に、人がイージーに聴けるのとは違った形で、魂が震えるような曲が出来る境地に到達するべく常にやっているんですけどね。
平野:何かあなたと話していると、僕達とは違っていて凄く幸せな時代に育ってジャズを演っているような気がするんです。だから“毒”が出せない?
上原:その通りですよ。私、昔あるジャズ評論家の人に、「マリファナを吸ってないとジャズは出来ない」と言われたんです。私はマリファナもやらないし、タバコも吸わないからその意味で出せない音があるのは仕方ない。最近、昔ドラッグ中毒だった人がどんどんクリーンになってヨガとかやってるから、ジャズもクリーンになっているんです。音楽ってその人の生活が反映されているから、お金もらっているのか判らない、起きたら人の家みたいな状態から生まれる混沌とした音楽を、私に求められても確実に無理ですね。だから私はよくジャズ雑誌で秋吉敏子さんと同じアメリカに渡ったことで比べられるんですけど、秋吉さんのなさってきた苦労に比べたら、私のしてきた苦労なんて本当にミソッカスみたいなものですよ。1ドル=350円の時代に、電話もインターネットもない、男女差別や人種差別を乗り越えていってアメリカで認められた苦労は、私が今からお金を払っても味わえないことです。平野さんが好きでいられるような毒のある混沌した音楽は、多分ドラッグ中毒になって、10年ぐらい娼婦やっているのにお金がない状態でも出来るかどうか。私はそんな状態にはなりたくないです(笑)。それに今NYに住んでても全然凄くなんかないです。秋吉さんの時代と違って、日本食はあるし、電話でもネットでもいつでも日本と繋がれるから淋しさもたいしたことない…って幾ら言っても雑誌に載らないんですけど(笑)、その中で反骨精神を持って音楽にハングリーでいられるのかは昔よりももっと難しくなっている。だから日本では黙っていても新幹線のチケットも取ってくれるし、お迎えも来るような、お姫様のように扱ってくれますけど、世界をツアーで回っている時は、ツアー・マネージャーも付けずに、全部飛行機やホテルの予約も自分1人でやっているんです。アメリカもプロモーターさんがしっかりしたところだけではないので、500人のホールに14人しか集まらない時もある。それは自分にとって若い間にやるべき最低限必要な修行だという気持ちがあるからなんですよ。
世界でツアーをしていると“死”の近さを感じずにはいられない

平野:僕は対談をやる際に必ず訊くことがあって、それは9.11NY同時多発テロの話なんです。あの時NYへ向かう3番目の飛行機でアメリカに行ったぐらい衝撃だった。僕にとってあれは21世紀になって起きた新しい戦争と認識するし、未だにそのショックも消えていません。それから僕は9.11以降の現実の中でどう表現しようとするのか多くの表現者に問いかけることを、自らのライフワークにしようと決めたのかも知れない。あなたはあの9.11をアメリカで体験していますよね。あなたはあのアメリカの怒りと悲しみをどのように体験したのか、今日そのことを訊きたかったのもこの対談を企画した大きな意図でもあるんです。
上原:9.11の時は私はまだボストンに住んでいたんです。私が在籍していたバークレー音楽院も急に閉鎖されました。友達がワールド・トレード・センターで働いていて、後に生きていたのが判りましたけど、その時は気が動転してしまいましたよね。TVを付けても、ビルが壊れた映像しか流れていなかった。ミュージシャン仲間も多かったんで、その日の内に追悼コンサートがあるから弾きに行かないかと誘われました。でもピアノを弾いてて何とも言えない気持ちでしたよ。悲しみとも、苦しみとも違う、吐き気に近い感情があって……。
平野:その時の演奏ってどうでした?
上原:……ほとんど音が弾けなかったですね……。無駄な音を出しちゃいけない気持ちになったし。人があれだけ亡くなって、人間って何だろう、何を自分はやりたいのかということに凄く向かい合わなきゃいけなくなったというのはありますね。
平野:そのライヴを観てみたかったな。あの体験の後、何か変わったことってありますか?
上原:凄くいろんなことを考えるようになったんです。確かに9.11で人がたくさん亡くなって、メディア的にも衝撃的な映像でしたよね。アメリカはあの事件でも結局映画を作ってお金を儲けるわけなんですけど(笑)。世界を回っていると内戦や宗教戦争ってもっと小さな規模で何十年も続いていて、9.11以上の人が亡くなっている。9.11を特別視して、そこで死んだ人達は見過ごしていいかと言ったら、それもやっぱりおかしいですよね? ひとつのところに募金するとそれだけを問題視して、他を捨てているような気がして最後は判らなくなってしまった。今も中東、イスラエル、インドネシアとかに行くと、ホテルでもボディ・チェックやセキュリティ・チェックは空港並みに厳しいし、向こうのプロモーターと話しているとホテルの斜め前で爆破があったとか出てくることもあります。凄く“死”が近いんですよね。それで海外のフェスに行くと、マシンガンを持った人達が突然私達が乗った車の中に入ってくることだってある。そんな経験を積んでくると、自分の音楽に対する責任がとても大きくなってくる。中途半端な気持ちでやったら、聴いてくれる人に失礼ですよね。インタビューとかでもあるんですよ。「挫折はありましたか?」とか「スランプはありましたか?」とか、そんな質問をされること自体がおかしいですよね。こんなに幸せに、こんなに普通に生きている中で、挫折やスランプなんてあり得ないですよ。だからこそ中東の人に演奏が終わった後、「今日まで生きてて良かった」と言われた時、私も生きてて良かったと思いますもんね。この人に聴いてもらえて良かったって。
音楽は世界を変えられると信じています
平野:僕はどこかで音楽を聴く時に勝負という感覚がある。それはただ音を聴くだけではなくて、ジャズを聴く時は黒人の抑圧の歴史を考えることまで含めてなんだけど。でも基本的にジャズのイージー・リスニング化は、もう変わらないのかな。
上原:私は1ライヴ毎勝負していると言い切れますけどね(笑)。それに黒人が抑圧されていた時代に比べたら微々たることだけど、アメリカでジャズをやる上で、女性であって、インストであって、アジア人というのは三重苦って言われていて、これが普通ならお客さんが誰も観に来ないパッケージなんですよ(笑)。この前バンド・メンバーも言ってたけど、ジャズをやるならまず黒人、黒人が雇えなければアメリカの白人、それがダメならヨーロッパ人、その次のランクでようやくアジア人というぐらい下なんです。それで女性はヴォーカルならOK、でもインストは女性なんてあり得ないって今もあるんです。自分のライヴだったら数年やってきてかなり状況は変わってきましたけど、フェスとかで新しい場所に行った時は、パッと私を見たら今も何か面白くなさそうという印象になるって判っているんですよ。私は向こうの人に比べたら凄くちっちゃいから、1曲目からガツンとやらないと終わっちゃう。そこから60分間勝負する。そこで或るフェスでここ10年史上CDが一番売れたということも凄く嬉しかったですけど、そこまでになるには相当の圧迫感はありましたよ。気持ちの上ではとにかく聴いて欲しい、相手の首根っ子をつかまえてゆくぐらいでないといけない。それをやるには自信がなかったり、責任を持てないものは出せないですよね。その上で自分は好きじゃないというのは仕方がないですけど。ただそんなレヴェルでもないもっと下らないことってやっぱりまだあるんですよね。今、アメリカ人の中でアジア人の女性って大人気なんですよ。アメリカの女性に比べて、一歩下がって大和撫子な気質が求められている。それでいて映画女優のルーシー・リューやツャン・ツィーとか見ても判るけど、小さめだけどホットな女の子だというのも判っている。だからまずライヴに行ったら、人によっては何処のホテル泊まってるのとか、何処の部屋にいるのとか、全くミュージシャンとして見られてないことってあるんですよ。電話番号を訊かれたら、それにセッションする為じゃなく、別の目的なんだっていう抑圧は今もある。物凄く頭に来るけど、演奏するまでは何も言えない。他にもバンドの大部屋が控え室の時には、トイレで着替えるしかないという状況もある。そういった小さなことでイライラするのもあるけど、それを変えるのは音楽で納得させるしかない気持ち良さもありますよね。白黒は音楽でしか付かないですから。自分がそこでどれだけ男女差別についてとか、人種差別について思想を語っても、音楽が良くなかったら誰も話を聞いてくれませんしね。
平野:でも今はミュージシャンも、音だけではなく話すことまで含めて表現になっている時代だよ。ジャズも60年、ロックも50年もの歴史があって、クイーンもマイルスも話すことで検証するしかない。今はそれぞれのエキスパートの情報の蓄積はあるから、それと合わせて男女差別の問題を語ることも不可能じゃない。それも含めてあなた自身で語る必要性もあると思うんだけどね。
上原:おっしゃって頂いたことはとても有難いとは思いますけど、世界の現実では難しいと言うしかないですよね。女性と男性がどう共存するかというのは、戦争や政治よりも大きな根元的な問題になってるじゃないですか。でも私は男性が子供を産めるようにならない限り、少なくとも仕事の上での平等は無理だと思う。また何をもってして平等とするかという問題は更に難しいですから。私にしても子供を産むということがあれば、お母さんとして一緒にいてあげたい。じゃあその間音楽活動をどうするのか、ツアーは今のようには出来なくなるけど乗り越えなくてはならない壁が幾つも出てくるのも予想出来ますよね。だけど私は女性としての生き方もちゃんと貫いた上で音楽を続けるともっともっと違うものが出るんじゃないかというのも含めて楽しみだという、自分にとってのワクワクもあるんですよ。
平野:僕なんかはそこでもう一発破天荒なスタンスのほうが面白いと感じるけどね。だからあなたは矢野顕子と一緒に演奏出来るのかな。僕にはそれが何かそこまで調和の方向に行かなくてもいいのにとも思うんだよね。
上原:矢野さんは子供を2人育ててきたんですよ。それが男の人にはどれだけ大変なのか判ってないです。その子供が不良にならずに育って、あれだけの自分の音楽世界を作り上げて、毎年ずっとNHKホールでコンサートが出来るということは、普通の男性アーティストが自分の世界を作り抜くのとは根本的に違うんです。それは強く言いたい。そこを男性は全く判ってない!(笑)
平野:何か怒られちゃったな(笑)。でもさ~、上原ひろみは矢野顕子じゃないじゃん。僕はあなたに27歳の今のスタンスで立ち止まって欲しくないだけの話なんですけどね。あと、音楽は世界を変えられると思いますか?
上原:変えられると思います。
平野:遂に初めて言い切る奴が出た! ミック・ジャガーが「音楽は戦争を止められない、ちょっと自殺したいと思っている人を止められるぐらいだ」とか言うじゃないですか。でもそうじゃない?
上原:そうじゃないです。何事も積み重ねだと思うんですよ。いきなり何かやっただけで世界が変わるかと言えば違うでしょうけど、自殺したいと思っている人が逆に人を殺したりすることもあるわけで、一つ一つ積み重ねてゆけば大きな力になりますから。「塵も積もれば山となる」と言うじゃないですか。諦めるのは簡単ですよ。
吉留:僕からも一つお訊きしたいんですが、平野さんが経営する新宿ロフトは昨年30周年を迎え、様々なジャンルのミュージシャンを輩出してきました。現在生ピアノは置いていないんですが、何らかの形で条件がクリアになれば、こんなとんでもないオヤジが作った店ですが(笑)、オファーがあれば出演って考えてもらえますか?
上原:それは、お互いが相思相愛になれればね(笑)。