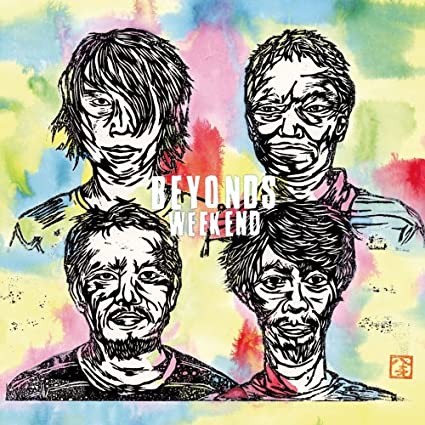瞬間の感情を切り取った全く新しいサウンド
──レコーディングは、健さんとは盟友関係にある吉村秀樹さん(bloodthirsty butchers)の紹介でフリーダム・スタジオのエンジニア、植木清志さんとタッグを組んだんですよね。
谷口:ええ。ヨーちゃんが紹介して下さって、ブッチャーズの最新作のような音にできたらいいなと思って、勇気を振り絞って植木さんにお願いに伺ったんです。
岡崎:とてもやりやすい環境でしたよ。植木さんのセンスと人間性なら任せられるなと思ったし。
谷口:こちらが思っていた以上に深い仕事をしてくれたと思いますよ。大事な音の録り方を熟知されている方でしたね。
岡崎:ちょっと感情に走った演奏をしても、そこを活かして上手く瞬間を切り取ってくれるというかね。普通のエンジニアなら、少し音を外したら「もう一回」となるんですよ。そこを植木さんは「今のは凄くいいテンションだったから残しておきましょう」と言ってくれる。そうやってテイクを積み重ねてアナログ的な手法で音を作っていったから、今っぽい音ではないと思うんです。音やタイミング、音程をずらすことも今は容易にできるけれど、そういうのは極力やめようと。それが結果的に良かったですね。
──リズムを全面に押し出したセッション色の強い「Tekkin #1 (a blue failure)」にはいきなり度肝を抜かれますよね。健さんの歌もラップっぽい感じがあって面喰らいましたよ(笑)。
岡崎:ラップね(笑)。それでもいいかもしれない。この1曲目は大自信作なんですよ。台本もない状態でセッションを始めて、あのまんま録ったんです。所々のギターは若干直したけどヴォーカルは一発録りで、アルバム全体を象徴しているような曲ですね。
谷口:唄い直しをするなと3人と植木さんから言われたんですよ(笑)。
──歌に入る前に健さんが即興で呟く“うかうか氷結”という言葉が個人的に思いきりツボなんですよね(笑)。
岡崎:僕もあれは好きですよ。プレイバックを聴いた時に、なんでこんなにドラムとジャストで入っているんだろうと思いましたから(笑)。みんなこのヴォーカルを活かすだろうなと思いましたよ。
──この曲は解散前でも再始動後でもない、紛れもなく全く新しいBEYONDSサウンドだと言えますね。
岡崎:でしょう? 置き場にも困った曲でしたけど、1曲目しかないだろうと全会一致で決まって。
谷口:うん、もう絶対に“この曲でこんにちは”でしょう(笑)。この曲なら後にどんな曲が来ても驚かないだろうし、後に続く曲も好きになってくれると思いましたから。
岡崎:ベーシックとなるリズム・ギターとドラムとベースは一発録りの音を全部使っているし、そこに足すべき部分は足して、ヴォーカルも唄い直すべき部分は唄い直したんです。曲によっては丸々唄い直しているのもありますけど、そのまま活かしているのも何曲かある。とにかく必要以上に直さなかったから、どの曲も凄く生々しい感じがすると思うんですよ。
谷口:今回は割と、他のメンバーから唄い直して欲しいというリクエストを受けたケースが多かったですね。
岡崎:唄い直したほうがいいのか、活かしたほうがいいのかの意見はみんなに出してもらったし、基本的には全曲ヴォーカルを入れて一発で録ったんですよ。スタジオに全員が揃わない時期も結構あって、たとえば健ちゃんがいない日には“このギター、OK出してくれるかな?”というプレッシャーを感じながら録っていたので、互いがそういう緊張感を与えていたのが好作用したところはありますね。
──「Over Shallow Sludge」は得も言われぬ昂揚感を与えてくれる曲で、アルバムのリード・チューン的な趣きがありますね。
岡崎:昂揚して唄い上げて欲しいと思って作った曲ですからね。今のBEYONDSがあれだけメロディックな旋律のある曲をどうサウンドで打ち出していけばいいのかをよく考え抜いて。イントロのギターは一度聴いたら忘れないフレーズだと思うし、僕は凄く自信があるんですよ。メロディックなものにしてもありきたりなものはもう飽きたというか、今のBEYONDSで新しいことにトライしたかったんです。
──そうした新しい試みは、BEYONDS流のダンス・ナンバーと言える「困惑のプリズム」でも如実に窺えますね。
谷口:あれは僕が弾き語りで唄っていた曲なんですよ。アレンジを善郎と2人で決めたんです。
岡崎:そう、その時はまだ8ビートだったんだよね。アレンジを2人で詰めている時に、スタジオでたまたまレッチリのライヴ・ビデオが流れていて、それを見てファンクっぽいアレンジにしたいと思ったんです。それで跳ねるようなリズムで不協和にギターを弾いてみた。
谷口:亜人君は逆に、跳ねさ加減をなくして叩いていると言っていましたけどね。そういうのも面白いですけど。
──健さんの唄う“somehow”という言葉の後に亜人さんが“ハッ!”と掛け声で応じるのは、居合い抜きのような切迫感がありますね。
谷口:“ハッ!”にするか“ウッ!”にするかだけで2時間ずっと議論していたんですよ(笑)。
岡崎:本当は“ウッ!”にして空気で音を出したかったんだけど、それだと音が録れないので“ハッ!”になったんです(笑)。ちょっと祭りっぽい感じに仕上がりましたね。

プライドを持って困難な現実に立ち向かう
──「periodicals」は、「New Frequency」という曲名ですでにライヴでも披露されていましたよね。
岡崎:「New Frequency」は“新しい周波数”という意味で、新しいBEYONDSを求めて僕が付けた仮タイトルだったんですよ。『シルトの岸辺で』を作っている頃から原曲があった古い曲なんです。
谷口:“periodicals”というのは燃えるゴミのことなんですよ。そのゴミは普段生活していると絶えず出てくるもので、“繰り返し起こること”に対する僕なりの見解なんです。
──メンバー各自が社会情勢や世事に対して一家言あるBEYONDSだけに、現代を象徴する世相の暗部をテーマにした楽曲も幾つか見受けられますね。表参道ヒルズに代表される商業施設の乱立に対して警告を促す「atomic cafe」然り、チェルノブイリ事故の放射能処理で尊い命を落とした人々に捧げた「リクビダートル」然り。
岡崎:4人とも皆、そうやって普段から社会に対して関心を持たずにはいられない気質なんでしょうね。だから、今のBEYONDSなら社会性を帯びた歌詞の曲があっても極々自然なことなんですよ。練習の半分は外に出てよくそんな話をしていて、すぐに2、3時間経っちゃうくらいだから。
谷口:「仮に東京に原発を置いたら、みんなはどう思う?」という話をしたりね。それが「atomic cafe」のモチーフになっているんです。まぁ、自分は本来そんなに俯瞰して洞察するような人間になるはずじゃなかったんですけどね…。でも、そうした僕の資質を善郎がポップに表現しようと意識することで上手くバランスが保てているんだと思います。
──「black september」は、同名のパレスチナの過激派組織と何か関連はありますか。
谷口:スピルバーグ監督の『ミュンヘン』(1972年に起こったミュンヘン・オリンピック事件後のイスラエル総理府諜報特務局「モサド」によるテロ組織「黒い九月」に対する報復を描いた作品)という映画が忘れられないんですよね。これは飛躍した言い方になりますけど、思想で世の中を変えるテロリズムの在り方は、ある意味で究極のロマンであり理想主義なんですよ。多分に破滅的ではありますけどね。だから僕は安易に暴力性を否定できないし、誰にでも暴力性はあると思うんです。暴力性がなくなったら、ルソーの理想郷じゃないですけど一列平等で暮らせて、日銭を稼ぐために働くという卑しい行為をせずに生きていける世の中になるはずで、でもそれは有り得ない。そうである限りはテロリズムを否定しきれないんです。もちろん、弱者に対する一方的な暴力は肯定できませんけどね。
岡崎:テロリズムを起こさなければならない状況に何故陥っているのかを考えることが大事だと思うんですよ。それが議論されないままに世界が動いているので、そこは凄くもどかしいですよね。まぁ、小難しい御託ばかりを並べていますけど、曲自体は凄くポップですから(笑)。
──「a proud man」の歌詞には魯迅の『阿Q正伝』が引き合いに出されていますが、自分を殴ってでもプライドを保って困難な現実に立ち向かう阿Qの姿に自らをなぞらえたのですか。
谷口:己の信念を持ってやっていることを周囲に笑われている阿Qの愚直な姿はもしかしたら僕達自身のことかもしれないし、逆に周囲の人達に対してもっと信念を持って行動してもいいんじゃないかと思える部分もあるんですよね。
──滑稽さの向こうに哀愁が充ち満ちているという点では、風車を巨人と思い込んで突進するドン・キホーテにも相通ずるものがありますね。
谷口:そうですね。中国の文学は示唆に富んだ物語が多くて、僕はこの『阿Q正伝』を読んで泣いてしまったんですよね。身近にいる友達のことが頭に浮かんで。「俺はこんなに凄い小説を書いているのに、芥川賞ひとつも獲れない」と言う友達がいて、僕は“そんな小説、誰も見向きはしないよ”と喉元まで出掛かっているのに、やっぱり言えないんですよ。実際、“こりゃ駄目だな”という小説なんですけどね(笑)。つまり、阿Qが銃殺されるのを傍観する民衆の一人が僕で、彼が阿Qなんですよ。その喩えを彼に伝えたらもの凄く怒りましてね(笑)。
──まぁ、自分達の力量のなさと動員のなさを観客のせいにするバンドも時折見受けられますけどね(笑)。
谷口:BEYONDSはそういうふうにはなりたくないですね。ちゃんと認められたいし、しっかり聴かせたいんですよ。ライヴでお客さんが僕達の音楽を聴いて“つまんないや”と思って帰ったとしたら、僕はそこで頭を抱えて恥ずかしくて恥ずかしくてしょうがなくなるわけです。
岡崎:それは表現者の端くれとして当然の思いですよね。今日のライヴが盛り上がらなかったのは客のせいだなんて考えるのは言語道断ですよ。ただ、みんなで盛り上がって行こうぜというのも、BEYONDSの場合また違うし。