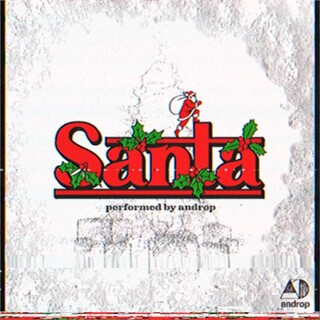早撃ちするガンマンのギリギリ感がたまらない
 ──カップリング曲の「スパゲティー・ウェスタン・ストーリー」は、THE RODEO CARBURETTORが従来得意とする物語性のある楽曲ですね。
──カップリング曲の「スパゲティー・ウェスタン・ストーリー」は、THE RODEO CARBURETTORが従来得意とする物語性のある楽曲ですね。
鍛治:この曲もツアー中に作ったので、勢いをそのまま出した感じですね。ライヴでやることを前提に書いた曲だったから、完成型が頭に描きやすかったんですよ。“セットリストのこの辺りに入れたら盛り上がるだろう”っていうのを狙って作りましたから。「glare」がかなり重いテーマを持った歌詞なので、「スパゲティー・ウェスタン・ストーリー」は逆に余り意味を持たせない歌詞にしようと思って。自分の中にある西部劇のイメージを膨らませて書き上げました。
──60~70年代に作られたイタリア製西部劇のことを日本では“マカロニ・ウェスタン”と呼ぶのが一般的ですけど、海外では“スパゲティー・ウェスタン”と言うそうですね。
鍛治:そうみたいですね。海外での呼び方をタイトルに使ったほうが単純に格好いいだろうと思ったんです。
──『荒野の用心棒』や『夕陽のガンマン』みたいな映画が昔からお好きだったんですか。
鍛治:最高ですよね。ガンマンが出てくる歌詞は今までも幾つかあったんですけど、自分でも好きな世界なんですよ。今回もスラスラ歌詞が書けましたからね。まず自分でストーリーを書いて、そこから抜粋していくやり方だったんですよ。まず、登場人物をノートの上のほうに全部書き出してみるんです。そこから一人一人のキャラクターや時代設定を細かく決めて、結末までを一気に書き上げる。それを曲として収めるために、重要な部分を抽出していくんです。曲が短くて余り詰め込めないから大変ですけどね。でも、そういう物語性のある歌詞は自分にしか書けないと思うし、自分にしか唄えないという自負があるんですよね。
──鍛治さんが西部劇を観てグッと来るポイントはどんなところですか。
鍛治:主人公とライバルが背中合わせに立って、10歩いてから振り向き様に早撃ちをするシーンにはグッと来ますね。あのギリギリ感が何とも言えない。そんなイメージの断片から妄想を膨らませて、曲を作り上げるんです。
──西部劇の居合い撃ちのギリギリ感というのは、メンバーがこよなく愛するバイクをアクセル全開で走らせる感覚にも近いんじゃないですか。
鍛治:そうかもしれないですね。3人とも期待や喜びに胸が高まる感覚が好きなので、作品も毎回進化を続けていくことを課題にしているんですよね。というか、いつも自ずとそうなってしまうんです。
──「God of Hell」と「Outblaze」のリミックス曲が収められているのも、シングルというフォーマットならではの新機軸ですね。こういう試みは以前からやってみたいと考えていたんですか。
鍛治:というよりも、世の中にロック・リミックスと呼ばれるものが余りないと感じていたんですよね。リミキサーに曲を投げて壊してもらうというフィードバックは多々あるけど、俺達は純然たるロック・テイストのリミックス曲を作りたかったんです。そこで、サウンド・プロデューサーと俺の二人三脚で楽曲を再構築してみたんですよ。ツアー中だったので、電話で自分なりのイメージを伝えてやり取りをして。テクノやハウスの要素を入れたほうが簡単だと思ったんですけど、そこを敢えてロックに聴かせるリミックスに仕上げたんです。
──2曲ともファースト・アルバムからの選曲というのは、何か意図があったんですか。
鍛治:それは偶然ですね。ただ、ライヴでは定番と言える曲だし、ファンにも馴染みのある曲のほうが面白いだろうと思って。
──第三者に任せるのではなく、鍛治さんの意志で原曲を解体して再構築させるところが面白いですよね。
鍛治:原曲をブチ壊すことには全く抵抗がないし、自分の用意した曲をメンバーの2人に聴かせて、音合わせをしたらガラッと曲調が変わることもよくありますからね。曲が格好良くなるのであれば、いつもそれが最優先なんですよ。ただ、それを全部人任せにするのではなく、1割でもいいから自分の考えをそこに入れたいんです。

俺達はロックを頑なに信じている
──こうした試みは今後も続けていきたいですか。
鍛治:そうですね。凄く刺激的な体験だったし、シリーズ化したら面白いでしょうね。リミックスだけでアルバムを1枚作ったら、かなり聴き応えのある作品になるんじゃないかな。
──リミックスに際して気を留めた点というのは?
鍛治:必要最低限のヴォーカルしか入れたくないというか、核となる部分を抑えつつ、どこまで新しい要素を採り入れられるかが課題でしたね。あと、若い人が車の中で爆音で聴けるような感じにしたかった。今の時代、ロックの若い人に対する訴求力が希薄になっているような気がして、個人的には凄く悲しいんですよ。“ロックにはこういうアプローチもあるんだよ”っていうのを若い音楽ファンに伝えたかったんですよね。
──たとえば20年前に比べると、ヒップホップやR&Bに押されて、ロックが少々軽んじられている傾向は否めないと思うんですよ。そんな中で、THE RODEO CARBURETTORのようにシンプルな3人編成でここまでストレートなロックを奏でるバンドも減ってきたし、その状況下でバンドがロックを追求する意義とはどんなところにあると考えていますか。
鍛治:ロックには50年以上の歴史がありますけど、たとえ使い古されたコードを奏でても、プレイヤーが違えば音も変わると思うんですよ。そのプレイヤーが生まれ育ってきた環境、胃袋を満たしたもの、眺めてきた景色が音に反映されているはずなんです。ギター、ベース、ドラムとそれぞれにプレイヤーのバックボーンがあって、それらが融合してひとつの音の塊になった時に何かが変わる。俺達3人はバカ正直にそのことを信じているんですよね。まぁ、俺がこんなことを言っても、若いリスナーにはピンと来ない部分があるのも一方では理解しています。それも恐らく正解なんだろうけど、俺達は頑なにロックを信じているんです。
──ロックとは本来凄く懐の深い音楽だと思うんですよ。あらゆるジャンルを貪欲に呑み込んでいるから、あらゆる表現が無尽蔵にできる。『glare』に収められたリミックス曲がいい例ですよね。
鍛治:言ってみれば、ロックって究極のミクスチャーですからね。異なるジャンルの要素を巧みに採り入れているし、その利便の良さは柔軟な発想ができる若いリスナーにも充分に訴えかけるものがあると俺は思うんですよ。
──これだけジャンルがセグメント化された昨今において、純真なまでのロックを奏でるには余程強靱な意志がないと初期貫徹できないんじゃないかと思いますけど。
鍛治:俺達がアマチュアの頃はエモ系のバンドが全盛期で、周りはそういうバンドばかりで肩身の狭い思いもしましたよ(笑)。凄く浮いてましたからね。でも、自分達のセンスを信じて今日まで突っ走ってこれたし、それはこれからも変わりないでしょうね。
──ヴァラエティに富んだ楽曲が収録された『glare』が示す通り、バンドがよりミクスチャーの方向に舵を切っているとも言えるんじゃないですか。
鍛治:そうですね。面白いことはどんどん採り入れてやっていこうと思います。
──11月から始まる“glare TOUR”は、意外にも初のワンマン・ツアーになるんですね。
鍛治:東京以外でのワンマンは初めてなんですよ。気負いもあるけど、凄く楽しみです。前回のツアーで各地を回った時に、「こっちでもワンマンを是非やって下さい!」という熱いリクエストも多々もらったので、やっと約束を果たせますね。
──ツアー・ファイナルは新宿ロフトで、シェルターのキャパの倍はありますけど(笑)。
鍛治:そこは臨むところですね。ロフトもずっと憧れのライヴハウスでしたから。欲を言えば、移転する前のロフトに出てみたかったですけど。今のバンドの状態も打てば響く感じだし、『glare』という自信作も作れたし、早くツアーに出てライヴを見せたいですね。もうテンションが上がりっぱなしですよ(笑)。このインタビューを読んで、少しでも俺達に興味を持ったら是非ライヴを観て欲しいですね。何かを必ず持ち帰れるんじゃないかと思います。そこだけは約束できますね。