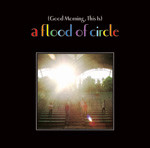2007年、間違いなく日本のロックの潮流を大きく変えるであろうルーキーの登場である。a flood of circle。メンバーは全員弱冠20歳、現メンバーに落ち着いてまだ1年半というキャリアの浅さを舐めて掛かると痛い目を見る。ジョン・ボーナムを彷彿とさせるドラムは闇雲に重低音を咆哮し、それに絡み付くベースはエネルギー密度の高い躍動を漲らせ、太く輪郭のあるギターは豪放でありながら繊細。そして何よりも記名性の高い渇いたヴォーカルが凡百のバンドとは一線を画した存在たらしめている。彼らの奏でる夜を焦がすブルーズが孕んでいるものは、点が曲線を描き始め、それが満ちる寸前の喜びと悲しみが混在したかのような昂揚感、そして狂気。ロックの本質が"対象"ではなく"対象との距離"を唄うことにあるのを彼らは本能で理解している。末恐ろしい若き才能が現れたものだ。(interview:椎名宗之)
いつものライヴに近い音をパッケージしたかった
──そもそも、同じ大学に通う佐々木さんと岡庭さんの2人がこのバンドを始めたんですよね。
佐々木:そうですね、元はと言えば。たまたま出席番号が近くて、音楽の話をするようになって、そのうち「一緒に曲を作ってみようよ」ってことになったんです。
──結成当初からブルースに根差したロックを志向していたんですか?
佐々木:ブルースというキーワードは特になかったんですけど、もともと聴いていたのがそういう音楽だったので、自分達の趣味を持ち合わせた結果ですね。それがたまたまブルース・ロック好きな人にヒットしたのかな、と。
岡庭:まぁ、似非ブルースみたいな感じですけどね(笑)。ブルースと言うか、黒人から影響を受けた白人が奏でるブルースが僕は好きだったんですよ。あとはやっぱり、ジョン・レノンが大好きで。ジョンのソロ・アルバムの内省的な感じに凄く惹かれたんです。まぁ、日本ではジョン・レノンって愛と平和の使者みたいに捉えられているから、ちょっと宗教みたいに思われるかもしれないけど。
──最初は2人でライヴをやっていたんですか?
佐々木:全然。2人でアコースティック・ギターを弾きながら遊んでいただけです。スタジオも入ったことがなかった。
──石井さんは、岡庭さんと幼馴染みだったんですよね。
石井:僕は専門学校でバンドをやっていて、ある時ふと岡庭にメールで連絡したんです。特に仲良くもなかったけど。
岡庭:仲は良かったよ(笑)。俺と亮介は2人で曲を作っていたんだけど、ベースとドラムがいなかったから石井を誘ったんですよ。ドラムは流動的で、ライヴをやる時はサポートで入ってもらってました。
──最後に加入した渡辺さんは、結成当初のドラマーからの紹介なんですよね。
渡邊:そうなんです。前任ドラマーの師匠が俺の師匠でもあった縁で。
──最初にa flood of circleの音を聴いた時はどう思いましたか?
渡邊:去年の正月にいきなりCDが送られてきて、“恰好いい!”と思って会ってみたらこんなヤツらで(笑)。
佐々木:音源を送った次の日の1月2日に初めてスタジオに入ったんだよね。その時に“全然曲を覚えてないじゃん!”ってムッとしたけど、今思えば昨日の今日だから当たり前ですよね(笑)。でも、僕と岡庭は、渡邊がボンゾ(ジョン・ボーナム)好きだと聞いただけでまず大丈夫だろうと思ったんです。プレイも良かったしね。
──そうして役者は揃い、バンド名をタイトルに冠した初の公式音源が完成したわけですが。ちゃんとしたレコーディング自体は初めてだったんですか?
佐々木:そうですね。リハーサル・スタジオで軽く録ってみたりはしていましたけどね。今回は戸惑うことのほうが多かった気はしますけど、エンジニアの杉山オサムさんの力とレーベル・スタッフの熱意に助けられて、何とか形にできましたね。
──オサムさんとはマンツーマンで作業を進めていったんですか?
佐々木:ええ。細かいところまで具体的にアドバイスして頂いたので、凄く有り難かったですよ。
──収録曲は、ライヴでもお馴染みのナンバーばかりですよね。
佐々木:ライヴで核を成す曲ばかりですね。特に「ブラックバード」は毎回ライヴでやってますから。全体的にアレンジ自体はいつも通りの感じで、コーラスを新しく録ってみたりした程度なんです。
──短期間で集中的にレコーディングを敢行したそうですね。
佐々木:その予定だったんですけど、生意気にも日程を延長させてもらいまして…。
岡庭:もうちょっと食い込みたかったんですよ。もっとできるはずだと思うところがあって。
佐々木:歌は特にそうでしたね。自分にしか判らないような細かい部分ですけど。
──最初はリズム録りから始めるパターンですよね?
佐々木:いや、一発ですよ。ベーシックは4人同時で一発。4人で同時に音を出しているので、その時に出ている音、なるべくいつものライヴに近い音をパッケージしたかったんですよ。特に気に留めたのはその部分ですね。
最後は“やりたいようにやるだけ”
──収録曲について伺っていきたいんですけど、1曲目の「ブラックバード」がバンド初のオリジナル曲なんですよね。
佐々木:ええ。すべては岡庭のギターの最初のイントロがあって、そこから広がっているんです。でも、ブルージーな曲を作ろうという意識は全然なくて、なるようになった感じですね。
──あのギターのリフがとにかく鮮烈で、一聴くしてすぐ耳に残りますよね。
岡庭:ギター・リフをこれだけパリッと弾くバンドも少ないんじゃないかと自分でも思うことがあって、そこはバンドの大きな特徴のひとつでもありますね。
──この曲が出来たのは佐々木さんと岡庭さんが2人でやっていた時だから、元はアコースティック・サウンドだったんじゃないですか?
佐々木:そうですね。イメージもこんな感じでしたよ。ギターを歪ませたらこうなるだろうと思ってましたし。
──ビートルズに同名のアコースティック曲がありますけど、“ブラックバード”は何かの象徴なんですか?
佐々木:具体的に何かを象徴しているわけではないんですけど、イメージにあったのは宮沢賢治の『よだかの星』なんです。宮沢賢治は小学校の頃から好きなんですよ。歌詞にはだいぶ時間が掛かった曲ですね。
──“ブラックバード”は不吉なことの象徴なのに、リフレインで叫んでいるのが「未来」という言葉で、このギャップが面白いですよね。
佐々木:先にその「未来」と叫ぶメロディから生まれたんですよ。一番最後のサビから大サビがあるんですけど、そこはよだかが死んだ後のイメージなんです。味噌を付けたような醜いよだかだけど、最期に死ぬ瞬間まで凄く逞しく生きようとする。僕らもそう在りたいと言うか。
──バンドの代表曲と呼ぶに相応しい曲ですよね。
佐々木:そうですね。最初に出来たのがこの曲で、最初に渡邊に聴かせて一緒に合わせたのもこの曲だったし。
──続く「ガラパゴス」は、サウンド的には「ブラックバード」の兄弟のような、リフで押しまくる曲ですね。
岡庭:「イントロがちょっとジミヘン(ジミ・ヘンドリックス)っぽくない?」と佐々木に言われたんですけど、実は俺、ジミヘンが余り好きじゃないんですよ。好きな曲もあるんですけどね。だから、ジミヘンを好きじゃない自分がジミヘンっぽいイメージで曲を作ったらこうなった、という…。
佐々木:ジミヘンが好きじゃない人が作ったジミヘン(笑)。だからジミヘンには程遠い曲なんですけど、僕の中ではスピッツとジミヘンは凄く共通しているんですよ。歌の部分は、最初はスピッツのイメージで作ったんですよね。
──エッ? スピッツとジミヘンの共通点というのは?
佐々木:まず歌がいいし、メロディもいい。ジミヘンはギター・ヒーローですけど、歌の持つポピュラリティの高さや曲の完成度はどちらも凄いと思うんです。だから、僕の中では凄く似てる部分がある。スピッツが黒っぽいという意味ではないですよ。大衆性の高さです。まぁ、単純に昔からどちらも熱心に聴き込んでいるのもあるんでしょうけど。
──「ガラパゴス」にはどんな意味が込められているんですか?
佐々木:唄っていることはだいたいどの曲も一緒で、この曲もそうなんですけど…司馬遼太郎さんが何かの本の中で「考えごとは夜にするな」と書いていて。「夜に悩んでも何も始まらないから、陽の高い明るいうちに悩め」と。それをウチの父親に高校の頃から言われていて、頭にこびりついているんですよ。いくら考えまくっても最後は開き直るだけと言うか、やりたいようにやるだけだ、ということをどの曲でも基本的に唄っています。「ガラパゴス」の歌詞もそんな感じですよ。
──「歌は刺青だ」という、いろんな解釈のできる言葉が耳に残りますけど。
佐々木:そうあって欲しいですね。基本的に言いたいことは同じなんですけど、表現方法をその都度変えているので、そこは聴いた人が捉えた解釈にお任せしたいと思っています。