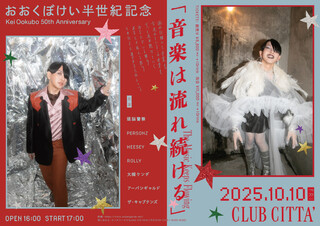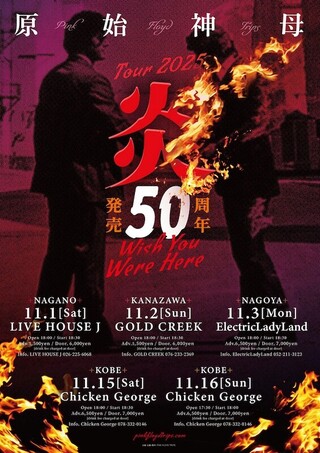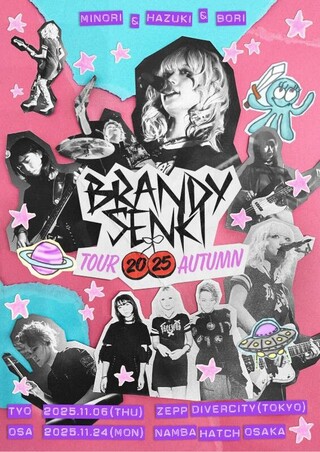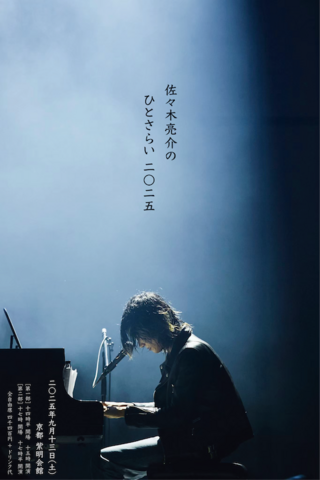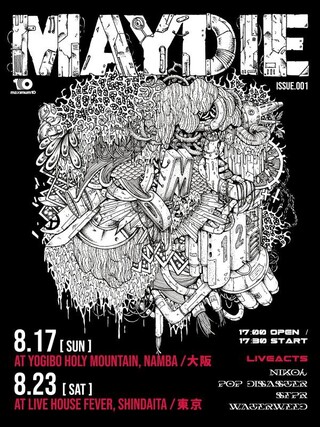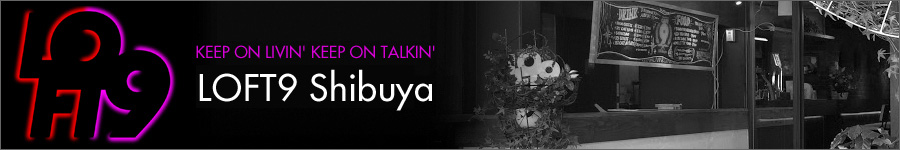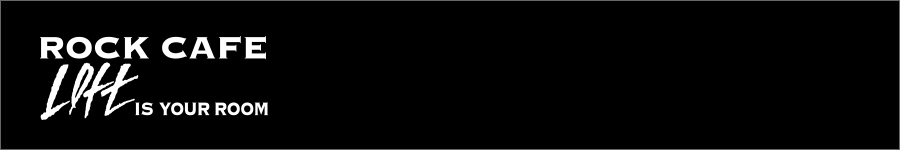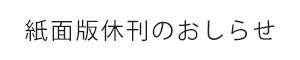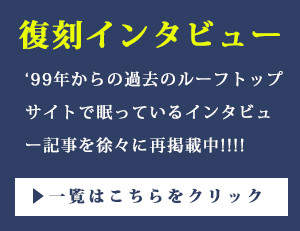タブーなもの、不可侵なものがなくなった
──「The Eternal Allergy」は“オ〜オオ!”というインディアンの雄叫びを思わせるコーラスが印象的で、とりわけ逞しいエネルギーに満ち溢れた曲ですね。我々のDNAに擦り込まれている太古のリズムを呼び起こすかのようで。
ナベカワ:もうエジプトの壁画系ですよね(笑)。何かの本で読んだんですけど、“音楽=リズムである”という一文を見つけまして。歌はその副産物的なものだ、と。人類最古の音楽って手拍子のリズムとかで、メロディがないじゃないですか? だからリズムは否応なしに人を高揚させるんだなと思って、そこからずっとリズムを追求しているところが自分の中ではありますね。曲を作る時もリズムから作るようになったし、そういうところは余りロック・バンドっぽくはないのかもしれないですね。
──2曲目の「Ghostwriter」は腰にクる跳ねたリズムが心地良い、強烈にソウルフルなナンバーですね。
ナベカワ:あれは完全に似非ファンクですね(笑)。だんだん自分達の中でタブーなもの、不可侵なものがなくなってきたと言うか、ファンクとかレゲエってやっちゃいけない音楽だとそれまでずっと思ってたんですよ。
──先行シングルに収録されていた「What Went Wrong!!!」もニューウェイヴの匂いを残したレゲエ・ソングでしたよね。
ナベカワ:ええ。あれで自分達でもやっていいんだと思えるようになって。「Ghostwriter」は最初、みんなでふざけて“デレデレデーッデッデ”ってドリフの「ヒゲのテーマ(DO ME)」をスタジオでやってたところから始まったんですよ(笑)。「ヒゲのテーマ」を自分達なりにやったらああなったという。
──ははは! 「ヒゲのテーマ」は我々30代にとって生まれて最初に出合ったソウル・ミュージックですからね(笑)。
ナベカワ:そうですよね(笑)。ヒゲダンスも『8時だョ!全員集合』だから、これもまた土曜日に繋がるんですよ。
──決して一筋縄で行かないBANDWAGON流レゲエ・ソングは、今回「John Graham Mellor」という曲で確立された感がありますけれども。
ナベカワ:そうですね。最初から最後までレゲエのリズムのままだと面白くないし、そこからどんどん曲調が変化していくのが自分達らしいと思いまして。
──ファンクもレゲエもヘンに神聖化することなく、軽やかなスタンスでロックとして消化/昇華しているのが如何にもBANDWAGONらしいと思うんです。
ナベカワ:ええ。あと、誤解を恐れずに言うといわゆるパクリっていうのも気にならなくなってきたんですよ。パクリと言うよりサンプルとして扱っていると言うか(笑)。「John Graham Mellor」にしても、CLASHの「Revolution Rock」のドラム・パターンをそのまま使ったりしてるんで。そこを突っ込まれても逆に有り難い感じなんです。気付いてくれて嬉しいし、そういうところを今後もっと上手にやっていきたいですね。
──BANDWAGONの場合は原曲に対する深い愛情が滲み出ているから聴く側もニヤリとするし、決して甲○バンドみたいじゃないですから(笑)。
ナベカワ:ははは。凄く大袈裟なことを言えば、「もう新しい音楽は出てこない」とか昔から言われてるじゃないですか? 確かにロックが生まれた時ほどの変革は今後迎えられないだろうと僕も思いますけど、その中で如何に自分達が楽しんで遊べるかと言えば、そういうサンプル的視点なのかなっていう気がするんですよ。吉田拓郎も「16小節まではパクリじゃない」って言ってましたからね(笑)。最後の「Urggggh!!!」も、『タッチ』の主題歌をみんなでやってみたところから始まってますから(笑)。
──ははは。土曜日から日曜日に移りましたね(笑)。
ナベカワ:聴いてみるとストイックさとかが印象として残るかもしれませんけど、やってる本人達としてはゲラゲラ笑いながらレコーディングしてるんですよ。4曲目の「It's A Closing Sentence」にも、最後にZIGGYの「Gloria」のメロディそのままのフレーズがありますから(笑)。
──遂に月9まで行きましたか(笑)。
ナベカワ:土曜から「Blue Monday」まで一気に(笑)。自分の原体験としての理想郷みたいなものは、やっぱり'80年代から'90年代初頭にかけての日本なんですよね。あの頃はインターネットもまだ普及していなかったから、海外からのカルチャーも微妙に間違って伝わってきたじゃないですか? あの間違い具合を出したかったんですよね。ネットがなかった時代って、今振り返ると牧歌的でいいなぁと思いますよ。
──海外と誤差があるぶんだけ、こちらの妄想を許してくれるのりしろがありましたよね。海の向こうのニューウェイヴの勃興も、日本のフィルターを通すと本田恭章になるわけで(笑)。
ナベカワ:ははは。イギリスで起こったニューウェイヴと日本で言われるニューウェイヴって全く別物なんじゃないかと最近思いますね。日本では音楽的にまとめようがないからメディアが使った便利な言葉だったんじゃないか、と(笑)。僕がニューウェイヴと感じた日本のバンドは有頂天を筆頭に、いわゆるナゴム系のバンドでしたね。ケンカは弱そうだけど口が立つ感じと言うか(笑)。




ナベカワミツヨシのカルチャー・アイコン
──ナベカワさんの原体験として深く心に刻まれている、'80年代から'90年代のカルチャー・アイコンというのは?
ナベカワ:そうですねぇ…音楽に関してはやっぱりCLASHしかないですね。本で言うと、初めてちゃんとした分厚い単行本を読んだのが村上龍だったんですよ。『コインロッカー・ベイビーズ』上下巻を当時付き合ってた彼女に貰って、そこを入口にして『限りなく透明に近いブルー』とかを読んだり。今の村上龍は文化人みたいで余り面白くないですけどね。映画は『キリング・フィールド』ですね。カンボジアの内戦の混乱を描いた作品で、未だに一番いい映画だと思ってます。最後にジョン・レノンの「Imagine」が流れるんですけど、オンタイムではないにせよ曲が時代に反映する瞬間を描いていると言うか、歌の力を思い知らされましたね。凄く強烈なイメージのある思い出深い映画なんですよ。
──なるほど。当時LOFTに出演していた日本のバンドとかはどうですか?
ナベカワ:イカ天が始まるまでの日本のバンドの状況が一番生々しいですね。イカ天はいわゆる自主制作というのを商売にした悪の根源だと思ってるので、その直前の時代。僕の中でバンドの活動方針や在るべき姿の理想はあの時代なんですよ。具体的に挙げると、NEWEST MODELが出した最初の2枚のアルバム(『Senseless Chatter Senseless Fists』『Pretty Radiation』)には色濃く影響を受けたし、あとは16TONSとか。あれがちょうど僕が中学を卒業する時くらいですね。
──2年前にLOFT/PLUS ONEで行なわれた『「レア盤対決vol.1」〜80年代日本のPUNK編〜』では、確かDOUBLE BOGGYSをフェイヴァリットに挙げてましたよね。
ナベカワ:そうですね。あの頃はもうジャンル的に多種多様でしたけど、今と違って棲み分けがなくて凄く渾沌としてましたよね。当時はどんなジャンルでも分け隔てなく聴いていたし、どんなバンドを聴いてもショックの連続でしたよ。僕が住んでた横浜には7th AVENUEくらいしかライヴハウスがなかったから、『宝島』で全部情報を得てました。背伸びしてLOFTに初めて行ったのが16歳の時で、確かMAGNETSが出てたと思います。それまでに得ていた情報では恐い所というイメージがあったんですけど、意外と普通のお客さんが多くて、“あ、こんなものなのか?”って思った記憶がありますね。だから願わくばANARCHYやARBが全盛の時にLOFTに行きたかったですよね。MODSは外見的なイメージも思いきりCLASHに近かったですけど、僕としては田中一郎さんがいた時のARBが凄くCLASHっぽいと思ってたんですよ。「Tokyo Cityは風だらけ」のカッティングの多さとか。
──そういうナベカワさんの幅広いカルチャー的素養を考えると、あらゆるジャンルを呑み込んだBANDWAGONの懐の深さがよく理解できますね。
ナベカワ:メンバーの文化的背景はそれぞれ違うと思いますけど、ドラム(ツジユウイチ)が蒲田出身で、僕とベース(アキモトタカジ)が横浜、ギター(イケダケイスケ)が新宿とか小田原に住んでたんです。みんなに共通するのは、テレビ神奈川(TVK)の影響が凄く強いってことなんですよ(笑)。映像としての音楽情報は『ミュージックトマト』や『ファンキートマト』とか、そのほとんどがTVKからでしたね。当時、夕方5時から横浜そごうの地下で伊藤政則氏や大貫憲章氏が“ミュートマ”の公開収録をやってまして、イケダ君は水曜日にやってた伊藤政則氏のメタルの日、僕は木曜日にやってた大貫憲章氏のパンクの日に学校帰りよく見に行ってたんです(笑)。
──ははは。神奈川県民にとってはツバキハウスの『LONDON NITE』や『HEAVY METAL SOUNDHOUSE』よりも、TVKの音楽番組のほうが圧倒的に生々しかったですからね(笑)。
ナベカワ:そうですね。当時は今みたいにスカパーとかもなかったし、自分の中で映像としてのアーカイヴみたいなものは同年代の人と比べても多いと思いますね。あと、DVDで出た『ライブ帝国』のARBとか、歴史的価値も凄く高いと思うし。…あ、それで思い出しましたけど、今回PVも撮ったリード曲的扱いの3曲目「Accidents, Don't Be Panic!!!」、これは思いきりSHEENA&THE ROKKETSの「レモンティー」です(笑)。タイトルを付ける前の最初の呼び名は「めんたいビート」でしたから(笑)。まぁ、どこがめんたいビートなんだよって話なんですけど、とにかく最初のテーマが大事なんですよ。そこで自分達のモチベーションを上げることが大事と言うか。笑える要素を含んだネタがひとつあれば、そこから一気に作曲が進んでいくので。