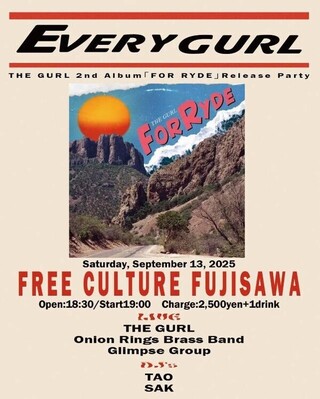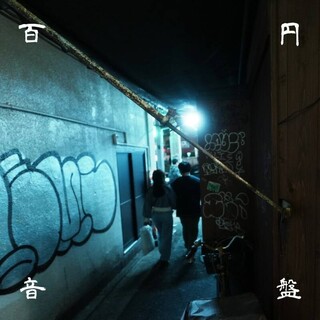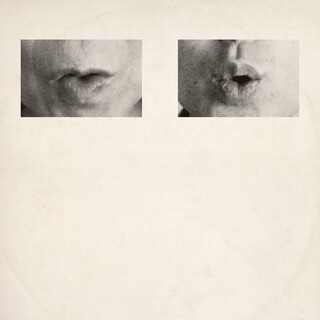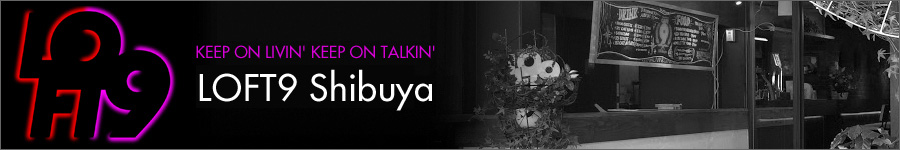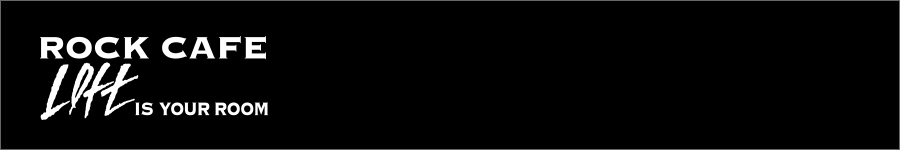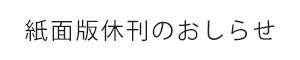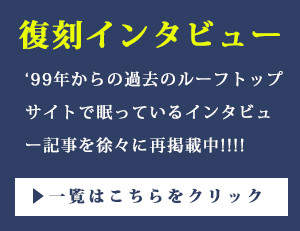誰もがもがいて暗闇のなかでドアを叩いてる
──(笑)。個人的には、「孤独な戦場」という曲にグッときたんですよ。今の話にも重なるんだけど、どんなにくだらない世の中でも、“生き延びてやる!”って気持ちは忘れないっていう…。
菅波:……違和感と葛藤、ですね。それを忘れないで生きていったほうがいいと思う。違和感や葛藤は、生きていく上でのパワーにもなると思うし。
──うん、パワーにするしかないですからね。
菅波:うん。違和感がなくなった時は、自分が、全体の一部になってるってことだから。それがイヤだったら、“孤独な戦場”で戦っていくしかないですね。
──疲れますけどね。
菅波:疲れますね。だけど、みんな同じようなもんだと思うんですよ。もがいて、暗い場所でドアを叩いて…。
──まぁ、栄純さんの場合は“ドアを叩く”にしても、ギターっていう武器がありますからね。このアルバムのギターも恰好いいし…。
菅波:ありがとうございます。
──今回は、どんなテーマを持って臨んだんですか、ギターに関しては?
菅波:や、そんな大袈裟なものはないんですけど、“まともに弾く”ってことですね。当たり前のことを当たり前にやるっていうか…。
──ん? どういう意味?
菅波:すげぇ根本的なことなんだけど、ギターを“ギャーン!”と鳴らそう、と。そういうレヴェルの話ですね。ギターを“ジャーン!”と鳴らす、とか、スネアを“パン!”と鳴らす、とか。そこは、突き詰めたいと思った。
松田:…判る、それ。ライヴをやると、痛感するよね。
──凄いバンドって、曲がいいってレヴェルを超えて、“ギターを鳴らすだけで恰好いい”ってこともありますよね。
菅波:うん、ありますよね。だから、そういうことですよ。
松田:それって、説得力の問題だと思うんですよ。ちゃんとした音として聴こえるかどうかっていうのは、曲の説得力につながってると思う。もちろん僕らは4人でやってるわけで、4つの楽器のバランスの問題もあるけど、それぞれがいい音を鳴らしていたら、それはきっと凄いものになるだろうっていうのはありますね。
──それは、ヴォーカルも同じ?
山田:うーん……今回のレコーディングで思ってたのは、気持ちよさ、ですね。唄ってる時の自分のマインドを気持ちいいところに持っていくこと。そういう心境でやれば、(歌が)小さくならないというか、聴いていても気持ちいいものになるだろうっていうのは、ちょっと思ってて。あとは、レコーディングに対する場慣れもあると思うし、体調管理なんかも必要ですけど。
──なるほど。その成果は、明らかですよね。歌に限らず、バンド全体の“伝える力”がかなり上がってるし。
松田:まだまだと思いますけどね、バンドとしては。もっともっと上がりますよ。というか、上がらなくてはいけないと思う。
山田:バンドの力が上がるっていうのは、技術だけではないから。そのことを忘れなければ、上がっていくはずなんですけど。技術、気持ちの込め方、そういうバランスも大事だし。
──でも、良い意味でバランスの取れたアルバムだと思いますよ、『イキルサイノウ』は。1曲目の「惑星メランコリー」(“俺達は害虫”)みたいに重い曲もあるけど、光とか希望もしっかり感じられて。
松田:そうなんですよね! 曲調もそうだし、内容もそうなんだけど、うまく行く時は全部がうまく行くんですよね。
──あと、このアルバムの曲って、アマチュア・バンドがコピーしたくなるような気がする。いろんな意味で、凄くバンドっぽいから。
松田:いいですねー。どんどんコピーして、ビデオとか送ってほしい。僕らより巧かったらイヤですけどね(笑)。
──(笑)。
松田:そういう時は、「確かに演奏は巧いけど、こういう曲は作れないだろ?」って言いますけど。
岡峰:大人げないなぁ(笑)。
松田:(笑)。でも、コピーするのはいいですね。自分達もコピーをしてたこともあるし、そこから自分達のやり方を築いていくと思うから。僕らの曲がその第一歩になると嬉しいです。
──『イキルサイノウ』は、THE BACK HORNにとって“自分達のやり方”を確立できた作品かもしれませんね。
松田:そうですね。まだまだ“途中”ですけど…。