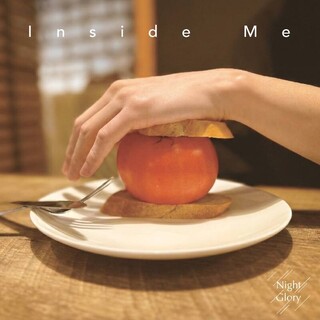"ソロ・アーティスト"中尾諭介、誕生!In the Soupのヴォーカルであり顔役の中尾諭介が、10年近く自ら温めてきた音世界をソロ・ワークスとして描出することになった。かねてからジョイントを願っていた名アレンジャー・瀬尾一三氏をプロデューサーに迎えて生み出されたミニ・アルバム『好きです』は、バンドとはまた違った彼のパーソナリティが色濃くにじみ出た好盤に仕上がっている。抑揚の効いた節回しにどこか懐かしく琴線を震わせるメロディ・ライン、どこを切っても中尾印なその歌声を最大限まで活かした絶妙なアレンジメントと、聴き所は多い。一連のソロ活動の渦中で彼は何を思い、見つめたのか──その心意を問うた。(interview:椎名宗之)
ささやくように唄ってみたいと思った
──何はともあれ、今回のソロ・プロジェクト始動の経緯から聞かせて下さい。
中尾:きっかけとしては、瀬尾一三さんとの出会いが一番デカイですね。瀬尾さんは僕にとって憧れの人だったんです。田舎にいた頃からずっと聴いてた長渕 剛さんや中島みゆきさん、吉田拓郎さんとかのCDに“編曲=瀬尾一三”っていうクレジットが必ずあって。で、もしソロ活動ができるんであれば『瀬尾さんと一度一緒にやってみたい』と、最初は冗談半分で伝えて…。
──まさか実現するとは思わず。
中尾:うん。何せかなりの大御所だから。でも、渋谷のホテルでご本人と対面した時に『2、3ヵ月だけど、その間で良かったら一緒にできるよ』と言われて、チャンスやと。これは運命やなと思って決めましたね。
──実際に瀬尾さんと仕事をしてみてどうでした?
中尾:唄う人を引き立たせるための作業を一からきちんとやっていく方なんです。バンドの時は、4人で持ち寄った曲をみんなで広げてぶつけ合っていく形だけど、今回はソロの重みっちゅうか、一人にのしかかってくるもののデカさとか、覚悟とか、そんなことを教えてもらってた気がしますね。曲を持っていくと『まだ君は爆発しきれていない』と指摘を受けて、そこから発奮したりね。
──アコギやハーモニカでクレジットはありますけど、基本的には今回“ヴォーカリスト”に徹したという感じですか?
中尾:そうですね。でも余り“ヴォーカリスト”っていうカタカナに馴染みがないんですよね。比重的にはそうだけど…“ヴォーカリスト”っていうよりも、“僕”とか“俺”とか、“オイラ”?(笑) オイラの家まで遊びに来てくれよ、と。
──このミニ・アルバム全体のコンセプトは?
中尾:せっかく瀬尾さんと一緒にできるなら、全体的にささやくように唄ってみたいと思った。自分では割と“ワーッ”とか“イヤッホーッ”ていうのが好きなんだけど、それとは全く逆のことをやってみたいなぁと。それは瀬尾さんにも最初に伝えて。今回はいろんな人の曲を取り上げてるけど、選ぶ時にそういうのが基準になりましたね。
──確かに“ワーッ”とか“イヤッホーッ”と強く叫ぶよりも、こうした抑えた唄い方をすることで聴き手との距離感が狭まったと思うし、より強く生々しく歌が伝わる気がしますよ。
中尾:そう言ってもらえると嬉しいですね。バンドでやってる時は公園でみんなで遊んでる感じだけど、今度のは一人の部屋で一人で唄ってる感じを出したかったんですよ。一人の人に対して唄ってるというか。それは瀬尾さんも僕も共通 の認識としてあった。
歌の表現により幅ができたことが嬉しかった
──そうは言っても、バンドと違って抑えて唄い上げるのはなかなか難しかったんじゃないかと思いますけど。
中尾:難しかったですね。長渕さんの〈東京青春朝焼物語〉とかは特に。
──ああ、このカヴァーは中尾諭介のパーソナリティと非常に合致してますよね。
中尾:やっぱり埋め込まれてますよね。好きですねぇ、こういう世界。これね、“ささやくよう唄う”なんて言っておきながら、最初は瀬尾さんの前で大熱唱したんですよ(笑)。
──(笑)オリジナルのアレンジャーだし、気持ちは判りますよ。
中尾:アコギを弾きながら、大声で“今日から俺~ッ!”って(笑)。僕は凄く自信があったし、長渕さんの歌やけど自分が唄えばどんな歌でも自分の歌になると思ってたから、それを全部ぶつけて。そしたら瀬尾さんに『長渕 剛の亡霊が見える、それはモノマネだ』って言われて。それはショックやったですね。でも、長渕さんは長渕さんで拓郎さんやブルース・スプリングスティーンとかからの影響があったり、拓郎さんやスプリングスティーンはボブ・ディランからの影響があったり、みんなそうなんだと。『そこから自分だけの歌を探すんだ』って言ってくれて。
──ディランはディランでウッディ・ガスリーやピート・シーガーからの影響があるしね(笑)。
中尾:だから、そこからいろんな調整をして“借り物ではない自分自身の歌”っていうのを瀬尾さんと探してアルバムに入れましたね。唄い方もグッと抑えるようにして。それで、トラックダウンの時に聴き返してびっくりしたんですよ。“こんなやり方があるんだ!”“こんな唄い方できるんだ!”って思った。デカイ声で唄わないと伝わらないっていう固定観念が吹っ飛びましたね。歌の表現により幅ができたことが嬉しかった。こうして全体を通 して聴くと、やっぱりもっともっと出せる場所が自分にはあるんだっていう意欲が湧いてきますね。“ここで終われないよ!”っちゅうのが(笑)。
自身を投影しやすかったフォークソング
──全体を通して聴いて感じたのは、紛うことなき中尾諭介の“声”が残響するんですよね。記名性の高い声というか、ワーッと来るアレンジにも声が埋もれていない。瀬尾マジックといえばそれまでなんだけど、最終的にはきちんと歌声が際立たっている。
中尾:素晴らしいアレンジでしたね。唄ってても気持ちよかったですよ、凄く。あと、〈相合傘ダンボール〉で一番最初にハーモニカを入れた時の雰囲気とか、凄い充実感でしたね。瀬尾マジックにかかると、ちゃんとあのハーモニカの音色になるんですよ。
──1曲目の〈こころ〉とかも、シンセサイザーの盛り上がり方が“いかにも!”な瀬尾節で、かなりグッときますよね。
中尾:うん。僕にとってはかなり貴重な体験ですよ、これは。
──この〈こころ〉以外にも、〈忘れないでください〉〈好きです〉と小田切 大さん作詞・作曲の曲が3曲選ばれてますね。
中尾:新宿フォークっていうインディーズ・バンドの方なんですね。小田切さんの〈好きです〉を知り合いを通 じて聴いて、実際にライヴを観に行ったら面白いと思って。名前も“新宿フォーク”だから、自分がやることと通 じるなぁと思ったし、CDを聴いても凄く通じる部分があって。僕がこれを唄ったら面 白いなぁと思って、唄わせてもらいました。これは今までにない世界観ですよね。
──諭介さんにとってはやっぱり、70年代のフォークソング/ニューミュージックが一番の音楽的ルーツとしてありますか?
中尾:他にもいろいろ聴いてはいたんですけどね。でもやっぱり、自分でギターを弾き始めた頃によく演奏したフォークソングっていうのが…簡単じゃないですか、コードが。それプラス、歌詞が判りやすいから心が凄く注入しやすかったりして。その10代の頃の喜びとか快感とかね、そういうところに今また戻ってる感じはしますね。
──自分自身というか“オイラ”を一番投影しやすかったのがその手の音楽だった?
中尾:やっぱり手身近でしたしね。一番簡単やったし。Fとか難しいコードは二の次で、とりあえずそれっぽい音を出して、それに声を乗せると何か嬉しかったりして。
──アルペジオとかスリーフィンガーとかを駆使する、妙に巧い奴とか周りにいませんでした?
中尾:いたいた。でも僕はそれでも負ける気せんかったですけどね。そん時に何か知らんけど、何の引け目も感じなかったですね。それも不思議やけど。自分に凄い自信があったんですかね。
──どれだけ完璧にコピーする奴がいようが、そいつらには絶対負けないオリジナリティがあったとか。
中尾:喜びですよ。簡単なEマイナーとか弾いて、“バンッ”と即興でも何でも自分で出せるっていう。自分にしか出せない空気がそこに生まれるっていうのが面 白かった。