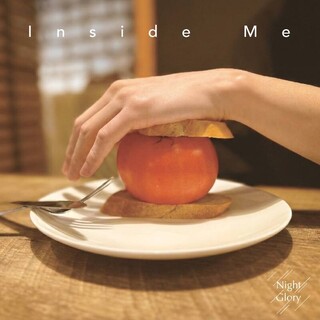中尾諭介アンドニックバッカーズの『東京インディアン』の裏ジャケットにはこんな但し書きが明記されている。「このCDは、著作権法上にのっとっていない使用は禁止されています。この音源権利者の承諾なく、お友達や親・兄弟に貸してあげることは大歓迎です。そのあかつきに、あなたの街のライブ会場でその皆様とこの曲達をわかちあえたら大感激です。ライブで会いましょう!」。無論これはアートワークにおける彼一流のユーモアでもあるのだろうが、中尾諭介はこの文面通りのことを本気で考えているに違いない。ホームグラウンドであるイン ザ スープの傍らで精力的に続けてきた2007年以降のソロ活動の集大成である『東京インディアン』には、青春との訣別を果たし、大人になるための裁きを受けた彼の逞しい姿が投影されている。自ら退路を断ち、誰かにぶら下がって生きることにケリをつけ、道なき道をひとりで転がり続けていく覚悟。あるいは、歌を唄うことで得られる生の実感や社会と関わることの意義。これまでに彼が発表してきた作品からは感じられなかった真に迫った表現がこの『東京インディアン』には通底している。呆れるほどのバカ正直が丹誠を込めて生み出した無垢な歌に、もう迷いはない。中尾諭介のスットコドッコイな音楽人生第2章、クライマックスはこれからだ。(interview:椎名宗之)
もっと強いものを提示しなきゃダメなんだ
──目下、イン ザ スープは活動休止中なんですよね。
諭介:ライヴは去年の5月で止まってますね。グルーヴァーズ兄さんやザ・ユースと一緒に吉祥寺のGBでやったライヴが今のところ最後です。
──バンドを休んで、裸一貫からソロ・アクトを始動させたのはどんな経緯があったんですか。
諭介:特に深い意図はないんだけど、自分の歌と生ギター1本だけで勝負してみようと思って。
──意地の悪い言い方になりますけど、バンド形態が煩わしく感じたとかは?
諭介:煩わしいことは全然ないけど、ちょっと冷却期間を置きたいと思ったのは事実です。バンド形態はパワーがドカーン!と出るから好きやし、今も中尾諭介アンドニックバッカーズっていうバンドをやってますからね。まぁ、自分たちの気持ちの中で向かうところがそれぞれになっていったっちゅうのが結構あるとは思ってます。でもそれでバンドが終わるわけやないし、今はたまたまそんな時期なんだろうなっていう感じですね。
──本格的にソロ活動を始めたのは2003年で、瀬尾一三さんがプロデュースを務めた『好きです』というミニ・アルバムも発表したじゃないですか。今の表現形態はあの当時とはだいぶ趣が異なりますよね。
諭介:全然違いますね。瀬尾さんとタッグを組めたことは凄くいい経験になりましたよ。一度やってみたかった世界だし、実際にやってみて自分の足りない部分がよく判った。歌の本質的なパワーって言うか、より真実に肉薄してムダを削ぎ落とすことが大事なんだって言うか。どんな表現形態であれ、もっと強いものを提示しなきゃダメなんだと思い知らされたんですよね。ちゃんと転んでケガをしなければ判らないこともたくさんあるんだなと痛感しました。
──ニックバッカーズは諭介さんのために集ったバンドなんですよね。
諭介:まぁ、そうですね。各人はそんなふうに思ってないみたいだけど(笑)。僕が彼らを引っ張っているんじゃなくて、自分たちが諭介を引っ張ってやっているみたいな(笑)。
──イン ザ スープからKさん(草場敬普)が参加しているのは、慣れ親しんだベースの音が必要だったからですか。
諭介:それよりも、その人の持ち味ってことかな。あのベースがどうしても欲しいってわけでもない。結果としてはイコールなんだけど、その人となりっていうのが大事なんですよ。Kは僕以上にバカやし、それでいてしっかりしてるところもあるから。まぁ、そんなことよりも単純にまた一緒にやりたいと思ったのが一番の理由ですね。
──『東京インディアン』はバンド名義の作品ですけど、諭介さんのパーソナルな側面がより強まったことを顧みるに、これこそが真の意味で中尾諭介のファースト・アルバムだと思うんですよね。
諭介:その気持ちも判るんですけど、『好きです』を好きだと言ってくれる人は今も多いし、自分としては何とも言えないですね。
──ご自身でも手応えのある歌が揃ってきたからレコーディングに踏み切ったんですか。
諭介:別にプラプラしてたわけじゃないんだけど、ニックバッカーズの田中の大ちゃん(田中大介)に「CDを作ったほうがいいよ」って言われたんですよ。ケツを叩かれてようやく重い腰を上げたっていう。
──アルバムを作りたい欲求はそれまでになかったんですか。
諭介:僕自身、"アルバムを作りたい"っていう感覚が余りよく判らなくて(笑)。実際に作り始めるとその過程はやっぱり面白いし、みんなに聴いてもらいたいとも思うんですけどね。曲もちゃんと出来るけど、誰かにどうしても聴いて欲しいって気持ちは余りない。イン ザ スープの時も、曲出しの時に「何かないの?」って言われて出すケースが多かったし。
──諭介さんは昔からそういうところがありますよね(笑)。
諭介:自分ではサイコーだと思ってるけど、人が聴いてどう思うのかな? ってところで、そんなに受け入れられるとも思わないですから。本来、そこまで謙虚な男ではないはずなんですけどね(笑)。
"東京"と"インディアン"への憧れ
──でも、曲作り自体は好きなんですよね? 『B-PASS』のネット連載でも"曲が出来た時はまだ先に行ける、誰かに聴いてもらいたいなと少しずつ思う"と書いていたじゃないですか。
諭介:うん。そんなに数が出来るほうでもないけど、自分でも"これだ!"と思える曲が出来た時は大袈裟だけど生きてて良かったと思いますよ。あと、人に「いいね」って言われたらもうちょっと頑張ろうと思う。イン ザ スープの『檸檬〜レモン〜』が出来た時は自分でも"これで行こう!"ってみんなを引っ張ったこともあったんですけど、それは稀なケースですね。自主性も余りないし、基本的には引っ込み思案ですから(笑)。
──と言うことは、真っ新なオリジナル曲が9曲も入ったアルバムを出すなんて大変なことじゃないですか(笑)。
諭介:そうですね。大ちゃんに「曲ないの?」って言われて作りかけの曲を出すと、大抵の曲を「いいね」って言って、そこから広げてくれるんですよ。それも大きかった。
──ああ、田中さんとの共作である『ココペリ』と『タクシードライバー』は作りかけの曲だったんですね(笑)。
諭介:そうなんです(笑)。
──アルバムの収録曲を追って見ていきましょう。まず、1曲目の『さらば、青春』には道なき道を突き進む堅い決意みたいなものを感じたんですよ。歌とアコギだけで唄われる"「終わっちまったのかな」一生言ってりゃ壊れたオモチャ/いつまで昔話 引きずりながら生きてくつもりだい"という冒頭のフレーズは尋常ならざる切迫感もあって。
諭介:これまでずっと誰かにぶら下がって甘えてたところも、いよいよ甘えられなくなってきたと感じたからじゃないですかね。それがリアルな表現に繋がってる気はします。
──バンドを休止して、いよいよひとり立ちしなければという境地に達したと?
諭介:休止したっていう意識は余りないんだけど、今まで人任せにしていた部分とか、"どうにかなるさ"と一歩引いて見ていた部分があったんですよ。それが、ひとり親方みたいな感じで何でもかんでも自分でやってみると意外と気持ちがいいし、風通しも良かった。
──ステージにひとりで立つことは元より、ライヴのブッキングから本作のプレス発注まであらゆることを諭介さんが一手に引き受けているんですよね。
諭介:うん、そういう事務的なことまで全部。まぁ、たまに胃が痛むことはあるけど(笑)。『さらば、青春』はそんなふうに自分の意志で突き進んでいる実感を持てた時に出来た曲なんです。
──『東京インディアン』というアルバム・タイトルは『風うたう』の歌詞の中にある言葉ですね。
諭介:『風うたう』は晴れ渡った気持ちいい日に窓辺でギターを弾きながら作ったんだけど、何の苦もなく出来た曲なんです。いつも曲を作る時は心の深い部分まで潜っていくイメージで言葉を探したりするけど、これはまるで鼻歌みたいな感じで出来たんですよ。そういう曲があってもいいかなと思って。
──近代的な都市である"東京"とアメリカ大陸の先住民である"インディアン"という相反するニュアンスの言葉を組み合わせているのがユニークですね。
諭介:"東京"も"インディアン"も、僕の憧れなんです。"東京"は「天下獲ったろ!」みたいな意気込みで宮崎から出てきた憧れの都。"インディアン"は、『リトル・トリー』っていう本を読んだらインディアンの教えがしっくり来て好きになったんです。木とお喋りをしたくなるような本で、僕の中で思想的に一番強く共感できるのはインディアンの教えだなと思って。ウチの田舎は工場地帯だったから自然がたくさんあったわけじゃないけど、自分には波長が合ったんです。"東京"と"インディアン"、どっちも好きなのは矛盾してるなと最近気づいたんですよ。田舎に引っ込んでエコ暮らしみたいなことはいずれやりたいけど今はできないし、かと言って青山や六本木みたいな東京の最先端とされる場所を闊歩するのも性に合わない。そういう中途半端な自分を表すのにちょうどいいタイトルだと思ったんです。

"アーティスト"という肩書きへの違和感
──『ココペリ』はインディアン神話に出てくる妖精をモチーフにした曲ですが、ニックバッカーズのアンサンブルの妙味が楽しめる1曲ですね。ファンクを基調としたグルーヴがとにかく心地良い。
諭介:大ちゃんが手癖で弾いたフレーズをそのまま続けてもらって、即興で出来たような曲ですね。『風うたう』と『ココペリ』は無条件に楽しんで欲しい曲です。
──そんな和やかな世界観から一転、『東京12月』は恋人との別離を唄った憂いを帯びた大作ですね。
諭介:切ない歌ですね。自分にとって大切な人たちとの別れが重なるように起こった時に書いたんです。
──後々、中尾諭介のソロ初期における代表曲のひとつに挙げられそうな風格がすでにあると思うんですが。
諭介:自分の中ではいいポジションにある曲です。歌詞の頭に"2007年12月"っていう具体的な時期を示す言葉があって、『さらば、青春』の歌詞みたいなことを思う少し前の話なんですよ。
──歌とアコギとハーモニカだけでシンプルに奏でられる『祈り』のような曲を聴くと、歌の説得力が格段に増したことを強く感じますね。
諭介:ああ、嬉しいですね。普段ひとりでやるライヴはまさにこのまんまなんです。この曲はイン ザ スープでも何回かアレンジしたんだけど、"これだ!"っていうレヴェルまで行けなかったんですよ。ニックバッカーズでももうひとつで。ブッチャーズの小松さん(小松正宏:ブラッドサースティ・ブッチャーズ)がニックバッカーズで叩いてくれた時はかなり凄いことになったんですけどね。その時のライヴで一番聴いてもらいたいポジションに行くくらいの演奏で。
──"なんだか 叫ばなければ この僕がどこにもいなくなる"という歌詞がありますけど、叫んでいたり唄っていないと正気を保てないと感じることはありますか。
諭介:うん、ありますね。最近よく思うのは、こうしてずっと歌を唄い続けていると頭がおかしくなっても不思議じゃないなっていうことなんです。そういう道をこれからも歩いていくんだし、だったら自分の思いを全部歌にしたほうがいいなと思って。
──表現と向き合わざるを得ない人は、狂気という名の湖に張る薄氷の上を常に歩いているわけですからね。
諭介:誰もがそうなんじゃないですかね。最近そういう歌も作ったんですよ。『ヘイヘイホー』っていうふざけた歌をね。"みんなパープリンでしょ?"っていうカントリー調の歌なんですけど。某男性アイドルが公園で全裸になった時にインスピレーションをもらって、"みんなもこういうことあり得るよね?"っていうような歌で。
──うん、大いにあり得ますよね。それで思い出したんですけど、「誰もがアーティストなんだから、わざわざそういう呼び方は要らないんじゃないか」と以前ブログに書いていましたよね。"アーティスト"や"クリエーター"という呼称に違和感を覚えるという趣旨の内容で、個人的にも凄く共感できたんですよ。僕は"アーティスト"という呼称を使わずになるべく"バンドマン"や"ミュージシャン"という言葉を使うようにしているんです。
諭介:ああ、よく判ります。僕もイン ザ スープでデビューした当時、ラジオや雑誌の取材で"アーティスト"っていう言葉に引っ掛かりを覚えたんですよ。まぁ、受け流すようにはしてましたけど。青山とかを歩いていると、"クリエーター"と称したモード系の人たちと出くわしますよね。そういう人たちが何をやっているのかと言えば、外国の雑誌を切って貼っただけのことしかやってない。だから"クリエーター"の顔をしている人たちの一部に僕は属したくないんですよ。
──諭介さんは、自身の肩書きをどう考えていますか。"唄い手"とか?
諭介:うん、そういう感じですね。"シンガー・ソングライター"はちょっと荷が重い(笑)。
──ブログには"フォーク・シンガー"とありますけど。
諭介:ああ、それがちょうどいいです。それほどフォークに詳しいわけじゃないけど、ピッタリ来る言葉ですね。
──"ロック"ではないんですね?
諭介:ロックでもいいけど、ロックもちょっと荷が重いですね。四六時中ケンカしなくちゃいけなさそうだし(笑)。
こんな時代だからこそ唄い手が頑張らなくちゃ
──『空っぽ空地』は穏やかなワルツ調の曲ですが、アコーディオンが絶妙な味付けになっていますね。
諭介:これも『ココペリ』みたいに、ギターのオバッちゃん(小幡浩司)がリハの前に手癖で弾いてたのを広げていったんですよ。『空っぽ空地』みたいな軽やかな曲は、唄っていて気持ちがいいですね。
──歌詞にあるように、知らないことだらけだからライヴ・ツアーという旅を続けている意識がありますか。
諭介:ツアーでも毎日の生活でもそんな感覚ですね。まぁ、旅の途中で知らないことを知った時は純粋に面白いけど。ちょうど今、龍之介と大久保海太と一緒にツアーを回っていて、ふたりからはだいぶ刺激をもらってます。ギターをもっとちゃんと弾かなくちゃいけないとか、そんなレヴェルですけどね。
──そういった刺激は、イン ザ スープのツアーでも共演するバンドから散々受けていたのでは?
諭介:確かに。でも、当時は刺激を受けることに今ほど意識的じゃなかった。今思えばかなり心を閉ざしていたと思うし、誰かと友達になろうとかも思わなかったし。今は何でも知りたいと思いますけどね。
──そこはやはり、晴れてひとり立ちをした成果なんでしょうね。
諭介:自分で歩いてみることにした成果なんですかね。昔も自分では歩いていたけど、今は自分でやることも増えたから。
──自転車の補助輪が取れたみたいな感じですか。
諭介:そうですね。未だにフラフラ走ってますけど(笑)。
──『タクシードライバー』はラップ調のセリフを大々的に採り入れた、とりわけユニークなナンバーですね。
諭介:フォーク・シンガーとラッパーって凄く似てると僕は思うんですよ。イン ザ スープの『東京野球』の最初のほうにも"ゆらゆら揺れてる湯気が出そうな真夏の午後"から始まるラップっぽい部分があったし、自分でも好きな手法なんでしょうね。しかも、"ビルディングとビルディングの谷間"っていう『東京野球』にある同じフレーズをこの『タクシードライバー』にも入れちゃってるんですけど(笑)。まぁ、これで韻を踏んだり遊び心を採り入れられればラップになるんでしょうけど、伝えたいことを伝えるという意味ではフォークと余り変わらない気がするんです。
──不景気や国の政治を嘆くタクシードライバーに対する諭介さんなりの所感がセリフの部分で綴られていますが、諭介さんの歌には珍しく社会性を帯びた内容ですね。
諭介:それだけ歳喰ったってことでしょうね(笑)。子供の頃にオジサンやオバサンが政治家の悪口を言ってたのも思い出したんですよね。確かに政治家にも問題はあるだろうけど、いつも誰かのせいにして他力本願なんだなぁ...って言うか。
──諭介さんくらいの歳にもなれば、世界の政治経済の動向に目を向けざるを得なくなりますよね。
諭介:これだけ100年に一度の経済危機なんて叫ばれるとね。柳原陽一郎さんも言ってたけど、不景気になればなるほどウチらみたいな唄い手が頑張らなきゃいけないと思う。こんな時代でもずっと信念を持って音楽を続けていれば、いつかみんながこっちを向いてくれる気がしてる。それを信じて唄ってますね。
──「音楽で世界を変えてくださいよ」とタクシードライバーに言われて、"自分と誰かの気分なら変えられるかもね"と唄うところが諭介さんらしいと思ったんですよ。ジョン・レノンみたいに声高に叫ぶことはないけれど、最後に"世界と気分てのは そんなに遠くないとおもうよ"と締めるところに僕らも希望を抱けるし。
諭介:嬉しいですね。今ちょっとだけ鳥肌が立ちました(笑)。イン ザ スープでメジャー・デビューした時、せっかく全国にCDが行き届くなら世の中を変えるくらいの曲を作ったろと意気込んでたんですよ。それが『歌いたくない歌』とかだったんだけど、意外と世の中がスルーしていったから、"あれ?"と思って(笑)。今は世の中を変えるなんておこがましいと思うけど、人の気分は変えられるんじゃないかな、くらいは思ってますね。押しつけは好きやないから、余り大きなことは言いたくないけど。
──でも、諭介さんも長渕剛さんの歌に背中を押されて上京してきたようなところもあるじゃないですか。
諭介:うん。音楽を聴いて自分が変わるところもありますよね。水槽の中にインクが落ちてフワッと色が変わるくらいのものだと思うんだけど。
ちょっとでも希望があれば歌は出来る
──この『タクシードライバー』のように、メロディを薙ぎ倒すように言葉をまくし立てるのも諭介さんらしいスタイルですよね。
諭介:僕は余りメロディに執着しないんですよ。自分のことをメロディ・メーカーだとも思ってないし、言葉が勝手にメロディを連れてきたぜ、くらいじゃないと自分でも信用できないっちゅうか。
──曲先ではなく詞先のケースが多いですか。
諭介:いや、一緒ですね。一番いいパターンは詞と曲が一緒に降りてくる。『さらば、青春』はそんな感じで出来た曲のひとつです。最初の言葉とコードがバチッと来れば、その時点で自分としては"出来たな!"って思う。サビはどうでも良くて、とにかくAメロが信用できるかどうかが大事。
──『ガチャガチャ』は平易な言葉とメロディで唄われるリズミカルな小品といった佇まいですが、まるで童謡のような趣きもありますね。
諭介:そういう歌が好きなんですね。もうちょっと込み入った感じのことを唄ったほうがいいんだろうなとは自分でも感じてるけど、たとえばブッチャーズが"ドラム叩くんだー!"(『banging the drum』の一節)って唄ってるのを聴くと、僕は凄く解放されるんですよ。
──"「大人になるとつまらなくなるぜ!」/フォークシンガー教えてくれたけど/それはそうやとおもうよ/だって僕らをみればわかるもの"って、随分と自虐的な歌詞じゃないですか?
諭介:田舎に帰った時に、「大人になると打算的になるよね」って友達と話したことがあって。昔も打算的だったと思うけど、その割合が増えてきた。人を疑ってしまうようになったり、どうせこういうことなんやろなぁ...っちゅう諦めに似た気持ちを抱くことが多くなったり。まぁ、昔は人に対して過度に依存したり、期待したり、勘違いしてたんでしょうね。要するに、メチャクチャ世間知らずやった(笑)。でも、友達と話して出した結論としては、打算的で当たり前だろうと。打算的ばかりじゃ面白くないけど、そういう部分があって当然じゃん、みたいな話になって安心したんです。『ガチャガチャ』の歌詞は自虐的かもしれないけど、そういうのを吹き飛ばして3つのコードでガチャガチャしようぜ、決起してドーン!と行こうぜ、って最後は唄ってるんですよ。
──ドン詰まりの極みでも、ささやかな希望だけは忘れないぞ、と。
諭介:もちろん。希望が全くないと音楽にならないんじゃないですかね。言葉でネガティヴなことを言っていても、ちょっとでも希望があれば歌は出来ると思うんですよ。昔、石川県でやったライヴで泉谷しげるさんとご一緒させてもらったことがあって、楽屋で『好きです』の資料を渡したことがあったんです。そしたら泉谷さんがその資料をバーン!と投げて、「オマエ、カヴァーなんてやってんじゃねぇよ! 歌はメロディがあるから何を唄ってもいいんだよ! "死にたい"って普通に言ったらバカだけど、メロディがあれば"死にたい"って唄ったっていいんだよ!」って言ってくれて。何を唄ってもいいんだっていうのを泉谷さんが教えてくれたんです。
──『朝焼けミルク』はアルバムの最後を飾るに相応しい希望の曙光に満ちた歌ですね。なりたい自分になれなくて悶々としていた自分が"これが僕なんだ"とようやく思えたという歌詞と同様に、諭介さん自身もこれでやっと本当の意味でスタート・ラインに立てたように思えるんですが。
諭介:そういう解釈もできるんですかね。まぁ、歌詞で描いているのはいつも通りの何も変わらない朝なんですけどね。でも、朝の力って言うか、自分が生まれ変わる気持ちになれるのはインディアンにも通じると思うんですよ。
──『東京インディアン』を作り終えて、意識の変化や一本立ちできた感覚はありますか。
諭介:宿題はまだいっぱいありますね。今はもっとすげぇアルバムを作んなきゃダメだなと思ってますけど。昔、ある人に「そういう人のせいにする生き方はそろそろやめたら?」って言われた言葉が今も残ってるんです。僕はひとつのことだけに専念していれば全部がうまく行くと思ってたんですよ。たとえば、僕がステージ上で光みたいなものを爆発させれば何もかもがうまく行くと思ってたけど、実際はそんなことなかった。やっぱり、"人生レール"は自分で敷かなくちゃダメなんですよね。
──この先続く人生行路の道中でどんな歌を唄っていきたいですか。
諭介:最近よく思うのは、自分はアンテナみたいなものだなって。まぁ、いろんなものをキャッチしているはずなのに余り自覚がないんですけど(笑)。それでも『東京12月』や『さらば、青春』みたいな歌が出来ると、アンテナからパワーを放出する感覚になる。その瞬間に生きてる実感を覚えるし、この社会の中で僕みたいなオッチョコチョイがひとりくらいいてもいいだろうと思えるんです。僕のアンテナはCDを売ってナンボの世界じゃなくて、歌を聴いてもらえればそれでいい。だからライヴへ遊びに来て欲しいし、そこで歌を分かち合えたら凄く嬉しい。僕が音楽を続けている目的はそこなんですよ。