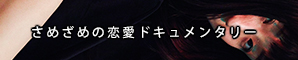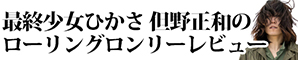「35年前、40歳、ドミニカに移住することになった時の思い出」(平野悠 著『セルロイドの海』より……」
この長いコロナ禍の中、繁華街にも闇営業の飲み屋にも行けず、年老いた自分は淡々とロックやフォークを聴きながらひとり過去の思い出というか総括に浸っている。
そうそう、長い76年の歴史の重みを感じながら、「あっ、こんなこともあったな」「あんなこともあったな」と感動に浸っている毎日だ。
ドミニカ共和国の思い出
沈みきらない北海の太陽を眺めながら、ちょっと寂しくなり、日本での日常を思い出す。やはりキラキラしてまばゆい矮小な新宿のネオンが懐かしい。そういう世界がイヤになったから、仕事を放り出して長い旅に出たり船に乗ったというのに。
私はふとドミニカで私の雇った女中との別れを思い出したていた。
一九八三年、私は四年間にわたる世界放浪の旅を終えたのだが、まだ日本に帰る気はなかった。
次の挑戦は、日本から遠く離れた外国に仕事を持って市民を持って暮らすことに挑戦した。旅人の時とは違い近隣から尊敬されパーティぐらいは招待されたいと思っての挑戦だった。
そこで、カリブの美しい島ドミニカ共和国で市民権を取り、日本から板前を呼んで日本食レストランをカリブ海に面した海岸に無理やりオープンさせた。japan sa no1と言われた時代だ。日本は愚かにもバブルに沸き返っているらしい。
国際的に日本の寿司や天ぷらが流行していたが、まだこのカリブの地域には日本食レストランがなかったのだ。日本から圧倒的に遠く、日本人が少ない地を選んだ。世界一美しいカリブ海に店を開くのが夢だった。
よく考えてみれば、こんな状況で成功するはずはなかったのだがただ夢が勝ったのだ。
当時のドミニカは政情が比較的安定していて治安もよく、レストランのオーナーでも銃を持たずに街を歩けた。カリブの海とドミニカ独特の音楽であるメレンゲが素敵な人口六百万(現在は800万)の小さな開発途上国である。当時の中南米の殆どの国は独裁政治だったから稀有な国だったようだ。当時のカーター民主党政権が小躍りしたりした。
この国で商売をするとなると最低限のスペイン語は喋れなければ仕事にならないので、毎日教師を呼んで一日十時間は悪戦苦闘し続けた。
現地の日本人商社会に入会した。天皇誕生日には大使館に招かれ、付近の金持ちの家庭にも招待されるようになった。
いわゆるこの地で市民権を得たということだ。市民権をゲットするには若干の賄賂が必要だった。
夢は実現したが、経営は赤字続きだった。ドミニカは貧しくても寿司を食べられるくらいのアメリカ帰りの金持ちはそこそこいたので、イケるかと思ったのだが甘かった。
さらには貧しい国ゆえ食料は輸入禁止だった。日本レストランで必要な醤油とか海苔とかわさび、日本酒はマイアミの日本人マーケットまで飛行機で買いに行かねばならず、さらには冷凍設備がないので毎日漁師に魚を突きに行ってもらうしかなかった。そうなると雨の日などは海が濁っていて魚が出せない。
寿司に必要な日本米は50年近く前に移民で入植した日本人農民から買った。所詮この国で日本食レストランを成功させるには無理があったのだ。
営業の中心を寿司から天ぷら、カツ丼、親子丼などに変えるしかなかった。
当初は張り切って、「俺はこの国で自分の生涯を終える」と意気込んだが、長い間の赤字経営は辛い。石油ショック以降だんだん街も危険になってきたので、五年後に私は完全撤退を決めて帰国することにした。
初めて住み込み女中を雇った
ドミニカに移住し、日本食レストランをオープンさせた私は生まれて初めて現地人の女中を雇うことになった。
私が借りていたフラットはカリブ海が見渡せプールやテニスコートもある。近くには世界的に有名なゴルフ場もあった。
フラットの門番に連れて来られた女中は、ガリガリに痩せ、身なりは圧倒的に貧相だった。名はマリサと名乗った。二十三歳だという。報酬は住み込みで月二百ペソ。日本円にして七千円程度だ。
面接が終わって私は彼女を車に乗せてダウンタウンに行って二百ペソを無造作に渡した。
「好きなものを買っておいで」
こう言って、戸惑う彼女を車から降ろした。
「下着も買っていいですか?」
マリサはおずおず聞いてきた。
「もちろん」と私は答えて海が見えるサント・ドミンゴの雑多なダウンタウンの車の中で待機した。
車のラジオからはメレンゲが激しく鳴り響いている。この音楽、この紺碧の海があるから、私はこの国を選んだのだと思った。
一時間ほどして、彼女はすばらしい笑顔で大きな荷物を抱えて戻って来た。フラットに戻る車の中でマリサが消え入るような声でポツンと言った。
「私は多くのお金持ちに雇われて来たけど、雇い主からこんなことをされたのは初めて」
彼女はそう言って涙を浮かべた。カリブ海の真珠のような涙だった。それから五年の間、私は彼女に家族同様に接し、彼女は私のスペイン語のいい教師になった。
私たちは恋人のように食事やディスコや映画に行った。女中と主人とは明らかに身分の差があり、小さなサント・ドミンゴの日本人社会の話題となったが、私は気にしなかった。
また、現地で女中を雇うということは、いかに物を盗まれないかを警戒監視することだったが、彼女は私の部屋から一ペソも盗まなかった。
私の経営するレストランは石油ショックの煽りを受けてさらなる赤字が続いた。それでもがんばったのだが、板前の共同経営者が先に帰国し、さらに私が連れてきた親友で元ミュージシャンの板前が自殺したことで、店を閉め帰国を決めた。
私はマリサと別れなくてはならなかった。あとはすべて日系人のマネージャーに任せ、車や店の財産は全て私の自称アミーゴたちに分けた。私は五年余りドミニカに暮らしたが何一つ持ち帰る気は無かった。お金に変える気すらなくしていた。
私の心の傷は深く、誰の見送りもなく独りサント・ドミンゴの空港にたたずむ姿は、自分らしいと思った。
自殺した友は、カリブ海を見渡せる丘の共同墓地に眠っている。いつか墓参りには戻って来ようと思っていた。ドミニカを発ったものの、すぐに日本に帰る気にもなれずに一週間ほど大好きなニューヨークに滞在し色々なパーフォマンスを見に行った。
三日目にドミニカの自称アミーゴから連絡があり、「マリサがフラットの荷物を全部盗んで逃げた」と言われた。秘密警察に頼んで追跡中なのだという。これは痛快だ。
「マリサよくやった。逃げろ! 絶対捕まるな!」
私はマリサに喝采を送り、逃げ切ることを祈りながら帰国した。
三か月ほどしてマリサが逮捕されたという噂を聞いた。
一時はマリサを日本に連れて帰ろうかとも思ったのだが、やはり無理であった。もう三十五年も前の話だ。彼女は今ごろどうしているのだろうか。