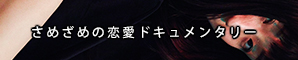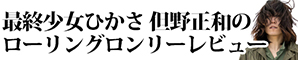60年代後半から始まった日本のロック、ポップス作りは、80年代前半で最初の到達を見せます。その象徴とも言えるフェスティバル、1985年6月15日『国際青年年記念ALL TOGETHER NOW』。今回も再結成の意味を追求します。(文責・牧村憲一)
洋楽の受容史=日本のポピュラー音楽の歴史
牧村:当時はっぴいえんどが所属していた風都市は、プロデュースの時代が来るという予見を持っていた。しかしながらその主張は早すぎて、音楽界界隈では充分に理解されなかった。大瀧さんプロデュースの〈ナイアガラ・レーベル〉は、エレック、日本コロムビアからCBS・ソニーへ、細野さんはクラウンでのティン・パン・アレーからアルファでのYMOへと展開してブレイク。そこからはっぴいえんど、さらにエイプリル・フールへと遡ると。
澤部:そうですね、エイプリル・フールにも何曲か日本語詞はあったけど、主な楽曲はまだ英詞ですもんね。
牧村:洋楽コンプレックスというか、洋楽のコピーだった時代からその影響を受容し、自分たちのものとした後に何を生み出したのか。先駆者は加藤和彦率いるサディスティック・ミカ・バンド、はっぴいえんど、さらにYMO。その先駆者たちが1985年に国立霞ヶ丘陸上競技場で行なわれた『国際青年年記念ALL TOGETHER NOW』で揃って再結成。


▲『国際青年年記念ALL TOGETHER NOW』のプログラム表紙と、はっぴいえんどの紹介ページ。
再結成したはっぴいえんどはなぜテクノだったのか?
──『国際青年年記念ALL TOGETHER NOW』のはっぴいえんど再結成の映像
澤部:これは当時、放送されたんですか?この後に細野さんの唄う「風をあつめて」、茂さんの唄う「花いちもんめ」と続くんですよね。
牧村:ラジオでのオンエアーがありました。はっぴいえんどの曲はメドレー形式でしたね。澤部くんとツイッター上で話をしていて、「1985年のはっぴいえんど再結成はなぜテクノだったのか?」というメッセージがありました。澤部説をまずは聞きましょう。
澤部:まず何より、松本さんがなぜシモンズを叩いているんだ? って話なんですけどね(笑)。はっぴいえんどが出てきた70年代初頭は、ロックというものがカウンターであったと思うんです。『THE HAPPY END』のブックレットでも彼らは演歌の対抗としてロック的なものをやっていたと語っていました。だけど1985年において再びはっぴいえんどをやる上で、ロック的な方法を取ることはもはやカウンターではなくなってしまった。だから新たなカウンターとしてテクノを取り入れたのかな?と僕は思ったんです。
牧村:カウンター、なるほど! その視点は今日まで持ってなかった。実は〈ニューミュージックのお葬式〉説というのがあって、プロデューサーの亀渕さんにとっても、またそうだったらしいんだ。ミカ・バンドはミカの代わりにユーミン、亀渕さんはまずユーミンに声をかけて、それでサディスティック・ユーミン・バンド結成。加藤和彦、高中正義、高橋幸宏、後藤次利というオリジナル・メンバーに坂本龍一が参加。はっぴいえんどの場合は、亀渕さんがまず大瀧さんに声をかけたんですね。大瀧さんから他のメンバーに話が伝わっていき、OKが出たんです。これ、サード・アルバムの『HAPPY END』の制作経緯と同じ構造で、『HAPPY END』も入口は大瀧さんだったんです。
澤部:アメリカへ行くという高田渡さんが大瀧さんに一緒に行かないかと話を持ちかけたんですよね。それから大瀧さんが他の3人にも誘いをかけたという。
牧村:大瀧さんも再結成を提案されて困ったとは思いますね。これは想像ですが、自分を説得する物語を作ったんじゃないでしょうか。それで〈ニューミュージックのお葬式〉という物語が生まれた。ミカ・バンドとはっぴいえんどが幕引きを務めて、佐野元春やサザンオールスターズといった新世代へバトンを引き継ぐ儀式を執り行なったわけです。大瀧さんは自分たちのやってことを自分たちの手で納める時が来たと考えて、出演する決心を固めたと勝手ながら想像したんです。
澤部:実際、『THE HAPPY END』のブックレットでも大瀧さんは「僕の近況と言えば、お墓作りの日々である」と発言していますね。
牧村:コンサートが終わって打ち上げがあったんですが、その席の華はユーミンでした。ユーミンの周りにみんなが集まっていて、もうひとつの華であるべきはっぴいえんどの面々はわりと淡々としていましたね。大瀧さんは、「さよならアメリカさよならニッポン」でバックコーラスを務めた〈ノン・スタンダード・レーベル〉所属の若手ミュージシャンの一人に、「僕は今からスッと消えてしまうけど、気にしないでね。今日は自分の手で葬式ができた」と言って帰られたそうです。
澤部:はっぴいえんどを再現するために物語の構築が不可欠だったわけですね。
ステージでも次世代への引き継ぎを果たしたはっぴいえんど
牧村:オリジナル・バージョンとコンサートでのアレンジを比較してみるのも面白くて。「12月の雨の日」は、多少テンポ感と譜割が違います。それは大瀧さんの唄い方の変化ですね。はっぴいえんどではシャウトしていたのが、『A LONG VACATION』ではクルーナー唱法。新しい大瀧詠一、本来の大瀧詠一はクルーナー唱法だと判断したんでしょう。当日、僕はステージの真裏にいたんですが、大瀧さんの歌を聴いて「おっ、小林旭だ!」と思いましたよ(笑)。
澤部:ホントにそんな感じですよね。大瀧さんは小林旭が大好きですし。
牧村:12年間、ドラムを叩いていなかった松本さんのために打ち込み音源を使いつつ、上物を松本さんが叩く。再結成はっぴいえんどのサウンドは細野さん、それをSHI-SHONENの戸田くんがサポート。当時の〈ノン・スタンダード・レーベル〉の持っていたテクノ色が必然的に出たわけです。
澤部:すごく理に適ってますよね。ずっとドラムを叩いていなかった松本さんはテンポのキープができないから、おそらくキックはループなんですよね。で、スネアやフォルインとかは実際に叩いてるんですよ。もしかしたらスネアもある程度の部分は打ち込んであるのかもしれないけど。実ははっぴいえんどって一貫して目新しいことをやりたかっただけなんじゃないか!? と僕は考えたんです。日本語詞でロックを唄うのも、再結成でテクノをやるのも。牧村さんの話を伺って、『A LONG VACATION』があっての大瀧さんの歌唱の変化、松本さんがドラムから遠ざかっていたこと、細野さんが〈ノン・スタンダード・レーベル〉所属のSHI-SHONENのメンバーにプログラミングを任せたこととか、いろんな経緯や要因の積み重ねがあっての結果だったんだなと思いました。イベントの趣旨だけではなく、はっぴいえんどの演奏の中でも次世代への引き継ぎが行なわれていたわけですね。
牧村:このコンサートでは国立霞ヶ丘陸上競技場の中に8個のステージを作ったんです。ミュージシャンというのは観客の反応を見ながらライブをやるものなのに、フィールドの中にはひとりも観客がいないんですよ。事実上、誰も観ていない状況でライブをやったわけです。確かに観客はいるけれども、みんな豆粒なんですね。ちょっと異常なんです。映像ではカメラが近寄ったりするから観客との温かいリレーションがあるように思えますが、観客の姿が見えないんですから。このコンサートは6万人を集めたのは事実だけど、6万人に聴かせるために異様なステージを組んでいたんです。
▲国立霞ヶ丘陸上競技場の中には8個のステージが作られた。
澤部:確かに異様ですね。はっぴいえんどは日本語ロックなりテクノなり、その都度流行りを取り入れていただけなのではないか? という僕の推理は撤回します(笑)。
牧村:トレンドを取り入れるという目配せもあったかもしれませんけどね。
澤部:あったかもしれないけど、それが第一の理由ではないことがよく分かりました。
牧村:では、最後にかける曲として、このコンサートの「さよならアメリカさよならニッポン」を聴いていただきましょう。
──はっぴいえんど「さよならアメリカさよならニッポン」(ライブ音源)
牧村:こうして聴くと、やっぱりすごくいいですよね。音楽が音楽だった時代を思い出しますね。
澤部:そういう話がブックレットにも書かれていますね。「音楽の時代じゃなくなりつつあるからまたはっぴいえんどをやるんだ」って。これまで何度も再結成するタイミングはあったけど、音楽がまず第一であるために再結成をするんだという。ちなみにこのレコードはエイベックスから出た『はっぴいえんどBOX』の中の1枚としてCD化されたことがあるんですが、その時は吉田拓郎さんのメンバー紹介が全部カットされたんですよね。このライブ盤はぜひ単体でCDにしてほしいです。
客席からの質問コーナー(凄い質問ばかりだった)後の、エピローグ
澤部:最後にいいですか。僕は10年くらい前に「今年、はっぴいえんどが再結成するかもしれない」という話を聞いたことがあるんです。でも結局、それも実現には至らなくて、一体どんなやり取りがあったんだろう? と想像することしかできないんですけど。
牧村:(ここは内緒話でしたが、この原稿を書いている時点である確信ができました。それはまたいつか)
澤部:もうひとつ、話そうと思っていたことを話していいですか。〈日本語ロック論争〉で「『はっぴいえんどなんてフォークだ!』と言ってる連中の言い分がある」というくだりがあって、その言い分って何だったんだろう?と思って。
牧村:〈日本語ロック論争〉では松本さんの存在がすごく大きいんです。洋楽に影響を受けて新しいことを始める一期生は、概ねフォーク派とGS派に分かれた。GSは日本のロックにつながるわけですが、当時の日本のロックは洋楽のカバーをやるのがメインだったんですよ。それに対して松本さんは、洋楽の本質を受容した上で独自の日本的表現にどう置き換えるかを志向していた。クリームの曲をクリーム以上に巧みに演奏することを目標にしていた人たちと、クリームとは一体何であるかを追求していた人たちの差は大きかった。…そんな話をするだけでも数時間経ってしまいますね(笑)。冬期ゼミは今日で最後ですが、『月刊牧村』を再開させたらこの続きをやりましょうか。澤部くん、付き合う?
澤部:もちろんです。ぜひまた呼んでください。