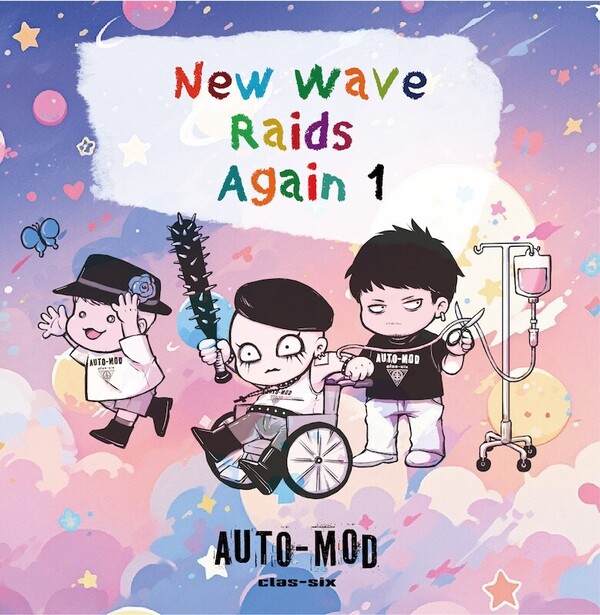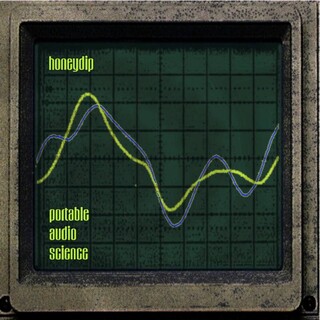人力を排した状態でどこまで表現できるかという面白さ
──AUTO-MOD clas-sixとしてAUTO-MODの楽曲を取り上げる基準とはどんなものなんですか。
渡邉:僕がジュネに「これはどう?」と訊いています。彼がこういう曲をやりたいという意向はあまりないですね。これはやりたくないというのはありますけど。選曲については、今年の2月に亡くなってしまった友人からのリクエストが大きいかもしれない。彼がAUTO-MOD好きで、「貢さん、あれやってよ」とよく言われていたんです。「哀しきモッド人形」も彼が亡くなる前にぜひ聴きたいと言っていたのでジュネにことわりを入れて、最初のEPに入れることにしたんです。あと、あの曲は良かったはずだという自分の記憶を頼りにしている部分もあります。そもそもベースと打ち込みと歌だけなので、やれそうな曲とやれそうにない曲が明確にあるんですね。その中で今はやれそうな曲から手を付けています。ベースがメインのリフを弾いている曲だったり。
──『New Wave Raids Again』と題した2枚のEPに収録した6曲(「哀しきモッド人形」「CANNIBAL OF LOVE」「LOVE GENERATION」「遠い声」「OUT OF THE DARKNESS」「ETERNAL THEATER」)は比較的手を付けやすいものだったと。
渡邉:ベースが曲を牽引していく感じがあるのと、やっぱり歌詞の良さありきで選びました。
──AUTO-MOD clas-six名義の初音源の1曲目を「哀しきモッド人形」で飾ったのが象徴的ですね。1980年に新宿LOFTで行なったライブ音源集『METAMORPHOSIS』に収録されていた最古参の楽曲から始まるという意味で。
渡邉:「哀しきモッド人形」は僕が入る前の初期の曲で、現役当時はライブでやってないんです。確か『HISTORY 1980-1985』というビデオにも入っていたのかな。さっきも話したようにAUTO-MOD好きな友人からリクエストを受けて、最初は「いいよ」と空返事だったんだけど、2月に亡くなってしまったこともあってリリースにあたって収録することにしたんです。
──文字通りの“レクイエム”だったんですね。
渡邉:そうです。空の上の彼にも聴いてほしかったので。
──2枚のEPにはいずれも新録2曲(「CANNIBAL OF LOVE」と「LOVE GENERATION」、「OUT OF THE DARKNESS」と「ETERNAL THEATER」)の1985年当時のライブ音源が対比するように収録されています。こうした構成を取ることで聴き比べができるのが面白い趣向ですね。
渡邉:過去のライブ音源については音質も含めて本意ではない部分もあるんですけど、当時の環境を考えれば仕方ないのかなと思って。ほぼ40年前の音源だし、歴史的価値があるのは間違いないので。
──ご自身としては聴き返すのが恥ずかしいものですか。
渡邉:そんなこともないです。むしろちゃんとやっていたなと思って。自分としては当時はまだちゃんと弾けていなかった印象があって、今もそれなりに努力をしているんですけど、当時と今では意外と変わらないものだなと感じています。それが良いのか悪いのかは分かりませんけど。若い頃はそれなりに頑張っていたし、勢いのあるパンチの強さは薄れたかもしれないけど、曲に対するアプローチがそれほど変わってないのは発見でした。
──レコーディングに際しては、PERSONZでもサポートに貢献しているアーバンギャルドのおおくぼけいさんがプログラミングで参加しているんですね。
渡邉:僕が打ち込んだものを彼に渡してブラッシュアップしてもらうのが基本ですね。結果として彼が良い味付けをしてくれています。ドラムレスの編成なのでどんなふうにアレンジするかは難しいけど、面白い部分でもあります。
──ex.GRASS VALLEYの上領亘さんをゲスト・ドラマーに迎えたライブもありましたし、その経験を踏まえた上でのドラムレスという判断なんですよね。
渡邉:そうですね。自分としてはPERSONZとは別にバンドをやるなら、女性ボーカル、ドラム、ギターのいない編成でやるというMyルールがあるんです。ギターに関しては友森が入ったことで許して欲しいんですけど(笑)。バンドである以上はもちろんドラムがあったほうがいいに決まっているんですが、このAUTO-MOD clas-sixに関しては人力を排した状態でどこまで表現ができるかという部分で面白さがあるし、ハンディキャップがある中での探究に敢えて挑み続けてみたいんです。ただ絶対にドラムを入れないというわけではないし、何かの折にドラムを入れたライブをやるのもいいとは思っています。
“New Wave Raids Again”=“ニュー・ウェイヴの逆襲”というタイトルに込めた真意
──12月13日のライブで先行発売される『New Wave Raids Again 2』にはex.沖縄電子少女彩の彩Sayaさんがコーラスで参加していますが、この起用の意図は?
渡邉:ジュネのボーカルが非常に個性的なので、僕や友森がコーラスをしてもあの声に上手くハマらないんです。おそらく音域が違いすぎるのもあって広がりが生まれない。それで音域が近いところで唄ってくれる彩Sayaに声をかけて、コーラスを入れてもらうことにしました。彼女はジュネの妹分みたいな存在で交流があったんです。彩Sayaは沖縄出身で少し訛りがあって、それが癖の強いジュネのボーカルと合う部分があるんですね。
──2枚のEPを通してAUTO-MODの往年の楽曲を現代に蘇生させる試みは上々の結果になったと思いますが、総指揮の立場としてどう感じていますか。
渡邉:自分としても自信を持ってお届けできる作品になりました。AUTO-MOD clas-sixとしてまだまだやれることがあるのを実感しましたし。
──“New Wave Raids Again”=“ニュー・ウェイヴの逆襲”というタイトルも、日本におけるニュー・ウェイヴの礎を築いたAUTO-MODらしくて良いですね。
渡邉:マネジメントの42(金子司)が考えてくれました。ジュネが“ニュー・ウェイヴの逆襲”というワードを話していて、それを英語にすればタイトルらしくなるんじゃないかって。
──マスに対するカウンターとしてのニュー・ウェイヴというバンドの姿勢を言い表しているようだし、傍流から主流に向けた反撃を今こそ喰らわせてやるというニュアンスも感じられます。
渡邉:80年代って対峙するものが今より明快だったと思うんです。敵対視するもの、闘うものが明確だったけど、今はそうしたものがとても見えづらい。何が正しくて何が間違っているかすらも情報の取捨次第で見方が180度変わってくる。その中で80年代当時に自分たちが感じていた思いやスタンスが未だ残っていて、今の釈然としない世相に向けた僕らなりの主張とでも言うんですかね。それをタイトルに込めてみたというか。その思いを知らしめるためにジュネの詞があるし、CDだけではなく彼の詩集を出したいくらいなんです。ジュネが土壌を開拓したヴィジュアル系の若手バンドが、彼に作詞を依頼してもいいんじゃないかとすら思うし。あれほど詩的でいろんな解釈のできる詞を書ける人間が今の日本にどれだけいるんだと僕は本気で思っていますから。
── 一時代を築いたPERSONZというマスなバンドを40年にわたり続けている貢さんが、その一方でAUTO-MOD clas-sixという極めてマイナーなバンドに心血を注ぐ構図が面白いんですよね。マスとニッチの双方あるバランスが相乗効果をもたらすこともあるのでしょうか。
渡邉:自分としては双方のバンドをやる本質に変わりがないんです。バンドの打ち出し方や楽曲の届け方はもちろん違うし、その部分でジュネには欠けたところがあるので、僕が僭越ながらPERSONZで培ってきたものをAUTO-MOD clas-sixで発揮できればいいなと思っています。せっかく作り上げたものをより多くの人たちに聴いてほしいし、聴いてもらえないのはもったいない。そのための折り合いをどう付けるかジュネにアドバイスをして上手く誘導できればいいなと。
──ジュネさんはそうした貢さんのアドバイスを素直に聞いているんですか。
渡邉:聞いてはいると思うんですけど、上手く実行できないんですよ(笑)。聞く耳を持っていないわけではないんだけど、すぐに忘れてしまう。さっきのギターの話と同じですね。
──1985年のラスト・メンバーである友森さん、河野さんと共に39年ぶりとなるレコーディングを行なって、何か印象の変化みたいなものは感じましたか。
渡邉:河野さんは昔と変わらない感じでした。彼は僕よりちょっと年上で、当時からお兄さん的立場として物を言う感じだったので。友森は逆に年下だったし、僕の中での彼の評価は正直なところあまり高くなかったんです。実は布袋さんがAUTO-MODを抜けた後に本田(毅)さんを誘ったんですけど、いろいろあって時間が取れないということで本田さんから友森を紹介されたんです。友森は本田さんの弟(本田聡)と同級生で、一緒にバンドをやっていた。たまにPERSONZのライブを観に来ていて知ってはいたんですけど、布袋さんや本田さんのような敏腕ギタリストを知る立場としてはどうしても点が辛くなってしまって。ギタリストとしてもっと自分のカラーを出すべきだと当時は感じていたんです。
──その印象が39年の歳月を経て変わったと。
渡邉:以前はセッション・ギタリストのように感じていたんですが、今は彼なりのスタイルが出来上がっているんだなと思いました。今回は「こんなふうに弾いてほしい」という依頼もしなかったし、しなくてもいいくらい彼のスタイルが構築されているのを感じましたね。本田さんがPERSONZを一時離脱した後に友森に手伝ってもらうこともあったんですが、そのときよりも自分のスタイルを形成しているのを感じて頼もしかったです。