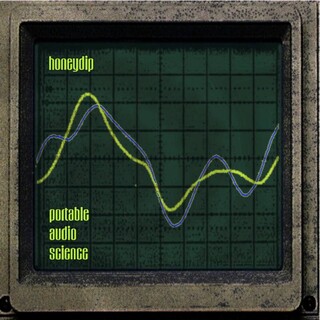日本のポジティヴパンク・シーンを牽引し、AUTO-MODのフロントマンとして44年にわたり活動を続けるジュネ(Vo)と、1980年代にAUTO-MODのベーシストとして活動を共にした渡邉貢(PERSONZ:Bass, Vo, Programming)が2022年、実に37年振りに邂逅。往事のAUTO-MOD楽曲を再現するバンド、AUTO-MOD clas-sixとして精力的に自主企画ライブを開催している。1985年解散時のギタリストだった友森昭一(ex.レベッカ)が2023年に正式加入し、今年9月に待望の初音源『New Wave Raids Again 1』を、12月に同タイトルの"2"を矢継ぎ早にリリースするなど活動の速度と深度をさらに増幅させる"clas-six"。その実質的ブレーンとしてバンドと楽曲の解体と再構築を促進させ、不世出のパフォーマーかつ詩人であるジュネの才能をもっと世に知らしめたいという渡邉に、"clas-six"発足の経緯や活動の真意を聞いた。12月13日(金)に渋谷LOFT HEAVENで行なわれる『2nd.CDリリース&2024総括 "New Wave Raids Again 2"』で彼らが魅せる2020年代最新形ニュー・ウェイヴの真髄をぜひ体感していただきたい。(Interview:椎名宗之)
ジュネに拾ってもらったところからすべてが始まった
──AUTO-MOD clas-sixを始動させた経緯から聞かせてください。
渡邉:3年前にジュネの奥さんが亡くなって、お葬式で彼と軽く話したんです。そのすぐ後だったかな、「もう音楽をやめるから最後に一枚CDを作りたい。そのプロデュースをしてほしい」と相談を受けまして。ちょうどAUTO-MODを手伝っていたYukinoくんが辞めた辺りで、打ち込みと歌だけのデモテープをもらって。それでジュネとの交流が再開したんです。
──それまでジュネさんに連絡したりは?
渡邉:ほぼありませんでした。たまに食事をしたり、イベントで共演する程度で。
──そのデモテープはどんな内容だったんですか。
渡邉:15曲くらいの新曲で、どれもアジテーションのような彼の語りがとめどなく溢れたものでした。でも音楽の体を成していなかったし、そのまま出すのはどうかと感じて。それに最後だから、ドラムはBUCK-TICKのアニイ(ヤガミトール)とか縁の深いミュージシャンをいろいろ呼びたいというリクエストもあったんですけど、彼の構想を形にするにはバジェットがかかりすぎた。その資金を捻出するためにAUTO-MODのヒストリーDVDを出すのはどうか? なんて話も出たんですけど、結局その“最後のCD”はお蔵入りしたんです。ちょっと力が入りすぎて音楽として面白みがなかったのもあって。そうこうしているうちに、昔からの友人が運営するJAP工房(シルバーアクセサリーとミュージシャンの衣装制作を担う会社)の開催するイベントにゲストで出てほしいと依頼を受けて、ジュネと二人で何かやろうかという話になって。それがそもそものスタートですね。で、僕が打ち込みでトラックを作ってベースを弾き、彼が唄うスタイルでやろうと。JAP工房に誘われたイベントでは3曲だけだったけど、これは意外と面白いんじゃないかという手応えもあったのでレパートリーを増やしてやってみない? という話になって。ジュネも奥さんを亡くして元気がなかったけど、徐々に調子を取り戻してきて。最初はジュネが弾けないギターを弾きたがって大変でしたけど(笑)。
──ジュネさんと貢さんが揃うならAUTO-MODのクラシック・ナンバーをやろうというのは自然な流れだったんですか。
渡邉:そうですね。AUTO-MOD本体はプログレッシヴかつヘヴィなロックを基調としたものだけど、それとは全然違う、ベースと打ち込みと歌でポップなものをやりたかった。ジュネはもともとポップセンスに溢れた人で、僕は彼のポップな曲作りに昔から影響を受けていたんです。
──9月に発表された『New Wave Raids Again 1』にも収録されていた、AUTO-MODのファースト・シングル「LOVE GENERATION」も実にポップな曲でしたね。
渡邉:そうなんです。歌謡曲とは言わないまでも、それに近い親しみやすさがある。
──本体のAUTO-MODはジュネさんが継続しつつ、AUTO-MOD clas-sixが別個にあるという形態なんですよね。
渡邉:ジュネが本来やりたいことはAUTO-MOD本体でやれているからこそAUTO-MOD clas-sixで非常にポップなことをやれるんだろうし、その二つを彼が楽しんでやっているように僕は感じます。最初はとにかく、彼を元気づけたい一心で始めたことだったんですけど。
──貢さんの中でAUTO-MODの往年のナンバーを再現することに抵抗みたいなものは?
渡邉:全然ないです。作品として世に出ていないけど「あの曲は良かったな」みたいなものも結構ありますし。
──AUTO-MODはPERSONZ以前に渡邉貢の名を世に知らしめたバンドでもあるし、ジュネさんへの恩返しとしてAUTO-MOD clas-sixを始めたところもありますか。
渡邉:ありますね。すべての始まりはAUTO-MODで、ジュネに拾ってもらったところから僕のキャリアは始まったので。
──当初は下北沢SHELTERや南青山RED SHOESで自主企画を開催し、二人以外のゲスト・プレイヤーを招いてみるなど試行錯誤を繰り返していましたね。
渡邉:サウンド的には凄く面白い自負があったし、これはいけるという手応えもあったんだけど、ギタリストが決まらなかったり編成が定まらない時期がありました。そもそもジュネがギターを抱えているのに言われたことを一切できなかったりして。彼の頭の中で鳴っている音を再現できないジレンマもあって、最初はリハーサルに凄い時間をかけたんです。ほぼ休憩なしで6時間演奏し続けるんだけど、ジュネに「この部分はこう弾いてくれ」「ここはベース・ソロだから何も弾かないでくれ」と伝えても全部忘れて言うことを聞かない。ライブ本番になるとリハーサルでやったことを一つもやらないし、この人にいろいろ教え込んでも無駄なんだと理解するのにだいぶ時間がかかりました(笑)。
ジュネの秀逸な詞を万人に伝えたい
──それが渡部充一さん(ex.DEEP)をギタリストに迎える前の時期ですね。
渡邉:二人だけで試行錯誤していたら、ベースと打ち込みと歌だけだとバリエーションとしてやれる曲が少ないことが分かって。30分以内ならやれるけど1時間のステージはやれないので、充一くんに声をかけました。でも彼は諸事情によりバンドに打ち込めないということで、友森(昭一)に打診することにしたんです。
──結果的にジュネさん、貢さん、友森さんというAUTO-MODが1985年に解散したときのメンバーが揃いましたね。サックスの河野利昭さんもまた然り。
渡邉:友森が入ってきた時点で、1985年のラスト・メンバーが邂逅したと割り切って打ち出してもいいのかなと思って。ライブの集客を増やしたい気持ちもあったので。
──友森さんが加入した2023年7月以降は安定期に入ったと言えますね。
渡邉:サウンド的には何の心配もないし、友森が入ったことでジュネに「もう弾くのはやめなよ」とギターを取り上げることに成功しました。ついこのあいだの話なんですけど(笑)。
──タイプは違いますけど、氷室京介さんや吉川晃司さんのようにジュネさんもピンボーカルが似合うボーカリストだと思うので、賢明な判断だったのでは?(笑)
渡邉:吉川くんはちゃんとギターを弾けるけど、ジュネはそもそも弾けてないので(笑)。それはありつつもギターを持つ画が様にならないというのはありますよね。
──AUTO-MOD clas-sixはAUTO-MODという日本のポジティヴ・パンク、ゴシック・ロックを牽引したバンドの解体と再構築を試みるユニットとして存在自体がユニークだし、既存のロックに対して問題提起する在り方はロックが不遇な時代である2020年代的とも言えると思います。
渡邉:AUTO-MOD clas-sixに真剣に取り組んでから考えているのは、ジュネの詞を万人に伝えたいということなんです。ポップな曲の面白さも伝えたいけど、それよりもジュネの詞の秀逸さを世に知らしめたい。
──たとえば『New Wave Raids Again 1』にも収録された「哀しきモッド人形」の「日常の裏側に 組み込まれたファシズム/こんな時代だからこそ ぶち壊さなきゃならない/日常の欺瞞に 我慢できなくなって/今僕らは目覚める 失われた自己の証しへと」という歌詞は44年前に書かれたものなのに現代社会への警鐘のようで示唆的だし、ジュネさんの歌詞はどこか預言者めいたところがありますよね。
渡邉:そういう視点や歌詞の世界観が全く古びてないし、今の時代に通ずるものがある。それに、今日のヴィジュアル系と呼ばれるジャンルで歌詞を書く人たちはジュネのような歌詞を書きたいんじゃないかと思うんです。ああいうことを唄いたいんだろうなという歌詞を書き上げる道標のような唄い手であると僕は思います。ジュネは作詞家としてもっと評価されるべきだと当時から感じていたし、メジャーな世界で詩的な歌詞を書くPANTAさんの裏返しのような存在だと思っていました。マイナーな存在で光は当たりにくいけれど、PANTAさんと同等の歌詞を書ける才能がジュネにはあると。
──AUTO-MODは確かに知る人ぞ知る存在だったかもしれませんが、デビューこそ地引雄一さん主宰のテレグラフ・レコードだったものの2ndアルバムの『DEATHTOPIA』はメジャーのSMSレコードからリリースされたし、アンダーグラウンドとオーバーグラウンドを行き来した稀有なバンドだと思うんです。
渡邉:BOØWYと掛け持ちする形で布袋(寅泰)さんと(高橋)まことさんが加入していた時期は音楽的にかなりのレベルまで成熟しましたからね。ジュネがやろうとしていた本質は変わらなかったけど、布袋さんとまことさんが入ったことで表現の質が格段に上がった。とりわけ布袋さんのアレンジ能力の凄さは当時まだ十代だった僕も大きな影響を受けました。布袋さんはメジャーなものからマイナーなものまで海外の最新鋭の音楽を常に貪欲に吸収していたし、布袋さんに「これ聴いた?」と訊かれて「聴いてない」と答えるのが嫌だった。イギリスのギャング・オブ・フォーやアダム&ジ・アンツ、ドイツのDAFといったニューウェイヴ・バンドを基本としてあらゆる音楽を徹底して聴きました。布袋さんと一緒にバンドをやっていなければ今の自分はなかったと思いますね。どれだけマイナーなバンドでもポップでキャッチーな部分を掬い取るセンスが絶妙で、布袋さんのあのセンスに学んだ部分はとても大きいです。