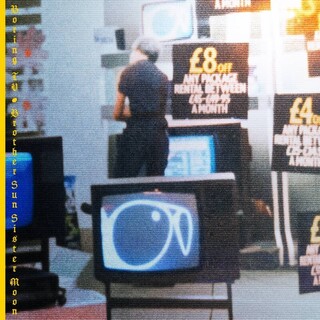大阪を拠点に国境と言葉を越えて映画を撮り続けるマレーシア出身のリム・カーワイ監督が、『どこでもない、ここしかない』『いつか、どこかで』に続いて制作したバルカン半島3部作の完結編『すべて、至るところにある』が公開された。
物語は、バックパッカーのエヴァが旅先で映画監督のジェイと出会い、バルカン半島で映画を撮影することになるが、その後、コロナ禍と戦争が世界を襲い、ジェイはエヴァにメッセージを残して姿を消してしまう。フィクションとドキュメンタリーが交錯する本作には、実際に1990年代に起こったボスニア・ヘルツェゴビナ紛争を体験した人たちが登場し、彼らが語る戦争体験が映画の重要なモチーフにもなっている。
パンデミックと戦争がいまだ世界中に暗い影を落とす中、リム監督は観客にどんなメッセージを伝えようとしているのか。監督にお話を伺った。(TEXT:加藤梅造)
世界中が未来の見えない閉塞感にとらわれてしまった
──“シネマドリフター(映画流れ者)”でもあるリム監督は、知らない場所に行って、その土地の人たちと即興で映画を撮影していくという独自のスタイルで知られています。今作は、そのスタイルの原点となったバルカン半島を舞台とした3作目という位置付けですね。
リム 撮影方法はこれまでの2作同様、少人数のスタッフで移動し、即興で撮っていくスタイルです。ただ今までと違うのは、時系列がバラバラになっていたり、フィクションとドキュメンタリーが交錯するものになってます。
──当初は2020年に撮影するはずが、新型コロナウイルスのパンデミックで中断を余儀なくされました。
リム そうです。1作目『どこでもない、ここしかない』はバルカン半島のスロベニアと北マケドニアで、2作目の『いつか、どこかで』はクロアチアとモンテネグロとセルビアで撮ったんですね。それで再びバルカン半島で3作目を撮ろうと思った矢先にパンデミックが起こった。日本に閉じ込められて撮影はできなくなり、さらには2022年にウクライナで戦争が起こってしまい、世界中が未来の見えない閉塞感にとらわれてしまった。それは今作に大きな影響を与えてます。
──映画の主人公であるジェイは映画監督という役で、パンデミックと戦争に絶望したジェイが「人生の目的がわからなくなった」と独白する場面から始まります。ジェイはリム監督を投影した人物なんですか?
リム もちろんそういう部分もあります。ジェイがなぜバルカン半島で映画を撮っているのかを説明するのに、私の過去の作品を劇中に引用するメタ映画の手法を取り入れるのがいいと思いました。それで、役者の尚玄さんに映画監督のジェイを演じてもらったんですが、私とは見た目はもちろん性格も違うので、ジェイ=私自身というわけではないですね。
日本映画業界でも起こっているハラスメントの問題
──ドキュメンタリー的なパートとして街のカフェが重要な場所になっています。そこではカフェの客がかつての戦争体験を次々と語っていきますが、あれは即興で撮ったんですよね。
リム 今回、ボスニア・ヘルツェゴビナのどこで映画を撮るかを考えた時、サラエボはすでに多くの映画が撮られているので、モスタルで撮るのがいいんじゃないかと思い、ロケハンに行ったんです。そこでたまたま入ったカフェが撮影場所としてすごくよかった。モスタルという街は30年前、ボスニアとクロアチアの紛争で街も破壊され、無数の人が亡くなったんです。つまり廃墟から立ち直った。そのカフェで語ってくれた人たちも実際の戦争体験者です。家族や親戚が亡くなって一人で暮らしている人がたくさんいます。彼らが今のウクライナ戦争に対してどう感じているのかをぜひ聞きたいと思いました。それでドキュメンタリーの手法で彼らに語ってもらったんです。それを劇中ではジェイが撮影し、ジェイが失踪した後に、残された映像をもう一人の主人公であるエヴァが観るというメタ構造になっています。
──エヴァ役のアデラ・ソーさんは前作『いつか、どこかで』の主役でもありますね。
リム はい。今作も彼女と一緒にやろうという所から企画が始まっています。
──バックパッカーとして旅をしているエヴァが旅先でジェイと出会い、一緒に映画(『いつか、どこかで』)を撮り、やがてジェイが失踪するというストーリーが映画の1つの軸になってますが、撮影中のジェイのハラスメントが二人が決裂するきっかけになってます。ここはもちろんフィクションだと思いますがなぜあのシーンを入れたんですか?
リム それは、ハリウッドはもちろん、日本映画業界でも起こっているハラスメントの問題を扱おうと思ったからです。映画監督が俳優やスタッフにいやな仕事を無理矢理させるということの反映です。ジェイはナルシストで自分はなんでもできると思っているという人物設定なんですが、そのジェイがエヴァに逃げられ、村人からも撮影を拒否され、徐々に孤独と自信喪失に悩むようになる。さらにボスニアに行って、街の人たちから戦争体験を聞いていく中で世の中のことを考えるようになる。そうしたジェイの変化のきっかけとしてあのシーンはとても重要だと思いました。
パンデミックがあっても、戦争があっても、生き続けることがとても大事
──劇中でジェイが「自分の前世はバルカン半島に住んでいたかもしれない」と語ってますが、実際、リム監督はなぜバルカン半島3部作を撮ろうと思ったんですか?
リム 僕が最初にバルカン半島という存在を知ったのは歴史の教科書で、まさに「ヨーロッパの火薬庫」として、ずっと紛争があり不安定な場所というイメージでした。それで2016年に初めて実際にバルカン半島を訪ねてすごくショックを受けたんです。自分のイメージとはかなり違っていて、みんな平和に暮らしているし、治安もいいし、目立った対立もなかった。はたしてそれは表面的なものなのかどうか、実際に人々はどんな思いで暮らしているのかをもっと知りたくなった。その中でいろいろな面白い人物に出会っていくんですが、例えば『どこでもない、ここしかない』に出てくるフェルディというムスリム人は、ムスリムがやってはいけないこと、女の子を口説いたり、ドラッグをやったりするんです。私としてはそこにすごく魅力を感じて、最初にフェルディの話を撮った。そこからどんどん撮りたいテーマが広がっていって、結局3部作になったんですね。
──今作でもフェルディさんは出てきますが「お前の映画には二度と出ない」と怒ってましたね(笑)
リム そこをなんとかお願いして出てもらったんですが、3度目はないかもしれないですね(笑)。でも僕のような言葉も文化も違う人に対してああやって本音をぶつけてくる所は、逆に彼の情の厚さを感じますね。
──モスタルにあるアーチ状の橋(「スターリ・モスト」)は内戦で一度破壊され再建された橋だそうですが、現在も東側のムスリム系地区と西側のクロアチア系地区をつなぐ架け橋として平和の象徴的な存在になっているんですね。
リム そうです。21世紀は戦争の時代ですが、ウクライナでもガザでも今だに殺戮が日々起こっている。つまり歴史が繰り返しているわけですよね。バルカン半島はいまは平和ですが、またいつか不安定になるかもしれない。再建されたモスタルの橋もそうですし、映画の撮影場所となった「スポメニック」も、かつての戦争で犠牲になった人たちを記憶する墓でありモニュメントです。この映画のメッセージは、パンデミックがあっても、戦争があっても、生き続けることがとても大事だということ。劇中のジェイは現実を生きることをあきらめてしまったけど、その対比を含め観てくれた人にいろいろ考えてもらえると嬉しいですね。