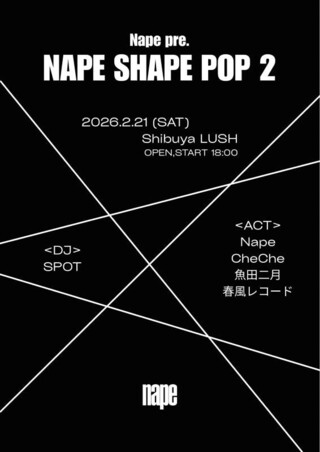ワタシは佐村河内守にはなりません!
──ただ、タワーレコード新宿店での対談でも、端々に二人の音楽理論に裏付けられた知性に圧倒された覚えがありますし、以前、達郎さんにインタビューした際に、「僕は正当な音楽教育を受けたとは言えない。だからひたすらレコードを聴いて、レコーディングやライブを積み重ねて実践を重ねてきた」と言われていて、その洋輔さんの仕事も達郎さんの大きな学びになったのではないかと推測できます。つまり洋輔さんが坂本さんと達郎さんに影響を与えた数少ない存在であるのは、日本のポップ・ミュージック史に自覚的であれば誰でも気づきますけどね(笑)。
山下:そうであれば嬉しいですけど、でもその理由が、僕が正当な音楽教育を受けていたからだとするなら完全に買い被りですよ(笑)。小さい時からデタラメな演奏を続けてきたにすぎないんですね。国立音楽大学の作曲科に入学したのは、何かいつも目障りな(笑)、つまり気になるクラシックというジャンルを一応勉強すれば、何も知らないでやっているよりは自信がつくかもしれないと考えたからなんです。
──とは言え、高校を卒業してプロのジャズ・ピアニストとしての活動を始めていたのに、2年後に音楽大学に入学するなんて普通は考えないですよ。そこでちゃんと理論を学ぼうとしたことが、結果として洋輔さんの個性を育んだように感じられてなりません。
山下:小心者だっただけなのかもしれませんけどね(笑)。もともとは、母親がずっとクラシック・ピアノが好きで家にピアノがあったんです。僕は興味を持って勝手に弾いていたんですけど、母親は教えようとするんですね。その段階で楽譜を見ることを拒否する子どもだったんです(笑)。そこで母親がバイオリンを習わせた。するとそっちは、完全に楽譜に従ってレッスンを素直に受けるんですよ(笑)。そこで音楽の基礎を学んだというのもあるんですね。やはり西洋クラシック音楽が、人間の巨大な文化的財産として残っている事実がわかってくる。これはちょっと知っておかなければ、と思った。でも自分のやりたいのはジャズだ!(笑)というわけなんですが、あと考えたのは作曲という行為が即興演奏と似ているのではないかと思ったんですね。後年わかったんですが、バッハ、モーツァルト、ベートーヴェンといったクラシックの大家は皆、即興演奏を極めているんですよ。
──彼らが楽曲のカデンツァ部、自由に演奏できるパートにおいて卓越すべき才能があったのは、近年証明されていますからね。
山下:それが当たり前だったらしいですね。即興演奏のコンテストもあったらしいですから(笑)。
──それに超絶技巧で知られるフランツ・リストも、即興演奏が素晴らしかったと言われていますよね。
山下:「何か弾いて」と言われたら、即興でどこまででも弾いている姿がすぐに浮かんできます。ただ、彼らはそれを後で譜面にさらさらと書けた。ここが違う!(笑)

 ──でもそうやって洋輔さんが音楽理論を学んだことが、結果としてジャズ・ピアニストとして、または作曲家としての個性を育て、最終的には自ら交響曲を書くまでに発展するとは、本人も想像していなかったのでは?
──でもそうやって洋輔さんが音楽理論を学んだことが、結果としてジャズ・ピアニストとして、または作曲家としての個性を育て、最終的には自ら交響曲を書くまでに発展するとは、本人も想像していなかったのでは?
山下:想像していませんでした(笑)。結果的にそうなったのは、1986年にガーシュインの『ラプソディ・イン・ブルー』をオーケストラと共演しないかという依頼があったことから始まるんですよ。最初は全部譜面ありきだと思ってお断りするつもりでいたんですが、何回かあるソロのカデンツァを自分の即興演奏にすれば何とかやれることに気づいて、簡単に言うと楽曲を山下編曲版に改造したんです(笑)。そして一度だけのつもりで演奏したら、なぜか山下がムチャクチャにした『ラプソディ・イン・ブルー』が面白いと噂になって(笑)、何度も再演するようになるわけです。そうしているうちに東京オペラシティから新年の公演を一晩任せるという話が来て、それなら自作のコンチェルトを書く、と言っちゃった(笑)。それで2000年の発表に向けて取り組むようになるんです。
──考えてみると、もともとオーケストラとの共演を断ろうとしていた人の発想とは思えませんけどね(笑)。
山下:ただ、最初に作った『ピアノ協奏曲第1番』は、ガーシュインからのヒントがあるんですよ。『ラプソディ』はガーシュイン自身が作ったものに違いないけど、オーケストレーションはグローフェが全部やった。ちょうど僕も、今村昌平監督作品『カンゾー先生』の音楽で作編曲家の栗山和樹さんと知り合っていて力量に感服していたので、「コンチェルを作りたいんだけど、おれ、ガーシュイン、君、グローフェ」と言ったらすぐにわかってくれた(笑)。
──自分が楽曲を聴いた時には、洋輔さんと栗山さんの関係は、デューク・エリントンとビリー・ストレイホーンに近いのかなとも考えていました。
山下:彼らの場合は、良い意味でお互いの作編曲家としての領域がわからないところがありますよね。僕らのほうは、はっきりと山下=作曲と演奏、編曲=栗山と分かれている。公式にそう表記されています。『第3番』をやってもらった挾間美帆との場合でも同じです。だからワタシは佐村河内守にはなりません! ...すみません、このネタはマネージャーからそろそろやめたほうがいいと言われてはいるんですが(笑)。
──でもこのネタ、今でも確実に笑いを取りますよね(笑)。
山下:ちゃんと自分で作曲と演奏をしているからこそ言えるネタではありますから(笑)。
荻窪ロフトは文学的な空間でしたよね
──洋輔さんは毎年年始に初台の東京オペラシティで演奏されますけど、以前観た際に、「コンサートホールなのにライブハウスみたいな空気感になっている」と感じたことがあります。
山下:それは嬉しいですね。いま話していて感じたんですけど、もしかしたら、東京オペラシティで年に一度クラシック奏者と真剣に向かい合うことと、むかし荻窪ロフトに出演していたことは根底ではつながっているのかもしれない。たとえば山下洋輔トリオでヨーロッパをツアーすると、まったく異質な外国人のお客さんの前で演奏しますが、最終的には自分たちのすべてを爆発させるしかない。それで何か良い結果を得られたからこそ、今日まで続けてこられた感覚がありますが、その点において東京オペラシティと荻窪ロフトは同じような感覚があるような気がします。
──そう感じられたのは、やはり荻窪ロフトが洋輔さんにとっても特別な場所であったからと考えられます。その上でお聞きすると、他のライブハウスと荻窪ロフトは出演者の視点で見ると何が違っていたのでしょうか?
山下:ひとつ言えるとすれば、荻窪ロフトは文学的な空間でしたよね。あとからオーナーの平野さんが、文学者の平野威馬雄さんの縁者であるのを聞いて、その血筋の影響はあるのかなと感じたこともありました。それともうひとつ大事なのは、上手く伝わるかわかりませんが、荻窪ロフトは音楽だけのライブハウスではなかったんですよ。いろんな討論会とかも非常に多かった気がするし、だからこそそのなかで僕たちもブッキングされて演奏する時は刺激的だったんですよ。
──現在のロフト・グループはトークライブハウスの経営が増えて、それこそ"政治家から犯罪者まで"面白い人なら誰でも出演させるというスタンスが根底にはあるのですが、以前、平野さんが「実は荻窪ロフトや新宿ロフトでもけっこう討論会なんかもやっていたんだよ。だから俺のやっていることはそれほど大きく変わってはいないんだよね」と語っていたのを記憶しているんですよね。
山下:その通りだと思いますね。だから平野さんの求める感覚は当時から一貫していたんでしょうね。僕には新宿ピットインという大切なライブハウスがあるんですが、その一方で、出演するには覚悟のいる荻窪ロフトが対極としてあった(笑)。しかもお店にもお客さんにも文学的な批評精神があって、常にその視線に晒されるけど、ちゃんと観たいという気持ちは伝わってくるから、決して嫌な視線ではなかったという印象が今でも残っているんです。それと60年代には、新宿ピットインでも深夜に唐十郎さんが芝居をやりに来たことがあったんですね。当時はまだ新宿にロフト・グループはお店を営業していませんよね? もしかしたら新宿ロフトや、その後にできたトークライブハウスとかが、結果として60年代の新宿ピットインが持っていた文化的側面を受け継いだのかもしれないとも感じられるんです。

 ──興味深い考察ですし、今回の洋輔さんのLOFT HEAVEN出演は、昨年12月に行なわれた新宿ピットインでの洋輔さんのライブに、当日参加した現在達郎バンドのドラムである小笠原拓海さんが平野さんを招待したことが起点となっています。つまり、すでにこの時点で語り尽くせない多くの宿縁があって成立しているライブなんですよね(笑)。
──興味深い考察ですし、今回の洋輔さんのLOFT HEAVEN出演は、昨年12月に行なわれた新宿ピットインでの洋輔さんのライブに、当日参加した現在達郎バンドのドラムである小笠原拓海さんが平野さんを招待したことが起点となっています。つまり、すでにこの時点で語り尽くせない多くの宿縁があって成立しているライブなんですよね(笑)。
山下:本来なら小笠原君がやれれば良かったんだけど、現在達郎さんのツアーに重なっていて参加できないことが、今回唯一残念ですけど、でもタイミングさえ合えばまた来年でもLOFT HEAVENでやるチャンスはあると考えていますから。それにイベントで共演してはいますが、僕と向井秀徳さんとの対バンを考えてくれるのは、たぶんLOFT HEAVENくらいじゃないですか(笑)。またアンコールで一緒にやることもあるかもしれませんから、一応備えをしておきたいとは考えています。でもとても光栄で楽しみな対バンだと心から感じています。
──では最後はごくシンプルに、9月12日のライブに向けてのコメントをお願いします。
山下:すでに知っている方も、初めての方も、こういうピアニストがいると知っていただければ嬉しいです。同じ時間を過ごすなかで、少しでも何かを感じてもらえるように全力で演奏したいですね。
あと蛇足ですが、平野さんが「森山威男の山下洋輔トリオからの脱退は荻窪ロフトで決まった」と自分の本で書かれているようですけど、そこまでドラマチックな展開だったかと問われると違うような気がします(笑)。当時、1975年いっぱいの森山の脱退は、じわじわと穏やかに進んでいたんです。荻窪ロフトで平野さんが見聞きしたような決定的な論争が僕たちにあったとは思えないんですけど、ただそれも平野さん特有の文化的文学的批評精神では、そのように捉えられてもおかしくない状況があったのかもしれません。あえて真偽は問わないでおきましょう(笑)。