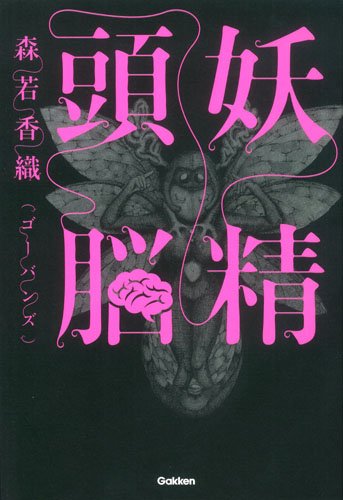憧れのTH eROCKERSを東京で初めて観たのも、東京で初めてGO-BANG'Sのライブをやったのも、小滝橋通りにあった新宿ロフトだった。歌舞伎町へ移転して間もない新宿ロフトのバー・ステージで始めたのが、ポエトリー・リーディングの要素を取り入れたアコースティック・ライブ『Kaolyrics 2000』。それはいつしか『KaolyriX』と綴りを変えてネイキッドロフトの人気イベントとして定着し、昨年からはロフト9渋谷でのマンスリー・イベント『KaolyriX 9』としてみたび復活。渋谷のラストワルツをロフトがプロデュースすることになればそのプレオープニング・イベントの初陣を飾り、ロックカフェロフトがオープンすれば自ら唄って踊る異色のDJイベントを主催する。ロフトが新たなコミュニケーション・スペースを立ち上げるたびに図らずも森若香織が新たな自主企画を始めるというウィンウィン関係の不思議。この図式はもはや偶然ではなく必然、運命の輪なのだろう。今年、GO-BANG'Sのメジャー・デビュー30周年を迎え、キュートな歌声と妖精トークにますます磨きがかかる森若に聞く「ロフトと私」クロニクル、約40年分。(interview:椎名宗之)
"類ツボ"の人たちが集う場所を大切にしたい
──昨年の10月からロフト9で『KaolyriX 9』を月一ペースで開催していただいていますが、手応えはいかがですか。
森若:『KaolyriX』に集まってくれるお客さんは私のコアなファンなんですよね。「あいにきて I・NEED・YOU!」を別にやらなくてもいいと思ってる人が大多数で(笑)。森若香織のソロはGO-BANG'Sとは違って内省的で玄人受けする感じなんですよ。そんなマニアックなお客さんが8年前にネイキッドロフトでやっていた『KaolyriX』に来てくれるようになって、今も懲りずにずっと応援してくれる人たちが『KaolyriX 9』に来てくれてるんです。本当はGO-BANG'Sっぽいライト層というか、マニアックな人たち以外にも観てもらいたいんですけど、ロフトさんからは「もっと客を集めてから来いよ!」なんて絶対に言われないし、それどころか「継続は力なりですよ!」と背中を押されながらやらせてもらってるし、もう本当に足を向けて寝られませんよ(笑)。
──まぁ、以前から森若さんの番記者みたいな男が現社長ですからね(笑)。
森若:(加藤)梅造さんですね。ロフト9がオープンした頃、私が10代の頃にファンで新宿ロフトまで観に行ってたザ・ロッカーズのトークライブがあって、そのMCをスマイリー原島さんと一緒にやらせてもらったんです。ちょうどその頃にまた『KaolyriX』をやりたいと思って梅造さんに連絡したら、いつのまにか社長になっててビックリしたんですよ。社長案件だとすごく話が早くて、即「やりましょう!」ってことになって、あっという間にスケジュールも決まって。これはもう運命だなと思いましたね。ロフト的に言えば因果鉄道の旅ですよ(笑)。コアなお客さんと私の関係もそうだけど、ロフトと私の因果鉄道の旅が急に加速していったんです。
──以前の『KaolyriX』はポエトリー・リーディングの要素が取り入れられたアコースティック・ライブでしたが、今は森若さん独特の妖精トークが大きな比重を占めてきましたね。
森若:私のソロは歌詞が好きだと言ってくださるお客さんが多いんです。暗いけど「人生を楽しもう!」というテーマが一貫してあって、GO-BANG'S時代の「楽しんだほうがお得!」みたいな歌詞と実はつながってるんですよね。『KaolyriX』ではそういう歌詞をもっと具体的に、なぜ楽しむべきなのか? をちょっと哲学的に話したりするので、自ずとトークの部分が長くなっちゃうんです。お客さんも私もお互いに年齢を重ねて、守られる側から守っていく側に、自分から発信していく側になって、人を動かす立場になってきた。その立場になった今、誰かの犠牲にならずに人生をどう楽しむべきか。それを突き詰めると、まず自分自身が幸せになることが大事なんですよ。自分が楽しくて幸せであれば誰かを傷つけることはしないし、争い事もなくなりますよね。そろそろ私たちの年代はそっち側にシフトチェンジしませんか? と『KaolyriX』では伝えてるんです。私のコアなファンは類友ならぬ類ツボというか(笑)、類友よりも共感できるツボがことごとく近いし、そんな人たちが集まれば怖いものなんてないと思うんですよ。
 ──僕もそうでしたが、ライブハウスに一人で行くような人は教室の隅でポツンと浮いた少数派ですよね。でもその少数派を温かく受け入れてくれるのがライブハウスという特殊な空間だったと思います。
──僕もそうでしたが、ライブハウスに一人で行くような人は教室の隅でポツンと浮いた少数派ですよね。でもその少数派を温かく受け入れてくれるのがライブハウスという特殊な空間だったと思います。
森若:GO-BANG'Sはもちろん、私のソロのマニアックな曲が好きだという共通項があれば、知らない人同士でもすぐに打ち解けられると思うんです。そういう類ツボの人たちが居心地よくいられる場所を私は大切にしたいんですよ。以前、梅造さんと平野(悠)さんの対談を読んで腑に落ちることがたくさんあったんですよね。特に「ライブハウスはお客さんと演者と店の三位一体でつくるものだ」という平野さんの言葉は本当にその通りだなと思って。私の根底にあるのはロフト魂、ロフトイズムなんだなと実感しましたね(笑)。ロフトはどの店舗も居心地がいいというか、実家感がものすごくあるんです。それは別にお世辞で言ってるわけじゃなくて、普通にそう感じるんですよ。札幌に住んでた頃からロフトは憧れでしたしね。
GO-BANG'Sを名乗ると必ず何かが動き出す
──ロフト9のみならず、森若さんには今年オープンしたラストワルツ・イン・ロフトとロックカフェロフトにも立て続けに出演していただきましたが、新店舗の感触はいかがでした?
森若:もう私のためにオープンしてくれたんですか? って感じで(笑)。今年はGO-BANG'Sがメジャー・デビュー30周年だから何かイベントをやりたいねとポニーキャニオンのディレクターと話していた時に、ちょうどラストワルツの話を梅造さんからいただいたりして。これはGO-BANG'Sマジックと言うか、私が特に何もしてなくても、なぜか周りが動いてくれるんです。GO-BANG'Sの屋号を掲げた途端に何かが勝手に動き出すんですよ。札幌のスタジオミルクを介して(忌野)清志郎さんが私たちのデモテープを見つけてくれたのもそうだし、GO-BANG'Sの名前がついた途端にいろんなことが動いていくのが昔から自分でも不思議で。
──神は細部ならぬ屋号に宿ると(笑)。面白いですね。
森若:ラストワルツの打ち合わせを梅造さんとした時、会場を女性仕様にしてくださいよと話したんです。ライブハウスは男社会すぎて、女性のお客さんが怖がるじゃないですか。トイレの壁に猥雑な落書きがストレートに書いてあったりして。そしたらラストワルツのライブ当日、楽屋に女優鏡が置いてあったんですよ(笑)。会場もラグジュアリーな雰囲気でライブがやりやすくて。叶えてもらえるかどうかはともかく、そうやって演者の希望を聞いてくれるのがロフトのいいところだと思います。他のライブハウスには言えませんからね。それにスタッフの皆さんの挨拶もちゃんとしてるし、愛想もいい。ライブハウスは女性からすると怖いとか暗いとか行きづらい印象があるので、普通のお店以上に接客がちゃんとしていないとダメだと思うんです。ロフトはそのへんもしっかりしてるし、老舗の安定感がありますよね。コミュ障みたいなお客さんでも温かく迎えてくれる包容力と多様性を大切にする懐の深さがあるというか。たとえば犯罪者とか、ちょっと引くような演者でもロフトは全く動じないし、相手を尊重しながらもちゃんと面白がってるって言うのかな(笑)。その絶妙なバランス感覚がロフトイズムというか、私にも通じる部分があるんです。
──そこまで言っていただくと、逆にロフトのダメな部分を挙げてもらわないとバランスが取れませんね(笑)。ロックカフェロフトはいかがでした? GO-BANG'Sの曲に合わせて唄う姿がスナックのカリスマ・ママ状態だったと評判でしたが(笑)。
森若:2階に上がってまで唄いましたからね。自動ドアをなぜか力ずくで閉めて1階に戻って(笑)。ああいうバカなことをやってこそ森若だと理解してくれるお客さんしかいなかったので、私も気を使わずに伸び伸びとやれました。いつもサポートしてくれてるFAIRY ROCKのみんなも自由に楽しんでくれたし、ああいうコアなイベントはロフト以外ではできませんよ。
 ──ロックカフェロフトは70年代のロック喫茶がテーマなんですけど、森若さんはロック喫茶の世代じゃありませんよね。
──ロックカフェロフトは70年代のロック喫茶がテーマなんですけど、森若さんはロック喫茶の世代じゃありませんよね。
森若:でも私、中学生の時に札幌のロック喫茶に入り浸ってましたよ。レッド・ウォーリアーズやイエロー・モンキーとかのサポートをやってた三国(義貴)さんがフェアリーっていうハードロック・バンドを札幌でやってて、フェアリーがよくライブをやってたライブバーみたいな店とか、周りにあったロック喫茶に年齢をごまかして行ってましたもん。そこで大人に混じってリクエストとかして。
──ではロックカフェロフトのコンセプトも理解していただけていたと。
森若:というか、私のためにつくったのかな? って(笑)。クイーン、キッス、エアロスミス、ベイ・シティ・ローラーズとか70年代のロックは私がいちばん最初に好きになった音楽ですからね。その前のレッド・ツェッペリンとかディープ・パープルは札幌のロック喫茶で知ったし。それにラモーンズやパティ・スミスとかニューヨーク・パンクも70年代だし、私の音楽遍歴とロックカフェロフトのコンセプトが被りまくりなんですよ。70年代の私は「日本でいちばん洋楽に詳しい中学生」というキャッチコピーで生きてましたから(笑)。でも決してコミュ障ってわけじゃなく、漫画や映画のオタク、軽音部のモテない人たち、モテる女の子たちや男の子たちとちょっとずつ仲良くできてたんですよ。各グループに深入りはしないけど、私が行くと喜ばれるみたいな。そういう特異な性格をその頃からフル活用してましたね。