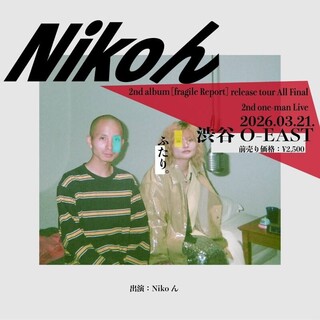スキーター・デイヴィスの「The End of the World」を筆頭に、ビートルズ、ローリング・ストーンズ、フー、キンクス、スモール・フェイセス、ラモーンズなどの名曲をカバーしたアルバム...と聞くと、なんだ、ずいぶんとベタな企画だなと特にミドルエイジのロック好きは思うかもしれない。東京生まれLA育ちの21歳女性ヴォーカリスト・AKIRAを中心に今年結成された、平均年齢25歳のメンバーからなるラヴェンダーズのデビュー作となる『Luv-Enders' Invasion!』はまさにそんな内容だが、ポップでカラフルで芯の太い硬質なビートの効いたアレンジに彩られたパンキッシュなカバーの数々は、AKIRAのプリミティヴで瑞々しい歌声も相俟って清新な輝きを放ち、2017年最新鋭のロックとして現代に蘇っている。それは森山達也(ザ・モッズ)とKOZZY IWAKAWA(ザ・コルツ、ザ・マックショウ)による共同プロデュースの手腕も大きいが、蘊蓄を傾けることばかり優先されてきたロックを若い世代に取り戻せとばかりに意気込むバンドのロックに対するピュアな真情があってこそだ。ロックの女神に導かれたとしか思えないAKIRAの生い立ちから現在に至るまでの話を聞きつつ、伝承音楽であるロックの奥深さ、面白さを掘り下げてみたい。(interview:椎名宗之)
若い世代にロックを伝えるメッセンジャーになりたい
──今年の3月に赤坂BLITZで行なわれたモッズとコルツの『LITTLE SCARFACE FESTA 2017』でラヴェンダーズがオープニングアクトを務めた時は、メンバーが今の編成とは違いましたよね。
AKIRA:あの時はギターがKOZZY IWAKAWAさん、ベースが原宿でレッドモーテルという洋服屋さんをやってるTAKA5H1くん、ドラムが大島賢治さんという形態だったんですけど、今回、CDをつくるにあたっては私と同世代の若いメンバーでバンドを固めようと思ったんですよ。それで昔から知り合いだったTAKERUにギターを、知人の紹介でスカコアとかを通ってきたTOSHIにドラムを、パブロックのバンドをやってるKAZUKIにベースをそれぞれお願いしたんです。
──バンドをやる構想はどれくらい前からあったんですか。
AKIRA:ずっとやりたいとは思っていたんですけど、私自身、LAのカレッジに在籍していたのもあって、なかなか実現できなかったんです。きっかけはモッズの森山さんからの電話だったんですよ。B.A.Dのコンピレーション・アルバムに入っていた私の曲(B.A.D RECORDS UNITED presents『Rock, Everybody, Rock 〜Rocksville Studio One In Tokyo〜』に収録された「AKIRA & THE ATOMIC DADS」名義の「恋を抱きしめよう」、2014年発表)を森山さんが気に入ってくださったんです。上手く唄おうとしていない、素直に唄っているところがいいってことで。それで森山さんが私をプロデュースしたいと言ってくださって、その流れで本格的にバンドをつくることになりました。
──B.A.Dのコンピ収録曲がAKIRAさんにとって初めてのレコーディングだったんですか。
AKIRA:その前に、これもB.A.Dから出たハイチ震災の復興支援チャリティ・アルバムに参加したことがあったんです(『B.A.D COVERS FOR HAITI 〜ROCK'N ROLL WILL CHERISH EVERY MOMENT, THE LIFE, THE WORLD〜』に収録された「AKIRA & THE ATOMIC DADS」名義の「I WANT YOU TO WANT ME」、2010年発表)。あれが最初のレコーディングでした。
──ラヴェンダーズを結成した時の基本的なコンセプトはどんなものだったんですか。
AKIRA:ロックを大人たちのものだけじゃなく、若い人たちのものにもしたいっていうのがありましたね。ずっと聴き継がれてきた、こんなに格好いいロックもあるんだよっていうのを若いジェネレーションに伝えていくメッセンジャーになれるようなバンドをつくりたかったんです。
──そもそもAKIRAさんはなぜ古き良きロックンロールやブリティッシュ・ビートを好んで聴くようになったんですか。
AKIRA:子どもの頃からロックが身近にある環境だったんですよ。両親がロックカフェをやっていて、家もそのカフェの二階で、ビートルズ、ストーンズ、キンクス、フー、スモール・フェイセスといった今回のアルバムでカバーしたバンドの曲がカフェでよく流れていたし、自然と刷り込まれていたんですね。そういったバンドの曲が自分の大きな基盤になっているんです。
──でも、小学校や中学校の同級生とはまったく話が合いませんよね?
AKIRA:そうですね。話を合わせるためにポップスやJ-POPを聴いてみた時期もありました。中1の時に西野カナさんとかGReeeeNがすごくヒットしていた世代なんですけど。
──西野カナやGReeeeNなんて、ぼくらからすれば一昨日くらいの感覚ですけどね(笑)。
AKIRA:いっときロックから離れた時期もあったんですけど、高校の頃にまた古いロックに戻り始めたんです。当時、都内の国際高校に通っていたんですけど、なんか物足りなさを感じて1年で自主退学したんです。それでLAへ留学させてもらうことにしたんですよ。
──広い世界の見識を深めたかったからですか。
AKIRA:それもあったし、英語を学ぶ上で日本だとリミットがあるなと思ったんです。それなら海外に出て、生身の英語や文化を学ぶほうが意味があるなって。そのほうが英語を自分の言葉にできるじゃないですか。自分の言葉として海外のロックを聴けるし、字幕なしで映画を観たりもできるし。そんなふうになってほしいという父からの後押しもあったんですけどね。
英語を習得すれば自分なりの解釈ができる
──では、LAのパブやライブハウスで本場のロックを体感する機会にも恵まれたんですか。
AKIRA:そうしたい気持ちは山々だったんですけど、向こうは年齢制限がすごく厳しくて、21歳にならないとライブハウスには行けないんですよ。18歳から入れる店もあるんですけど。
──それは残念でしたね。だけど、あの映画『ラ★バンバ』にも出てくるリッチー・ヴァレンスの墓地を有する高校に進学されたというのは何やら運命めいたものを感じますね。
AKIRA:墓地が真横にある高校だったんです。ああ、こんなところにリッチー・ヴァレンスのお墓があるんだ…と思って。
──リッチー・ヴァレンスを知っている日本の女子高生っていうのもすごいですけどね(笑)。ネイティブ・スピーカーの話す英語を理解できたり、彼らと対等に会話ができるようになったのがやはり留学のいちばんの収穫ですか。
AKIRA:もちろんそれもありますし、今回のアルバムでカバーしたような曲を誰かの対訳なしで、自分なりの解釈で聴けるようになったのが大きいですね。
──内田久美子や山本安見の対訳なしで聴けると(笑)。ちょっと話が逸れてしまいますが、ビートルズの「Tomorrow Never Knows」や「A Hard Day's Night」といったタイトルはやはりちょっとおかしな言い回しなんですか。文法的には正しくない、リンゴ・スター独自の表現だと言われていますけど。
AKIRA:ヘンですね。ビートルズの曲はぜんぶヘンです(笑)。英語というよりビートルズ語なんですよ。イギリス人っていうのもありますけど、すごい独特な言語感覚だと思います。それも私なりの解釈ですけどね。ジョン・レノンが本当に唄いたかったことと日本語の対訳が合致していないこともありますけど、それは翻訳者の都合のいい解釈というか、受け手が自分の好む言葉を選んでいるからじゃないですかね。映画の字幕は特にそうですよね。「そんなこと言ってないよ!?」っていうのがいっぱいありますし、役者のセリフじゃなく、翻訳者の言葉になってますから。
──その辺の話はとても興味深いので、また改めて聞かせてください。森山さんから電話があってアルバムをつくることになったのが理由で帰国したというわけですか。
AKIRA:そうなんです。「アルバムをつくるから日本へ帰ってきて」と突然言われて(笑)。それまで私は向こうのカレッジで音楽を学んでいたんですけど、音楽の勉強ってこんなものなのかなぁ…と思い始めた時期ではあったんですよ。それよりも森山さんにプロデュースしてもらってアルバムを一枚つくるほうがよほど音楽の勉強になるんじゃないかって。
──カレッジでの勉強は実践的ではなかったと。
AKIRA:音楽理論を学んだり、自分で曲を書いたり、ロックの歴史を学んだりする勉強はできるんですけど、楽器をプレイするとかはできなかったんです。授業で音楽を学ぶのもなんか違うなと思ったし、自分がこの先やりたいことの参考にはあまりならなかったし、自分の興味と共通の会話ができる友達もいなかったんですよね。
──森山さんからのお誘いは渡りに船だったわけですね。
AKIRA:森山さんにも「ミュージシャンになりたいんだったら、大学で勉強するよりも実際にアルバムをつくるほうがためになると思うけどね」みたいなことを言われたんです。森山さんとしては、「21歳までにデビューしたほうがいい」ってことで。あと半年でカレッジを卒業するところだったんですけど(笑)。そんな話をもらったのが今年の初めで、3月に日本へ帰ってきて、すぐに赤坂BLITZのライブに出させてもらったんですよ。今はカレッジを休学中なんです。
──なぜ森山さんは21歳までにデビューさせたかったんでしょう?
AKIRA:森山さんのデビューが25歳で、自分が遅かったから早いうちがいいってこともあったんでしょうし、シド・ヴィシャスを引き合いに出してましたね。
──シド・ヴィシャスが21歳で亡くなったからですか。
AKIRA:シド・ヴィシャスは21歳で「My Way」を唄った、AKIRAは21歳で「The End of the World」を唄った。そういうのがハッタリとしてもいいんじゃない? って。
──なるほど。考えてみれば、デビュー曲が「世界の終わり」だなんてヘヴィですよね。
AKIRA:でも、「終わりは始まり」とも言いますから。ああいうヘヴィな失恋の歌をポップに唄うことの面白さもありますし。