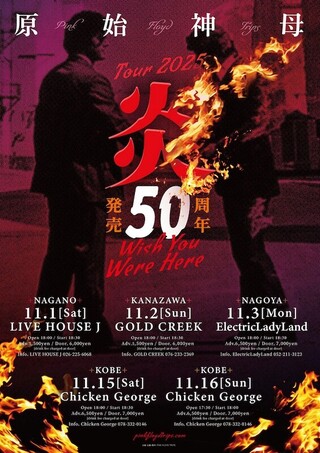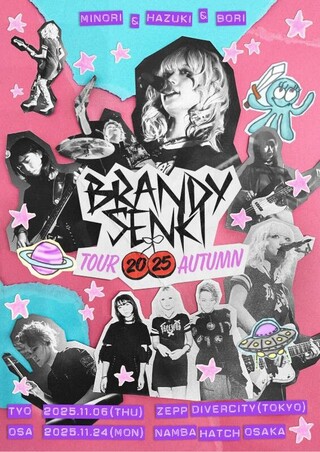a flood of circle(以下、AFOC)がニュー・アルバム『GOLDEN TIME』を完成させた。熱く、がむしゃらに、転がり続けるロックンロール・バンドの生き様を見せてきた彼ら。勢いと逞しさを増してきたここ数年を経て、先日には新ギタリストとしてDuranが加入。いよいよ"黄金期"を迎えようとしている。ニュー・アルバムは、そんなバンドの充実を痛感させるような一枚。そして、新作はロックンロールの芯を守りながらも、新たな音楽的挑戦の数々を繰り広げたアルバムでもある。「2014年に鳴らすブルース、今の時代にぶち込むロックンロール」として、彼らはどういうものを目指したのか? バンドはどう変わってきたのか? 佐々木亮介(vo, g)に語ってもらった。(interview:柴 那典)
──まず、新ギタリストとしてDuranさんが加入したという話から訊ければと思うんですけれども。彼のギターのどういうところに魅力を感じて、どういう経緯で加わったんでしょう?
「もちろんギターも魅力だったんですけど、まずポイントとして大きかったのは“人”なんですね。彼は2つ上なんですよ。今まではもっと歳上の兄貴たちがサポートとして加わる形でライブをやってきた。そういうものだと思ってやってたんです。3人でレコーディングをやって、ライブはサポートをお願いする。そこに腹を括ってやってたから、別にギタリストの枠をあけていたわけじゃなくて。たまたま出会ってしまったのがDuranだったという。そういうことですね」
──人としての魅力はどういうところに感じたんでしょう?
「彼もいろんなバンドをやってきたので、経験的にも似たような悔しさを持っていたり、似たような苦さの汁を舐めていたりしたんですよね。そもそも彼もブルースが好きだという不幸な趣味を持って(笑)、それをこの2014年にどう鳴らすのかということをずっと考えているヤツだったし。で、そういう人間性がギターに出てるんですよ。だから、こいつがいると同じ目線で夢が見れると思った」
──単純にギターの腕前だけを買うんだったら、サポートでいいわけですからね。メンバーに加入したということは、同じビジョンを共有して、同じ苦労をできるという信頼感がある。
「そう。俺らはもともとブルースとロックンロールが好きで、それを如何に今の時代にぶち込んでいくかというところで試行錯誤してきたバンドだったから。そこでガッチリ合ったんですよね。と言うかね、ギターに関してはもう少し下手でもいいくらいだったんですよ(笑)。上手すぎるから、ホントに」
──振り返って、前のアルバム『I'M FREE』は、言わば逆ギレ的なアルバムだったと思うんですよ。“自由”と“無料”のダブル・ミーニングだったタイトルがその象徴だった。バンドのスタンスはそこから変わってきた感じでしょうか? それともその芯は変わらず持っている?
「無駄にキレてる部分は変わってないかもしれない(笑)。ただ、そのアルバムを持って全県ツアーをやったんですよ。ホントに47都道府県をくまなく回ってきた。で、その後に3日間で80曲やるという全曲ライブをやって。それを経て自然と変化してきたところはあると思いますね。ただキレてるだけじゃなくなった。ロックンロールで転がっていく様を見せて、目の前にいる全員を連れていくためにはどうするかを考えるようになった。そういうことを考える中で『GOLDEN TIME』という言葉が生まれてきた」
──『GOLDEN TIME』という言葉はどういう象徴として出てきたモチーフだった?
「基本的には、ライブの時間を示す言葉なんです。ただ、そこにもいろんな思いがあって。世の中の状況に対して思うこともあった。ちょうど今年の4月頃に憲法改正の話があって。それも大きかった。別にバンドマンが社会的なことを発言する責任があるとか思ってるわけじゃないんですよ。だけど、自分の身近なところを見ても、俺の周りにいる人たちが傷つく方向に変わっていると思うようになって。そこで『GOLDEN TIME』という言葉の大きさが生まれてきた。俺にとってライブの時間はそうだし、それ以前に、音楽をやって、ロックンロールを鳴らして、突き抜けてる瞬間って、なんて愛しいんだって思ったんですね。誰かが決めたルールに従うんじゃなくても、自分でそういう時間を作り出せる。作らないといけない。それを『GOLDEN TIME』と呼びたい、という」
──AFOCはそういうものを作ってきたバンドである、という宣言も込められている?
「そうだし、希望も込めてるかな。これからもそうしていきたい、という」
──僕としては、最初にこの言葉を聞いた時、4人になって新しいバンドの黄金期が始まるという宣言かな、とも思ったんですけれども。
「なるほど! それにしときましょう(笑)」
──実際、アルバムを聴くとバンドの曲作りにおいても新しいチャレンジをやってきている感があって。新しい挑戦が結実したアルバムでもあると思うんです。
「そう言ってもらえると嬉しいですね。そういう新しいことを始めたのは『KIDS/アカネ』というシングルからなんです。『I'M FREE』までの3枚で、姐さん(HISAYO/b)が入って3枚なので、そこでひとつのスタイルが完結した感じがあって。何かを変えないとバンドも止まるし、せっかくこのスピード感でやってるんだから、それを活かすためには何かを変えないといけないと思って。単純にまずメロディから作るようにしたんです。それまでは歌詞から作っていたんだけど、曲作りの方法を変えた。あと、ドラムにもいろんな要求をしたのもあります」
──「KIDS」はその始まりになった。
「そうですね。新しいリズムをやろうと思った。コード進行にしてもリズム・パターンにしても、如何にはみ出すか。いわゆるロックンロール・バンドがやろうとしないことにどれだけ挑戦するかを考えていましたね」
──と言っても、AFOCは基本的にはロックンロール・バンドであって。
「そうですね。シーンをどうこう考えた時に、軸足はロックンロール・バンドにあるから。こないだ『ロッケンロー☆サミット』に出たんですけど、やっぱり居心地がいいんですよ。ギターウルフを見ていても、凄くアートに見えるし。それがいいなって思ったし。キングブラザーズもSAも、みんなヘンだし。ロックンロール・バンドに軸足があるっていうのは重要なことなんですよね。そこから派生した今の戦い方、尖らせ方がある」
──ただ、ロックンロールの美学として「変わらないことをやり続ける」というスタイルもあるわけですよね。だけど、AFOCはその道は選んでいない。新しいことにどんどんトライしている。
「そうですね」
──で、「KIDS」は特にそうですけれど、このアルバムは随所に、「動物がダンス・ロックをやってる感じ」みたいなのがあるんですよ。
「そう言ってくれるのは一番嬉しいですね。どれだけダンス・ビートをやっても、俺たちは機械的にできないから。『Rodeo Drive』という曲も、俺らの世代だったら、もっときっちりとしたダンス・ビート、もっと速い4つ打ちをやると思うんです。でもそれはやらないし、スネアを外したりキックをずらすだけで動物的になる。それはAFOCの武器になると思いましたね。ただ俺らとしては、若手と対バンしても浮いてるし、『ロッケンロー☆サミット』に出ても浮いてるっていう」
──「KIDS」のビートは個人的にはレゲトンっぽい感じがして。それを高速化したらロックンロールになったというような発明だと思うんです。そういう新しいビートでやりたいという欲求はどういうふうにして出てきたんでしょう。
「最近、マネージャーにヒップホップの本をもらって読んでるんですけど、そこに『ヒップホップはコンペだ』ということが書いてあるんですよね。基本的なルールが決まっていて、その中でいかに優れたものを出すかという。言ってみれば、ブルースもそうなんですよね。ロックンロールだってそう。『ロッケンロー☆サミット』に出てるバンドって、みんな革ジャンで、みんなスリーコードで、同じルールでコンペやってる。でも、この感じが馴染めないんだと思って。若手のバンドだって、今の時代に4つ打ちでダンス・ロックをやってるのはコンペっぽい。シーンから外れたいとは思ってないけど、自分たちの戦い方にはそういうコンペっぽい発想がない。それに気づいたんですよね。ヘンなことをやろうと思ってるわけじゃないけど、たまたまヘンなところにいたんだという。だからビートもヘンなものが出てきちゃう。そこは武器なんだと思うようにしてますね」
──「Golden Time」というリード・トラックもそういう曲ですよね。曲の中でビートがクルクルと変わる。
「そうそう。5パターンくらい入ってるかな」
──これもメロディとビートに力を入れている曲だと思うんです。
「やっぱり歌とリズムが一番大事だと思うから。そこの変化を求めたところはありますね。単純に俺たちがやってきてないことをやりたいというのもあるし。1曲の中に5つもパターンがある、みたいなことの面白さもやりたかったから。ナベちゃん(渡邊一丘/ds)は器用なタイプじゃないから大変でしたけど、そこは頑張ってもらいました」
──そこで高いハードルを超えてもらうというのは、どういう感じだったんでしょう?
「苦しそうでしたよ。めっちゃ苦しそうだった。でも、ロックンロールの“ロール”をするためには、なあなあじゃダメなんですよ。延命治療をしちゃいけない。一瞬で燃え上がるのは“ロック”でいいんですけど、“ロール”をするためには、それだけじゃダメで。だからナベちゃんにも妥協するつもりはなかったし。あいつも応えてくれたから。曲になった喜びはデカいですね」
──しかもこの曲のAメロのビートって、よく聴くとかなりヘンなんですよね。実はめちゃめちゃ実験的なことをしてる。
「そうなんですよ。コード進行も分析すると変わったことをやっていて。そういう違和感の連続が今回のアルバムにはたくさん入ってる」
──「Rodeo Drive」も、そういうタイプの曲ですよね。かなり変わった感じになっている。
「そうですね。これ、細かいことを言うと、ドラムが4つで刻んでいる上で、ギターが2拍目だけシャッフルしてる。跳ねてるんですよ。凄くヘンなことをやってる。音楽的に解析できなくて。なんでそんなことをやったかと言うと、最近、ロック・バンドでもクリックをきっちり聴いて録音することが多くなってきて。自分たちもそうすることは多いんですけど、それが堅苦しく感じるようになっちゃって。で、こないだ久々にジミヘンを聴いたら、クリック通りになんてとても弾いてないんですよ」
──そういう、ビートにきっちり乗ってないギターにした。
「そう。ドラムはきっちりと刻んでるけれど、ギターは全然リズムに乗ってないという。そこがだいぶ動物的だという。で、この曲はタイトルも『Rodeo Drive』と決めてたんで。これは乗りこなすとか振り回されてるって感じより、乗っかってるものをすべて振り切りたいという。そういうイメージでしたね」
──ただ、そういう変則的なことも、ただ単に頭で考える実験じゃなくて、ちゃんと動物的と言うか、身体的な音楽として形になっている。そういうバンドだなって思います。
「それは嬉しいな。それこそDuranが入って、4人でやれるようになったことも大きいのかもしれない。前は自分で2本のギターを入れていたんで。それはある程度考えないとできない。今回は4人で『せーの!』でできるから、その場で楽しめるし、アイディアも出てくる。それがクリエイティブなこととしてやれているという」
──「スカイウォーカー」もそういう、バンドならではの曲ですよね。
「まさにそうですね。この曲はDuranが入ってなかったらできなかった。この曲のビートはクイーンズ・オブ・ザ・ストーン・エイジを参考にしたところもあって。そういうルーツを2014年のロックンロールに落とし込むということもやったし。ただ、それを頭でっかちな部分だけじゃなくて、肉体的にできるようになった。レコーディングの感覚も前より自然になったと思いますね」
──「STARS」はどうですか?
「これもできて嬉しかったですね。Duranのギター・ソロも気に入ってるし。リード曲になるとは考えてなかったんですよ。がむしゃらに作っていった曲が、それになった。自分の想像していたものをバンドが超えていった感じがした」