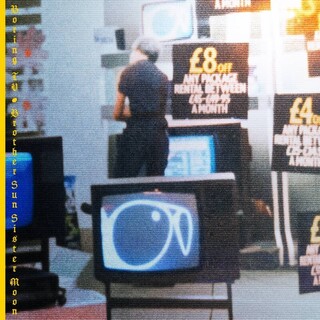フックとして作用するノイズ成分の大切さ
──4人で音を合わせてみて、元のイメージが大きく変わる曲もあったんですか。
マツキ:今回はそんなにないですね。
コヤマ:うん、ないよね。何かを付け足すっていうよりは、シンプルにしていこうみたいな進め方だったんですよ。「ここは要らないからはしょっちゃおうか」って感じで。あとはスピード感ですね。やっててかったるく感じた時はテンポを上げてみたりして。今回はそんなふうに、スピードが上がって曲が短くなる傾向があったかな。デモの段階よりも余分なところをどんどん削ぎ落としていった感じですね。
──全12曲収録ってかなりのボリュームだと思いますけど、どの曲もタイトな構成になっているから何度でも繰り返し聴けますよね。
マツキ:トータルで38分くらいですからね。
コヤマ:まさにLPサイズだよね(笑)。
──LPと言えば、今回もアナログ盤は出すんですよね。
マツキ:単純に自分たちが欲しいだけなんです。趣味みたいなものですね。アナログはグッズ感があって、モノとして集める楽しさがあるし、今年はこの作品を作ったんだなというメモリアル的な気持ちになるんです。僕らだけじゃなく、ライブに足を運んでくれる人たちとそんな気持ちを共有できるアイテムがアナログなんですよ。作れる限りは作り続けていきたいですね。
──LPサイズのトータルタイムにするのは意図的だったんですか。
マツキ:さすがに分数までは考えていませんでしたけど、曲はとにかくシンプルなのがいいなと思って。イントロ、歌、サビで完結するみたいな。それでパーッと聴けるんだけど、1曲ずつよく聴き込むと実はいろんなことをやってるっていうのが一番いいなと思ったんです。シンプルだけど奥が深いっていう。
──ソウル・ミュージックの典型的なリズムが土台の「やっかいなお土産」も、耳を凝らすと妙なギターのノイズが後ろでぐるぐる回ってますよね。
マツキ:何かしらの引っかかりとなる音を入れたくなるんですよね。ノイズ成分が大事っていうのは、PEACE MUSICでレコーディングを始めて以降、僕らの裏テーマみたいなものなんです。たとえばケータイの着信音で始まる曲だったり、何かしらのノイズが入っているんだけど違和感なく聴ける曲っていっぱいあるじゃないですか。一概にノイズと言っても決してアンダーグラウンドなものじゃなくて、人の記憶にふと入り込むフックとして作用することもあるんですよ。
──「無情の嵐」にもサーフ・インストでよく聴かれるピチャピチャした音が入ってますよね。
マツキ:それもフックなんですよね。別に入れなくてもいいっちゃいいんだけど(笑)。昭和歌謡によくあるラテンっぽさと言うか、曲調は純然たる歌謡曲なんだけど、オケはボンゴやコンガが鳴ってるラテンっぽい感じをやりたかったんですよ。そこにサーフ感が入ると歌の世界観とは真逆になるんだけど、それが違和感となって耳に残るかなと思って。
──「無情の嵐」と「囚われ者」の連なる2曲はGS(グループ・サウンズ)の血中濃度が高いですよね。
マツキ:そうですね。そもそも僕らの音楽は全体的にGS感が強いですから。
──「囚われ者」みたいにギターの音を終始大きく歪ませているのは珍しいケースじゃないですか?
マツキ:言われてみればそうですね。まぁ、デビュー・アルバムにはそういう曲が入っているものじゃないですか(笑)。
──得も言われぬ昂揚感と爽快感が訪れる「月に手を伸ばせ」や「あなたを教えて」みたいな正調スクービー節の曲があるからこそ、ノイジーな楽曲も映えますよね。
マツキ:たとえばGSのバンドで言えば、メンバーが書いた曲だけだと物足りないし、作家が書いた曲だけでも物足りないし、アルバムのサイズってとてもいいバランスなんですよね。作家が書いたシングル曲もあれば、メンバーが書いたオリジナル曲もあって。それと同じように、作家が書いたような完成度の高い感じがある「月に手を伸ばせ」や「あなたを教えて」みたいな曲もあれば、4人が勢い任せで作った「囚われ者」みたいな曲もある。そういうのが理想なんです。それがポピュラリティとして伝わるといいんですけどね。
──職業作曲家を仮想した曲作りって面白いですね。
マツキ:なりきりバカラックみたいな感じで。全然なりきれてないんですけど(笑)。
不完全な部分があるからこそグッとくる
──ところで、ライブ会場限定販売のカバー・アルバム『GRAND-FROG SESSIONS』(2014年2月発表)を制作したことで曲作りに影響を及ぼした部分はありますか。
マツキ:ありますね。あのカバー・アルバムに入れたのは僕らが結成当初からやっていたレパートリーばかりで、時々思い出しては演奏していたんですよ。それをいざアルバムとして録ることになって気づいたのは、どれもバンドの音だけで成立する良く出来た曲だなってことなんです。サビが来たら音を分厚くしたいからギターをもう1本入れたいとか、コーラスを重ねたいとか、そういうのが全くない曲ばかりなんですよ。一筆書きで起承転結がはっきりしていると言うか、バンドの4つの音だけで過不足なく成立するんですよね。自分たちはそういう曲がやっぱり好きなんだなと改めて思ったし、4つの音だけで充分に盛り上がれる曲を頑張って作りたかったんです。
コヤマ:『GRAND-FROG SESSIONS』を録ってくれたニートビーツの真鍋(崇)さんも、PEACE MUSICの中村さんも、人力で鳴らされた音を録音するのが基本で、そのやり方は今や貴重なんですけど、音楽的には絶対に正しいし、それがロックンロールだと俺は思うんです。この間、フェイム・スタジオのドキュメンタリー映画(『黄金のメロディ〜マッスル・ショールズ〜』)を見たんですよ。そのなかで、スタジオを経営しながらエンジニアもやっていたリック・ホールが「不完全でもそれが人間らしさだ。そういう不完全さが音楽には必要だと思う」と話していたんです。同じようなことを真鍋さんが『GRAND-FROG SESSIONS』のアナログ盤のライナーでも書いていて、中村さんにもそんな考えがあるみたいなんですよ。もちろんリズムは合っていたほうがいいし、コードもキレイに響いていたほうがいいんだけど、ちょっと演奏のズレた部分、不完全な部分があるからこそグッとくることがあると。今の時代、デジタル的なドーピングはいっぱいできるし、ピッチもいくらでも合わせられますけど、そんな音楽には心が躍りませんよね。
マツキ:それがさっき話したノイズ成分ということで、そういう不完全さが記録されてこそレコードなんですよね。多少ミスをしても直さないほうがいいんですよ。
コヤマ:年々直さなくなってきたよね。歌がちょっとヨレてるけどいいなと感じたりすることもあるし、ギターのリズムがズレててもノリが良かったりするし、気持ちが出ちゃってる部分はそのまま残したほうがいいんですよ。今は波形編集でいくらでも手直しができるけど、そういうのをやっても全然面白くないじゃないですか。
マツキ:ちゃんとした演奏がいい音楽ってわけじゃないからね。
ロックの魔法が真実に変わる瞬間を提供したい
──確かに。ちなみに、アルバム制作のたびに自分たちに課していることは何かありますか。
マツキ:その時々で自分たちが一番やりたいことをやってるだけですね。自分たちは変わることなく、周りが変わっていけばいいっていう思いが根本にあるし、自分たちの好きな音楽はずっと変わらないんですよ。それが変わらないまま、その年その年でいいと思える楽曲を作るっていうのがスクービーのコンセプトなんでしょうね。僕らもバンドをもっと大きくしていきたいけど、ミリオンセラーを出してドーム・ツアーを目指すことよりも、常にクオリティの高い作品を作ってリスナーの信頼を少しずつ勝ち得ることのほうがリアリティがあるんですよ。CDだけじゃなくて1本1本のライブを大切にやっていくことで信頼を得ていけば、その先に何かが待っているのかなと思うんです。
──来年は結成20周年という節目の年ですが、何か面白いことを計画中なんでしょうか。
マツキ:いろいろと考えているところです。計画通りに行けば派手な感じになりそうですね。計画通りじゃなければ、また考えなくちゃいけないんですけど(笑)。まぁ、来年もいっぱいライブをやるのは確かでしょうね。武道館みたいな大きな会場を満杯にすることもバンドの目標としてはありますけど、それは通過点であってゴールではないんですよ。だからどんな形であれ、バンドをやり続けることが一番大事だと思うんです。続けていなければ武道館やドームでライブもやれませんからね。
──「行こう 何度だって/それがやりたかったこと」という「転がる石」の歌詞の通り、苔が生える間もなく転がり続けるのがスクービーの流儀なんでしょうね。そんなバンドに「生きてることは何度も始められるってことさ」(「いいぜ いいぜ」)と唄われると、こんな時代だからこそグッときます。
マツキ:ロック・バンドはでっかい音を鳴らして、普段の素の状態なら言えないようなことを唄ってほしいんですよ。それがいつか真実に変わるようなエネルギーを持つ感覚を提供できるのがロック・バンドのCDやライブだと思うし、それを通じてロックの魔法が真実に変わる瞬間を僕らは提供したいんです。こういうちょっと元気のない時代だからこそ勇気がもらえる音楽を聴きたいし、ロック・バンドにはウソでもいいから何かでかいことを唄ってほしいんですよ。特に今はそんな時期に差しかかっている気がしますね。去年くらいまでは僕らもまだ震災のムードを引きずっていたけど、2014年は次のステップに行けるような、勇気や元気を提供する音楽やライブをやっていかなくちゃいけないんじゃないかと。僕らみたいなロック・バンドは面白いことをやってないといかんだろ!? と思うし、せっかく自分たちの手でCHAMP RECORDSという自主レーベルをやっているんだから、メジャーにはできない痛快なことを常にやっているバンドでありたいですね。