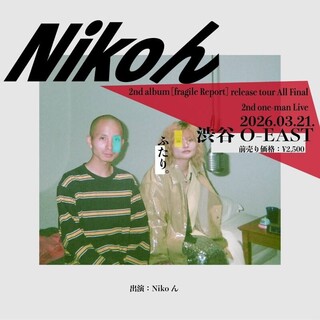ジョン・レノンの生誕70周年/没後30年のメモリアル・イヤーである今年はビートルズ関連を含めジョンの様々なアイテムがすでにリリースされているが、TIMESLIP(TIMESLIP-RENDEZVOUSより改名)の近藤金吾が主催するイヴェント『ジョン・レノンへの招待状』をきっかけに生まれたトリビュート・アルバム『#9 DREAM』は一風変わった作品だ。近藤を始め、宙也(De+LAX)、PLECTRUM、酒井ミキオ、ka.lei.do.scope、サクマツトム(HUCKLEBERRY FINN)、下石奈緒美、声音人 石田匠(ex. The Kaleidoscope)、松本タカヒロ(ザ・タートルズ)、ukishizumiらが参加したこのアルバムは、"凶弾に倒れたジョン・レノンを救いたい"という思いを込めながら各ミュージシャンが書き下ろしたオリジナル・ナンバーを中心として、精選されたカヴァー曲を挿入した構成。単なるカヴァー集とも異なる、ジョンへのピュアな愛情が詰まった唯一無二のトリビュート・アルバムと言えるだろう。
18歳の真冬にジョンの訃報を聞いた近藤金吾が30年後にジョンを愛する仲間たちとしたためた招待状は、まるで音楽を介した時間旅行のようだ。尽きせぬ思いは時空を超え、ジョンの遺した妙なる音楽とそのDNAが今なお僕らの心を激しく揺さぶり続けていることを証明する。あれから30年、"ジョンの魂"は確かに鼓動を打っているのだ。(interview:椎名宗之)。
各人が純粋な思いを込めたオリジナル楽曲
──そもそも『ジョン・レノンへの招待状』はどんな経緯で立ち上げた企画なんですか。
K:自分がTIMESLIPというバンドをやっているだけあって、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』とかタイムスリップする物語が昔から好きなんですよ。それと似た感じで、“ジョン・レノンを救いたい”という思いを込めて作った曲を1980年12月8日(ジョンの命日)に向けて、時空を超えて唄い届けるイヴェントをやろうと。企画自体は去年の12月8日から始めたんですけど、今年はジョンが亡くなって30年ということで、タイムスリップ的な面白いことができないかなと思ったんです。
──当初からジョンに捧げるオリジナル・ナンバーを書き下ろす趣旨だったんですか。
K:最初からそうでした。共演者の皆さんにも「ジョンへの思いを込めた曲を書いてきて下さい」と宿題みたいにお願いをして(笑)。そこにカヴァーを織り交ぜつつ、30年前に思いを飛ばしてタイムスリップさせるという真面目な遊び心を持った企画なんです。ジョンが亡くなった40歳をとうに超えた今、ジョンの凄さを昔以上に実感していますね。
──ジョンの享年に並んだ時は感慨深いものがありましたか。
K:いや、そうでもなかったです。ジョンはずっと僕の22歳上のままですからね。僕が生まれた1962年10月15日はビートルズがデビューした直後で、勝手に運命めいたものを感じているんですよ。そういう後づけやこじつけが大好きなんです(笑)。
──イヴェントを重ねるたびに手応えを感じた結果、今回のトリビュート・アルバムを作ろうと?
K:最初はアルバムを作るなんて全く想像もしませんでした。ただ、ジョンのラッキー・ナンバーである“9”にちなんで、イヴェントを9回やって翌年の12月8日をファイナルにしようとは決めていましたね。あと、開催日をポールの誕生日にするとか、ジョンと縁の深い人たちのアニバーサリーにすることも考えていました。
──トリビュート・アルバムに参加した各人のオリジナル・ナンバーはどれも出色の出来で、とても聴き応えがありますよね。
K:そう言ってもらえると凄く嬉しいですね。みんなで一丸となってカヴァーに取り組めたことも嬉しかったんですけど、それはあくまで副産物なんですよ。それよりも、一人一人がジョンと向き合って純粋な思いを込めた歌を作って、それをいいと言ってもらえるのが僕は一番嬉しいです。こうしてトリビュート・アルバムまで作れたのは決して自分一人の力じゃなくて、参加してくれたミュージシャンのジョンを愛する気持ちがあってこそなんですよ。今回はそのチームワークが素晴らしかったし、何よりも楽しく作れたのが良かったですね。
──金吾さんの『ジョン・レノンへの招待状』という歌は企画を立ち上げた当初からあったんですか。
K:イヴェントに合わせて書きました。最初は回を重ねるたびに書き下ろしの曲を発表していこうと考えたんですけど、それよりも毎回同じ歌を唄い継いでいくのがいいかなと思って、僕はこの『ジョン・レノンへの招待状』をずっと唄ってきたんです。みんなそれぞれの持ち味をふんだんに活かした曲を持ち寄ってくれたし、世代の違いもあるのか、ジョンへの思いのベクトルが各自違うのが面白かったですね。酒井ミキオ君の『あなたが愛した日本人』の切り口も凄いなと思ったし。
──“ジョン・レノン”という言葉を直接使わずに普遍的な音楽讃歌に昇華させた松本タカヒロさんの『WELCOME TO MY MUSIC』、下石奈緒美さんが『LOVE』のカヴァーからメドレーで聴かせる『「ジョン」と私にできること』の歌に対する純粋なひたむきさ、30年後の世界の現状を真摯な思いでジョンに伝えるka.lei.do.scopeの『今人』…挙げていけばキリがないですが、すべてが聴き所と言っても過言じゃないですよね。
K:みんなホントに凄いですね。タカタタイスケ君(PLECTRUM)の『70』は『TOMORROW NEVER KNOWS』っぽい効果音が最初に入っていたり、遊び心もあって。ただ、どの曲も今はまだ歌詞を読み込んでいないんですよ。チラチラと耳には入ってきているんですけど、じっくり読み込む楽しみを後に取ってあるんです。
自分たちの音楽を波動にしてジョンを救う
──金吾さんの『ジョン・レノンへの招待状』は30年前にジョンを失った悲しみとジョンに会いたい思いを切々と唄い上げたナンバーですが、“ジョン・レノンを救え”というフレーズがとりわけ強く印象に残りますね。
K:イヴェントのテーマそのものですからね。ジョンの無念さをすくい上げたい思いもあるし、自分たちの音楽を波動にしてジョンを救いたいんです。未来からやって来たタイムトラベラーがジョン・F・ケネディの暗殺を食い止める『タイムクエスト』という映画とか、親子でジョンを救出しようとする『イマジン』という清水義範さんの小説とか、タイムスリップして過去を変えようとする物語に僕はロマンを感じるんです。荒唐無稽かもしれませんけど、そういう遊び心のある話が好きなんですよね。
──その昔、『新春かくし芸大会』でジュリーがタイムスリップしてジョンを凶弾から救い出そうとするドラマがあったのを思い出しましたが、それはさておき。“ジョン・レノンを救え”というフレーズは、とかく“愛と平和の使者”という聖人君子的イメージを植えつけられるジョンを救えという意味にも捉えられるんじゃないかと個人的に思ったんですが。
K:ああ、それはまるっきりなかったですね(笑)。でも、新しい解釈としてはアリなのかもしれない。
──故人なのをいいことに、やたらとジョンを偶像崇拝する風潮が僕は凄くイヤなんです。元来皮肉屋の極みみたいな性格だし、「ビートルズのツアーはまるでフェリーニの『サテリコン』みたいだった」と赤裸々に語っていたように、酒池肉林に溺れた時期もあったわけじゃないですか。でも、その一方では凄く繊細で感受性が強くて、そういう清濁併せ持つ人間味に溢れたところに僕は惹かれたんです。この『#9 DREAM』に参加したミュージシャンも、ジョン・レノン=愛と平和を唱えた偉人という固定観念にとらわれることなく、一人の生身のミュージシャンとしてジョンと対峙しているところがとても共感できたんですよね。
K:なるほど。そんな話を聞くと、また新しい気持ちで『ジョン・レノンへの招待状』を唄えるような気がします。僕にとってのジョンはやっぱり、プライマル・セラピーの効果でパーソナルな人間性が色濃く出た『ジョンの魂』(『JOHN LENNON / PLASTIC ONO BAND』)なんですよね。『MOTHER』とかを聴くと、自分の代わりに叫んでくれているような気になるんですよ。分身というわけじゃないんですけど、『ジョンの魂』は自分自身が抱える心の闇の身代わりみたいな印象があるんです。ただ、捉え方は千差万別ですよね。ジョンのことを純然たるロックンローラーと捉える人もいるだろうし、愛と平和の伝道師と捉える人もいるだろうし。
──意外ですね。金吾さんの艶やかな歌声やTIMESLIPのポップな音楽性は、どちらかと言えばポール寄りだと思っていたので。
K:まぁ、持って生まれた声質は変えられませんから(笑)。
──TIMESLIPがカヴァーした『NOWHERE MAN』は、オリジナルに比肩するほど美しいハーモニーで感服しました。
K:みんな唄うのが好きなんですよね。アレンジはウチの弟(近藤泰次)に任せて南国風になったんですけど、面白い仕上がりになりましたね。『NOWHERE MAN』でのジョンは偏執的にヴォーカルのリズムを重ねていて、今回はそれを忠実にやってみたんですよ。エンディングのヴォーカルのリズムは特にそうですね。ジョンの声の重ねは一聴すると適当に聴こえるんですけど(笑)、ヴォーカルは全部ダブリングしてあるじゃないですか。だから適当には唄っていないんです。それが判った時に、ちょっと狂気に似たものを感じたんですよね。エンジニアの福本(良一)さんに「ジョンは何でこんなことを思いついたんですかね?」って訊いたら、「天才やからやろ?」ってサラッと言われましたけど(笑)。
──金吾さんが唄う『#9 DREAM』のハモりもかなり偏執的だと思いましたが(笑)。
K:確かに(笑)。全部自分で重ねたんですけど、何回重ねたか判らないですね。福本さんは僕をいじめるのが大好きで(笑)、何度重ねても「もう一回」って言われるんです。“Ah, bowakama pousse, pousse”の部分は、多分20回近く重ねたんじゃないかな。凄く広がりのあるヴォーカルを録りたかったので、5回や10回じゃ全然足りなかったんですよ。「もう一回」っていうのはやり直しということじゃなくて、「もう一本重ねる」ってことなんです。瓶ビールを注文するみたいに「もう一本」みたいな感じで(笑)。
──“音の壁”ならぬ“声の壁”みたいな感じですね(笑)。
K:最後の段階になると、自分の声を聴いているのか自分が唄っているかよく判りませんでしたからね(笑)。