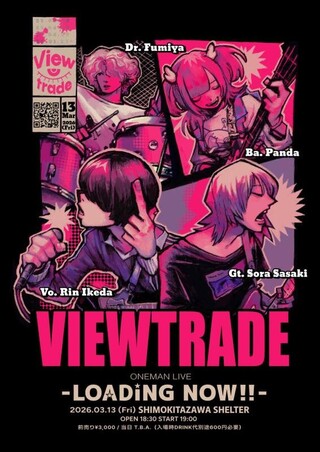個人的にも敬愛してやまない現役パンク・ライター、中込智子さんが監修を務めた『ジャパニーズ・オルタナティヴ・ロック特選ガイド』が刊行された。400枚に及ぶディスク・ガイドやバンドのバイオグラフィ、遠藤ミチロウからザ・バンド・アパートまでキーマンへの貴重なインタビューなどを通して、70年代末から現在に至る日本のオルタナティヴ・ロックの系譜に肉迫した大変な労作である。僭越ながら僕も諸先輩方に混じって執筆参加しており、何とかこの好著を世に知らしめたいとの思いから発刊記念トークライヴを阿佐ヶ谷ロフトAで開催することにした。その打ち合わせがてら、本書の制作意図と監修に懸けた思いを中込さんに伺ったので是非ご一読頂きたい。はみ出しまくった愛情がすべての行動原理である純真なゴメさんの姿勢に全身全霊全力全面リスペクト!(interview:椎名宗之)
"病み"と"闇"があるか否かが大事
──日本のオルタナティヴ・ロックの歴史や系譜を俯瞰した本を作りたいと、中込さんは以前からよく話していましたよね。
N:漠然と考えてましたね。昔は『宝島』が『ROCK FILE』っていうバンド名鑑をよく出してましたけど、それはその時に活動してるバンドをメインに五十音順でピックアップした本だったんですよ。当時はああいう本も有り難かったんですけどね。
──ただ、単なるバンド図鑑だとバンド単体の特性を掘り下げる縦軸は追えても、いろんなバンドの交流やシーンの背景といった横軸までは言及できませんよね。中込さんの本はそれができているのが素晴らしい。
N:当時の現場を見てきた立場として、その時代の空気をちゃんと伝えることがやりたかったんですよ。今までその手の本がなかったし、これは自分で作るしかないなと思って。この本はアメリカ編、ブリティッシュ編に続くオルタナティヴ3部作的な位置付けなんですが、何とか完成に漕ぎ着けたのは先の2作を監修したライターの鈴木喜之さんの力も大きいんです。本書でも彼が激しく手伝ってくれましたので。
──70年代末期から30年分の歴史を網羅するわけですから、バンドを精選するのも相当苦労されたと思いますが。
N:アルバムが出てないからという理由で、好きなのに載せ損ねたバンドも結構あるんですよ。自分が10代後半から20代前半だった80年代の前半が思い入れは一番強くあるんです。ハードコアの始まり辺りでライヴハウス・シーンが劇的に変わった印象が私にはあったんですが、如何せん7インチやカセットしか出ていないバンドも多くて。
──"オルタナティヴ"の解釈は千差万別でしょうし、取り上げるバンドと作品に違和感を覚える人もいるでしょうし、チョイスはなかなか難儀ですよね。その中で取り上げるべき基準はどんなところだったんですか。
N:たとえば、AとBという音楽性のよく似たバンドがいたとします。Aは凄く好きだけど、Bはどうも苦手だと。それは何故かと言えば、BはAと音が近いけど、"匂い"が違うからなんです。その"匂い"にこそリアリティがあったし、心を揺さぶられる何かがあったんですよね。後年判ってきたんですけど、その"匂い"とは病んでるか否かなんですよ。"病み"と"闇"があるか否か。乱暴な言い方をすれば、私は健全な精神を持ったバンドは受け付けられないんです。だから、この本では"病み"と"闇"を抱えたバンドを数多く紹介してることになりますね。
──ビヨンズの谷口健さんへのインタビュー然り、ブラフマンのTOSHI-LOWさん、バック・ドロップ・ボムのSHIRAKAWAさん、フロンティア・バックヤードのTAGAMIさんの座談会然り、"病み"と"闇"の話が度々出てきますよね。
N:そこに気がついて頂けると本望でございます。パンクをやる側も聴く側も、学校でも何でもはじき出された人間だったはずなんですよ。反論のある人もいるでしょうけど、基本的にはじき出された人間が当時のライヴハウスには吹き溜まっていた。クラスの中で浮いてる80年代前半のパンクスはヤンキーにもなれないし、どこにも居場所がない。"しょうがない、独りなんだ"って自覚することから始まるんですよ。
──執筆陣の顔触れは中込さんの采配振りが光っていますが、平易な言葉で的確に対象を表現する中込さんの筆力に僕は改めて感服したんですよ。たとえば、"スキンヘッズ・ナイト"のコラムの中でスキンズの本質を捉えたくだり...「右翼の集合体といった誤解を受けることも少なくなかったが、実際は、冷め切った時代の流れに反旗を翻し、日本男児の心意気を胸に突進する、言わば江戸っ子かたぎの熱い漢たちの集まりであったにすぎない」という一文にはシビレました。
N:スキンズは危険な匂いや怖い部分も含めて格好良かったし、だからこそ人気があったと思うんです。音としての魅力を判って欲しかったのに、いつも右翼的なイメージで捉えられるのが私は不満でしたね。怖さっていうのは結構重要なポイントで、当時、ライヴハウスへ独りで行くのは怖かったけど、全く寂しくなかったんですよ。何故かと言えば、一体感というものがそこには存在しないから。バンド対お客さんの一体感も、お客さん同士の一体感もなかったんです。みんなてんでばらばらに暴れてるんだけど、孤独ではなかった。特にハードコア・シーンはそうでした。あの殺伐としたムードは"みんな独りで来てるんだな"っていう感じがしたし、そこで友達を作るわけでもなく、独りで来て独りで去っていく美学がありましたね。
どこかツッコミ所のあるほうが愛おしい
──表紙にある"an Introduction"という言葉が言い得て妙だなと思いまして。この本は日本のオルタナティヴ・ロック・シーンを知る導入部にすぎない、この先を探究するか否かはあなた自身だという。このベタつかない感じが馴れ合いを拒否するパンクスの姿勢にも繋がるんじゃないかなと。
N:突き放してますよね。親切じゃないんですよ、この本は。索引もありませんし(笑)。でも、昔はそういうものだったじゃないですか。親切じゃないほうが一生懸命調べたし、自分で歩き回って自分で見つけ出すくらいじゃないとのめり込まないと思うんです。
──この本を監修して、新たに感じたことや再発見したことは?
N:たくさんありましたね。さっき話したライヴハウスに独りでいても孤独じゃなかったことは、ここ30年くらい考えてなかったですから。小学生の弟を連れてハードコアのライヴに行けたのは何故なんだろう? と改めて考えさせられるきっかけにもなりましたし(笑)。あと、この本は"オルタナティヴ"という言葉を便宜上使ってますけど、本来の意味でのオルタナではないんですよ。鈴木さんからは「タイトルを変えてもいい」と言われていたんですが、敢えてこの言葉を使ったのは、決め付けや限定を嫌う人たちがたくさん載ってるし、ジャンルとしての言葉を使うと語弊があるからなんです。仮にパンクという言葉を使うと、「俺たちは別にパンクじゃないよ」っていう本意じゃないバンドも出てくるので。
──特定のジャンルからはみ出したり、ジャンル分け自体を拒否するのが"オルタナティヴ"だとも言えますしね。
N:ジャンルを分類し出すとキリがないんですよね。それに、この本は一見客観的に章立てていますけど、私の主観の塊みたいなものなんですよ(笑)。反論がおありになる方もいっぱいいるでしょうし。
──80年代のハードコアだけでも充分一冊として成り立つでしょうね。
N:トロピカルゴリラのCim君にも「ひとつの章ごとに一冊作ったほうがいい、俺はそれが読みたい」って言われて、凄く嬉しかったんですよね。
──それは僕も読みたいですね。中込さんの噛み砕いた言葉で是非。
N:取っ付きにくいものを取っ付きやすく紹介するのはライターを始めた頃から強く意識してるんですよ。"一見入りづらいけど、実はこんなに格好いいんだよ!"っていう感じで。あと、真面目なことを書きつつも如何に笑える原稿にするかを普段から心懸けてます。クスッと笑える部分があれば興味を持ってもらえるし、硬い文章は読み手も疲れちゃうんですよ。音楽もそうで、どこかひとつツッコミ所があったほうが愛おしいし、印象に残るんですよね。
──そもそもは高校時代、中込さんのバイト先にミスター・カイトのベーシストである尾崎隆さんがいて、尾崎さんが始めた新しいバンドを見に行ったのが日本のアンダーグラウンドなロックの世界に足を踏み入れたきっかけなんですよね。
N:そうなんです。その後にデザイン学校へ進んで、同じ学年にレピッシュの杉本恭一がいたり、一学年下に当時あけぼの印でドラムを叩いてた佐藤稔君(後にフリクションへ参加)やゲンドウミサイルのメンバーがいたり、バンドをやったりミニコミを作ったりする人たちが身近に多かったんですよ。卒業後はデザイン会社に入ってデザイナーをやっていたんですけど、ライターになったのはなし崩し的だったんですよね。学生の頃からミニコミを作っていたので『宝島』とかから原稿依頼が来るようになって、いつの間にか本業が逆転しちゃったんです。
提灯できないバンドには触らないのが掟
──『宝島』のキャプテンレコードからは『STRAIGHT AHEAD II』という名オムニバスをプロデュースしましたね。
N:20歳そこそこの小娘によくやらせてくれたなと思いますよ。新宿ロフトでも自主企画をよくやらせてもらいましたね。ただのお客さんだったのに、当時ロフトの店長だった蟹江(信昭)さんが「イヴェント、どんどんやりなよ」と言って下さって。商業ベースじゃない企画ばかりだったにも関わらず、凄い有り難かったです。自分が企画したオムニバスについて言うと、本意ではないことを当時いろいろと書かれたんですよ。そんなことを書くくらいなら載せないで欲しかったって何度も思ったので、自分はそういうことはしないぞと。提灯ライターだとか言われたこともありますけど、提灯できないバンドには触らないほうがいいと私は思ってるんです。好きなバンドに不満がある時は直接本人に言うし、原稿には一切書きません。だから、私は全然評論家じゃないんですよ。自分はもともとデザインや広告畑の人間ですから、極論を言えば自分の原稿も広告でいいと思ってます。ただ、少しでもいい広告を作りたいし、そう思えるバンドや盤に精一杯力を注ぎたいですね。
──中込さんのオルタナティヴな嗜好は先天的なものなんでしょうか。戦隊シリーズで言えばレッドよりもグリーン好きだったりとか。
N:まさにグリーン好きでございます(笑)。『機動戦士ガンダム』だったらガルマ・ザビが好きですし、『サイボーグ009』なら004が好きなんですよ。そういう好みもあるんですかね? 自分の分析はしないのでよく判らないですけど。
──でも、「とにかくこのバンドが好きなんだ!」という純粋な愛情から原稿を書き、イヴェントを企画し、オムニバスを何枚もプロデュースするなんて、その愛情が如何に濃厚で濃密なのかが窺えますよね。
N:まさかそれが仕事になるなんて思ってもいなかったのに、もう30年ですからね(笑)。今の音楽業界は一番キツイ時かもしれませんけど、90年代初頭のライヴハウス氷河期とイメージが被る部分はありますね。不景気に突入して結構経つし、もうちょっとすれば見たことのない突破口が開けるんじゃないかと期待はしてます。若手でも"何これ!? 格好いい!"って思うバンドはちゃんといますし。いつの時代もそうですけど、先頭に立つバンドが現れると流れが変わってくるんですよね。ラフィン・ノーズ然り、ブルー・ハーツ然り、ハイスタ然り。そのバンドの負担は大きいけれど、シーンが判りやすくなって活性化するんですよ。
──今後、ライターとして取り組んでみたいことは何かありますか。
N:格好いいバンドのライヴを見られれば充分ですね。自分が楽しいから原稿も一生懸命になれるし、楽しければ"このバンドとあのバンドを集めて企画をやろう!"って想像力も働くんです。とにかく、娯楽を全うしてくれる素敵なバンドが今後も頑張って下さることを望んでやまないですね。別に癒しなんて要らないんですよ。それよりも高揚させてくれるもの、ハラハラドキドキさせてくれるものが見たいし聴きたい。
──"何じゃこりゃ!?"っていう異物感は絶対に欲しいですよね。
N:それは凄く大事ですね。"あり得ないでしょ、これ!"って時の楽しさときたら!(笑) あり得ないものをいっぱい見たいんですよ。それがあれば生きていけますし、これからもずっと娯楽に命を懸け続けていきたいですね。