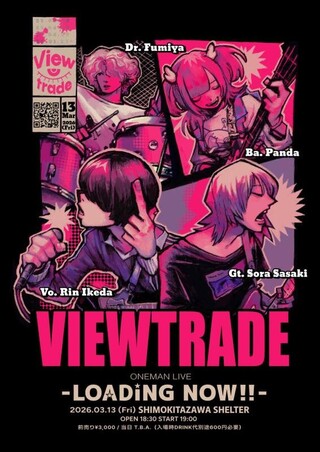ヒダカトオルの単独デビュー10周年と本厄突入を記念して今年の2月に発表されたメジャー移籍後初のベスト・アルバム『VERY BEST CRUSADERS』が好調なセールスを記録し、その直後には初の全国ワンマン・ゼップ・ツアー"Oh my ZEPP"を敢行するなど、まるで本厄を振り払わんとばかりに引きも切らぬ疾走を続ける異能のお面集団、ビート・クルセイダース。その最初で最後と噂されるゼップ・ツアーの感動と興奮を余すところなく封じ込めたDVD作品が発売されることになった......のだが、そこは決して一筋縄では行かぬお面さんたちのこと、ただのライヴDVDであるはずもない。ライヴというノンフィクションとは真逆を行くフィクションをそこに織り込むべく、『プリティ・イン・ピンクフラミンゴ』と題した完全オリジナル・ドラマを制作するという前代未聞の策に出た。誰もやらない面白いことを無理を押してでも楽しんでやるという彼らの流儀はここでも一貫している。様々な障害を乗り越えながらバンドとしての夢を追いかけるというベタにも程があるがホロリとさせるストーリー、シンガー・ソングライターの高橋瞳やグラビア・アイドルの谷桃子を始めとするさり気なくも豪華な出演陣、原典を知れば知るほど心をくすぐられる挿入歌の数々、劇中の随所に見受けられる小道具に対する深いこだわり。そのどれを取っても彼らが極めて真摯な姿勢で創作に臨んでいることがよくわかる。その真摯な姿勢がアルバムの好セールスやライヴの動員増に結実していることに、僕はある種の安堵感を覚える。飽くなき表現欲求に従い、労を惜しまずディテールに精魂を込めた表現が悪かろうはずがないからだ。フィクションにせよノンフィクションにせよ、あらゆる表現衝動の分母には夢がある。『プリティ・イン・ピンクフラミンゴ』なるドラマはそんなことを僕に思い起こさせてくれるのだ。(interview:椎名宗之)
"ライヴ"の対極に位置する"ドラマ"
──ライヴ映像と併せて収録されている主演ドラマ『プリティ・イン・ピンクフラミンゴ』なんですが、脚本を読んだ後に映像を拝見しまして...これ、かなり魅せる仕上がりになっていますよね。
ヒダカトオル(vo&g):自分で言うのも何だけど、なかなか面白いですよね?
クボタマサヒコ(b):ちょっと長くなかったですか?
──いや、全然。間延びさせない趣向が随所に凝らしてあって、あっと言う間でしたよ。
マシータ(ds):177分くらいあるんですよ、ライヴ映像を合わせると。
ヒダカ:ドラマだけで1時間ちょっとあるのかな。普通に映画を1本見た感覚にはなると思うんですよ。
──ライヴ映像の間を縫うようにドラマを挟み込むのが良かろうと当初から考えていたんですか。
クボタ:ダラーッとライヴが続くと飽きちゃうんじゃないかと思って。逆に、ドラマがずっと続くのももどかしい部分が出てくるんじゃないかなと。
──ライヴ映像とドラマをミックスさせてしまおうという発想がどこから生まれたのか、改めて聞かせて下さい。
ヒダカ:ただのツアー・ドキュメンタリーを撮っても面白くないと思ったんですよ。ウチは意外と地味だし、オジサンばっかりですからね(笑)。俺なんて今月めでたく本厄に突入するアラフォーだし(笑)。
マシータ:仮にドキュメンタリーを撮っても、お面をしてるから凄く胡散臭いですよね(笑)。
ヒダカ:お面をしたまま「ツアーの移動中に○○へ行きました」なんて映像を見せても白々しくなっちゃうだろうし、あるいは楽屋風景を撮って後でお面をハメたとしても、ドラマティックなことは何ひとつ起こりませんからね。
ケイタイモ(key):せいぜいラジオ体操くらいだよね。
カトウタロウ(g):本番の10分くらい前に本気でやってますからね、アラフォー男たちが(笑)。
ヒダカ:そんな冴えないドキュメンタリーを撮るくらいなら、ライヴというノンフィクションに対するフィクションとしてドラマを作るとか、それくらい振り切っちゃったほうが面白いんじゃないかと思って。で、いざドラマを作ってみたら意外と大変だったっていう(笑)。
マシータ:いやホント大変でしたよ。スタッフ・チームは特に大変だったと思います。
ヒダカ:スタッフは朝の5時くらいに集合して、メンバーは7時くらいに入って撮影がスタート、撮影が終わる頃には余裕でテッペン(深夜0時)超えてます、みたいなね。
マシータ:そんな収録モードの生活を2、3週間過ごしたんですよ。プチ俳優生活ですね(笑)。
カトウ:プチ俳優生活をやってみると、本物の役者さんの凄さが身に染みてよくわかりますね。
──タロウさんは監督に対してセリフのことで熱心に進言していたと伺いましたけど。
ヒダカ:勝手にアドリブを入れてただけですよ。
カトウ:そう、ただそれだけです。自分のアドリブを理由づけたかっただけなんです(笑)。
──ジ・アマテラスのメンバーがバス停でユウキと落ち合う場面で、ヒダカさんに「なげぇよ!」と思いきりツッコミを入れられてましたよね(笑)。
ヒダカ:あれは演技じゃなくて本気のツッコミです(笑)。
カトウ:お面の下で本気の顔をしてましたからね(笑)。
ヒダカ:最初から「なげぇよ!」って台本に書いてあったから、監督のマッスン(増山準哉)はタロウのアドリブを予想してたんだろうね。
ケイタイモ:さすが、よくわかってるなぁ。
カトウ:オレたちの人間性をよく理解してくれている監督で助かりましたよ(笑)。
ヒダカ:まぁ、普通に友達だからね。
──シノプシスはヒダカさんと増山監督の手によるものなんですか。
ヒダカ:ふたりでいろいろとアイディアを出し合いましたね。広島に広島東洋カープのファンがやってる有名な店があって、そこでいろいろと話をして。その店はカープの悪口を言っちゃいけない上に、メニューが全部カープの選手の名前になっていて、凄く頼みにくいんです(笑)。俺は小早川とか衣笠の世代だから、最近の選手の名前なんてよくわからないんですよ(笑)。
カトウ:しかも選手の名前で料理が運ばれてくるから、「こんなの頼んだっけ?」ってまるでピンと来ない(笑)。
ヒダカ:とにかくその店で、男闘呼組が主演した『ロックよ、静かに流れよ』みたいにもの凄くクサくてベッタベタなバンド・ドラマをやろうと話したんですよ。で、いざやってみたらクサいっちゃクサいんだけど、80年代を俯瞰して笑うみたいなのよりは一歩上のものになったんじゃないかと思うんですよね。最初はそういう80年代的なものをゲラゲラ笑うようなパロディでいいかなと考えてたんですけど、意外なことにひとつの作品として鑑賞に耐え得るものになったんです。

いつかの自分を重ね合わせてしまう感動巨編
──ご丁寧なことに、特典映像として予告編まで収録されていますね(笑)。
ヒダカ:あれも最初は笑って見てるんだけど、高橋瞳ちゃんが『ビコーズ・ザ・ナイト』を唄うところになると何だか妙にグッと来るんですよね。
カトウ:高橋瞳ちゃんが唄うためにキーを上げたんですけど、予告編のそのシーンはヒダカが唄ってるところから高橋瞳ちゃんに繋がるから、まるで転調したように聴こえるんですよね。そこがまた絶妙で、感情をグッと盛り上げてくれるんですよ。
──しかもそのシーン、"プリティ・イン・ピンクフラミンゴ製作委員会"なんてクレジットが入るものだから、ホントに劇場公開している作品のように思えるんですよね(笑)。
ヒダカ:そうそう。夕張国際映画祭とかに出品してもおかしくないくらいの出来ですよね(笑)。
カトウ:遂にオレたちも銀熊賞が射程距離に入ってきたか...(笑)。
マシータ:レッドカーペットの上を歩く日も近いか...(笑)。
ヒダカ:オマエらにはベルトコンベアで動くレッドカーペットのほうがお似合いだけどね(笑)。
──その予告編に"いつかの自分を重ね合わせてしまう感動巨編"というテロップが流れますけど、なかなか言い得て妙ですよね。
ヒダカ:あながち嘘じゃないと思いますよ。共感できる部分が必ずあると思うし。
──現役のバンドマン、かつてのバンド経験者はジ・アマテラスの姿に感情移入しやすいでしょうね。
ヒダカ:音楽をやってる人にとって、このドラマの中で描かれているような話は何十年も変わってないんだと思いますよ。この間、シュープリームスをモデルにした『ドリームガールズ』を見たんですけど、そのストーリーも同じようなものでしたね。音楽業界で成功していく中での友情、裏切り、恋愛っていうね。その仕組みは今もずっと変わらないものだし、この『プリティ・イン・ピンクフラミンゴ』も老若男女楽しめると思うんですよ。
──たとえば、バンドがメジャー・デビューを果たすにあたって「ドラマーを替えろ」とディレクターから宣告されるのは、ビートルズの時代からずっと変わらないことですよね。
ヒダカ:その手の話は我々の周りにもいっぱいありますからね。
クボタ:漫画で言えば、上條淳士さんの『TO-Y』みたいな世界ですよね。
ヒダカ:『NANA』みたいな漫画は我々のルックスから懸け離れてるし、『TO-Y』も我々にはちょっと垢抜けすぎてるね(笑)。
──女性陣のキャストに関しては、ヒダカさんの個人的な趣味が如実に表れていますが(笑)。
ヒダカ:そう、とにかく谷桃子さんに会いたくてしょうがなかったっていう(笑)。実際に会ってみたらホントにかわいかったんですけど、かなりおっちょこちょいな方だったのは予想外でしたね(笑)。でも、そのお陰で現場の雰囲気が凄く和んで良かったですよ。
カトウ:谷さんは裏表がなくて、ヴァラエティ番組の『ゴッドタン』に出てた雰囲気そのものでしたね(笑)。
──ヒダカさんが気になるグラビア・アイドルのひとりとして、以前から谷さんの名前を挙げていましたよね。
ヒダカ:ああいう大人っぽい雰囲気の女性が好きなんですよ。OL感があるって言うか。キレイな人ももちろん好きなんですけど、生活感がないと一緒にいてこっちも緊張しちゃうんですよね。そういう緊張を強いない包容力のある女性と言えば、やはり谷桃子さんが一番なんじゃないかと。
──ドラマの終盤、ゼップの楽屋にいるユウキに電話をするシーンの谷さんはまさに迫真の演技でしたね。
ヒダカ:あのシーンは泣けますよね。実際にああいうシチュエーションを経験したことのない人でも感情移入しやすいと思いますよ。それくらいの名演技だと思うし。裏話をすると、あの谷さんが電話をしてる病院のセットと俺の部屋のセットは同じ建物の中にあるんですよね。
カトウ:あと、谷さんが号泣するあのシーンは朝一の撮影だったんですよ。
ヒダカ:あのシーンの撮影が終わってから、俺がユウキを押し倒そうとしていると勘違いして野菜でブン殴るシーンだったんですよ。そんなコミカルなシーンの前に号泣していたんだから、やっぱりプロですよね。
──『湯けむりスナイパー』の芸者役ともなると格が違いますね(笑)。
ヒダカ:まぁ、『湯けむりスナイパー』はもっと露出して欲しいですけどね(笑)。ホントはこのドラマでも露出して欲しかったんですけど、台本にそういうシーンがなくて残念でした(笑)。
木村世治の冷徹無慈悲な怪演
──高橋瞳さんの起用は、ビート・クルセイダースと高橋さんのPVをどちらも増山監督が手掛けていたことの縁からですよね。
ヒダカ:そうですね。俺の妹なのか娘なのかわからない少女が話に出てくるということで、誰か適任者はいないかと考えた時にすぐ思いついたのが高橋だったんですよ。最初からピーンと来たんですね。まずボーイッシュだし、でもよく見ると女性っぽいし、パッと見は10代っぽいけど大人っぽくも見えるし。そんな多面性があるから「高橋、いいんじゃない?」と提案して、実際に起用したらホントに適任だったんです。
カトウ:何よりもちゃんと歌に説得力がありましたからね。
ヒダカ:そう、唄える子じゃないとダメだったから、その意味でもバッチリだったんです。
──『ビコーズ・ザ・ナイト』をあれだけ堂々と唄える女性シンガーもなかなかいないでしょうしね。
マシータ:『ビコーズ・ザ・ナイト』を唄うあの感動的なシーンを一番最初に撮ったんですよ。ゼップ・ツアー初日の札幌で。
──ヒダカさんを除く4人と高橋さんでリハを詰めたりしたんですか。
ヒダカ:レコーディングは一応しておいたんですけど、実際のライヴ・リハみたいなものはほとんどしてなかったですね。『ビコーズ・ザ・ナイト』を唄うシーンはお客さんを入れてのものだから、あの撮影がまずファースト・テイクなんですよ。撮影のリハは一切なしのぶっつけ本番だったんです。
カトウ:高橋瞳ちゃんが凄いなと思ったのは、『ビコーズ・ザ・ナイト』を唄うシーンが一番リラックスできたと言ってたことなんですよ。あんな大観衆の前なのに、肝が据わってるなと思って。
ヒダカ:「歌だから気がラクだった」って言ってたね。大物ですよ。
マシータ:あのシーン、お客さんから自然に偽村コールが起こったりしたんですよね。事前にお願いしたわけでもないのに。
カトウ:あと拍手もね。演奏の終わった後のウワーッていう拍手も自然と湧き起こったんですよ。
──助演男優賞を捧げたいのは木村世治さんですよね。サニーレコードの取締役というとても胡散臭い役柄なんですが。
ヒダカ:ああやってケータイをパカパカさせて妙に馴れ馴れしい人、いるでしょ?(笑)
ケイタイモ:世治さんの演技はおっかないですよね(笑)。アタシはホン読みの段階で初めて世治さんとお会いしたんですけど、世治さんが来て空気がピリッとしたんですよ。それまでアタシたちはダラダラ棒読みしてたんですけどね。
ヒダカ:世治さんはホン読みの時から巧かったですね。演技なんてしたことないからイヤだなんて言ってたけど、実際は凄く巧かった。さすがロック界の加藤鷹ですよ(笑)。
──素顔の木村さんはとても温厚じゃないですか。だからこそ余計にあの冷徹な演技が怖いんですよね。
ヒダカ:世治さんは"下北の太宰治"と言っても過言ではないくらい繊細なギター・ロック青年だったわけですよ。ゼペット・ストアがメジャーに行って以降、世治さんがタフになったイメージが俺の中にはあったので、繊細さとタフさの両方を世治さんなら演じきれるだろうと思ったんです。怒髪天の増子さんとかコレクターズの加藤さんとか、いろんな先輩方をイメージした結果、この役は世治さんが一番面白いんじゃないかと思って。
──ヒダカさんと木村さんがバーで大乱闘を起こすシーンも大きな見所のひとつですよね。血糊もふんだんに使われているし、思わず見入ってしまいました。
ヒダカ:結構ドキッとするでしょ? あの辺の後半に向かってのシーンは、俺たちを知らない人が"何じゃこれは!?"って笑うか、俺たちを知ってる人が食い入るように見るか、その両極にうまく振り切れたんじゃないかと思いますね。だって、高橋瞳ちゃんが唄ってる後ろでお面の男が4人演奏してるゼップのシーンなんて、冷静に考えればおかしいじゃないですか(笑)。何も知らない人が見た時の違和感と、ビート・クルセイダースを知ってて見た人の入れ込みのギャップが出れば出るほど面白いんじゃないですかね。
──メンバーの皆さんの名演技も随所で光ってますよね。まぁ、演技も何も、お面ですけど(笑)。
ヒダカ:マシータがヒドいのは予想してましたけど、俺とマッスンの感想としては、意外とクボタさんの棒読みがヒドかったなと(笑)。
──いや、レトルトのグリーン・カレーを差し出す演技はなかなかのものだと思いましたけど(笑)。
ヒダカ:そこはノリノリでしたけど、マシータに次いで撮り直しをさせられたのは意外なことにクボタさんだったんですよ。
クボタ:多分、声のノリが悪かったからでしょうね。
ヒダカ:演技ノリのしない声だったっていうね(笑)。


無表情のお面に表情が生まれる不思議
カトウ:個人的に必見だと思うのは、ユウキちゃんを迎えにみんなでバス停へ向かうシーンでヒダカ、ケイタイモ、マシータの3人が立ち止まった時の足元ですね。それが『フラッシュダンス』とかミュージカル系の立ち止まり方で、ふくらはぎのシシャモ具合がハンパねぇと思って(笑)。
マシータ:セリフじゃなくて、その足元が大根役者っていうのが凄いね(笑)。
カトウ:その足元だけで7テイクくらい撮りましたからね(笑)。
──お面着用のままセリフを喋るのもしんどそうですね。
マシータ:でも、表情を作る必要がないからラクなんですよ。だから世治さんや高橋さんは凄いなと思って。演技初挑戦のはずなのに。
──皆さんの演技を見ていると、お面に表情が生まれるように感じるから不思議ですよね。バーで木村さんになじられるヒダカさんのお面は本気で怒りを感じているようにも見えるし。
ヒダカ:そうなんですよ。バス停のシーンでユウキにギターを触るなって怒られた時のタロウの顔はホントに申し訳なさそうに見えるし。
カトウ:お面に表情が出てくるのは、卓越したカメラ・ワークもその一因のような気がしますね。ヒダカ演じる偽村が親父からの電話を受けるシーンもいろんな角度から撮ってるから、凄く臨場感があるんですよ。
ヒダカ:ドラマはライヴと違って一度客席を確認できるのがいいんですよ。カメラ目線っていうのは客席目線ですから。ライヴはどれだけリハをやっても客席から自分たちを見ることはできないし。そういう意味では、ドラマにはレコーディングに近い面白さがありますね。
──新宿ロフトで撮影されたジ・アマテラスの演奏シーンで、足元に架空のセットリストが貼ってあるじゃないですか。ああいうディテールを考えるのはきっと楽しいんじゃないかなと思ったんですよね。
クボタ:ああいうのは凄く楽しいですね。あのセットリストも考えるのに5分掛からなかったくらいだし。
ヒダカ:みんなで1曲ずつ挙げてね。『BAD FEELIN'』じゃなく『GOOD FEELIN'』とか(笑)。
──グリーン・カレーや偽村の部屋にある無数の香辛料もそんなディテールへのこだわりですよね。
クボタ:そうなんです。何でもないことなんだけど、実は凄く大事なんですよ。
──ジ・アマテラスのレパートリーである『THIS TIME / LAST TIME』の出来にも思わずニヤッとしますね。だってこれ、完全に"ライヴハウス武道館へようこそ"の世界じゃないですか(笑)。
ヒダカ:本来この曲は笑うところのはずなんですけど、10代には新鮮に聴こえちゃってるらしくて、普通に「いい曲ですね」って言われるんですよ(笑)。
ケイタイモ:クボタも延々直立不動でダウン・ピッキングですからね(笑)。
ヒダカ:挿入歌の話で言うと、怒髪天の増子さんに唄ってもらった『五月雨ゲッタウェイ』は名曲だと思うんですよ。これはかなり力を入れたんですよね。
──大瀧詠一さんのファンにはグッと来るナンバーでしょうね(笑)。
ヒダカ:ああいう曲を作りたかったんですよ。増子さんもノリノリでしたからね。
マシータ:何せ自前の衣装で出演してくれましたからね。
ヒダカ:俺は森進一さんっぽく演じて欲しかったんですけど、森さんはそんなにオーヴァー・アクションじゃないだろうっていう(笑)。
マシータ:拳の流し方は五木ひろし入ってたし(笑)。
ヒダカ:清水アキラさんのモノマネみたいだよね(笑)。まぁ、『五月雨ゲッタウェイ』は本編ではAメロしか使ってないんですけどね。『THIS TIME / LAST TIME』も『五月雨ゲッタウェイ』も、特典についてるPVで全部見れることにはなってるんですけど。こういう挿入歌もディテールへのこだわりのひとつで、増子さんの唄う『五月雨ゲッタウェイ』みたいにクオリティの高いパフォーマンスを贅沢にドラマの中で使ったり、そういうことがやりたかったんですよ。
──ユア・ソング・イズ・グッドのメンバーの起用もかなり贅沢だと思いますけどね。
マシータ:あと、トロピカル・ゴリラのMxTxRxがあんな形で登場するのも贅沢ですね(笑)。
ヒダカ:ADを演じたズィ〜レイとダ〜タカはハマり役でしたね。ホントのADみたいだったし(笑)。リズム隊っていうのはやっぱりああいう立ち位置になるんですね(笑)。


苦労を厭わないクリエイティヴな現場
──ああいうカメオ出演は純粋に楽しいですよね。ラトルズの『オール・ユー・ニード・イズ・キャッシュ』にジョージ・ハリスンやミック・ジャガーが出てくるみたいな感じで。
ヒダカ:そう、そういうのが楽しくて。シライシがニュースキャスターの格好をした時のみんなの喜びようったらなかったですからね。完璧でしたよ。余りにハマりすぎちゃって、もう全然面白くないですからね(笑)。ドラマでここまでのものが作れたわけだから、ここまで来たら次は映画を撮ってみたいですね。映画となると億単位は掛かるから、誌面上でスポンサーを募りましょう。このインタビューを読んでいるどなたか、是非我々に出資して下さい(笑)。それとも、出資元よりも先に監督を呼び掛けたほうがいいのかな? クドカン(宮藤官九郎)に頼んでみたりとか。
──今のビート・クルセイダースの勢いならそんなことも実現できそうですけどね。
ヒダカ:グループ魂とウチで合同で映画を撮ったりね。昔のスパイダース VS タイガースみたいな体だったらやってくれそうな気もしますね。
クボタ:それか、石井聰亙監督の『爆裂都市』みたいな映画もいいよね。
──それ、いいですね。平成の『爆裂都市』を是非皆さんで作って下さいよ。
ヒダカ:確かにそれは面白いかもしれませんね。『爆裂都市』の出演者に類するバンドを今のバンドで当てはめればいいわけでしょう? まぁそれも、グループ魂とウチで充分お腹いっぱいですよね(笑)。
マシータ:あと、ブッチャーズの吉村さんとかいいんじゃないですかね。
ケイタイモ:今回のドラマにチャコちゃん(田渕ひさ子)も写真で出演してるしね。
ヒダカ:まぁ、吉村さんは"リアル『爆裂都市』"だからね(笑)。
──ひさ子さんの起用の仕方も贅沢だなと思ったんですけど。
カトウ:後日、チャコちゃんに会った時に「出演してくれてありがとう」って言ったら、「写真だけだしね」って笑われましたけどね(笑)。
──ドラマの設定上のせいなのか、ひさ子さんと高橋瞳さんはイメージ的にかなり近いですよね。
ヒダカ:そうなんですよね。高橋は椎名林檎ちゃんが好きだから、林檎ちゃんと発育ステータスを組んでたチャコちゃんを尊敬してたんですよ。チャコちゃんに会えた時も凄く喜んでたし。
──高橋さんの唄う『ビコーズ・ザ・ナイト』も名曲ですよね。"夢を忘れそうなときは いつも急いでスタジオへ"っていう歌詞もいいし、バンドをやっている人なら誰しも共感し得る曲なんじゃないでしょうか。
ヒダカ:『ビコーズ・ザ・ナイト』を作る時に、レベッカの『MAYBE TOMORROW』をずっと繰り返し聴いてたんですよ。『MAYBE TOMORROW』にもうちょっとリズムが入るようなイメージで作ろうと思ってたんですけど、なかなかリズム・アレンジが決まらなかったんですよね。結果としては、レベッカのいろんな曲をミックスしてみたらこうなったんですよ。だからレベッカのいいところが1曲に凝縮してるんです。こういう曲を今の若い人たちがどう聴くのか楽しみですね。トロく聴こえるのか、感動のバラードに聴こえるのかっていう。
──こういう挿入歌にも一切手を抜かないところにもディテールへのこだわりを感じますね。
ヒダカ:むしろ演技よりも力が入ってますからね。我々の演技はあれが限界なので(笑)。
カトウ:限界点がかなり低いですけどね(笑)。
──撮影中の裏エピソード的なものは何かありますか。
クボタ:撮影チームのひとりが、余りの撮影の過酷さに辞めていきましたね(笑)。
ヒダカ:被写体である我々も長い時間待たされたり、いろいろとやらされたりして大変だったけど、撮るほうはもっと大変ですからね。
マシータ:基本は待機状態だし、待ってる間にいろんな仕込みとかをやってるわけですからね。
──天気待ちとかも普通にあるでしょうしね。
マシータ:天気すら変えたところもあるんですよ。部屋の中のシーンをライティングで晴れた感じにしてみたりとか。
ヒダカ:偽村の部屋のシーンを撮影した日はどしゃ降りだったんですよ。雨が降ってるようには全然見えないと思いますけどね。窓の外からライトを当ててる人たちは撮影中にずっと外にいなきゃいけないわけだから、やっぱり凄く過酷ですよね。
──それは脱落者のひとりやふたり出てもおかしくないですね。
ヒダカ:だから無理を押してでも映画を撮りたい、ドラマを作りたいっていうのは、俺たちが音楽を作りたいという情熱と凄く近いと思うんです。エンジニアだったりローディーだったり立場は違えど、音楽を作りたい気持ちはみんな一緒なのと同じで。苦労を厭わないクリエイティヴな現場っていうのはやっぱり凄く楽しいですよ。こうしてドラマを作ってみて思いましたけど、これが映画だったら劇場で上映できた時の喜びってきっと凄いんだろうなと想像ができますよね。だからいずれは是非映画を作ってみたいですね。監督なのか出演なのかはわからないけど、どちらかと言えば撮る側に回りたいですね。キャスティングを考える面白さもあるだろうし。

メンバー各人がメガホンを取りたい映画
──仮に映画を作るとしたら、どんな感じの1本を手掛けてみたいですか。
マシータ:『ブルース・ブラザーズ』みたいな映画を仲間内で作ってみたいですね。何気ないバーのシーンでRYUKYUDISKOのふたりがいたりとか、自分たちの友達が出演してるのがいいですね。
ヒダカ:それは面白そうだね。ユアソンがブッカー・Tみたいなソウルフルな曲を演奏してみたりね。俺はミッチー(及川光博)が出てた『クローンは故郷をめざす』みたいなSF映画をもっとインディーっぽくやれたらいいなと思って。アンドレイ・タルコフスキーが撮った『惑星ソラリス』っぽい映画を線の細いミュージシャン主演で作ってみたいですね。
ケイタイモ:アタシは『ジャッジメント・ナイト』みたいなのがいいですね。ロックとヒップホップが一緒くたになったあの映画のサントラが凄く好きだったんですよ。最近はヒップホップ系のミュージシャンと知り合いになることも多いので、その辺との絡みがあっても面白いのかなと。サントラもいいのが出来そうだし。
クボタ:ただ、『ジャッジメント・ナイト』は映画がホントにつまらないんだよね(笑)。
ヒダカ:確かに。でも、ああいうギャングスターっぽいものを日本に置き換えると面白いだろうね。何かやりようがある気がする。井上三太さんの漫画みたいな感じでね。
カトウ:オレは出たがりなもんで、マシータとふたりで『ウェインズ・ワールド』をやりたいです。
──タロウさんはやっぱりメタルなんですね(笑)。
マシータ:シュウィーン! ってね(笑)。まぁ、普段から『ウェインズ・ワールド』みたいなことをやってるようなもんだけどな(笑)。
カトウ:ジミー・ペイジの前で土下座してみるとかさ(笑)。
ヒダカ:面白そうだけど、別に見たくはないかな(笑)。5分くらいの内容で、ネットでタダで見れる程度で充分だよ(笑)。
クボタ:僕は今回衣装で黒いパンツにエンジニア・ブーツ、ライダースっていう格好をしてるんですけど(笑)、それは高校生の時に大好きだった横道坊主へのオマージュなんですよ。横道坊主の中村さんが主演した『ザジ』っていう映画があって、それを昔、ライヴハウスのあった寺田倉庫まで見に行ったことがあったんです。整理番号1番だったんですけど(笑)。まず映画をみんなで見て、その後に幕が上がって横道坊主が演奏を始めるという趣向で。そういうのを体験しているので、映画とライヴが合体したようなものを自分たちでもできたらと思いますね。
──最近はそういう音楽と映画のクロスオーヴァーって少なくなりましたよね。
クボタ:去年公開された中江裕司監督の『40歳問題』っていう映画には浜崎貴司さん、大沢伸一さん、真心ブラザーズの桜井秀俊さんが出演してるんですよ。その3人をスタジオに集めてただ1曲を作らせるというドキュメンタリーで、ああいう新しい試みも面白いと思うんです。
ヒダカ:VERBALが撮った『DEAD NOISE』っていうヒップホップのドキュメンタリーも相当面白いみたいだからね。
クボタ:それをパンク・バンドに置き換えて、インディーズ・シーンを赤裸々に語るドキュメンタリーも面白いかもしれないですね。
──かなり生臭い話になりそうですけどね(笑)。
クボタ:そういうのはロフトが似合いそうですね。撮影はロフトプラスワンでやるとか(笑)。
──検討させて頂きます(笑)。今年は単独デビュー10周年の節目の年ですけど、後半戦も派手に動き回る感じですか。
ヒダカ:今はいろいろと仕込み中なんですけど、新曲を出すつもりではいます。最近はメロン記念日とコラボレーションができたり、今回のドラマでも高橋や世治さんと一緒に音楽も作れたので、外部モノも自分たちの新曲と並行してやっていきたいと思ってます。それによっていいフィードバック効果も生まれると思うし。
──WISEさんとコラボレートした『Into the sky feat. BEAT CRUSADERS』のPVはワイドショーでよく拝見しましたけど。
ヒダカ:PVに出演してるIMALUちゃんのお陰ですね。そうだ、IMALUちゃんを主演にした映画だったらスポンサーもすぐつくかもしれない(笑)。お父さんとお母さんにも出演してもらってね(笑)。