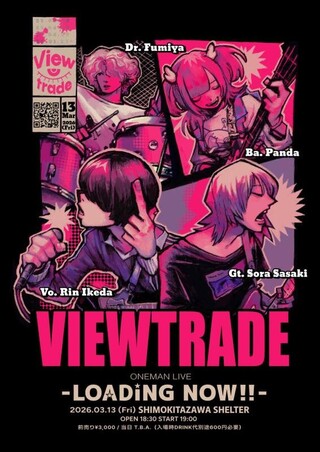2008年10月に1st.アルバム『IRIE RACKIT』をリリースし、11月には憧れのザ・ヴァインズのオープニングアクトに抜擢されたVeni Vidi Vicious(ヴェニ・ヴィディ・ヴィシャス)。満を持してリリースされる今作の1st.ミニアルバム『ベートーベンは好き。特に詞が良い。〜I Like Beethoven. Especially His Lyrics〜』は、彼らを知るにふさわしい1枚。タイトルからもわかるように、ビートルズのリンゴ・スターの有名な言葉を拝借し、シリアスな現実を彼ら独自のジョークに変えた楽曲を多く聴かせている。楽曲以外にはほとんどこだわりがないという衝撃の発言をした彼らだけに、インタビューは言葉少ないながらも、伝えようとしている姿が印象的だった。(interview:やまだともこ)
タイトルに特にこだわりはない
──1st.ミニアルバムのタイトルが『ベートーベンは好き。特に詞が良い。〜I Like Beethoven. Especially His Lyrics〜』ですけど、これはリンゴ・スターの言葉ですよね? タイトルに付けたのは意味があるんですか?
入江良介(Vo.Gt):このタイトルは俺達じゃなくて、スタッフの人に付けてもらったんです。前回のジャケット写真とPVをやってもらった人なんですけど。タイトルに特にこだわりがなかったので、客観的にバンドを見てイメージを付けて欲しいなと思っていたんです。だからジャケットとかも人任せ...と言うと言葉が悪いですけど、今回は僕の妹に描いてもらいました。アルバムのタイトルとか方向性は特にないんです。
武井優心(Ba.Cho):これがコンセプトアルバムだったらまた違うのかもしれないですけど、そういうわけでもないので。
良介:アルバムタイトルというよりは、中身とか曲が大事なんです。
──まず、1曲目の『Ano-Hacienda』ですが、聴かせて頂いた時に映画の『24 Hour Party People』を想像しましたが、ニュー・オーダーやハッピー・マンデーズのような世界に憧れはありますか?
良介:あんまり詳しいことはよくわからなくて、『24 Hour Party People』も昔見たことがあるぐらいなんです。その映画をたまたま覚えていて、渋谷にあるGAMEというクラブに行った時に雰囲気が似てるなって思ったんです。"テキーラ69"っていうGAMEでやっているイベントにクアトロやミイラズが出ていて遊びに行っていた時に歌詞を思いついたんですが、クラブってカオスな感じがするんですよ。それを客観視しているんです。
──第三者的に、一歩引いたところで見ている状態ですか?
良介:そういう時もありますけど、自分がその輪の中に入っていることもありますし。
──前作の『IRIE RACKIT』に入っている『Marihuana Monkey』では、インタビュー中に「マリファナを吸ってるヤツとか寒いと思う」とおっしゃっていたように、どこか冷めた視線を送っているようなイメージがあったんです。
良介:冷静に客観的に見ているのかはよくわからないんですけど。お酒を飲んで自分がおかしくなっている時もありますからね(笑)。意識はしていないですけど、当時のイギリスの音楽シーンや、僕がライブハウス通いをしていた時の影響は受けているかもしれないですね。高校生の時にはアンチノックとか20000Vとか、モヒカンで鋲がついているようなライブばかり行っていたから。でも、そうかと言って同じ音楽をやりたいと思うわけではなくて、良い影響を受けていると思います。
──歌詞は自分の中で生まれた言葉を自分で解釈して詞にしているという雰囲気がありますね。どんな時に歌詞は書けますか?
良介:どんな時でしょうね。書こうと思って書けるものではないですね。
──家でお酒を飲んでいるときに一気に書けるとかは?
良介:飲んでる時は何も考えてない...。
──詞は、書こうと思って迷って悩んで出来上がっていくという感じですか? 1曲の歌詞には時間はかかりますか?
良介:いやぁ。30分ぐらいです。
下手なフレーズを作り出せ!!
──今回は全曲歌詞も曲の元も良介さんが作られていますが、そこからみんなでアレンジしていくという感じになるんですよね? アレンジや曲を作る段階で大変だったのはどの曲になりますか?
武井:『Ano-Hacienda』ですね。
良介:唯一6分を超える曲なんですけど、展開も多く作ってきちゃったので大変でした。
──作品の全体的にはドラムが想像に反して軽やかな音だなと感じたんですけど、そういう音を作ろうと意識したんですか?
山崎正太郎(Dr.Cho):そこはマスタリングで意識して。
DS(ディレクター志賀氏):ドラムは初めにザ・ハイヴスのセカンドを意識してって言って作ったんです。ぐしゃっとしたというか、つっこんでくるような感じというか。リバティーンズもそういう感じですよね。ガレージ感は出ているかなと思いますね。
──音作りはどなたが主導でやられたんですか?
武井:エンジニアさんじゃないかな。
DS:エンジニアさんにこちらの意向を伝えて作りました。
──どんな感じで伝えるんですか? ザ・ハイヴスっぽくしたいとか?
DS:もう、ざっくりとしたイメージですね。
山崎:最初はスタジアムロックにしたいとか言ってなかった? 広がりのある広大なロックサウンドを最初はイメージしたんです。ザ・ヴァインズの新しいアルバムがそういう感じで、音域も広いのでこういう感じにしようという話はあったんですけど、直前にやっぱりガレージ感というかギュッとした感じにしたんです。
──直前に!?
良介:直前にスタジアムロックがわかんねーってなったんです。イメージがつかなかった。スタジアムでやったことないし(笑)。
──もしかしたら、いつかはそういう音になっていくかも? みたいな構想は?
良介:それは、エンジニアさん次第ですね。俺達そういうのがよくわからないから。
──でも毎回こういう音にしたいというのはあるんですよね?
山崎:あるんですけど、うまく伝えられないんです。
良介:極端に言えば、僕はマイク1個だけで素人が安っぽい感じで録った感じのほうが好きなんです。でもライブはバンドのほうが楽しいですからね。
──バンドでやっていくということは、バンドだからこそできる音があると思うんですけど、
良介:個人が音作りを好き勝手にやっているから、バンドとしてこういうのを意識して出すと言うよりは、一人一人がVeni Vidi Viciousの音だよみたいなことは意識していると思います。
──Veni Vidi Viciousの音だよというと、"らしさ"みたいなものってどんなところだと思います?
山崎:楽しくて落ち着きのない感じです。最近「うまく叩くな」って言われるんですよ。下手にやれと言うわけではないんですが、枠のない感じでやれって言われるから、そういうのが求めているものなんだなと思って、頑張って枠から抜け出そうとしているんですけど、なかなかハマって怒られてます(苦笑)。
──抜け出すほうが大変ですよね。練習をすればするほど上手くはなっていくでしょうし。そういえば、前回のインタビューの時は山崎さんは練習が好きじゃないとおっしゃってましたね。
山崎:今でも練習は好きじゃないですけど、そうは言ってられないじゃないですか。上手くなるのは良いんですけど、上手い中にも下手なフレーズを作り出せって言われて、研究して考えながら叩いてます。
武井:そういうのがあったんだ!! 知らなかった(笑)。
良介:僕は、好きにやるということですね。
──みんなが好きにやってくれたら良い?
良介:いや。それだと曲が成立しなくなっちゃうので。
山崎:各々がアレンジを考えてきて好きにやらせてくれるんですけど、間違ったことをやっていると、すぐに曲が止まってしまう。みんなが好きにやれて、なおかつボーカルもそのサウンドに合わせて楽しいと思えればバンドにとって一番気持ちの良い音が出せるんですよね。
良介:曲作り全部に口を出しちゃうんですけど、その段階で楽しくなくても良くて、ライブが楽しければいいかなって思ってます。
──曲作りは楽しくないんですか?
良介:楽しいですよ。ただ、あんまり好き勝手にやるときは、首を押さえて「違う!」って(笑)。
山崎:だから、押さえられないように頑張って考えてやっていくんです。
──武井さんはどうですか?
武井:うーん。みんなが楽しめるということは考えないですね。自分が気持ち良いところを考えてます。
ロックンロール・リバイバルと呼ばれることについて
──今回6曲目に入っている『アルペジオ』は、ギターの循環コードの感じが加山雄三さんの『君といつまでも』を思い出させましたが。
良介:加山雄三さんの曲は、『お嫁においで』と『サライ』しか知らないんです。ただ、エルヴィス・プレスリーの『マイ・ウェイ』を加山雄三さんが何かの番組で英語で歌っているのを昔に見たことがあって、すごいと思ったんです。『お嫁においで』もいいなと思いましたが、そこから掘り下げて聴くことはなかったですね。
──かなりグループサウンズの色が強いと感じる曲でしたが、『アルペジオ』はグループサウンズで行きたいというのがあったんですか?
良介:それが、思っていたわけではないんですけど、けっこう言われることが多いですね。前作に入っている『cosmo』とかも、ちょっと歌謡曲っぽい感じがあるよねって。そっかーって思うぐらいですけど。『アルペジオ』が出来た時に家に帰って聴き直してみたんですけど、入っていない状態のものを聴いたスタッフの方にグループサウンズみたいだねって言われたのを思い出して、改めてそうだなと思いました。
──そもそもグループサウンズに馴染みはあるんですか?
良介:ブルー・コメッツは聴いたこともあって知っています。ライブも見たことがあります。ブルー・コメッツの方の娘と小学校が一緒で、ライブをしに来たんですよ。と言っても、落ち着きがない子だったので、ちゃんと見てたのかと言われたらそうだとは言えないんですが...。
──みなさん、洋楽の雰囲気を持った楽曲でありながら、日本らしさも取り入れるというのは、これまでのご自身が聴いてきた音楽を踏まえた上で出来上がる曲だからということなのでしょうか?
良介:はい。そうだと思います。
──日本のバンドで影響を受けたミュージシャンってどんな方ですか?
武井:日本のバンドだと、ベースプレイで影響を受けてるバンドはないです。
──初めて買ったCDは?
武井:小4の時に買った『WOW WAR TONIGHT 〜時には起こせよムーヴメント』です。
山崎:僕もドラムで影響を受けているバンドはいないんですが、好きなのは真心ブラザーズとかユニコーンとか。初めて買ったCDは槇原敬之さんの『もう恋なんてしない』ですね。
良介:何があったの? その時期に(笑)。僕はRIP SLYMEとかを小学校6年生か中学生ぐらいの時に聴いてました。初めて買ったCDは志村けんと田代まさしが出していた細いヤツですね。
武井:細いヤツって表現するの? 若い子は。
──若い子って、武井さんも充分若いですけど...(笑)。そういう経緯もありつつ、今作は所謂ロックンロールと言われるものに忠実な作品だと感じましたが、ロックンロール・リバイバルだと言われているように、楽曲は正直、酸いも甘いも経験して楽器のテクニックも豊富な40〜50歳ぐらいのおじさん達の音楽に聴こえたんです。それはベテランの人がやっている音楽とも言えますが、そういう匂いがしたんですよ。
武井:おじさんくさかったんだ。そう思ったことはないですね。敢えて言うなら、懐かしいなって感じるのは『アルペジオ』ぐらいかな。
DS:レディオヘッドのように小難しいことをやっていた反動で、単純にリフから作っているというロックンロール衝動を彼らがやっているから、昔っぽいなって感じるんだと思うんです。ミイラズもアークティック・モンキーズが60年代ぐらいのバンドだろうなと検索したら最近のバンドだったという感じと同じかも知れませんね。
──自分達がリバイバルと言われることについて抵抗はありますか?
山崎:特にないです。あんまり興味がないんです。ずっとロックンロール・リバイバルって言われていて、最初はなんだよって思いましたけど、言われすぎてどうでも良くなってきました。
武井:その言葉自体、ミイラズの畠山くんが言っていたのを聞いて、そんな言葉があるんだぐらいだったので、あんまり何とも思わないです。ロックンロール・リバイバルって括ってわかりやすいなら括って良いと思います。俺達自身がロックンロール・リバイバル・バンドだとは言ってないので、何て括られようがいいんです。
良介:そうそう。言われ始めたのが、俺達を紹介してくれている記事でそうやって書いてあって、そうかーって思ったぐらいです。別に何でも良いというか...。
──○○っぽいとか○○みたいだとか言われるのも抵抗がない?
良介:ないです。
武井:それはどのバンドも永久に言われるんじゃないですか? ○○っぽいと言ったほうがわかりやすいですから。
──今みなさんはそのシーンにおいて、第一線にいるかと思いますけど。
良介:そうとも思ってないですけど、良いことですよね。そういうシーンができていて、みんなと一緒にやれているということは。それを盛り上げるためにいろんな売り文句があるだろうし、俺達はそこに反骨精神は湧いてこないです。
──なるほど。今の言葉を思い返してみると、このシーンにおいて自分達が率先して盛りあげようという意識はないですよね?
良介:はい。ないです。
──盛り上がってればいいなって感じ?
良介:クアトロとかミイラズとか、一緒にいて楽しいから一緒にいるっていう感じですからね。
歌詞は熟読します
──ところで、最後にボーナス・トラックとして『R.I.O.W.A.』が入ってますが、これだけ曲の雰囲気が違いますよね? でも聴いてもらいたいからボーナス・トラックという括りにしたんですか?
DS:協議のうえです。この曲は評判が良いんです。だから、コンセプトアルバムでもないので、普通に入れちゃおうと思っていたんですが、収録曲が7曲になるか8曲になるかでアルバムかミニ・アルバムかの標記が変わるみたいで。
良介:僕らとしては、そういうところにこだわりは特にないので、いいですよーって言ってお任せしますと。
DS:でも、この作品は最初は6曲入りの予定だったんですよ。
──どの曲が増えたんですか?
DS:『ラスト・ワルツ』ですね。プリプロで録って良いから入れちゃおうって。この曲はプリプロの音源にボーカルを入れているんです。
──詞が衝撃的ですよね。
武井:俺ら知らないんで、歌詞を見せてもらって良いですか? 耳で聴き取れる分しかわかってないんですよ。
──歌詞はリリースされるまで見ないんですか?
武井:いや。けっこう好きで熟読します。
──そう言われてみたら、もともとは山崎さんと武井さんはVeni Vidi Viciousのファンだったんでしたよね?
武井:好きだったころは健さんの歌詞でしたけど(苦笑)。
山崎:ライブで演奏する上で、歌詞を全部知っておきたいんです。
武井:正太郎は熱唱しながら叩いてますから。
山崎:でもこの曲は最後にできたから知らないんです。今初めて見ました。「ロンドンピクチャー〜」という詞だったんだ。俺「ノンノンミキチャン」だと思ってた。
──でも、レコーディングまでに歌詞が完成しているとも限らないですからね。
山崎:その時は、リハやライブの時に聴き取れたものを勝手に解釈して。
──良介さんは、この詞は大事に言葉を選んで書いているような気がしましたが。
良介:16〜17歳ぐらいの時によく遊んでいた友達の彼女が死んじゃったんです。あとはフィクションも入ってます。ティム・バートンの『ビッグ・フィッシュ』という映画が好きで、そこからイメージを湧かせた部分もあります。歌詞とかって、事実とそうじゃないところをちょっと脚色して作っていくことが多いですね。
──おとぎ話を書いていくような感じ?
良介:でも現実の話で。この曲はライブでたまにしかやらないです。
──歌詞とかは映画からイメージすることが多いですか?
良介:あまりないです。だいたい元は実際に起きたことに脚色して書いていくという感じですよ。そういえば、今日は健(Gt.)が来れなかったんですが、まだ会ったことないですか?
──いや、前回のインタビューで会ってますよ。
武井:今度は健さんの単独インタビューだな(笑)。
良介:健がいないから言うわけではないですけど、次に出すCDは健と優心に1曲づつ作らせて入れたいと思っています。文字にしておけば、否が応でもやらなければならないですからね。2人はもともと作曲をしていた人だから、今回は俺が全部書いてますけど、俺が一切介入しないでやってみたいんです。俺が曲を作る時はベースをこうしてとかドラムをこうしてとか指示を出すことが多いので、こういうギターを弾いてとか指示してもらいたいし、その形で1回やってみたい。最近、できるぜっていうアピールが来るから。
──そしたら、前回アルバムタイトルが『IRIE RACKIT』だし、今回は曲の中に『IRIE MAN』というのがあるし、武井さんが作るなら『TAKEI MAN』が良いんじゃないですか?
武井:それ、ダサいですねー。嫌です(笑)。