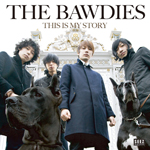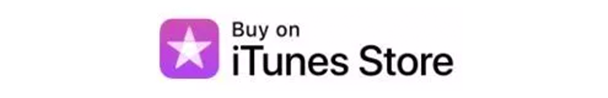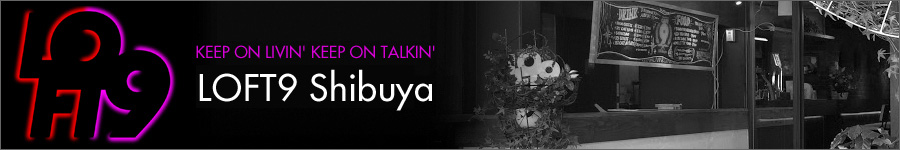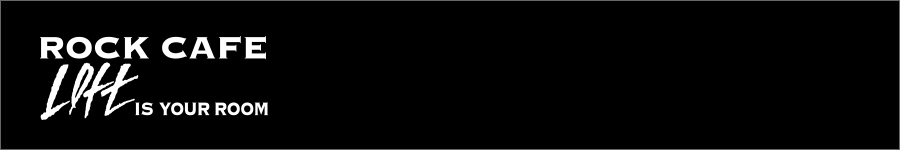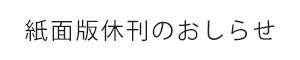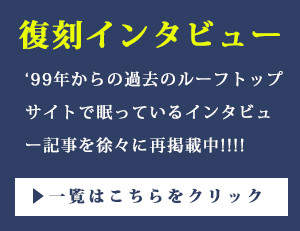ストロークスを筆頭に、ホワイト・ストライプス、ヴァインズ、ハイヴスらが巻き起こした"ロックンロール・リヴァイヴァル"なる21世紀初頭のムーヴメントはここ日本へも飛び火し、近年では"ストロークス以降"と称される正統的なロックンロールの再生を謳う新進気鋭のバンドが増えてきた。その中でも一歩抜きん出た存在なのが本稿の主役、ザ・ボゥディーズだ。オールディーズ・バット・ゴールディーズな50〜60年代のリズム&ブルース/ロックンロールを敬愛する自身のルーツ・ミュージックとして今の時代に蘇生させるのが彼らの身上だったが、LOVE PSYCHEDELICOのNAOKIをプロデュースに迎えたメジャー・ファースト・アルバム『THIS IS MY STORY』で彼らは確たる核を据えた揺るぎない音楽性を終ぞ確立した。ルーツ・ミュージックを礎としながらも、そのダイナミックなエナジーを湛えたプリミティヴな音像は間違いなく2009年最新型のロックンロールだ。一部の好事家から熱狂的な支持を受けるバンドとこれまで目されていた彼らが、ロックンロールの未来を託されたバンドとして幅広く認知される時が遂に来た。散在する点と点が線として繋がる輝かしいロックンロールの物語は真の意味でここから始まる。(interview:椎名宗之)
曲を良くするために何をするかが最優先
──活動の場をメジャーに移して、周囲を取り巻く状況も各自の心境もだいぶ変化してきたんじゃないですか。
MARCY(ds, cho):単純に自分たちの音楽を聴いてもらえる機会が格段に増えるわけで、ライヴに対する取り組み方が今まで以上に真剣になりましたね。音源のほうも、ライヴに行きたいと思わせるだけの曲をもっとたくさん作らなければダメだと思うし。
ROY(vo, b):ロックンロールに詳しくない人たちが聴いても踊れるような曲を書かないとな、とは思いますね。それはライヴもまた然りなんですけど。その部分はかなり気合いを入れて取り組んでいるところで、とてもいい具合にやれている手応えはありますね。
JIM(g, cho):メジャーって一見華やかそうに見えるかもしれないけど、浮き足立っているとすぐダメになる怖い環境だと思うんですよ。"これがボゥディーズなんだ!"という何を言われても絶対に揺るがない音楽を作らなきゃいけないし、未だにずっと気が張りっぱなしですね。
TAXMAN(g, cho):今までにない大きな一歩としてアルバムを出さなきゃいけないというプレッシャーを全員が感じていましたけど、凄く自分たちらしいサウンドの出た作品を作れたと思いますね。ただ、ピュアなロックンロールの楽しさを伝えたいというこれまでの意識は何も変わっていないし、メジャーへ移籍する機会を得たことで、今後はその意識をより強めていきたいと思っているところです。
──環境が変わって、ヴィンテージな楽器や機材を使えるようになったりとかは?
ROY:そういうこだわりも以前はあったんですけど、今はその曲が良くなるためにはどうすればいいかを最優先に考えるようになったんですよね。曲が必要とするならヴィンテージの楽器を使うし、必要としていないなら使わない。何が何でもヴィンテージを使うという頭でっかちなこだわりがなくなって、力を抜くこともちゃんとできるようになってきたんですよ。
JIM:曲が欲しているなら、場合によってはコードをアンプにではなく卓に直接差してみたりね。そういうサウンド・アプローチは今回初めてできたんです。
TAXMAN:それも、ヴィンテージ楽器の特性を理解していたからこそできた新しいアプローチだと思うんですよね。
──前作『Awaking of Rhythm And Blues』で敬愛するルーツ・ミュージックの自己解釈がある程度の高みにまで達することができたことも関係しているんでしょうね。
ROY:前作が周囲から高い評価を貰えたことが大きな自信に繋がったんですよね。ルーツ・ミュージックを自分たちなりにしっかりと咀嚼できたことも確認できたし、今回新しくアルバムを作るに当たっては凄く自由に臨めたんですよ。何をやっても土台がブレない自信があったし、だからこそ今回はいろんな試みをやってみようと考えたわけです。
──先行シングルの『EMOTION POTION』をCDではなくアナログ盤と配信で発表するというのもボゥディーズらしいユニークな試みでしたね。
ROY:20代の若者が50年代の音楽に根差した音楽をやっているというバンドの在り方にも合致していると思ったし、そういうイレギュラーなリリースをやっている人が他にいなかったのでやってみようかなと。
──ルーツ・ミュージックを土台とした新しいアプローチと言えば、この『EMOTION POTION』が最も象徴的な曲ですよね。リズム自体はモータウン系のソウルを彷彿とさせながらも、ちゃんと最新鋭の武骨なサウンドになっているし。
ROY:そうですね。収録曲の中では最初に『EMOTION POTION』が出来て、この曲がアルバムの方向性を決定付けたんです。この曲でいろんなチャレンジができたので、これは何をやっても形になるぞという強い手応えを感じたんですよ。
JIM:結果的に『EMOTION POTION』が凄くスタンダードなロックンロールに仕上がったので、他にももっと面白いことができると思ったんですよね。
本来の資質を引き出したNAOKIの存在
──あと、『EMOTION POTION』はアコギの音色が絶妙な隠し味になっているのが大きな特徴ですよね。
ROY:隠し味に関しては以前からいろいろとやってみたかったんですけど、どうすればいいのか判らない部分が多かったんですよ。そこを今回、NAOKIさんの力を借りて実現できるようになったんです。NAOKIさんは「まずは自分たちのできることをやってごらん」と言ってくれたし、そこから僕らの眠っていた資質を引き出してくれたので、その意味でも今回はNAOKIさんがキーマンだったんですよね。
JIM:NAOKIさんは「これをやりなよ」という言い方ではなく、「これを試してみれば? 合わなければやめてもいいし」っていう言い方をしてくれたので、僕らも構えることなくトライすることができたんですよ。実際にNAOKIさんの言う通りにやると曲が凄く活きたし、さすがだなと思いましたね。
ROY:ただ、そこで隠し味の面白さを覚えてしまったので、全編に渡って隠し味のオンパレードなんですよ(笑)。JIMが『OH! MY DARLIN'』でマンドリンを弾いてみたりとか。
JIM:ライヴでは普通にギターで弾くんですけどね。ただ、マンドリンはかなり高い音が出るので、ギターだと音が足りないんですよ。
──そうやってマンドリンを使ってみたのも、曲が必要としていたからこそですよね。
JIM:そうですね。曲の持ち味を最大限まで引き出すためです。
TAXMAN:NAOKIさんは凄く柔軟な考え方をする人で、試してみてダメなようなら「これはないな」とはっきり言ってくれたので、とてもやりやすい現場でしたね。その時々で曲が必要としているものを一緒になって探してくれたし。
──ちなみに、皆さんLOVE PSYCHEDELICOの音楽はお好きだったんですか。
ROY:好きでしたね。初めてLOVE PSYCHEDELICOの曲をCMで聴いた時は、てっきり洋楽だと思っていたんですよ。曲も良かったからCD屋に買いに行ったら洋楽のコーナーになくて、後で日本人だと知って凄く驚いたんです(笑)。
JIM:「ちょっとこのCDを聴いてくれ」ってROYの家で聴かせてくれたもんね(笑)。
──ROYさんがLOVE PSYCHEDELICOを聴いて"洋楽だと思った"というのは、僕が初めてボゥディーズの音楽を聴いた時の印象と全く同じですよ。
ROY:そう、おこがましいですけど繋がる部分があると思うんですよね。ルーツ・ミュージックを大事にしつつ自分たちのカラーが出た音楽を作りたいという思いは前作の時もあったんですけど、セルフ・プロデュースだとどうしても限界があったんですよ。ルーツ・ミュージックから少しブレた方向に行くことを不安に感じる面もあって、その結果ルーツ・ミュージック寄りの内容になったわけです。作品としては凄くいいものになった自負はあるんですけどね。ただやっぱり、もう少し自分たちにしか出せないカラーを打ち出したかったので、今回はバンドを客観視する人をプロデューサーとして迎えようと考えたんです。それにはまず自分たちがリスペクトできて、しっかりとしたルーツ・ミュージックを持っている人が良かった。尚かつ、僕らのルーツ・ミュージックもちゃんと理解してくれる人ですね。そう考えた時に、僕らが日本人アーティストの中で衝撃を受けた数少ない存在であるLOVE PSYCHEDELICOのNAOKIさんが一番だと思ったんです。ルーツ・ミュージックが僕らと被りすぎてもマニアックな方向に行ってしまうし、NAOKIさんのルーツ・ミュージックとうまい具合に被っていなかったのも良かったんですよね。そこの違いはお互いリスペクトできたし、凄くいいバランスだったんです。その意味でも完璧な人選だったんじゃないですかね。
──意外なことに、NAOKIさんがご自身のバンド以外のプロデュースを手掛けたのはボゥディーズが初めてだったそうですね。
ROY:今回はたまたまタイミングが合ったとは言ってくれたんですけど、とても時間があったとは思えない過密スケジュールの中で僕らに時間を割いてくれたんですよ。
──それはボゥディーズの音楽に可能性を見いだしたからこそじゃないですか?
JIM:『Awaking〜』を聴いたNAOKIさんが「凄く惜しいと思った」と言ってくれたんですよ。自分が手解きをするのではなく、「こういうやり方があるよ」と教えられればもっといいアルバムになったのに、って。だからNAOKIさんにはボゥディーズの進むべき方向性が最初から判っていたんだと思います。

結成当初から目指していたひとつの到達点
──でも、自身のルーツ・ミュージックを突き詰めた『Awaking〜』があったからこそ、本作のようにポップで開かれた作品が生まれたように思えますけど。
ROY:そうなんですよね。ボゥディーズを結成した当初から今回のアルバムのレヴェルまで行くことをはっきりと目指してはいたんです。ただ、そのレヴェルに行くためにも『YESTERDAY AND TODAY』と『Awaking〜』は必要不可欠な段階だったんですよね。その過程で単なるルーツ・ミュージックに根差したバンドだと勘違いされることも多かったですけど、僕らはずっとこの『THIS IS MY STORY』がひとつの到達点としてあったので、"ちょっと待っていて下さい"っていう感じだったんですよ。
──『EMOTION POTION』、『FORGIVE ME』、『NOBODY KNOWS MY SORROW』、『LEAVE YOUR TROUBLES』といったNAOKIさんがプロデュースに携わった4曲は特に、ボゥディーズが目指していた到達点がどんなものだったかがよく窺えますよね。
ROY:その4曲を最初に録って、残りの7曲もNAOKIさんから教わったことをちゃんと吸収してレコーディングに臨めたので凄く満足していますね。
──NAOKIさんからは具体的にどんなことを学べましたか。
ROY:曲の活かし方、向き合い方ですね。僕は本来"こう唄うんだ!"という思い入れの強い唄い手だと思うんですけど、自分が良かれと思って唄い込んでもその曲が活きるとは限らないんです。こだわりはもちろん大事なんだけど、曲を活かすためなら少し引くことも時には大切だと言うか。
JIM:それはヴォーカルだけじゃなく、楽器も同じことなんですよ。藪から棒に弾きまくるのではなく、押し引きが凄く大事なんだってことをNAOKIさんが教えてくれたんです。
TAXMAN:お陰で凄く考え方が柔軟になれたし、凄く勉強になりましたね。
JIM:やっぱり、今までは何かにつけてプラスしがちだったんですよね。『EMOTION POTION』は最初、サビのギターをAメロで弾いていたんですよ。サビはそれ以上に過剰なフレーズを弾いていたんですけど、NAOKIさんがそれを聴いて「そのAメロで弾いてるのをサビにしたら?」とアドバイスしてくれたんです。「じゃあAメロはどうすればいいですか?」と訊いたら、「別に弾かなくてもいいじゃん」って(笑)。AメロはTAXMANに任せて、僕はサビでガツンと入っていけばいいと。確かにそのほうが曲としても活きるし、各々のギター・フレーズも活きるんですよ。
ROY:まさに引き算の先生だよね。
MARCY:ホントだね。余計なフレーズを載せずにずっとリズムを叩いているだけでも格好いい曲になることを教わったし、自分では気づけなかったアタックの強弱を見直せたことも大きかったですね。
──これまではビートルズが『PLEASE PLEASE ME』を1日で録り終えたように勢いを重視した作品作りだった気がしますけど、今回は細部に渡って丹念に音を作り込んでいる印象を受けますね。
ROY:しっかりと構築したアルバムを作りたかったんですよね。今までの作品作りはライヴを自宅に届けたいというニュアンスが強かったんですけど、ライヴはライヴで楽しんでもらって、作品は作品として充分楽しめるものにしたかったんですよ。
──以前なら『EVERYDAY'S A NEW DAY』はもっとモータウンの匂いを強めていただろうし、『YOU GOTTA DANCE』ももっとダイレクトにジェームス・ブラウンっぽさを出していたと思うんですよ。そのバランスが過不足なくいい塩梅なんですよね。
JIM:『YOU GOTTA DANCE』は割とサクッと弾けたんですよね。リハの時点でTAXMANが凄くファンクっぽいギターを弾いていたので、僕は好き勝手に弾いたんですよ。そのバランスが功を奏したのかもしれませんね。ROYはこれでもかッ!っていうくらい太い声で唄ってますけど(笑)。
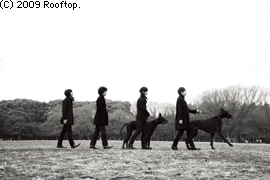
ひと工夫加えることでもっと面白くなる
──ソウル・ミュージックのDNAが宿った曲はどうしても力を込めて唄ってしまいますよね。
ROY:最初は抑え気味に唄うのがかなり苦労しましたね。でも、声量で調整するのではなく引き算の発想に頭を切り換えたらすんなりと抑えて唄えるようになったんですよ。
──『SO LONG SO LONG』はTAXMANさんが作詞・作曲を手掛けて唄っているナンバーですけど、従来のボゥディーズ節を残しつつもちゃんと今日性を提示した仕上がりになっていますね。
TAXMAN:『EMOTION POTION』が出来て、それを基準として曲作りに臨んだところがあるんですよ。だから『SO LONG SO LONG』の音作りも自然とルーツ・ミュージックに寄り切らない感じになったんですよね。NAOKIさんのアドバイスのお陰で、JIMと僕のギターの絡みもより有機的なものになったと思うし。
ROY:NAOKIさんが各々のギターの特性を引き出して、その良さを敢えて離れさせることで2人のキャラクターを活かす感じだったよね。
──敏腕プロデューサーは優れた洞察力もお持ちだったわけですね。
TAXMAN:NAOKIさんは僕らのことをちゃんと知ろうとしてくれましたからね。リハにも立ち寄ってくれたし、オフの日も一緒に食事をしたりして、4人のキャラクターを事前に理解しようとしてくれたんですよ。だからこそ僕らも臆することなく伸び伸びとやれたんだと思います。
──ギターの話をもう少ししたいんですけど、『NOBODY KNOWS MY SORROW』ではサビでワウペダルを使っていますか? ちょっとトーキング・モジュレーターのようにも聴こえるんですけど。
JIM:お察しの通り、あれはマウス・ワウを使っています。最初は普通にオブリガートで弾いていたんですけど、NAOKIさんのアイディアでワウワウやってみることにしたんですよ。
ROY:そうやって楽しいスパイスを入れることをNAOKIさんに教わりましたね。普通にやるのもいいんだけど、そこにもうひと工夫加えることでもっと楽しくなるっていう視点の大切さと言うか。
JIM:だから、フレーズ自体をヘンにいじったりはしないんですよ。ただ、そのフレーズを今以上に活かすためにはこんな手段があるよ、っていう。NAOKIさんのいない7曲もそういう"もうひと工夫"の姿勢で臨んで手応えのあるものにできたので、凄く大きな自信に繋がりましたね。
──『NOBODY KNOWS MY SORROW』は女性コーラスが聴けるのも新鮮ですね。
ROY:僕がどうしても女性コーラスを入れたくて、NAOKIさんの知り合いでゴスペルを唄っている方を2人紹介してもらったんです。期待以上の出来で満足していますね。
──『TINY JAMES』で聴かれる美しいハーモニー・ワークも見事ですよね。
ROY:過去にも『BABY SUE』というハーモニーに重きを置いた曲があって、仕上げるのに苦戦したんですけど、今回は割とスムーズでしたね。自分たちが影響を受けた音楽の要素は黙っていても出るものだし、自然にやってみようと思って。特に歌はそうで、『TINY JAMES』もヘンに力むことなくスラッと唄えた感じなんです。
TAXMAN:ROYが今まで以上に歌をコーラスに合わせることを意識してくれたんですよ。それもすべて曲を活かすためなんですよね。
──ファルセットを多用した『TELEPHONE MAN』でのヴォーカルの掛け合いも面白いですね。
ROY:『TELEPHONE MAN』は最後の最後に出来た曲なんですよ。ストックが尽きて真っ白になって、何もアイディアが浮かばない状態で振り絞ったらあんな曲になったんです。だから自分の素の部分が凄く出た曲だと思いますね。ただ、それをどうアレンジするかっていうところでギター陣は凄く困ったと思いますよ。
JIM:具体的なアレンジ案も特になかったし、あるのは「ファルセットで唄わせろ」っていう要求だけだったからね(笑)。
TAXMAN:でも、今の自分たちは特に意識しなくてもルーツ・ミュージックの要素を出せるし、そこに新しい要素もあることを再確認できた曲だよね。
JIM:そうだね。遊び心も試せる余裕みたいなものも感じたし。
先人の音楽を次の世代へ伝えていきたい
──それはつまり、どんなタイプの曲をやろうとボゥディーズになるというレヴェルにまで到達できたということですよね。
ROY:何をやっても芯の通ったものができるという自信は付きましたね。だからこれから先が凄く楽しみなんですよ。
──『LEAVE YOUR TROUBLES』で聴かれる4つ打ちも、ボゥディーズがやると単純な4つ打ちにはなりませんからね。跳ねるような躍動感がある一方で重くタイトな部分もあるし。
MARCY:4つ打ちは今回初めてやったんですよね。今までもアイディアだけはあったんですけど、ルーツ・ミュージックに根差した音楽性にうまく溶け込ませることができなくて。でも今回はNAOKIさんからも「4つ打ちを使ってみたら?」という提案を受けたし、実際にやってみたら曲にピッタリとハマったんですよ。
ROY:4つ打ちの曲っていうイメージに引っ張られることをずっと懸念していたんですけど、ピンポイントで4つ打ちの良い部分を出せたのがプラスに働いたと思いますね。『YOU GOTTA DANCE』も4つ打ちなんですよ、余りそうは聴こえないけど。
JIM:ヘンな4つ打ち感がないからね。"流行りでやってみました"みたいな4つ打ちじゃないから説得力もあると思うし。
──『THIS IS MY STORY』というアルバム・タイトルには、ここから本格的にバンドの物語が始まるという意味が込められているんですか。
ROY:バンドの本質的なカラーが出るのは基本的にファースト・アルバムですよね。でも僕らの場合は、自分たちが持っていた本来のカラーをやっと出せたのが今回のアルバムなんです。これが僕らの色なんだ、これが僕らの物語なんだと胸を張って言える作品となったので、迷うことなく『THIS IS MY STORY』というタイトルを付けたんですよ。
──このアルバムで真の意味でのスタート・ラインに立ったという意識はありますか。
ROY:ありますね。ようやくボゥディーズ・サウンドが確立できたし、ここから先はどんなことでもやれると思うので。あとはボゥディーズ・サウンドをどんどん進化させていくだけですよ。
──ところで、『IT'S A CRAZY FEELIN'』が収録された『UNDER CONSTRUCTION』は"ロックンロール・リヴァイヴァル"をキーワードとしたコンピレーション・アルバムでしたけど、そういう括りで語られることに関してはどう思いますか。
ROY:いいことなんじゃないですかね。『UNDER CONSTRUCTION』に参加しているのは、ジャンルは違えどちゃんとルーツ・ミュージックを持ちながら唯一無二のサウンドを奏でていて、音楽を楽しむことをライヴでしっかりと伝えられるバンドばかりなんです。そんなリスペクトできる本物のバンドたちと一緒にシーンを生み出して活性化させていけたらと思いますね。今の時代、お客さんもバラけてしまっているし、個々で頑張っているバンドはたくさんいるけど目立ったシーンがないので、ここで僕らが先導して大きなうねりとなるようなシーンを作りたいんですよ。
──確かに、散らばった点が1本の太い線になるようなムーヴメントは近年ありませんよね。
ROY:日本の音楽シーンで一番良くないのは、流行で終わって歴史が繋がっていかないところだと思うんです。海外なら親が聴いていた音楽を子供に聴かせてちゃんと伝承していくじゃないですか。その子供たちがやるバンドには親の聴いていた音楽の要素も垣間見えるし。海外ではそうやって芯の通った音楽が文化として育まれていくけど、日本はその面ではまだ未成熟なんですよね。日本が世界に誇れるロックの歴史は未だにちゃんと確立されていないと思うし、まずは僕らが先代からの音楽をしっかりと受け継いで、それを次の世代へと伝えていきたいんですよ。今はそんな思いが揺るぎなくありますね。