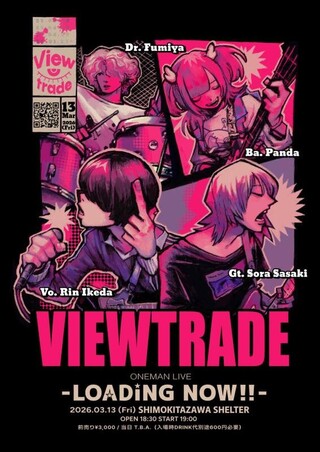2004年の初夏に背徳のメジャー契約を交わし、ミニ・アルバム『A PopCALYPSE NOW〜地獄のPOP示録〜』でメジャー・デビューを果たしてから早5年。異能のお面貴族ことビート・クルセイダースがメジャー移籍後初のベスト・アルバム『VERY BEST CRUSADERS』を発表する。堅苦しい話は抜きにして、その尋常ならざる"POP"血中濃度の高い優れた楽曲の数々を堪能して頂ければただそれで良いのだが、ひとつだけ。彼らのお面史におけるこの5年間は、ヒダカトオルというポップ・ミュージックに取り憑かれた男がメジャーという大舞台で自分の信じる音楽と常に真っ向勝負を挑み続けた闘争の日々だったと言える。インディー末期に自身以外のメンバーが脱退するというアクシデントをモノともせず、名うてのメンバーを招集してバンドを新生させたヒダカは、異常なまでの過密スケジュールの中で極めて高水準な楽曲を生み出し続けた。それは結果としてシングル9枚、ミニ・アルバム1枚、オリジナル・フル・アルバム3枚、スプリット・アルバム3枚として結実し(これに各種客演やコンピレーションを加えると膨大な数になる)、バンドは一躍衆目の的となった。僕がいつも感心するのは、彼らがインディーのアティテュードとプライドを胸に秘めながら大衆音楽の土壌で闘っていることである。メジャーに偏ることも、インディーに偏ることもなく、ごくごく軽いスタンスでその境目を自由に行き来している彼らの存在はとてもユニークだし、小さなライヴハウスを出自とするバンドがどんどん大きな存在になっていくのを見届けるのは純粋に楽しい。そしてとりわけ素晴らしいのは、ポップ・ミュージックに対する彼らの偏愛っぷりが全く薄れていないことである。こよなく音楽を愛し続ける男たちが世間から真っ当な評価を受けているのを見ると、思わず性善説を信じたくなる。インディー時代の単独デビューから今年で10周年、彼らの愛と幻想の"POP"シズムはお面の下で益々激しく脈打っているのだ。(interview:椎名宗之)
増え続ける新しいファンに向けたベスト・アルバム
──このタイミングでメジャー移籍後初のベスト・アルバムをリリースするというのは...。
ヒダカトオル(vo, g):もちろん、レコード会社の決算に合わせてですよ(笑)。
カトウタロウ(g, vo, key):「出せ! 出せ!」と散々言われたので(笑)。
──去年の6月に発表した『popdod』が、メジャー移籍以降のひとつの到達点という感覚もあったんじゃないかと思ったんですが。
クボタマサヒコ(b, vo):『popdod』は、『EPopMAKING〜Popとの遭遇〜』の翌年にフル・アルバムを出すこと自体が僕らの中で面白いことだったんですよ。内容的にも原点回帰したと言うか初期衝動を取り戻した感じがあって、人生ゲームを逆に進むみたいだったんです。その先の展開として、たとえばB面集的なものを出すとかいろんなプランを考えたんですけど、そういうのも何か面白くないなと思って。だったらいっそのことベスト盤を出しちゃう? みたいな話が出て、それで行こうと。
マシータ(ds, cho):ベスト盤を出したいと伝えたら、メーカーの人がビックリしてましたからね。まさかこのタイミングで!? っていう。でも、オリジナル・アルバムはもう3枚も出てるし、その中から選んだ曲を並べただけで盤が結構ギュウギュウになっちゃって。
──初回生産限定盤も通常盤も全23曲収録で約78分、収録可能時間の限界に挑戦してますもんね。
ケイタイモ(key, cho):そう、まとめるのがかなり大変だったんですよ。
マシータ:曲間の秒数とか、マスタリングの時に結構手こずったもんね。
──選曲はどんな感じで決めたんですか。
ヒダカ:俺が年代順にバーッと並べたリストをみんなにメールで送って、「これでいいんじゃない?」って返事をもらって。5分くらいで終わりマシータ(笑)。
クボタ:基本的にはライヴでよくやってる曲が集まりましたよね。去年はずっとツアーを回ってたんですけど、メジャーで初めて出した『P.O.A.〜POP ON ARRIVAL〜』の曲をやっても意外と反応が薄いのを感じたんですよ。
──『HIT IN THE USA』とか?
クボタ:あの辺ですね。『popdod』の曲のほうが俄然盛り上がってましたから。
──それはつまり、新しいファンが増え続けているということですよね。
クボタ:そうですね、有り難いことに。まだ中学生くらいの人が生まれて初めてのライヴとして来てくれてるんでしょうね。そういう人たちに向けて過去の曲も聴いてもらおうという目的もあって、こうしてベスト盤を出すことにしたんですよ。
──でも、ここまで何の衒いもないド直球な選曲はビート・クルセイダースらしからぬモノのようにも感じますけど。
クボタ:うん、そう思ってもらえるのが一番嬉しいですね。
ヒダカ:ベスト盤にしろ、それを受けてのZEPPワンマン・ツアーにしろ、普通のバンドが当然のようにやることをウチはまだやってないんですよ。ビート・クルセイダースがやると"意外!"と思われるようなことを一度やってみようと思って。ひねりにひねりすぎて結局最初の位置に戻ったと言うか、今のところやることがそれしかなかったと言うか(笑)。
──ただ、年代順の選曲だからこそ、メジャー移籍後の音楽的な変遷が手に取るように判りますよね。
ヒダカ:そうですね。ウチはチマチマ細かいことをやってるんで、こんなに幅広いタイプの曲をドドーンと作ってたんだなと思って。
──自分たちのレパートリーを改めて聴き込むこともそうはないでしょうしね。
ヒダカ:ライヴ前に予習で聴く程度ですね。日常的に聴くようなことはまずないし。
──じゃあ、『A PopCALYPSE NOW〜地獄のPOP示録〜』の収録曲も新鮮に響いたり?
ヒダカ:新鮮でしたよ。あと、通常盤だけに入るカトウタロウが唄った『DANCING QUEEN』が予想以上にヒドかったですね(笑)。
カトウ:自分で言うのも何ですけど、ホントにヒドいです(笑)。
ケイタイモ:オマエ、責任取れよ!(笑)
ヒダカ:余りにヒドすぎて面白いから入れてみたんですけど。
カトウ:『DANCING QUEEN』はアルバムの真ん中、ちょうどトイレに行きたくなるくらいのタイミングで入ってると思うので、まぁこれもアリかなと。
──ストーンズのライヴで言えば、キースが唄うパートみたいなものですか(笑)。
カトウ:そんな、おこがましい! 全然比較にならないですよ!(笑)

リスナーの意識を変えたメジャー移籍以降
──初回生産限定盤にも通常盤にも収録されている『LET'S ESCAPE TOGETHER』を聴けば、カトウさんが二の線もイケるのが判ってもらえるでしょう。オートチューンを駆使したヴォーカルではありますが(笑)。
ヒダカ:まぁ、それもサビを俺が唄ってるのでギリギリ大丈夫かなっていうレベルですね(笑)。
──メジャー・デビュー曲の『HIT IN THE USA』以降、その都度発表されてきたシングル曲がある種の節目みたいな役割を果たしているのが判りますよね。
ヒダカ:そうですね。すっかり忘れてたけど、思ってたよりもシングルを出してたんだなと。ドーナッツ盤を入れたら9枚出してますから。
──野外フェスや長期ツアーに明け暮れて疲弊しきった末に生まれた『DAY AFTER DAY』とか、ヒダカさんの作風が徐々に変化していく節目もシングル曲から窺えると思うんですよ。
ヒダカ:確かに。その時々の自分たちのモードも判るから、選曲作業が一番楽しかったですね。マスタリングは苦痛でしたけど(笑)。マスタリングは特に『DANCING QUEEN』が苦痛でした(笑)。
カトウ:そういや、『DANCING QUEEN』のマスタリングはホントにトイレ・タイムだったのを今思い出しました(笑)。
マシータ:イントロを聴いただけで、みんな一斉に席を立ってたからね(笑)。
──メジャー進出後のビート・クルセイダースの歩みを見て個人的に感じるのは、作品のタイトルの頻出単語である"POP"という概念とその具象化を一手に引き受けてやるぞという覚悟なんですよね。その境地が年々強固なものになりつつあると言うか。
ヒダカ:だんだん怒髪天の増子(直純)さんみたいになってますね(笑)。
マシータ:しまいにはオラが坂さん(怒髪天の坂詰克彦)みたいに激ヤセしちゃったりして(笑)。
──ラストラム時代はアルバムを発表するごとに目まぐるしい音楽的な変化を遂げていましたけど、そうした急激な変化はここ数年やや緩やかな印象を受けますね。
ヒダカ:あの余りにも激しい変化に、当時のメンバーが付いていけなくなったんですよ。俺すらも付いていけてなかったし(笑)。
──ヒダカさんの中では、現在のビート・クルセイダースとラストラム時代のそれは全くの別物という感覚ですか。
ヒダカ:どうなんでしょう...自分が曲を作って歌を唄う限りは余り差がないんですよ、俺の中では。ただ、自分たちの変化がどうこうというよりも、リスナーの意識を変えた感じは凄くしますね。メジャーに行くことを決めた時点で、それまで支え続けてくれたリスナー全員から愛想を尽かされてもいいぞっていう覚悟もあったし。その覚悟は凄く大きかったです。
──大きなターニング・ポイントだったのは、やはりヒダカさんとクボタさんがタッグを組んだことですよね。
ヒダカ:そうですね。ポップキャッチャーとビート・クルセイダースが合体したようなものですから。
クボタ:そんな展開になるなんて、全く想像してませんでしたけどね(笑)。
ヒダカ:最初はポップキャッチャーの3人(クボタ、美濃隆章、一瀬正和)にそのままビート・クルセイダースに入ってもらおうっていう話もあったんですよね。でも、それだとコスプレをしてくれるヤツがいないんで(笑)。現アスパラガスの一瀬ならやってくれたかもしれないけど(笑)。
──その面子、仮に実現していたら当時のインディーズ・シーンにどっぷり浸かっていた今の30代前半の世代には堪りませんね。
ヒダカ:そういう面子でやってるバンドが今の10代、20代に受け入れられるようになるとは全然思ってなかったんですよ、最初は。だから今の希望としては、ASA-CHANG&巡礼みたいな立ち位置まで行きたいんですよね。
──ああ、ASA-CHANGが東京スカパラダイスオーケストラのリーダーだったことを知る若いリスナーが年々少なくなっているのと同じように?
ヒダカ:それプラス、ASA-CHANG&巡礼みたいにツウが唸るようなポップ・マニア的立ち位置に行きたいと思ってやっていたら、結果的には全然違ったっていう(笑)。
趣味嗜好の異なる人間同士が演奏する面白さ
──今のビート・クルセイダースのオーディエンスは、モンハンもナツメンも知らない人たちが圧倒的なんですか。
マシータ:全然知られてないでしょうねぇ。『HIT IN THE USA』ですら、ぎこちなくも楽しそうにノッてるくらいですから。地方の若いお客さんは特にそんな感じがしますよ。
──『BECK』も観たことがなかったりとか?
マシータ:今、中学生になったばっかりのお客さんはそうかもしれないですね。
──インディーズ時代から追いかけてきた我々からすると、『P.O.A.〜POP ON ARRIVAL〜』はオリコンで最高3位、『EPopMAKING〜Popとの遭遇〜』は同2位、『popdod』は同4位と、ことごとく好セールスを叩き出しているのが素直に凄いと思うんですよね。ちゃんと結果を出しているわけですから。
ヒダカ:だけど、テクマ!とも友達っていうね(笑)。そのバランスは凄く大事なんですよ。
──大衆性を獲得したビート・クルセイダースが、ユア・ソング・イズ・グッド、トロピカル・ゴリラ、アスパラガスとのスプリットを発表することでインディーズ・シーンを底上げした功績は特筆すべきことですよね。
ヒダカ:あのスプリット・サーガ(3部作)は楽しかったですね。ユアソンはその後メジャー進出を選んで、トロゴリは潔く"ド"インディーのまま、アスパラガスはインディーでありながらも商業としての音楽も確立していたりと、三者三様で凄く面白かったんですよ。それに伴うツアーも3つとも面白くて、打ち上げにおけるパンチの出し所まで三者三様で(笑)。
──差し支えなければ詳しく教えて下さい(笑)。
ヒダカ:ユアソンはズィ〜レイ(タナカレイジ)の悪酔いですね。ユアソンのメンバーも俺たちとのスプリット・ツアーで初めてそれに気づいたっていう(笑)。トロゴリはステージ上で暴れん坊なぶん、意外と地味な打ち上げなんですよ。ただ、酔えば酔うほどCIMの話が長くなりますけどね(笑)。アスパラガスはシノッピ(渡邊忍)の言動がライヴでも充分面白いのに、打ち上げになるとさらに面白くなるんです。あれは無敵ですよ(笑)。
──考えてみれば、ラストラム時代からレジストレイターズやキャプテン・ヘッジ・ホッグ、ルード・ボーンズやスカイメイツとスプリット作品を発表していたし、異種格闘技戦には以前から意識的でしたよね。
ヒダカ:ああいう趣向が大好きなんですよ。趣味嗜好の全く異なる人間同士が一緒になって曲を作ったり、演奏するのが純粋に楽しいんです。ポール・マッカートニーがピート・タウンゼントなんかと一緒にやったロッケストラとか、リンゴ・スターのオールスター・バンドとか、昔のロックにはああいうスーパー・セッション的なものがあったじゃないですか。その縮小版をやりたい感覚がずっとあるんですよね。
──スプリット・サーガを経たからこそ『GHOST』という毛並みの変わったシングル作品も生まれ得たわけで、積み上げた経験値をちゃんとバンド本体にフィードバックしているのが見事ですよね。
ヒダカ:『GHOST』は、アスパラガスとのスプリットがなければ完成しなかったでしょうね...曲のネタ自体はずっと前からあったんですけど、全然完成できなくて...コードが多かったり、アレンジが難しすぎたりして。それが、アスパラガスとスプリットを作ったことでアレンジの糸口があっという間に見つかったんです。『GHOST』のアレンジに再度着手したら、モノの5分くらいで出来ちゃいましたからね。だからフィードバックは多いほうだと思いますよ。
──ビート・クルセイダースが木村カエラさんに『Snowdome』を楽曲提供して、それが大ヒットしたこともフィードバック効果として大きかったんじゃないかと思いますが。
ヒダカ:この間、『COUNTDOWN JAPAN 08/09』の大阪公演で初めて『Snowdome』をウチの演奏でやってみたんですよ、カエラとシノッピも呼んで。シノッピはともかく、この小汚い5人に混じってカエラがいるという違和感が自分でも面白くて(笑)。
──違和感と言えば、メロン記念日主催のDJイヴェント『MELON LOUNGE』にライヴ・ゲストとして出演したのも相当な違和感だったのでは?(笑)
ヒダカ:あれも面白かったですね。客席の違和感も凄くて(笑)。
カトウ:男子の部室感が激しく漂ってましたからね(笑)。
ヒダカ:でも、裏を返せばあの客席にいたオタクたちは俺たちと大差ないんですよ。ヘタすれば普段のライヴの客よりもむしろ俺たちに近い人種だと思うし。そういう意味での共鳴感はハンパなくありましたね。


ブッチャーズがギター・ポップ魂に火をつけた
──『summerend』で客演しているブラッドサースティ・ブッチャーズの吉村秀樹さんとは、ライヴでも同曲で共演する機会が増えましたよね。ヒダカさんは吉村さんのソロ企画『only the lonely』にも度々駆り出されていますし(笑)。
ヒダカ:ラッキーなことに、俺だけは吉村さんからの被害を被ってないんですよ。マシータやタロウは毎年吉村さんに年貢を納めてますからね(笑)。
カトウ:主に上着や機材を年貢として納めさせてもらってます(笑)。
マシータ:ツアー先で買ったばかりのパーカーをブン取られたこともありましたね。まだ試着の時にしか着てない服なのに、「これ、いいなぁ!」と言いながらごく自然に吉村さんの手に(笑)。
ヒダカ:実際に吉村さんに着せてみたらホントに持ち帰ったっていう(笑)。
カトウ:でも、後でマシータ宛に吉村さんからメールが来たんですよ。「着て帰っちゃったけど、どうしよう?」って。それを聞いて、吉村さんって心優しい悪代官なんだなと思って。
マシータ:ただ、オラが「東京までそのまま着て帰ってもらえますか?」と返事をしたら、「トランポ代、高く付くぞ!」って連絡がありましたけど(笑)。
カトウ:それを聞いて、吉村さんはやっぱり悪代官なんだなと思って(笑)。
──吉村さんのジャイアンっぷりは相変わらずなんですね(笑)。
ヒダカ:俺はそのジャイアンに取り入るスネ夫みたいなポジションで、タロウとマシータがWのび太であると(笑)。
ケイタイモ:でも、打ち上げの席は全員がのび太みたいなもんですよ。吉村さんの指令で全員上半身裸ですからね(笑)。吉村さんが真っ先に脱いでるから、俺たちも脱がないわけにいかないんです(笑)。
マシータ:まぁ、上半身裸は俺の場合ステージ上の衣装と余り変わらないからいいんですけど、吉村さんとの打ち上げはそこにビンタが加わるんですよ。みんなで円陣を組んで、隣りのヤツを思いきりビンタするっていう(笑)。
カトウ:"ガキの使い"の『絶対に笑ってはいけない病院24時』で蝶野正洋が山崎邦正にビンタを喰らわすような感じでね(笑)。
マシータ:そうそう(笑)。"ボコンッ!"という打撃音と共に、目だけ残って顔がズレるみたいな感じになります(笑)。
──スプリット・サーガで共演を果たした3組はよく判るんですが、ブッチャーズとの接点は最初凄く意外だったんですよね。
ヒダカ:ブッチャーズとライヴを一緒にやるようになって、俺のギター・ポップ魂に火がついちゃったんですよ。一緒に回ったツアーが終わって速攻で『summerend』を書き上げて、吉村さんに電話して「ギター弾いて下さい!」とお願いしたら、曲も聴かないで「ああ、いいよ」って引き受けてくれたんです。ちなみに、CDに入ってるテイクは1テイク目で、一発でOKだったんですよ。ただ、吉村さんが「もうちょっとちゃんとしたソロも弾かせてくれ」ってことでもう一度弾いてもらったんですけど、そのテイクは余り吉村さんっぽくなかったので、最初のカオティックなテイクを使わせてもらうことにしたんですよね。あのレコーディングは面白かったですね。ちょうどその時、タロウとマシータは北海道でラジオのレギュラーをやってるので不参加だったんですけど(笑)。
マシータ:吉村さんに年貢を納めてるふたりがいないってどういうことなんだよ!? って話ですよ!(笑)
カトウ:まぁ、その時のレコーディングに参加せずに礼儀を正さなかったから年貢を納めることになったとも言えますけどね(笑)。
ヒダカ:俺も罰として、このふたりには吉村さんの音をマスタリングまで聴かせませんでしたから。最初は永遠に聴かせないようにしようかなと思ってたんですけど(笑)。
──でもホント、この『summerend』は紛うことなき名曲ですよね。
ヒダカ:吉村さんのギターがなかったらただの鼻歌ですけど、吉村さんのお陰で曲がグッと引き締まりましたね。
──ヒダカさんの歌声も吉村さんのギターも相当クセが強いのに、ごく自然に溶け合っているのが奇跡ですよね。
ヒダカ:そう、食い合わせが悪くなるかもしれないんだけど、意外とハマッたなっていう。函館でブッチャーズとライヴをやった時に、ブッチャーズでモッシュが起きたことがあったんですよ。ウチのファンは若いから、ブッチャーズもメロディック・パンクっぽいバンドだと思って"ウォーッ!"と拳を突き上げながら迎えて(笑)。その光景が逆に面白かったんですよね。吉村さんもそれを楽しんでやってたし。何て言うか、吉村さんは誰彼構わずファック・サインを出すわけじゃなくて、唾を吐きかける相手を常に見定めているんですよ。それが凄く格好良かったし、そういう感覚が俺たちには欠落してるなと思って。かと思えば、吉村さんはCHARAさんの『タイムマシーン』を名越(由貴夫)さんと共作してるじゃないですか。その振り幅は純粋に凄い。だから『summerend』にはそんな吉村さんのエッセンスを入れたいと思ったんですよね。
カトウタロウの"30歳成人"説
──ブッチャーズを筆頭に、ビート・クルセイダースを触媒として多種多様なバンドを知ることのできる若いファンは幸せだと思いますよ。
ヒダカ:上から目線のフック・アップじゃなくて、「こんなに面白いバンドがいるよ!」って常に声高に言っていたいんです。だから、自分ではDJみたいな感覚なのかなと。クラブのDJ的でもあり、ディスク・ジョッキー的でもあり。クリス・ペプラーさんがやってる『TOKIO HOT 100』のインディーズ版、パンク版的な役割でいたいですよね。
クボタ:自分が10代の時に通ってた大貫憲章さんの『ガレージランド』でも、ヒップホップもレゲエもハードコアも全部一緒くたになって聴いてましたからね。いいものはいい、ただそれだけなんですよ。今はジャンルごとに細分化されて、全部バラバラになっちゃったけど。
ヒダカ:そうだね。スカもレゲエも取り込んだサブライムみたいなバンドが今の日本からはなかなか出てこないしね。もちろんそういうバンドもいるんだろうけど、ジャンルレスの面白さで聴かれることはないだろうし。
──ところでこの5年、皆さんの生活は"劇的ビフォーアフター"ばりに大改造...じゃなくて激変したと思うんですが。
ヒダカ:まず何より、家に帰れなくなりましたね。
マシータ:1年の1/3は家にいない感じですから。
ヒダカ:家賃の3ヶ月分くらいは損をしてますよ(笑)。なんせ年間120本くらいライヴをやってますし。
ケイタイモ:タロウとマシータとアタシは結婚してるし、マシータなんて子供までいるっていうのに...。
マシータ:だからホント、嫁と子供は実家に帰って空き家になっちゃってます(笑)。
カトウ:でも実際、激変ですよね。それまでにやってたバンドは、結局のところオナニーだったわけじゃないですか。"別に伝わらなくてもいい、オレたちの良さを判らないほうが悪い"なんていつも人のせいにして、音楽性もしっちゃかめっちゃか変えていったりして。当時の収入源はバイトで、今の奥さんともまだ結婚はしてなかったし、社会的な責任を一切取ってなかったわけですよ。それがビート・クルセイダースに参加することになって、やっと社会人としての入口に立てた気がするんですよね。これで何とか成人し始めることができたと言うか。
クボタ:"30歳成人"説だね。
──今の実年齢から10歳引くと昔の精神年齢になるなんてよく言いますしね。
カトウ:そう、それを身を持って体現している気がします。
──カトウさんの念願だったAC/DCのカヴァー・トリビュート・アルバム『THUNDER TRACKS』も、ビート・クルセイダースの威光があってこそ実現したと言えるでしょうし。
カトウ:そうですね。遂にはAC/DCのライヴを観にニューヨークまで連れて行ってもらえたし(笑)。でも、『THUNDER TRACKS』に全力で臨まなければそんなご褒美ももらえなかったと思うんですよ。今まではずっと逃げていた"自分でケツを持たなきゃいけないこと"をちゃんとやって、そこで見えたものはたくさんありますね。社会に出たら責任を取らされるのは当たり前のことだし、そこをずっと避けてきたことに気づかされた5年間だった気がします。
──怒髪天の『ドンマイ・ビート』の客演で"俺達界隈"からもお馴染みのケイタイモさんは?
ケイタイモ:『popdod』前後に年間120本のライヴをやって、そこで共演したヒダカよりも年上の諸先輩方との結び付きは大きな財産ですよね。ブッチャーズや怒髪天、少年ナイフ、コレクターズといった雲の上の存在だった先輩バンドと共演したことで、いい意味で後輩になれたなって言うか。吉村さんみたいに20年以上のキャリアを誇る先輩方が未だにバンドをキャッキャキャッキャ楽しんでいるのが新鮮だったし、面白いことに誘ってくれるのは大体が先輩なんですよね。怒髪天からはレコーディングとライヴに誘ってもらえたし、タロウは『COUNTDOWN JAPAN 08/09』で少年ナイフのステージに誘われたりもしたし。そうやってツアーが終わった後も交流を続けられるのが純粋に嬉しいし、自分もそういう先輩になりたいと思いましたね。
責任を取る前提で物事を考えるようになった
──足のケガによって戦線離脱を経験したこともあったマシータさんは?
マシータ:ああ、ケガには悩まされましたねぇ。そう言えば、「『SOLITAIRE』のイントロのドラム、最高ですね!」ってお客さんに言ってもらうことがよくあるんですけど、あの曲はトレードマークの大知里(荘介)が自分のケガの代打で叩いてくれてて(笑)。そんな絶賛の声を聞くと「はぁ...どうも...」としか返せなくて、未だにツライです(笑)。
──あと、マシータさんのドッペルゲンガーとも言うべきイラストレーターの安斎肇さんとご対面を果たせたのは大きなトピックでしたね(笑)。
マシータ:あれは最高でしたね。会うなり「キミか!」って熱い抱擁を受けましたから(笑)。また是非安斎さんにお会いしたいですよ!
──ビート・クルセイダースが注目を集めたことで個人的に良かったと思うのは、クボタさんが主宰するキャプテンハウス・レコーディングスの名が浸透したことなんですよね。クボタさんも参加しているクーやポーリーABC、トレードマークといった良質なポップ・バンドの良質なポップ作品のみを発信していく良心的なレーベルなので。
クボタ:ありがとうございます。活動自体は相変わらず地味なんですけど、ビート・クルセイダースの活動を通じて間口が広がればいいなと思って。その後の作品の良し悪しはお客さんが判断してもらえばいい。昔に比べてインディーとメジャーの違いにこだわるリスナーも少なくなったし、純粋に作品さえ良ければ先入観なく聴いてもらえるんです。実際、ビート・クルセイダースを入口としてトレードマークのファンになってくれた人も多いんですよ。もともとレーベルにそうした広がりを持たせたくてビート・クルセイダースに加入したので、今は凄く良い結果だなと思ってます。
──それにしても、ビート・クルセイダースは『NEVER POP ENOUGH E.P.』でラストラムからデビューしてから今年で10周年を迎えるんですね。正直、もうそんなに経つんだなと思いましたけど。
ヒダカ:早いですよね。今回、こうしてベスト盤を編纂することで今までやってきたことを一度終わらせる意味合いもあるんですけど...バンドを終わらせるという意味じゃなくて、次のステップに行くためにはこういうアイテムがあったほうがいいんじゃないかと思って。だから、思いつきでベスト盤を出そうと考えた割には意外と良い流れが出来たかなと。
──ヒダカさんの中では、メジャー移籍後のビート・クルセイダースは人間にたとえるならどんな時期に当たると考えていますか。
ヒダカ:インディーズの5年間が小・中学生くらいですね。小・中学生が"うんこちんちん"を連呼してまだ面白がれるレベル。
──"志村、後ろ! 後ろ!"の段階ですね(笑)。
ヒダカ:そうそう(笑)。で、メジャーに来てからの5年間が高校生から大学生。オナニーやセックスを覚えたり、タバコや酒の味を覚えたり、免許を取って車で外に出てみたりと、ワルに憧れつついろんなことを試してる時期ですね。だから、ここから先の5年間は社会人としての試練を受けるんじゃないかと(笑)。
──まぁ、その社会人も何の仕事をしているのか全然見当の付かない感じですよね。決して公務員や銀行員のようにカタギの仕事じゃない気がしますけど(笑)。
ヒダカ:怪しげなサラリーマンでしょうね。エイ○ックスのプロモーターみたいな(笑)。これ、イヤミじゃないですよ? パッと見、何を担当してる人なのか判らないことが多いので(笑)。
──それこそ、インディーズ時代のヒダカさんはバンドとサラリーマンの二足のわらじを履いて活動されていましたけど、作品作りにおける理想的な環境は年を追うごとに整ってきたんじゃないですか。
ヒダカ:そうですね。すべて思いつきなのはこの10年間全く変わらないんですけど(笑)。たまたまこういう曲を思いついたからやってみたら面白いんじゃないか、それで実際にやってみたら面白かった...っていう繰り返しなんです。ただ、その"面白かった"に対して、より責任を取らなきゃいけなくなるんですよね。インディーズの頃はもっと無責任でいられたし、何のイヤミでもなく、それこそがインディーズの良さだったと思うんですよ。ライヴハウスの中でも、責任は各々が取るものじゃないですか。インディーズなら、ライヴハウスでケガをしたからといってバンド側が訴えられることはなかったと思うけど、メジャーになるとその可能性もなくはない。だからメジャーに来て変わったと思うのは、責任を取る前提で物事を考えるようになったことですね。そういう成長の跡が音としてどんなふうに表れているのかは自分じゃ判りませんけど。


バンド活動の延長線上にある『COMPI CRUSADERS』
──あと、ベスト盤と同時発売される『COMPI CRUSADERS '88〜'97 vol.39』のように"音"故知新なコンピレーションをビート・クルセイダースのファンが聴くことで、古今東西の優れたポップ・ミュージックの世界に触れられるというのが本当に素晴らしいですよね。ティーンエイジ・ファンクラブから大瀧詠一さんまで、ヒダカさんのバックボーンをみんなで共有して堪能できるわけですから。
ヒダカ:こういうアイテムを作るのは凄く楽しいんですよ。何千組といるソニー・ミュージックのアーティストの中から、自分の好きな曲を年代ごとに10年ずつ区切って出しているんです。今回のラインナップを見て思ったのは、俺はやっぱりUKギター・ロックが凄く好きなんだなと。権利的な問題でアメリカ勢のアーティストを余り収録できなかったこともあるんですけど、90年代のイギリスの音楽にもの凄く影響を受けてるんだなと思って。
──選曲の基準というのは?
ヒダカ:無名でも有名でもどっちでも良くて、その曲に対して自分が本気でシンガロングしたか、あるいはしたかったかどうかですね。こういう選曲作業もビート・クルセイダースの延長線上にあって、このコンピレーションに入ってるような曲をビート・クルセイダースで作りたいというのが基本的な発想ですからね。
──UKギター・ロックの胸を締め付けられるメロディ・ラインは、間違いなくビート・クルセイダースの音楽性に通底していますよね。
ヒダカ:そうありたいですね。ティーンエイジ・ファンクラブみたいにショボくれた連中が一生懸命演奏することで胸キュン度が上がるっていう、あの感じには凄く影響を受けてますから。それとやっぱり、トランス・レコード勢からの影響も大きいですね。特にアサイラム、ゾア、YBO2のパンク感は凄く大きくて...刺々しいコワモテなルックスなのに、唄っている時は異常なまでに美しいっていうね。あとはもちろん、ウィラードやラフィン・ノーズあたりの当時王道とされていたインディーズ・バンドの男気にも影響を受けてますけど。
──ヒダカさんが吉村さん主催の『only the lonely』出演時にアリスやビリー・ジョエル、スミスといったルーツ・ミュージックのカヴァーを披露するのも興味深いんですよね。
ヒダカ:あのライヴに参加できたことはデカかったですね。そこではより剥き出しの歌を唄うしかないし、俺にはディスチャーミング・マンみたいなことはいきなりできないから、カヴァーをやってみたりしてあの手この手で工夫を凝らしたんですよ。でも、その工夫っていうのはビート・クルセイダースで普段やっていることと一緒なんだなと思って。それがより明確になったと言うか、要するに基礎が出来てないヤツはダメなんだなと。ギター教室に通って一から十まで手取り足取り教わるという意味の基礎じゃなくて、人それぞれの基礎をちゃんと作っていくことが大事なんですよね。ライヴハウスの良さはそこだったと思うんです。基礎はバンドにも客にもそれぞれあるし、そこで流血をしようがモッシュをしようが自分次第っていうね。そういう暗黙の了解が心地良かったわけですよ。でも、メジャーはきっとそういうものじゃない。だから今の自分たちとしては、音楽活動を続けながらそういった基礎をちゃんと伝えていけるかどうかだと思うんです。『おはスタ』の山ちゃんが子供たちに情報を教えてるみたいで面白いですよ。南海キャンディーズのほうじゃなく(笑)。
──同じ"DIY"(Do It Yourself)という言葉でもメジャーとインディーとでは多少意味が異なるでしょうし、その棲み分けは難しいですよね。
ヒダカ:かと言って、ライヴハウス的な"DIY"をメジャーに押しつけてもダメなんだろうし、そこは先輩たちや友達の活動を見ながら模索している感じですね。たとえて言えば、電気グルーヴが『虹』を作った時みたいになればいいなと思うんですよ。それまではただ単に面白くてヘンなことをやるユニットだと思われていたのが、『虹』を出したことでアーティスティックな一面もちゃんとあることを世に知らしめたじゃないですか。でもそこで(石野)卓球さんと(ピエール)瀧さんの軸がブレることは全然なかったし、未だに『虹』をライヴで聴くと素直に格好いいなと思うし。
──発表される楽曲はことごとく高水準なのに、パフォーマンスはその照れ隠しなのか三枚目に走る傾向がビート・クルセイダースにも電気グルーヴにも共通してありますよね(笑)。
ヒダカ:完全にオーケン(大槻ケンヂ)さんと卓球さんの系譜ですよね(笑)。昨日もちょうど筋肉少女帯が武道館でやった復活ライヴをテレビで見て、『踊るダメ人間』を全部唄えちゃう自分がいたりしますし。
メンバーの愛聴するベスト・アルバムあれこれ
──ベスト盤の話に戻りますが、個人的に改めて感じたのは歌詞の秀逸さなんですよね。英詞だから見過ごされがちかもしれないですけど、もっと評価されて然るべきだと思うんです。人生の無常さを唄った『TIME FLIES, EVERYTHING GOES』や、"絶望してるヤツの上には太陽は昇らないよ"と唄われる『DAY AFTER DAY』とかは特に素晴らしいですし。
ヒダカ:無責任に"大丈夫!"とか"俺が何とかする!"とは唄いたくないんですよ。巷のJ-POPで俺が苦手なのは、唄ってるポジティヴさに根拠がないものですね。俺はネガティヴなことをネガティヴに唄うし、ポジティヴなところにはその根拠をちゃんと唄いたいと。つまり、"なぜ前を向かなきゃいけないのか?"っていうことですよね。安直に"前を向こう!"と唄うことでリスナーを自己管理から乖離させちゃってるんじゃないかと思うし、根拠を外して唄いたくはないんです。純粋なバンドは根拠のないことを唄わないと思うんですよ。ルースターズの『恋をしようよ』が一番いい例で、"俺はただオマエとヤリたいだけ"っていう根拠をちゃんと唄えるかどうかが大事なんじゃないかなと。
──作品を追うごとにビート・クルセイダースなりの"POP"が極まってきた感がありますけど、年々"POP"を追求するハードルが高くなってきているのでは?
ヒダカ:最初はビート・クルセイダースがメジャーに移籍すること自体に違和感や異物感があったし、ありのままで良かったんですけど、ある程度認知された今はリスナーにとって異物感がないと思うんですよ。そういう違和感、異物感をちゃんと面白く作れるかどうかが"POP"の焦点になっていく気がしますね。
──確かに、皆さんがマツモトキヨシのCMに出演しているのを見た時も余り違和感を覚えなかったですもんね。
ヒダカ:自分でもそう思いマシータ。ラフィン・ノーズの登場以降、音の有り様はもちろんですけど、アティテュードの面での違和感や異物感もインディーズやパンクの在り方としてあったと思うんです。そんな違和感や異物感を現代風に面白く継承したいんですよね。
──ちなみに、皆さんが好きな古今東西のベスト・アルバムを挙げるとすると?
ヒダカ:俺はニール・ヤングの『DECADE』かな。しかも、『Winterlong』はあれにしか入ってないし。『Winterlong』を知ったきっかけはピクシーズがカヴァーしてたからなんですけどね。
カトウ:純然たるベスト盤ではないですけど、AC/DCの『LIVE』はベスト盤としても聴ける極めつけの1枚ですね。あれはちゃんとお客さんのことを考えてライヴをやってる人の選曲ですよ。
マシータ:よく駅前で売ってる、昔のロックンロールのベスト盤って凄くいいんですよね。車の写真がジャケットになってるヤツ! 意外と選曲が良くて、大学の頃に凄くよく聴いてました。
ケイタイモ:アタシはポール・マッカートニーの『ALL THE BEST』ですかね。あそこからオリジナル作品を1枚ずつディグってく感じでした。そういやあのジャケでリッケンバッカーのベースを知ったんですよ。
ヒダカ:でも、『ALL THE BEST』はジャケが最悪だよね...ポールはいつもジャケがヒドい(笑)。多分、ファーストが一番良かったんじゃないかな。
──そうなんですよね。雪山にヘンな人形が置かれた『WINGS GREATEST』のジャケなんてヒドすぎるし(笑)。
ヒダカ:あれは最悪ですね(笑)。部屋にあった骨董品だか何だか判らないけど。デニー・レインのソロもジャケがヒドいんだよなぁ、内容は凄くいいのに。
クボタ:僕はそうだなぁ...ポリスのベスト盤をよく聴いてましたね。
ケイタイモ:ポップキャッチャーの時に『Don't Stand So Close To Me』をカヴァーしてたもんね。
クボタ:ああ、バッドニュースの『悪報瓦盤』に入ってるヤツね。基本的にリアルタイムのアーティストはベスト盤を聴かないんですけど、ポリスはリアルタイムじゃなかったので。ビートルズも、マシータが言ってた駅前で売ってた車ジャケットのCDでよく聴いてましたね。
マシータ:車シリーズね(笑)。たまにレコードから落としたような音が入ってたりして音は良くないんだけど、内容的には安心と信頼のブランドだと思ってました(笑)。
ヒダカ:確実にアーティスト本人の意志は皆無だから良し悪しはあるけど、フーみたいに最初に取っつきにくいバンドはそういう車シリーズのベスト盤から聴くのもアリかもね。いきなり『SELL OUT』から聴いて"これ最高!"って思う10代もそうはいないと思うし(笑)。
──そこへ行くと『VERY BEST CRUSADERS』はマスタリングも素晴らしいし、内容も取っつきやすいし、まさに安心と信頼のブランドですよね。
ヒダカ:インディー時代の『BEST CRUSADERS』と比べて演奏も巧いし(笑)。
マシータ:でも、逆にアラキの一筆書きみたいなドラムは叩けないですから。あれはとても再現できないし、凄いですよ。
ヒダカ:確かに、アラキのドラムは吉村さんのギターに近いものがあるのかも...でも、その比較はイヤだな(笑)。
インディーズ時代の5年間があったからこそ今がある
──『BE MY WIFE』や『IMAGINE?』、『SECOND THAT EMOTION』といったラストラム時代の楽曲をセルフ・カヴァーしているのは、今のこの凄腕面子で再現してみたいという発想からですか。
ヒダカ:それもあるし、リスナーからのリクエストが高いんですよ。ライヴでも盛り上がる曲だし、オリジナルを知らないお客さんでも、知ってるお客さんと一緒に盛り上がってくれて。そういう意味でも、インディーズ時代の5年間があったからこそ今があると思います。だから、あの5年間をなかったことにしようとは全然思わなくて。インディーズ、メジャーと5年ずつやってきたから、今後はさらにその上のステージに突入したいですね。
──少々気が早いですけど、次なる作品の構想はすでにあるんですか。
ヒダカ:お、いい質問ですね...これはマシータに答えてもらいましょう。
マシータ:これからはもっと諸先輩方と言うか、高いプロ意識を持った人たちと何か面白いことをやりたいんですよね。これまで共演を果たした人たちがプロ意識が低かったという意味じゃなくて、たとえばスプリット・サーガに参加してくれたバンドはみんな歳も近い友達ばかりでしたけど、『THUNDER TRACKS』に参加してくれた奥田民生さんや斉藤和義さんのようなレベルの方々といつか共作してみたいんです。その前段階として、自分たちに足りないものは何だろうと考えると、ルーツ・ミュージックをちゃんとお客さんの前で演奏できるか? っていうことだったんですよね。これがなかなか難しくて、たとえばビートルズのカヴァーをやってもうまく形にならないんですよ。
──あれだけ演奏の長けた皆さんでもうまく行かないものですか。
マシータ:ヒダカとタロウはビートルズが大好きでしたけど、他の3人は実際に演奏したことが余りなかったですから。で、そういう基礎体力を付ける手始めとして、去年の年末にギグアンでビートルズのコピー・バンド(BEATLE CRUSADERS)をやったんです。梅ヶ丘にある"洋服の並木"に行ってピッタピタのスーツを5人お揃いで作ったりして(笑)。今年はそうやって自分たちの土台作りをした上で、さらにフォールドを広げた活動に繋げたいなと。
──今後、個々人で成し遂げたい課題みたいなものはありますか。
マシータ:俺はドラムを叩きながら唄うことですかね。ビートルズのコピー・バンドをやった時に初めてお客さんの前で叩きながら唄ったんですよ。リンゴ・スターがヴォーカルの『Yellow Submarine』だったんですけど、いずれはオリジナル曲でもやれたら良いなと!
ケイタイモ:インディーズの頃は"メジャー進出なんて必要ない"なんて根拠のない自信があって、生意気なことばかり言ってたんですけど、まだまだ自分には足りないことだらけなんだなとこの歳になって思うんです。キーボードのプレイもまだまだ追求する余地があるし、日々勉強なんですよね。だから自分の可能性をもっと広げていけば、音楽的にももっともっと面白くなるような気がしますね!
カトウ:オレはやること成すことすべてが課題みたいなもんですけど(笑)。ただ、『THUNDER TRACKS』を作ったことで見えてきたものがあったし、何事も能動的に行動しなければ何も見えてこないので、そこはより高い意識をもって臨みたいですね。『THUNDER TRACKS』という作品がなければ少年ナイフのライヴでギターを弾くなんてできなかったわけだし。踊れない人間が奏でるダンス・ミュージックよりも踊れる人間が奏でるダンス・ミュージックのほうが説得力はあるだろうし、唄えない人間が奏でるインストよりも唄える人間が奏でるインストのほうが説得力はあるじゃないですか。今まで自分が避けてきたことをやることでそういう説得力が増すと思うし、進むべき方向性に今は迷いがないです。
クボタ:個々の部分では今3人が言った通りですね。去年1年はビート・クルセイダースに没頭していたので、今年は自分のレーベルからのリリースを増やしたり、もっと幅の広い音楽活動をしていきたいです。
ヒダカ:2009年はアングラ演劇をやりたいですね(笑)。顔を白塗りにして天井からぶら下がっちゃうようなヤツを(笑)。
──はははは。ガロウの活動は?
ヒダカ:もちろんやりますよ。ライヴでも宣言しちゃいましたけど、新曲を作って何かしらのリリースをします。言っちゃえばやるだろうと思って。言わないといつまで経ってもやらないだろうし。だからそれプラス、演劇を(笑)。フレーミング・リップスのウェイン・コインが『CHRISTMAS ON MARS』っていう映画を撮ったじゃないですか。あんな感じのことをしたいですね。芝居なり映画があって、そのサントラを自分で作るみたいな。『summerend』のミュージック・ビデオを自分で監督したので、今後はそういうチャレンジもしたいですね。
──じゃあ、今年は働きまくって本厄が終わりそうな感じですね(笑)。
ヒダカ:確かに(笑)。まずは厄落としに行かないと。でもこの間、オーケンさんと対談した時に「ミュージシャンやロック・スターが"厄落としに行く"とか言うな!」って怒られましたけどね(笑)。