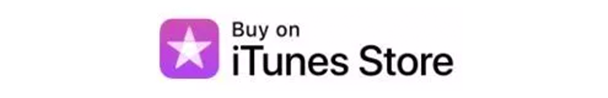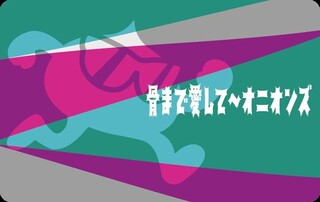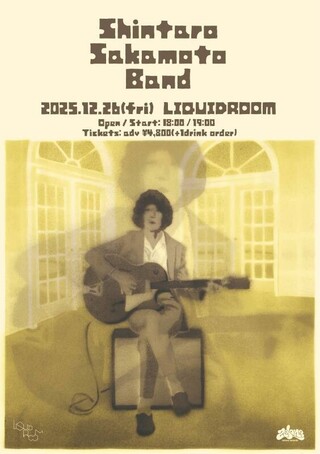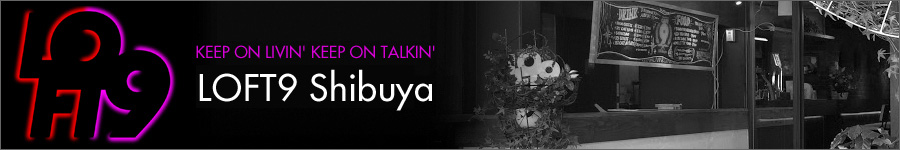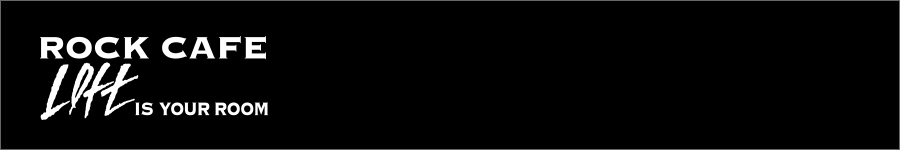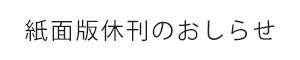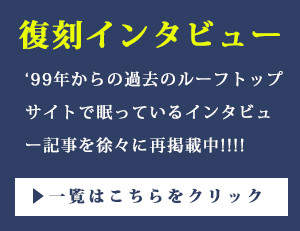今年5月に発表したシングル「CRAWL」がテレビアニメ『隠の王』のオープニング・テーマに起用されたことで、従来のファンのみならず実に幅広い層から注目を浴びるようになったVELTPUNCHが、まさに絶好のタイミングで5枚目となるオリジナル・アルバム『Paint your life gray』を発表する。如何にもVELTPUNCHらしい捻りの効いた楽曲は至上の音質によってより精度を増し、収録曲のヴァラエティさは過去随一。2年前にギタリストの姫野聖二が加入して4人編成となった彼らが今如何にベスト・コンディションにあるかが窺える作品であり、結成12年目にしてひとつの頂にまで到達した記念碑的アルバムと言えるだろう。VELTPUNCHをVELTPUNCHたらしめている唯一無二の"声"である長沼秀典(g)とナカジマアイコ(vo)に最新作の制作過程について訊いた。(interview:椎名宗之)
際限まで細やかな音色にこだわった
──前作『WHITE ALBUM』から僅か1年で新作を発表するに至ったのは、やはり前作とその後のツアーで得た手応えが大きかったからですか。
長沼:本当は『WHITE ALBUM』のツアーが終わったら、しばらくはスタジオでセッションをちんたらやりたかったんですよね。曲を作り上げるというよりは、音を吐き出すような感じで。でも実際はツアーの後半にアニメのタイアップの話を頂いたので、ツアーが終わった翌週にはもう新曲作りって感じでした。最初は"こんな音を出してるバンドに...冗談だろ!?"と思ったんですけど(笑)、せっかく頂いた話なので引き受けることにしたんです。きっかけとしては『a huge mistake』と『WHITE ALBUM』でマスタリングをお願いしたエンジニアさんのところにレコード会社から「いいバンドがいたら紹介してくれ」と話が来たみたいで、運良くVELTPUNCHに話が転がってきた感じです。
──それが『隠の王』のオープニング・テーマとなった先行シングル「CRAWL」なわけですね。オリコンのデイリー・チャートで25位を記録したくらいだし、予想以上に反響も大きかったんじゃないですか。
長沼:今年に入ってから半年間はライヴを休んでいて、再開してからまだ数本しかやっていないので何とも言えませんけど、ひとまずMySpaceには海外のアニメ・ファンからのフレンド・リクエストが殺到していますね。アニソンや声優さん好きな方のブログにも僕らのことを評価して下さっている記述があるみたいで。
ナカジマ:アニメ・ファンは求心力が高いし、ストライク・ゾーンも広いですよね。純粋にいい曲だと思えば誰が唄っていようが関係なかったりするし。ヘンな先入観がないんだなと感じましたね。
長沼:まぁ、シングルはシングルで、自分たちの持ち味の一部分を込めたに過ぎないんですけどね。「CRAWL」でVELTPUNCHを知ってくれた人が、仮に10人に1人でも100人に1人でもいいからバンド自体を好きになってくれたらタイアップの話を受けた甲斐があったと言うか、このシングルがバンドの入口として機能してくれればいいかなっていう。音楽は聴いてもらわないことには存在し得ないものですから。
──メジャー・カンパニーのお世話になって僕がいいなと思ったのは、贅沢なスタジオの使い方ですね。バズーカ・スタジオのエンジニア、パッチさんこと北口剛史さんのブログによると、4台のアンプを数本のギターで試しながら録ったそうですね。
長沼:そうなんです。使えるものは使っておこうと思って(笑)。結局は自己満足なのかもしれないですけど、楽曲によってカラーが全然違うし、楽曲を活かせるサウンドを追求するとどうしても凝ってしまうんですよ。今回は竿も1本1本替えて、際限まで細やかな音色にこだわったんです。
──構成ごとに音色が変わるがゆえに、ギターだけで10チャンネルも使っていたそうですね。
ナカジマ:パッチさんも大変だったと思いますよ。たまに消し忘れた部分があって、「STANDING OVATION」の歌録りの発声練習で「ヤラシイ」って連呼して唄ってた声がミックスで残っていたんです。パッチさんがその声を気に入っていて、結構最後の最後まで消さずにいたんですよね。それをメンバーの誰も気づかなかったので、危うく心霊CDとして世に出るところだったんですよ(笑)。
──もう少しでレベッカの「MOON」みたいになっていたと(笑)。しかし、音色への飽くなきこだわりは1曲目の「MOUSE OF THE PAIN」から如実に発揮されていますね。近年のVELTPUNCHには珍しいほどのハードで性急なサウンドで。
長沼:セカンドの『question no.13』にも同じようなテンションの曲はあるんですけどね。ただ、「CRAWL」という割とソフトでポップ寄りな楽曲を先にシングルとして出していたので、その対極にある楽曲をアルバムの頭に据えて先制パンチを喰らわしたかったんですよ。
──何処となくCOWPERSを彷彿とさせるサウンドですよね。
長沼:仮タイトルからして「COWPERS」でしたからね(笑)。やっぱり、凄く影響を受けていますから。セカンドから遠藤(タイスケ)が加入したんですけど、当時はCOWPERSみたいなサウンドを出したかったんですよ。で、遠藤を誘った時に「お前、COWPERS好きだろ?」と。それまで遠藤がドラムを叩くところは見たことがなかったんですけど、ヤツが遊びでやっていたギター&ヴォーカルのバンドの叫びが凄く良かったんです。それが一番の決め手だったんですよ(笑)。
ナカジマ:とにかく叫び優先で、ドラムは練習すれば上手くなるからって(笑)。
長沼:声帯の強さは持って生まれたものですからね。僕は叫ぶと喉が潰れやすいので。

濁った灰色こそVELTPUNCH本来の色
──そう言えば、「CRAWL」の歌録りは記録的な絶不調だったそうですね。
長沼:風邪を引いて全く声が出なかったんですよ。何せ1コーラス持たなかったですから。
ナカジマ:1コーラスどころか1フレーズじゃなかった?(笑)
長沼:2、3単語唄っちゃゲホゲホ言って...その度にうがいをしなくちゃいけなかったんですよ。2時間それを繰り返していたら声が出るようになって、何とかその日のうちに録り終えたんですけど。
──まぁ、ノイジーなギター・バンドにはケヴィン・シールズのようなか細い声が似合いますからね。
長沼:個人的には現動さん(元COWPERS、SPIRAL CHORDの竹林現動)みたいな歌声も理想ですけど、あれは天性の資質であり武器ですからね。僕が現動さんのようにライヴで唄ったら、1曲の半分で声が出なくなってオシマイですよ(笑)。
──アルバム・タイトルである『Paint your life gray』の同名曲はありませんが、PVも作られた「DIC 954」に"溢れ出すイメージは/君がいないこの部屋を/深いグレーに染めていくんだね"という間接的な表現がありますね。
長沼:"DIC 954"というのは特色指定番号で、大日本インキ化学工業株式会社(現・DIC株式会社)の定めた灰色を指しているんですよ。今回のジャケットやブックレットでも使っている色なんですけどね。最愛の人が目の前から去って行くと世界が灰色に染まるとよく言われますけど、具体的にどれくらいの濃さの灰色なのか、音楽では伝えきれないじゃないですか? だからあらかじめタイトルで「この灰色だよ」って指定しておこうと思って。僕が悲しみに暮れた時は、世界がこれくらい灰色になりますよ、っていう(笑)。
──ジャケットを見る限り、ドン詰まりに濃い灰色ってわけでもなさそうですね。
長沼:まぁ、余りに重い灰色なのも何か嘘っぽいし、これくらいの灰色なのかなと。
ナカジマ:カラーチップを持ち込んで、結構悩んでたよね(笑)。
──「DIC 954」という楽曲自体、物悲しい歌詞の割に曲調は胸の躍るポップさがあって、バランスとしてはちょうどいい色指定なんじゃないですか。
長沼:そうですね。アルバム・タイトルはその灰色というキーワードから膨らませたもので、各楽曲が凄くヴァラエティに富んでいるし、それぞれの持つカラフルな色が混ざり合うと最終的には濁った灰色になるというニュアンスもあるんですよ。その濁った灰色こそがVELTPUNCH本来の色と言うか。綺麗な絵の具の色を使って綺麗な花を描いたとしても、筆を洗うバケツの水はすぐ灰色に濁っちゃうじゃないですか? そんな理屈なんです。
──なるほど。確かに本作は従来になく多彩な楽曲が揃いましたよね。
長沼:それは短期間にアルバムを作り上げなければならなかった状況も関係しているんですよね。アイコさんとギターの姫野(聖二)さんも各1曲ずつ作曲をしたし、曲を完成させるプロセスもバラバラだったんです。今までは僕が完成型に近いアレンジを作ることが多かったんですけど、曲によってはほぼゼロの状態からバンドで組み立てるものも今回はありましたから。
──「四季を描く為に踏むビッグマフなど此処には無い」という楽曲の歌詞には、英語を母国語とする人が聴いたら不快になるような言葉が4つほど盛り込まれていますね。すべて巧妙な日本語として隠蔽されていますけど(笑)。
長沼:取材6誌目にして初めてそれを指摘されましたよ(笑)。そのままの英語を使おうとも思ったんですけど、各方面にいろいろと迷惑を掛けるんじゃないかと(笑)。
──察するところ、セッションから楽曲を煮詰めていった感じですよね。
長沼:セッションの中から生まれたインストっぽい楽曲がいくつか揃って、それを四季として描こうと考えたんですよ。一番核となる楽曲はとても穏やかな感じで、それは春のイメージだったんです。その前に冬の嵐が欲しくなったので、激しいパートを入れてそこから始めようと。で、春が過ぎて夏の昂揚感が欲しくてアッパーなパートを入れて、秋のしんみりした感じを切ないパートで表現して...っていう。そういう四季の移り変わりをサウンドで伝えようとしたんですよ。バンドのアンサンブルだけで気温や湿度の高低を表現したかったんです。
個性が際立つナカジマと姫野の提供曲
──姫野さんによる初の作詞曲「Color of dawn」は新機軸ですが、ナカジマさんと姫野さんがVELTPUNCHと並行して活動を続けるmpjbdでは自作曲を発表していたわけで、これもごく自然な流れですよね。
ナカジマ:mpjbdでは姫野さんと半々で曲を書いていて、もともと曲を書ける人ですからね。VELTPUNCHに入ったばかりの時はまだどういうバンドか勝手が判らないだろうから、入って1枚目(『WHITE ALBUM』)はともかくとして、いずれ姫野さんにも曲を書いてもらうつもりだったんですよ。ソングライターとしての素質は充分にあると思っていましたから。
──姫野さんの楽曲は英詞を多用したり流麗なメロディが特徴的だから、大別するとナカジマさん寄りの作風なのかなと思いましたが。
長沼:まぁ、僕の書く日本語の歌詞はヘンな感じだから、みんなからは避けられているんじゃないですかね(笑)。
──ナカジマさんがメイン・ヴォーカルを取る「Perfect days」と「TRAIN」は、どちらも女性ヴォーカルならではの持ち味がよく出ていますよね。特に後者はアコースティック・ギターを基調としながらしっかりとバンド・アンサンブルの映えるアレンジが施されていて、本作の大きな聴き所のひとつだと思います。
ナカジマ:ありがとうございます。自分の書く曲はコーラスも全部自分でやるんですけど、余りポップス寄りに仕上げちゃうと私の思い描くバンド像と違ってくるんですよね。だから「TRAIN」では女性ヴォーカルの特徴を活かしながらも、Bメロで異常に激しいギター・ソロやドラムが鳴り響く感じにしているんです。ミックスも、最初にパッチさんにやって頂いたものとはかなり変えてもらったんですよ。かわいいだけじゃない感じと言うか、歌以外のパートもちゃんと印象が残るようにしたかったんですよね。パッチさんには「ギター・ソロのヴォリュームはこんなに大きくていいの?」って心配されましたけど(笑)、私はもっと上げて欲しいと思ったくらいなんです。
──本作のミックスは過去随一のバランスだと思いますよ。前作は特にコーラスのミックスが若干引っ込んでいた印象がありましたけど。
長沼:実際、エンジニアさんが今回から変わったんですよ。録りの環境が変わったことで、音で伝えたいことが今まで以上に伝わりやすくなったと思うんです。理想的なミックスによって思い通りに楽曲の個性を出せるようになったと言うか。
──そう言えば、姫野さん作の「Color of dawn」というタイトルはアルバムの世界観を意識してのものなんでしょうか。
ナカジマ:ああ、言われてみればそうですね。今初めて気づきました(笑)。姫野さんは、歌詞にさほど深い意味がないからタイトルを「A Song」にしたいって言ってましたけど(笑)。
長沼:でも確かに、"色"や"花"というのは今回のキーワードになっているんですよね。
──そうですよね。「H.A.N.A.T.A.V.A」然り、「YOUR COROLLA」然り。
長沼:「YOUR COROLLA」の"COROLLA"というのは、"花冠"と言って花弁の集まりを意味するんですよ。
──アルバムの最後を飾るその「YOUR COROLLA」なんですが、これ、思い切り「My Sharona」のリフを拝借していますよね(笑)。
長沼:ええ、そうなんですよ(笑)。
──これはやはり、昨今のエド・はるみブームに乗って?(笑)
ナカジマ:この曲、仮タイトルが「エド」だったくらいですから(笑)。
長沼:歌詞の中に"Reality Bites"っていう映画のタイトルが出てくるんですけど、そのサウンドトラックの1曲目がKNACKの「My Sharona」なんです。だから本当は、「This song isn't included in original sound track Reality Bites」っていう曲名にしたかったんですよね。「この曲は"Reality Bites"のサウンドトラックには入っていませんよ」っていう(笑)。

「YOUR COROLLA」における怒濤のギター・ソロ
──なかなかシャレが効いていますね(笑)。でも仰る通り、"花"は本作のキーワードである"色"の移ろいを表すのに格好の対象ですよね。
長沼:そうですね。『WHITE ALBUM』の時は自分の中で"STUDY & SPORTS"というテーマがあって、「HAPPY SONG 2」の歌詞にも盛り込んだんですよ。それに対して今回は、最初から狙ったわけじゃないんですけど"色と花"っていうのが歌詞に出てくるようになったんです。アルバムの仕上がりも結果的に彩り豊かな楽曲が揃ったし、無意識のうちに"色と花"をテーマにしていたのかもしれませんね。
──「YOUR COROLLA」は8分を超える大作なんですが、やはり圧巻なのは3分にも及ぶ破天荒なギター・ソロですよね。突風が吹き荒れて、花びらが四方八方に舞い散るような風景が目に浮かびますが。
長沼:"これでもか!"って言うくらい、とにかくギターを弾きまくりたかったんですよね。メンバーは嫌がってましたけど(笑)。あのソロはある種の不快感を表現したかったと言うか、轟音の渦に呑み込まれてなかなか抜け出せずにもがいているイメージなんですよ。どれだけ耳障りなギター・ソロでも短い時間なら割とすぐに抜け出せるし、聴く人も"これくらいで終わるだろう"と予想するじゃないですか? だからその予想よりもとにかく長く弾き倒したかったんです。聴く人がだんだんと不安になってきて、曲を飛ばしたい衝動に駆られる。それでもまだまだ終わりそうにない...そんな不安な気持ちにさせたかったんですね。最後はその長いトンネルを突き抜けてカタルシスを得る感覚を聴く人に味わって欲しくて。
──ただ、最後の最後に唄われる歌詞が"こんな音楽、二度と聴かなくてもいい!"という自虐的なものなんですが(笑)、これは反語的な意味なんでしょうか。
長沼:この曲の歌詞では、とある男女の人間関係における駆け引きみたいなものを描いているんですが、仮に心から愛すべき魅力的な女性が自分にいるとしたら、こんなオルタナティヴ・ロックよりももっと流行りの音楽を聴いて欲しいわけですよ。たとえば夏場はレゲエを聴いたり、野外のレイヴで盛り上がったりとか。そうやって凄く素直に、ジャスト・フォー・ファンで音楽を聴けるような人っていうのは、長年バンドをやり続けている僕らからすると羨ましい部分もあるんです。決して頭でっかちにはならずに、いいものはいいというスタンスで音楽を楽しめるわけですから。VELTPUNCHと同一線上にSMAPを聴ける度量があると言うか(笑)、もしかしたらそれが音楽との一番いい付き合い方なのかもしれない。でも、自分は今更そんな聴き方ができないし、どうしてもそのミュージシャンの思想やら時代背景やらを含めていろいろと考えながら聴いてしまう。だから僕の思い描く理想の女性にはこんな音楽なんて聴かずに、みんなで盛り上がれる楽しい音楽だけを聴いていて欲しい、っていう。本当はそんな自分のことを理解して欲しいけど、シェルターになんか来ないでみんなでカラオケボックスに行きなよ、って言うか(笑)。
──長沼さんの仰る"ジャスト・フォー・ファンで音楽を聴けるような人"というのは、アニメのタイアップでVELTPUNCHを知ったリスナーみたいな人を指すのかもしれませんね。
長沼:そうかもしれませんね。固定的な観念とは無縁に音楽を楽しめるわけだから。
──「YOUR COROLLA」の歌詞にある"1994"という年は、長沼さんにとって思い入れの深い時期なんですか。
長沼:"Reality Bites"のサウンドトラックが出た年なんですが、僕自身オルタナティヴ・ロックにどっぷり浸かっていた時期なんですよね。SMASHING PUMPKINSの『Siamese Dream』という未だに大好きなアルバムが出た翌年で、ドキドキしながら新しい音楽と向き合えていた頃なんです。今は心の底からドキドキできる音楽と巡り会えるチャンスが少なくなってきたし、あの90年代初頭から半ば頃までの時代の空気みたいなものに憧れが強いんですよね。

安田大サーカスの団長が理想!?
──「STANDING OVATION」はそんなオルタナティヴ・ロックに淫した人ならではの溜めの効いたディスコティーク・ナンバーで、ありきたりな4つ打ち曲じゃないのでとても新鮮に聴けました。
長沼:この曲がまさにさっき言ったようなタイプの曲で、僕はコードとメロディしか持っていかなくて、後は全部バンドで叩き上げようとしたんです。自分では全く思い描いていなかったリズムやギターを持ち寄られて、純粋に面白かったですよ。ある程度まで作り込んだデモを持っていくと、どうしてもそれが基本になってしまうし、そこから大きく懸け離れたものは生まれづらいですよね。以前はレコーディングの1ヶ月前くらいになると楽曲の完成型を頭に描いていましたけど、今回はそういうイメージ作りをせずに、出来上がるものが格好良ければそれでいいんじゃん、と思ったんですよ。
──それは長沼さんが他のメンバーに対して揺るぎない信頼を置いているからでしょうね。
長沼:やっぱり僕は、各メンバーの音楽的な資質やセンスを尊敬していますからね。まぁ、ギター・プレイに関しては姫野さんよりも僕のほうが遙かに巧いと思っていますけど(笑)。でも僕は姫野さんの作る曲が好きだし、ギタリストとしてではなくミュージシャンとして一緒に音楽を作りたいんです。それにはこのバンドでギターのパートを担ってもらうのが一番いいと。だから極論を言えば、実は姫野さんがベースでもドラムでも良かったんですよね。それは遠藤にしてもアイコさんにしても同じで、アイコさんなんて最初はどうしようもなくベースがヘタクソだったんですよ(笑)。まだ指弾きしかできなくて、ヤマハか何かのもの凄くダサい木目のベースを使っていて(笑)。だからベーシストとしては全く興味がなかったんですけど、とにかくちゃんとハモれたんですよ。出しゃばらずにしっかりとヴォーカルを支えられるコーラス・ワークができたので、こんなに頼もしい武器はないと思ったんですね。この人と一緒なら音楽を作ってみたいと思えた。
ナカジマ:ドラム同様、ベースも練習すれば上手くなるからって(笑)。
──ナカジマさんから見た長沼さんと姫野さんのギタリストの特性とはどんなところですか。
ナカジマ:一言で言えば、姫野さんは森育ちで、長沼くんは街育ちっていう感じですかね。姫野さんはインスピレーション重視の人で、その場で浮かんだものをそのまま出してくるんですよ。だから良くも悪くも、余り小細工ができない(笑)。それに対して長沼くんは理論派で、常に聴き手のことを考えながらフレーズを作る人ですね。
長沼:姫野さんは自分が本当にやりたい音楽を自分のためにやり続けてきた人なんですけど、凄くキャッチーな曲も書こうと思えばちゃんと書けるんです。ただやっぱり、それだけでは飽き足らずに本能の趣くがままに我が道を行くタイプなんですね。僕はそれよりも聴き手の反応が欲しいし、その反応を思い浮かべて曲を作ることが多いんです。しめしめとか思いながら(笑)。
──こうして本作の制作過程を伺っていると、今回はバンドが極めて民主的に作業を進めていたことが判りますね。
長沼:昔は僕も独善的な面が若干ありましたけど、ここ数年は変わってきたと思いますよ。やっぱり各3人のキャラクターは僕から見ても凄く面白いし、際立ったものを持っていますからね。ただ、僕自身は自分の色や匂いを余り全面に出したくないんですよ。影を潜めつつアイコさんたち3人の個性を引き立たせるという意味では、安田大サーカスの団長が僕の理想ですね(笑)。