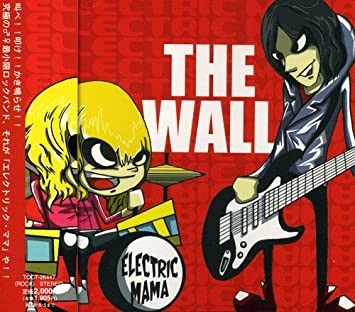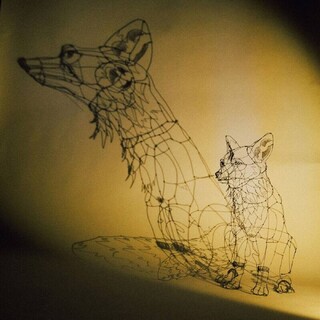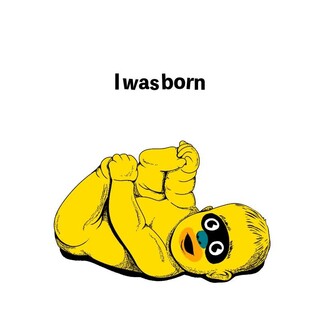生々しい空気感をステージから放ちたい
──あれだけパワフルで躍動感に溢れた亜里沙さんのドラムを聴けば、ブンブンと唸りまくるベースを欲しがるのが人情だと思うし、その辺は痛し痒しですよね。
健司:バスドラとベース音が被さった時の気持ち良さがないとアカンな、とは思ってましたからね。まぁ、まだまだこれから試してみたいことがあるし、サウンドはもっともっと変化させたいですね。
──ライヴ同様、ドラムの抜けの良さが本作でも際立っているんですが、エンジニアの方達から何かアドヴァイスはあったんですか。
亜里沙:特に細かくはなかったんですけど、私達のいろんな話を聞いて“こういう音色が好きなんだろうな”と考えて形にしてくれたんだと思います。個人的にはとにかく、ドラムの音を大きく録って欲しいと思ってましたね。
──こうして1枚録り終えてみて、率直なところどう感じていますか。
健司:今までやってきた曲が新旧織り混ざっていることもあって、最初のアルバムながら集大成的な感じが僕の中にはありますね。古い曲も一番いい形で残すことができたし、言ってみればちょっとしたベスト・アルバムですね。と同時に、またここから新しく始まるんやろなっていう感じも確かにあると思います。このアルバムに入ってる曲以降に出来た曲もありますし、これからもまだまだ作り続けていくんで。
亜里沙:今までは自主盤って言うくらいで全部自分達でああしようこうしようとやってきて、そういうのももちろんいいんですけど、今回のアルバムにはいろんな人達の手が加わってるから、今まで作ってきたCDとは全然違いますよね。だから凄く大きなアルバムなんです、自分の中では。人間は独りでは生きていかれへんなぁ…って、そんな当たり前のことを今回は凄く思いましたね。やっぱり人間同士が関わり合わんと、そこから新しいもんは生まれないんだなと実感しました。
──バンドの真髄であるライヴに対する向き合い方も変化してきたんじゃないですか。
健司:そうですね。最初の頃のライヴは、ヘンに押し付けるわけではなかったんですけど、自分達がいいと思ってる音楽を“どやッ!?”と見せ付けるようにやってた気はします。自分達がいいと思ってるんやからみんなも判るはずや、と言うか。今はそうじゃなくて、お客さんにはもっと単純に楽しんでもらいたいと思ってますね。
亜里沙:自分らのことだけじゃなくて、そこにいる人達のことも冷静に見られるようになったんですよね。ライヴで一番楽しいのは、客席の知らん人と目が合って、凄く気持ち良さそうにしてるのを感じた時なんですよ。それが一番嬉しい。演奏してる私達に、向こうから“今こんなこと思ってるよ”って表情や行動で返してくれてるわけですよね。そのやり取りが凄く面白いんです。
健司:ハッピーになることだけがすべてじゃないと思いますけど、“ええ曲やな”とか“テンション上がるな”とか、そういう純粋な楽しさを共有したいですね。
亜里沙:伝えたいことが変わってきたんでしょうね。最初は“私達はこんなやねん”みたいのを全面に出したかったんです。今はそういう時期が終わって、その場で生まれた生々しい空気とか生きてる感覚をステージから放ちたいと思ってますね。