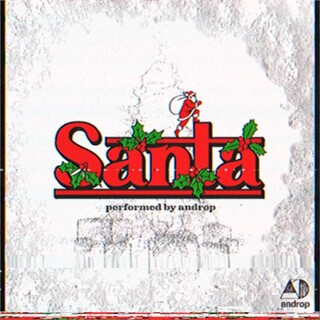行間に込められた歌の隠し味
──『Groria streetから愛を込めて#2』は『Groria streetから愛を込めて#1』に比べてこんなに変わったのかっていう驚きがありましたよ。
門田:そうですね。最初、#2は#1で歌っている視点の大人になった姿を歌おうと思って作っていたんだけど、やめたんです(笑)。#1の未来形としての#2だと現実感は増すけれど、#1のロマンシチズムが失われてしまったんですよね。だから定点観測にしてしまおうと思ったんです。#1で「さようなら。人間は独りだから」っていう素敵な別れがある風景の中で、隣の家ではこういうことがあっても良いなっていう。テーマとしては何かに関しての決別を歌っているから矛盾はないんですけどね。
──#1の続きとしての#2だったら、物語の起承転結の“結”を言ってしまう無粋さがありますよね。
門田:#2で物語をThe EndにすることはNOだなと思ったんです。
──歌詞はグサッと来るフレーズもありクスッと笑うところもあり、曲調はどたばたコメディーチック。
門田:音楽にユーモアを取り戻したかったんですよ。なぜニューオリンズの曲はあんなに陽気なのか。なぜ90年代以降の音楽は杜撰なのか、悲哀性を含んでないといけないのか。それは時代のせいかもしれないけれど、表現したいことに音楽を寄り添わす努力をしていないだけだと思う。音楽って茶道とか書道とかと一緒で「道」がつくものだと思っているんです。だから一生かけて極めたいと思ってる。自分のできない範囲のことをいっぱいやっていきたい。それを成功させないといけないんだけど、自分が表現したいことを「しらけ」で完結させたくないんですよ、絶対に。正直メロディーがどうこうじゃなくて、表現したい曲がそれだからそういう曲調になるんです。
──詩を読ませたければ詩集を出せばいいわけですからね。さっきニューオリンズの曲がなんで明るいかって言われてましたけど、それは絶望の裏返しなのかもしれないですね。表面だけなら陽気で楽しい曲だけど、その裏に何があるかが大事で、演者と受け手のイマジネーションのキャッチボールみたいなものなんじゃないかなって。
門田:『聖者の行進』を演奏してアフリカン系のアメリカ人が喜んでいるとしたらば、ニーナ・シモンが女性としての歌を歌う時は、絶対にそこには壮絶なドラマがあるんです。行間に込められている部分が歌の隠し味になっているんですよ。今、コミュニケーションの取り方に関して言うと、一番悲惨な世の中だから俺たちは表現の中に全てを込めているんです。
──正解はないけれど、考えるヒントを与えてくれる力が音楽にはありますからね。
門田:答えは出せないけれどきっかけにはなりますから。
──#2はサウンドの録り方が面白いですね。
門田:俺たち自体は適当に考えてやってるんだけど、適当な精神状態に持っていくまでのフィーリングを掴む努力はしているんですよ。『Natural Born Queen』で言ったら、ロックンロールのフィーリングをどういうふうに自分たちなりに解釈できるか。そこまでに時間をかけていて、録り自体は適当にやって終わり方も決めてなかった。だけど、その適当さ加減と言ったらものすごくレベルが高いんです。もちろんシビアな表現をしないといけない時は逆です。『ハイ・ストレンジネス』(the GOLDENBELLCITY ep1)は全然違ったし、曲ごとで取り組むフィーリングに関しての焦点をみんなに要求するんです。『Natural Born Queen』のリハをやろうって決めたときは、スタジオに行く前の日から適当な雰囲気を作るためにどんな会話をしたらいいだろうっていうことをずっと考えている。狂気の沙汰だと思いますよ。音に関係していないところでシビアになりすぎているんですよ。でも音楽って、音楽に関係ないことが音になりますからね。
当たり前のことを当たり前に表現しているだけ
──『Groria streetから愛を込めて#2』は音のメリハリとかボーカルのイコライザーの使い方とか、すごく計算しつくされてあの形になっているんですよね。
門田:エンジニアの松本さんがすごくアイディアマンだから、俺は初めてやることをすごくたくさんやらせてもらったんです。ボーカルはギター練習用のミニアンプで流してマイクで拾って録っているんです。マイクのキャップを全部はずして、むき出しになったマイクのコンデンサーに布を被せて叫びながら歌っています。ロータリースピーカーみたいな雰囲気が出ましたね。
──今回、アナログ機材面での試みは?
門田:『Natural Born Queen』に関してはギター・ボーカル・ドラム・ベース・コーラス全部アナログで録ってモノラルなんですけど、パフッとギュイーンという音だけステレオになってるんです。だからこの2つだけ異常にデカイ(笑)。
──コミックソングじゃないんだから(笑)。
門田:そうそう(笑)。そういう感覚でしたね。面白いことは何でもやってみようって。
──サウンドの実験性と愛というヘビーな内容を歌った絶妙なバランスの4曲が揃いましたね。
門田:愛というテーマで取り組んだ4曲のわりには愛至上主義ではない、愛は素晴らしいものではないという愛をテーマにしたCDなので、その部分をみんなに感じてもらえたらと思います。
──さっき“畏怖”とおっしゃいましたけど、愛はいろんなものを犠牲にしなければならない怖さがありますよね。
門田:何かに対してのイエスは何かに対してのノーですから、そう考えると愛は素晴らしいんだよって主張してしまうことはネガティブなんですよ。僕らは自分のCDを売りたいだけで音楽をやっているわけではなくて、聴き手が理解してくれるまで伝えなくてはならないんです。
──全部のピースはまだ揃ってないですけど、だいぶ『the GOLDENBELLCITY』の輪郭が定まってきましたね。
門田:実は、答えを出さない表現をするということに困っているんです。完成度の低さだとは思って欲しくないけれど誤解もされるし、はっきりしてないじゃんって言われるけど、物事ってはっきりしてないものなんですよ。そういった意味ですごく困っているんです。Good Dog Happy Menをやり始めてからずっと。その覚悟はしているんだけど、他の人たちが答えをはっきり言うから、その人達と比較をされて評論家の人と話をしていると、ものすごく困るんです。
──聴き手が予定調和に慣れちゃってるんでしょうね。
門田:麻痺しちゃってるんですよ。表現に携わる人間はそれは致命的なんです。
──音楽に良し悪しはないけど、“結”の部分を自分で想像しないのは絶対的な“悪”ですね。
門田:そうなんです。音楽云々ではなく、“結”を自分で持てないのは悪だと思う。『Twice Birds' Singing』も「何百回目のキスをしたね」って繰り返してるけど、聴きようによっては「それでどうしたの?」って感じなんですよ(笑)。でも、俺にとってその一言が愛の全てなんです。だから、そういう答えなら俺にははっきりある。
──今Good Dog Happy Menがやろうとしていることは、グレイゾーンの魅力だと思いますよ。
門田:グレイゾーンっていう言葉を聞いて思ったんですけど、イエスかノーかをはっきり持てるんであれば、宗教は世の中にないと思う。音楽っていうのは宗教の真逆にあるものだと思ってます。宗教は合理的なもので、救済というものを求めるでしょ。で、非科学的なことに救済を求めて、その救済で自分の中にイエスを作る。そこに俺は絶対的な疑いを持つことが表現だと思っているんです。事実というのは、驚くことなんです。なぜそういうことが起こるんだろうって、“なぜ”を探したいんです。答えがないことが多いから。表現は絶対なくならないだろうし。
──答えが欲しかったら禅問答に行けばいいわけですからね。
門田:俺が言ってることは禅問答とは絶対違うんだけどそう捉えられやすい。ものすごく当たり前のことを当たり前に表現しているだけなんです。だからGood Dog Happy Menは変化球だと思ってしまう日本の音楽シーンはおかしいなと思うんです。