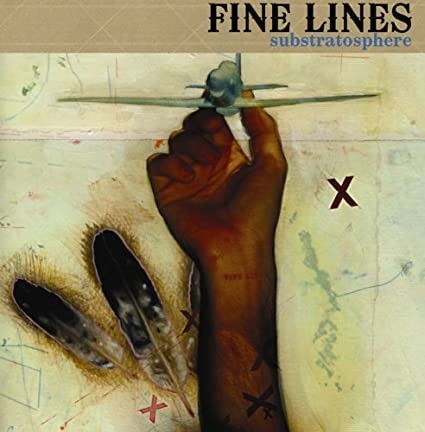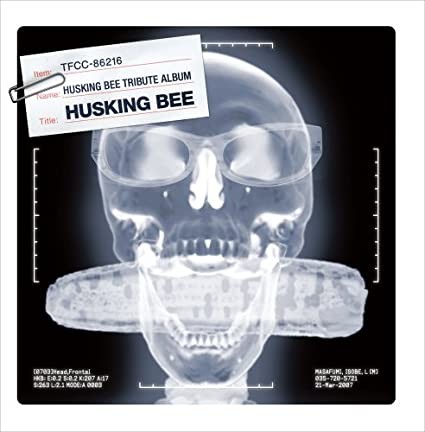長距離を飛行する時に適した空域
──そして遂に完成した初のアルバム『substratosphere』ですが、FINE LINESの名刺代わりに相応しい充実作となりましたね。
 平林:ありがとうございます。レコーディング前に考えたのは、“こういう感じの曲でライヴをやってますよ”っていうのをアルバムの中でちゃんと表したいということだったんです。“FINE LINESってこんな音楽なんですよ”っていうように、僕達のことをまだ知らない人に判ってもらえるようなものにしたいな、と。やっぱり、それまでサイド・プロジェクト的な見られ方をずっとされてきたと思うんですけど、もうそろそろそういうのもイヤだなと思って。僕達は本腰を入れてFINE LINESに取り組んでるし、あくまでバンドとしてそこに在るというのを音の面で強く表したいと思ったんですよね。
平林:ありがとうございます。レコーディング前に考えたのは、“こういう感じの曲でライヴをやってますよ”っていうのをアルバムの中でちゃんと表したいということだったんです。“FINE LINESってこんな音楽なんですよ”っていうように、僕達のことをまだ知らない人に判ってもらえるようなものにしたいな、と。やっぱり、それまでサイド・プロジェクト的な見られ方をずっとされてきたと思うんですけど、もうそろそろそういうのもイヤだなと思って。僕達は本腰を入れてFINE LINESに取り組んでるし、あくまでバンドとしてそこに在るというのを音の面で強く表したいと思ったんですよね。
──タイトルの『substratosphere』ですが、まず“サブストラトスフィア”とスラッと読めないのが逆にインパクトがありますよね(笑)。意味としては、成層圏よりも低い高度約10,000メートル付近の空域=“亜成層圏”とのことですが。
平林:インターネットの英和辞書で言葉を調べてる時にたまたま見つけたんですよ。アルバムのタイトルをどうしようかと考えていて、“s”から始まる単語がいいなと思って関連語をダーッと見ていたら“substratosphere”という単語が目に入ってきたんです。パッと見た感じのアルファベットの並び方がいいなと思って、僕は凄く好きだったんですよね。まぁ、完全に直感で決めたんですけど(笑)。
──“天候の変化もなく常に気流が?た安定し、長距離を飛行する時に適した空域”…バンドがようやくそんな域に達したという意味も込められているんでしょうか?
平林:そういうふうにも取れますよね。いろんな捉え方ができると思うんですよ。すでにその空域に居るのかもしれないし、これからそこへ向かうのかもしれないし。もしくは、一時的にそこに居るだけなのかもしれないし。もうその人の受け止め方次第と言うか。まぁ、不意に見つけた言葉で意味は後で知ったわけだから、すべて後付けなんですけどね(笑)。
──1曲1曲の完成度が高いのは、ライヴで試行錯誤を繰り返した末にレコーディングしたことも大きいですよね。
平林:そうですね。ほとんどが元々あった曲だし、ライヴの後に“ここはもっとこうしたほうがいいかな?”と考えて、練習の時にアレンジを加えていった曲が多いんですよ。
──巧者4人による卓越したアンサンブルは十二分に聴き応えがありますが、透明感のある平林さんの歌声にすべてが集約されている印象を受けますね。
平林:曲はアコースティック・ギターと歌だけで作るんですけど、それを核としていい歌を作ることを念頭に置いているからですかね。ただ、今回はドラムやベースがガッツリ鳴って、歌はちょっと小さくなるくらいでレコーディングの作業を進めたんですよ。ヴォーカルがちょっと埋もれるくらいでいいと思ったし、そういう音が基本的に好きなので。他の楽器が歌を支えきれてないようだったら面白くないし、一個一個の楽器が強く出ていて欲しいと言うか。最終的にミックスの時にはどのパートもよく聴こえるいいバランスになったんですけどね。
──曲の核がしっかりとしていれば、レコーディングでアレンジを煮詰める作業もそれほど時間が掛からないですか?
平林:今のところはそうですね。スタジオに曲を持っていく時点で7〜8割方は固まっているので、そこから先は余り手間が掛からないですね。
──当初は譲治さんとのアコースティック・ユニットとして始まったFINE LINESが、TEKKINさんと片山さんという鉄壁のリズム隊なしでは生み出せないグルーヴを内包した“バンド”であることが本作を聴くとよく判りますね。
平林:ええ。リズムに関してはTEKKIN君と片山さんの2人が事前にかなり練ってきてくれたんです。「こんな感じになったけど、どう?」って聴かせてくれて、進んでアイディアを出してくれたり。
響きのある日本語詞にこだわりたい
──アルバムは印象的な鐘の音から始まりますが、これは何か意味が込められているんですか? 「風鳴る夜」にも“あんなに鳴ったはずの鐘の音も…”という歌詞がありますけど。
 平林:ぶっちゃけ、意味は全然ないんですよ(笑)。2曲目の「Unbounded」を1曲目にしようと思ってたんですけど、その前に何かイントロ的なものを入れたほうがいいんじゃないかという話になって。他のみんなが録りの作業をしている時に、休憩室でMTRにギターの音を重ねて入れて、その場で作ったんですよ。そこに鐘の音を入れてみたら意外とハマったんですよね。「風鳴る夜」の後に入る7曲目の「Bronze Miscanthus」も、良いアクセントになるかなと思って挿入してあるんです。決して曲稼ぎのつもりじゃないんですよ(笑)。仕切り直しってわけじゃないですけど、レコードのA面、B面のような区切りの意味合いなんです。
平林:ぶっちゃけ、意味は全然ないんですよ(笑)。2曲目の「Unbounded」を1曲目にしようと思ってたんですけど、その前に何かイントロ的なものを入れたほうがいいんじゃないかという話になって。他のみんなが録りの作業をしている時に、休憩室でMTRにギターの音を重ねて入れて、その場で作ったんですよ。そこに鐘の音を入れてみたら意外とハマったんですよね。「風鳴る夜」の後に入る7曲目の「Bronze Miscanthus」も、良いアクセントになるかなと思って挿入してあるんです。決して曲稼ぎのつもりじゃないんですよ(笑)。仕切り直しってわけじゃないですけど、レコードのA面、B面のような区切りの意味合いなんです。
──譲治さんの手掛けた曲(「Spin Into Love」「Almost There」)はSHORT CIRCUITを彷彿とさせる英語詞で、ソングライターの個性の違いが表れていてバランスが絶妙ですね。
平林:譲治の曲はあと2曲あったんですけど、録りの段階で本人としては煮え切らない部分があったらしくて(笑)、次の機会に回そうってことになったんですよ。僕が譲治に求めているところは、まずギタリストとしてのしっかりとしたプレイと存在感、それとコーラスなんです。それによって自分は歌により徹することができるので。
──平林さんが書いた曲では「Small Red Light」のみが英語詞で後は全部日本語ですが、曲によって書き分けているんでしょうか?
平林:「Small Red Light」は一番古い曲で、その時は日本語詞でやろうとは思わなかったですね。単純に英語詞の響きが気持ち良かったので、自然な流れとして英語で作ったんです。それ以降に作った曲も詞を英語で書いてみようと思ったんですけど、なんか回りくどくて。時間も凄く掛かるし、日本語でいい聴こえ方をする言葉を探したほうが面白いと思ったんですよ。
──意味に比重を置くよりも、言葉の響きを優先して歌詞を書いている、と?
平林:やっぱり響きが僕は一番好きだし、唄っていて気持ち良いんですよね。かと言って意味を成さない歌詞になるのもダメだと思ったし、そのバランスは凄く難しいですね。普段から響きのある言葉をノートに書き留めたりはしているんですけ?たど、言葉の選び方には慎重になるし、凄く神経を使いますよね。
──絵画に喩えるなら、歌詞の世界は透明度の高い水彩画のようですね。色の濃淡が繊細な筆圧で描かれているような。
平林:その辺は意識しましたね。自分の内面を吐露したり、ある特定の事柄について唄うというよりは、いろんな人が聴いて自由な情景が浮かぶような抽象性の高い歌詞にしたいと思ったんですよ。どうにでも染まってくれ、って言うか。歌詞を書く時に思い浮かぶのは、ストーリーやメッセージというよりも風景や映像なんですよね。もちろん多少メッセージは織り込んであるんですけど、あくまで僕の場合、一番大事なのは情景描写だと思ってます。今のところは。
──英語詞を唄っていたHUSKING BEEが中期から後期にかけて「海の原」や「欠けボタンの浜」といった日本語詞の名曲を数多く発表したのも、極々自然な流れでしたよね。
平林:そうですね。磯部君も日本語で唄った時に気持ち良かったんだと思うし、そこで新たな発見があったんじゃないですかね。FINE LINESでも情感と響きのある日本語詞にこだわった音楽をこれからもやっていきたいし、譲治も次は日本語詞の曲をやりたいと言ってますから。今回譲治が書いた2曲はどちらもラヴ・ソングっぽいので、彼が日本語のラヴ・ソングを持ってくるのが今から楽しみですね(笑)。