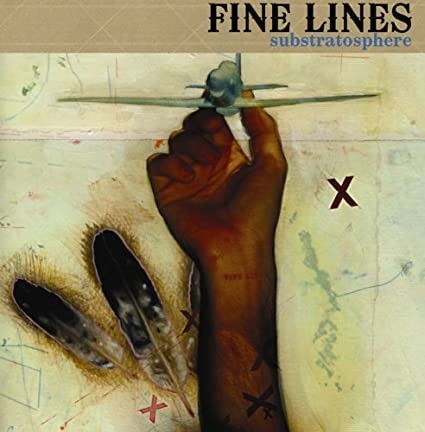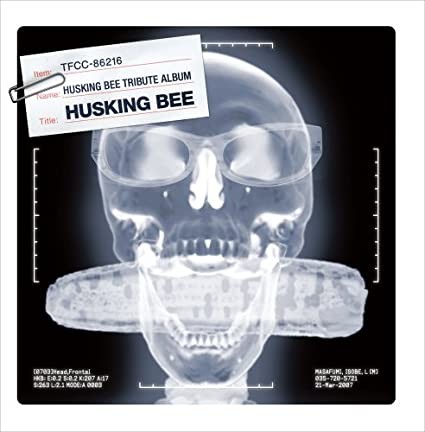元HUSKING BEEの平林一哉(vo, g)と元SHORT CIRCUITの黒澤譲治(g, vo)によるアコースティック・ユニットとして結成され、元HUSKING BEEの"TEKKIN"こと工藤哲也(WORD、BEYONDS/b)とSLIME BALLの片山豊(ds)が加入してバンド形態での活動にシフト・チェンジしたFINE LINES。日本のメロディック・パンク・シーンを牽引し続けてきた綺羅星の如きメンバーから成る彼らの初のフル・アルバム『substratosphere』が遂に完成した。繊細で情感豊かなそのメロディの高いクオリティはこれまで発表されてきたオムニバス盤参加曲やシングルで既に実証済みだが、本作は胸を締め付けるエモーショナルで彩り豊かな楽曲が更にぎっしりと詰まった、まさに会心の作。まるで少年のように透明感に溢れた清々しい歌声を聴かせるバンドのフロントマン、平林にFINE LINESの結成から今日に至るまでの道程について語ってもらった。(interview:椎名宗之)
“大事なのは歌なんだ”と再認識した
──晴れてファースト・アルバム発表と相成ったわけですが、考えてみると結成('03年6月)からもう4年近く経つんですよね。
平林:ああ、もうそんなに時間が経ってましたか(笑)。始めたばかりの頃は余り気負いもなく、暇な時にチョロッとやるような感じだったんですよね。
──そもそもの始まりはどんな経緯だったんですか?
平林:確かシェルターだったと思うんですけど、誰かのライヴの打ち上げに顔を出して、そこでたまたま譲治と会って話したのが最初ですね。アコースティックの形態でゆるい感じの音楽をやってみたいっていうのはそれ以前からずっと考えていて、そのことを譲治に伝えたら「一緒にやりますか」って話になって。最初は全くの一人でやろうと思っていたんですよ。せいぜいコーラスをやってくれる人がもう一人いればいいかな、くらいで。
──お手本とするユニットは何かあったんですか? 例えば、イアン・マッケイのTHE EVENSとか。
平林:いや、特にはなかったですね。当時、磯部(正文)君がCORNERを始めたり、HUSKING BEEのライヴの中にアコースティック・セットを採り入れてみたりしていて、その影響もあったと思います。それと、その時期によく聴いていた音楽がアコースティックを主体としたものが多かったんですよ。マット・プリオール(ex.THE GET UP KIDS)がやってたTHE NEW AMSTERDAMSとか、FARが解散してジョナ・マトランガが始めた弾き語りユニットのONELINEDRAWINGとか、そういうのを好んで聴いていたんです。特に、ONELINEDRAWINGみたいに宅録っぽい感じで完全に一人でやってる音楽は凄く面白そうだし、単純にいいなと思えたんですよね。
──HUSKING BEEとは異なる、平林一哉にしか表現し得ない音楽性を確立したいという思いは?
平林:今はそういう気持ちもありますけど、最初はそこまで志が高かったわけじゃないんですよ(笑)。もっと軽い気持ちで、純粋に自分が憧れてた音楽をやりたいっていうところから始めたので、時間にゆとりがある時にできればいいなっていう感じだったんです。
──実際に譲治さんと音合わせをしてみて、“これだ!”という手応えは最初から感じましたか?
平林:いや、最初からはなかったですね(笑)。初めの頃は、人のライヴにひょっこり出させてもらって、チョロッと演奏して逃げ帰るみたいな感じだったんですよ(笑)。いざ人前でアコースティックで演奏するとなると、やっぱり凄く緊張しましたからね。シンプルなぶんだけごまかしが利かないから、とにかく一杯一杯だったんです。だから、最初は手応えを感じるまでには至らなかったんですよ。それよりも、どうしたらギターと歌だけで成立させるかを考えることが凄く多かったです。
──と同時に、HUSKING BEEと違ってオーディエンスの注目を一身に集めるプレッシャーもあったでしょうし。
平林:そうですね。そういう場に敢えて自分から身を投じて、精神的に強くなりたいとも思っていたんですよ。2人でも4人でも、ライヴをやる以上臨む姿勢は一緒だと思うんですけど、自分の中でいろんなものを築き上げたかったし、アコースティック・スタイルならではの新しい発見をしたかったんです。
──その“新しい発見”は徐々に掴めてきましたか?
平林:個人的にはやっぱり、“大事なのは歌なんだ”ということを改めて気づきましたね。歌の周りで鳴っている音はもちろんあるんですけど、その芯さえしっかりしていれば表現形態はどうにでもできるんだな、と。だから歌の芯となるものをもっともっと強めていきたいと思ったんですよ。
──それと、アコースティック・スタイルになるとヴォーカルのアプローチも自ずと変わってきたと思いますが。
平林:そうですね。家でアコースティック・ギターを弾きながら唄っていて、バンドで唄うこととの違いがよく判りましたね。声の出し方ひとつで聴こえ方も全然違いますから。気持ち良い反面、怖いところもある。ただ、声も楽器のひとつと考えると、もっといろんな試みをしなくちゃいけないと思いましたね。シンプルがゆえに奥が深いんですよ。
アコースティック・ユニットからバンド形態へ
──バイオグラフィを紐解くと、「Small Red Light」が収録された『CARRY THAT WEIGHT』、ジミー・ソウルの「IF YOU WANNA BE HAPPY」のカヴァーが収録された『multiply ur bloodstone』という3P3B設立5周年を記念した2枚のオムニバス・アルバム('04年4月発表)が初の公式音源でしたね。
 平林:そろそろ音源を残したいと思ってたし、有り難く声を掛けてもらったので、いい機会かなと思って参加させてもらいました。その頃はもう、漠然としてましたけど長期的な展望でFINE L?たINESをやっていこうと考えてましたね。ゆっくりでいいから続けていきたい、と。
平林:そろそろ音源を残したいと思ってたし、有り難く声を掛けてもらったので、いい機会かなと思って参加させてもらいました。その頃はもう、漠然としてましたけど長期的な展望でFINE L?たINESをやっていこうと考えてましたね。ゆっくりでいいから続けていきたい、と。
──その後、'04年12月にシェルターで行なわれた『Get ahead of them 〜3P3B忘年会LIVE〜』でベースにHUSKING BEE時代からの盟友であるTEKKINさん、ドラムにSLIME BALLの片山さんを迎えて初めてバンド・スタイルでのライヴを行なうことになったわけですが、リズム隊はやはりこの2人しかいないと考えていたんですか?
平林:そうですね。片山さんのドラムは昔から聴いてきて、僕は凄い好きなタイプのドラムなんです。おっきい音を鳴らしつつ安定もしていて、抜けがいいっていう。だから、いつか一緒にバンドをやれたらいいなとずっと思っていて。TEKKIN君は、まぁ勝手知ったる仲と言うか…(笑)。
──勝手知ったる仲がボトムを支えていれば、ヴォーカルにより集中できますからね。
平林:ええ。一口にベースと言ってもスタイルも十人十色で面白いですけど、TEKKIN君の場合はやり始めやすいっていう部分はありましたよね。プレイの良い部分を引き出すことに専念する必要もないし。
──いずれはバンド形態にしようという構想は当初からあったんですか?
平林:いつかメンバーが増えていけばいいなぁ、という思いは漠然とありましたけどね。今すぐにというわけじゃなく、必要に応じて増やしていきたいとは考えていました。
──磯部さんのCORNERとのコラボレート・シングル『small happiness』('05年10月発表)は、HUSKING BEE解散後初の作品という話題性もあり、注目を集めましたね。
平林:『small happiness』の時はHUSKING BEEがもう終わっていたので、バンドとしてガッツリやっていきたいと考えてましたね。3P3Bのオムニバス用に録った「Small Red Light」をマスタリングし直して、自宅の機材で録音した「I DRIVE」を入れてシングルとして同じタイミングで出したりもして。
──意識してHUSKING BEE時代の曲とは違う方向性で行こうと考えたところはありましたか?
平林:“このバンドだからこんな曲にしよう”とかは、僕自身余り考えたりしないんですよ。自分が関わって好きにやれるバンドであれば、自分の歌として純粋に自分のやりたいことをやってみようと思うんです。だから、HUSKING BEEと違いをつけて曲を作ろうっていう意識は今もないです。
──4曲入りシングル『WRITE TO ME』('06年2月発表)を発表した頃には、アルバム制作を視野に入れた曲作りに勤しんでいた感じですか?
平林:そうですね。ライヴでやる曲の数がとにかく少なかったので、アルバムを作るというよりもまず何よりライヴでやれる曲を増やそうとしましたね。それで『WRITE TO ME』に収録した4曲を固めて、それでもライヴの持ち曲が足りないから他にも数曲作ったりして…。正直、当時はアルバムのことまでそれほど深く考えてなかったですね。発表できる機会が来た時にしっかりやろうとは思ってましたけど。そう考えると、結成してから今日までずっとマイペースにやってこれたのはラッキーでしたよね。