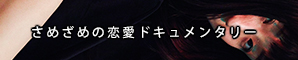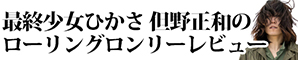「ナゴムレコードの映画を作りたいのだが、許諾をもらえないか」という相談があった。
ナゴムレコードというのは、1983年から約10年間、私がオーナーを務めていたインディー・レーベルであり、ここから作品をリリースしたのは、自分のバンドだった「有頂天」、大槻ケンヂ、内田雄一郎と私でやっていた「空手バカボン」、田口トモロヲ率いた「ばちかぶり」、石野卓球とピエール瀧(当時は畳)の「人生」、「筋肉少女帯」、「たま」等々、計50近いグループ。
結論から言うと、「ナゴムの映画」は丁重にお断りした。映画を通して何をしたいのかが不明確だったし、昨年末にレイト公開されてヒットした「たまの映画」を安易になぞって儲けようという魂胆が見え見えだったことも大きい。
ナゴムレコードという巨大な現象は、もはや私を含む当事者達すら掴み切れぬものだ。偉大だなどと言うつもりはない。むしろ、しょーもないものだった。ただ、なんだか得体の知れないエネルギーが渦を巻いていたのは確かであり、それは我々から一方的に発せられたエネルギーでは決してなく、ナゴムギャルと呼ばれたオーディエンスや、「宝島」に代表されるメディアや、「インディーズ」というシステム自体の力、そして80年代という時代とのマッチングが生み出した偶発的にして奇跡的なエネルギーである。
あのエネルギーを、30年近い時を経た今、リアルに伝えるのは至難の業なのではないか。当時のライブ映像を繋いだだけでは到底実感できまい。だからと言って、あの頃を回想して「すごかった」「楽しかった」を連発しているだけのインタビュー映画なんて、私は観たくもない。
しかしながら──。全体像なんぞ到底捕まえ切れぬ大きな現象ではあるが、ほんの一側面を切り取り、そこから全体を浮かび上がらせることは、可能かもしれない。
一体どこをどう切り取り、どんな視点で見つめるのか。そこんとこさえ明確なプロデューサーや監督がいれば、私としてはいつでもGOサインを出すつもりでいるのだが……。
音楽性はもちろん、ルックスやパフォーマンスも含めて異彩を放ち続けた個性派インディーズ・レーベル、ナゴムレコード。キャプテンレコード、トランスレコード等と並んで当時のサブカルチャーの一端を担った。リリースされた数々の音盤でお馴染みのトレードマーク「アヤトリシアワセ印」はゲルニカの太田螢一氏によるもの。ナゴムレコードからナゴムカンパニーに変わってもこのキャッチマークは変わらなかった。