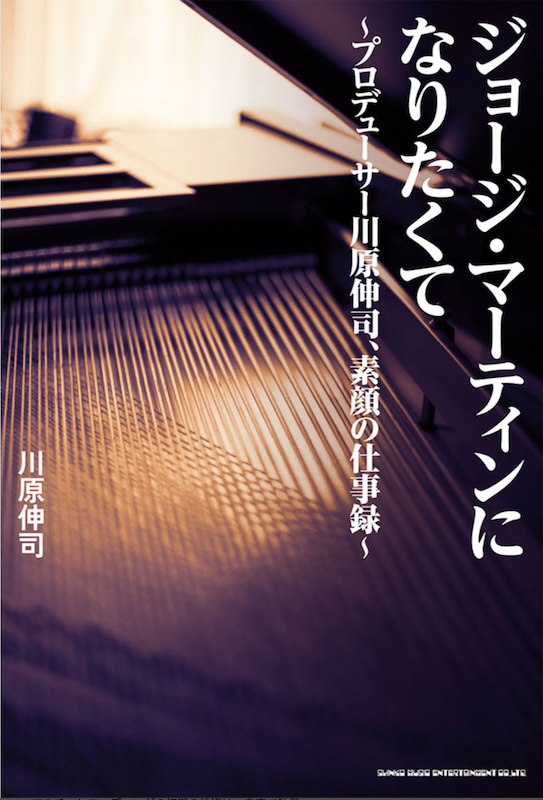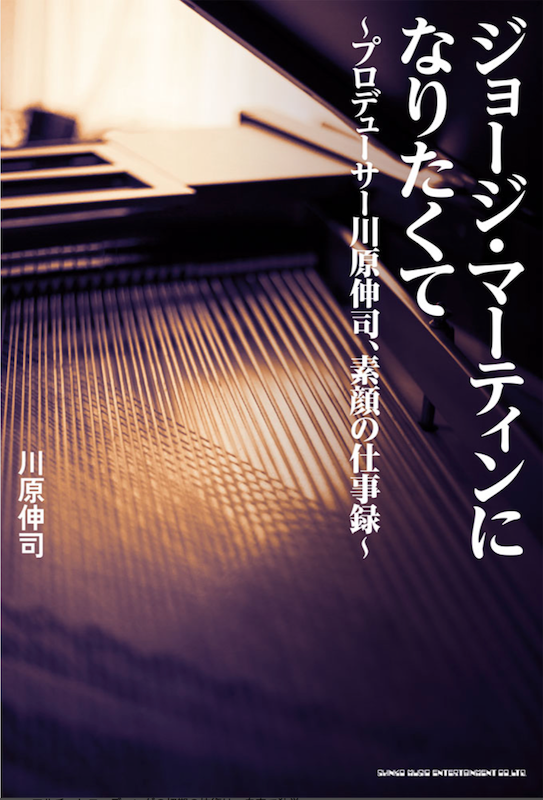2023年1月12日、新宿ROCK CAFE LOFT is your roomにおいて書籍『ジョージ・マーティンになりたくて〜プロデューサー川原伸司、素顔の仕事録〜』発売記念イベントとして、著者の川原伸司(ビクター)と、目黒育郎(ソニー)のスペシャル・トークセッション<80年代J-POPを作った男たち。ビクター VS ソニーの軌跡>が行なわれた。共にビートルズ・ファン、そして80年代の日本のポップス/歌謡曲シーンを牽引したディレクター/プロデューサーとして活躍されたお二人のトークを紹介する。司会進行は同書の編集担当・田中浩一。
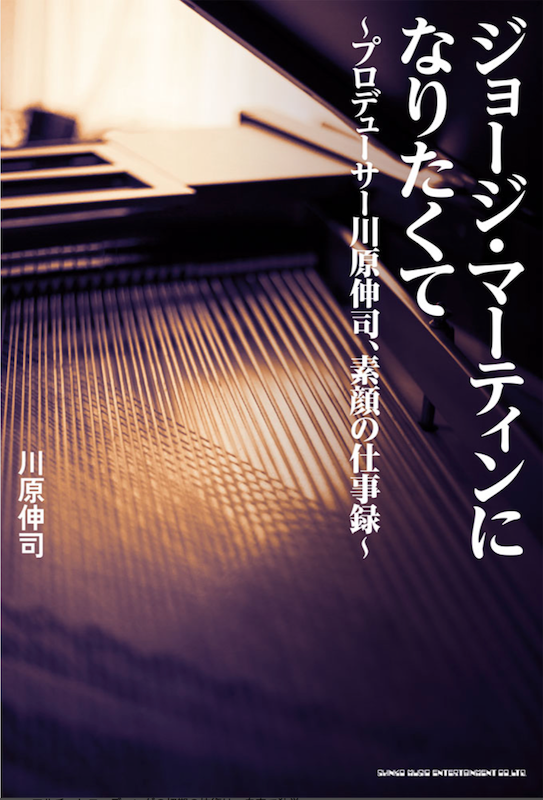
田中:まずは著者の川原伸司さんをお迎えしてのトークから(川原が松田聖子に書いた「ロマンス」をBGに登壇)。この『ジョージ・マーティンに〜』にもありますが、大滝詠一さんから「明日の朝までに書いて──」と言われて書かれた曲。
川原伸司(以下、川原):この頃、松田聖子さんは変声期で、高い声が一切出なくて音域が上下1音くらい低くなっちゃって。その中で作ったのでちょっと大変でした。聖子さんとは初めての仕事でしたけれど、同じ事務所(サンミュージック)の桜田淳子さんや森田健作さんはけっこうビクターと仕事をしていたから、従来の色合いとは違って面白かった。
田中:でも「翌日まで──」というのは。
川原:<従来の歌謡曲じゃないポップスをやればいい>っていう自信があったんでしょうね。ポップスといっても筒美京平さんや都倉俊一さんのとも違うポップスが見えていた時代なんですよ、大瀧さんや細野(晴臣)さん、松本(隆)さんも含めて。当時、アイドル・ポップスっていうのはニュー・ミュージックとは違うジャンルだったんだけど、はっぴいえんど系の人たちが松田聖子さんで実験したんです。彼女のパワーも凄いから、どんな難しい歌を与えても<松田聖子の歌>にしちゃうっていう才能があったから滅茶苦茶なことをやってました。当時、『アマデウス』っていうモーツァルトの映画の試写会を松本さんと観に行って、「モーツァルトって凄いよね」って話してたら、次の日に詞が上がってきて、それが「ピンクのモーツァルト」だった。それに細野さんがアヴァンギャルドな曲をつけて、それでも1位になっちゃう。だから松田聖子さんの声は何でもポピュラー音楽にしちゃうっていう独特の声でした。
田中:今日対談していただく目黒さん、実はソニーで最初に聖子さんのテープを聴いた方だったとか。ソニーでは最初、郷ひろみさん、山口百恵さん等の宣伝を担当され、その頃から川原さんとは親友に。その後はシャネルズ、DREAMS COME TRUE、JUDY AND MARYなど数多くのアーティストを育成されています。では目黒育郎さんを、お呼びしたいと思います(ディレクターを担当したザ・ストリート・スライダーズの「BLOW THE NIGHT」をBGに登壇)。イベントのサブ・タイトルに<ビクターVSソニーの軌跡>とはありますが、今日はそういう内容にはなりません(笑)。川原さんは最初ビクターに就職、それからソニーへ移り、そしてまたビクター、またソニーへと移られて。
目黒育郎(以下、目黒):音楽仲間っていうか、どこのレコード会社にいようが関係なかったからね。「この業界に入って最初に仕事をした人は仲間」っていうことで、「川原、今どこいるの?」って感じで。

当時は会社が別々でも宣伝・プロモーション担当が放送局や出版社に集まっては自然と行動を共にする──ということも多く、その中での仲間/音楽仲間だった。ここからは川原、目黒の担当した歌手やバンドのプロモーションやレコーディング現場の話など、貴重なエピソードがお二方提供のレアな写真とともに語られた。
目黒:(1973年/山口百恵)2曲目のシングル「青い果実」の時は、週刊誌のグラビア撮影で、青い果実=リンゴをもぎに夜行列車で青森に行きました。僕はまだ新入社員で他の人より年齢も近かったので、百恵さんは一晩中、彼女がどんな気持ちで『スター誕生』のオーディションを受けたか、そしてこれから家族のためにもこの世界で必ず成功しなければ、とい決意を私に話してくれました。その話は今まで少しも苦労したことがなく、のんべんだらりと生きてきた私には衝撃的でした。
川原:(1977年/岩崎宏美)11枚目のシングル「思秋期」は、それまでヒットを飛ばしていた筒美京平さんではなく三木たかしさんの曲。彼女の歌唱力も含め、これは名曲だ! と、ニュー・ミュージック系の専門誌までプロモーションをする手伝いをしました。
目黒:(1979年/大滝裕子)私が担当していた雑誌『セブンティーン』と組んで始めた「第1回ミス・セブンティーン」コンテストで優勝した大滝裕子を、EPIC・ソニーの設立と共にディレクターとなり最初に手掛けました。彼女は現在も「アマゾンズ」として活躍しています。この時の九州大会では松田聖子、東京大会では久保田早紀も出ていました。
川原:(1979年/ピンク・レディー)シングル「波乗りパイレーツ」でバック・コーラスにビーチ・ボーイズを起用しました。当時、アメリカでピンク・レディーがTVショウを持ち、ビーチ・ボーイズもレコード会社を移籍してプロモーションをするタイミングが合致し、マリブにあるメンバーのマイク・ラブ邸でのレコーディングでした。
目黒:(1981年/シャネルズ)シングル「ランナウェイ」がミリオン・セラーになったご褒美でアメリカに行った際、メンバー憧れのハリウッドのクラブ、ウィスキー・ア・ゴーゴーに出演してライブ・アルバムも制作しました。コースターズ、ドリフターズというグループのメンバーも呼んで。表でジャケットを撮影していたら、オープンカーに乗ったマイケル・ジャクソンが通りかかりました。
(1983年/ラッツ&スター)ドゥー・ワップ好きの大瀧詠一さんは、シャネルズがアマチュアの頃から気に入って弟分として可愛がってくれていました。ラッツ&スターに改名した最初のアルバム『SOUL VACATION』は大瀧さんがプロデュース、タイトルは『A LONG VACATION』をもじったもので、レコーディングには山下達郎さんも陣中見舞いに来てくれました。
川原:(1980年/大滝詠一)次々とソニーのディレクターがクビになって、大滝さんの制作に関して動く人がいなかったので、『A LONG VACATION』はレコード会社は違うけれど僕も参加して、毎週大滝さんとプロモーション会議をやってました。<このアルバムはデート・ミュージックに最高だ!>と、もっと若い女の子たちに広めたほうがいいとか、大滝さんに提言しました。
目黒:大滝さんくらいから、日本でもクォリティの高い音楽があって、<これを聴いてることがカッコいい>と思われる時代になったんじゃないですか。川原もそうだけど、僕らの世代は自分が好きなことしかやらない、押し付けられたものはやらない、その代わりなんとか結果は出すよう頑張ろう──というのがあって。数字で結果を出すのと、世の中に衝撃を与える/文化的に尖ったものとして残すことがいいことだというのがあったんです。
(1985年/ザ・ストリート・スライダーズ)だからシャネルズとかバブルガム・ブラザーズが売れている時に一方でスライダーズを見つけて、これほど尖っている奴らはいない、ぜひやろうと制作ディレクターを始めました。今活躍しているロックのアーティストには<スライダーズが大好きでやり始めた>っていう人が多いです。音楽的にはローリング・ストーンズ。演奏は一発録りで、クリックも使わないレコーディングでした。

川原:『A LONG VACATION』もクリックは使ってない(笑)。(1985年/松田聖子)松田聖子の復帰第一作。サン・ミュージックから、松本隆さんにオファーがあったけれど、それまでのプロジェクトでけっこう出し切っていたから、やりたくない──と松本さんは言ってた。でも、困っているんだからなんとか助けてあげようよ──と一緒に参加しました。曲は今までと違う新しい作家でと玉置浩二さんや大沢誉志幸さん、南佳孝さん等が書いて、最後に松本さんから「川原も書きなよ」とご指名があって、発注されたのが<タイトルは「瑠璃色の地球」。バラードで>とだけで。
目黒:川原もレコード会社に所属はしていましたけど、音楽人だから、所属とかは関係ないんですよ。だから相談しやすいし、はっきりした答えが出てくる、利害関係がないから言いたいことをスパッと言える。相談してきちんとレスポンスがある人だから、彼をいろんな人が信頼していて、レコード会社が違っても頼めるスタンスだったんだと思います。
川原:僕は、ソニーのことは全部目黒さんに相談してました(笑)。ソニーの人のわりには経営者的じゃなくて、これは目黒さんの特徴なんだけど、すごく軽く振るまえてたから、ソニー案件は何でも目黒さんに相談して。
田中:その後、『筑紫哲也 NEWS23』のテーマ曲を井上陽水さん、大瀧詠一さんと川原さんで作ることに。
川原:(1989年/井上陽水)大瀧詠一さんからの依頼で陽水さんと一緒に曲を作ることになり、三人で部屋に籠って<ニュースだから明るい日もあれば暗い日もある、長調でも短調でもない曲を作ればいい>と提案して二人をまとめあげたけれど、ようやく来週に──と決まったレコーディングに大瀧さんが来なかった。
田中:あはははは。
目黒:(1988年/DREAMS COMES TRUE)初めいろいろなレコード会社を当たったみたいですが上手く行かず、最後に来たのがEPICソニーでした。持ち込まれた「うれしはずかし朝帰り」等5曲入りのカセットを聴き、これは凄い! と感激し、直ぐに契約することを決めました。
(1996年/JUDY AND MARY)ソニーのSDオーディションで見た途端に契約を決めました。まだ、TAKUYAの参加前です。私はその頃、レコーディングの環境・費用の双方のメリットで海外でのレコーディングに理解を示していましたので、ストリートスライダーズ、ドリカム、ジュディマリもロンドンでレコーディングをしました。
川原:「海外レコーディングって空気や電圧が違うからいい」って言い始めたのはEPICなんですよ。電圧が違うと音が違うって。
目黒:アンプの鳴りが違う。
川原:でも最近分かったんだけど、アメリカのアーティストってアメリカ以外でレコーディングしないでしょ。じゃあイギリスのアーティストがなぜ海外でレコーディングするのかっていうと、イギリスでレコーディングすると1%もの録音税がかかるからなんです。だからヨットの上や、フランスのお城でレコーディングしたりするの。
目黒:それは初めて聞いた(笑)。
ここからはテーマ別の対談。
トーク・セッション①「日本のレコード会社の存在意義の変化」

川原:僕も目黒さんもレコード・マニアだったんです。コレクターじゃなくて、レコードが好き。レコードを作りたくて、レコード会社に入りたかった。
目黒:芸能界に対しては拒否反応──と言うと言い過ぎかもしれないけど、「音楽をやる人と芸能人は違うな」と思ってた。音楽が好きな人同士の話は合うじゃないですか、レコード会社はその最先端を走ってるわけですし。
川原:だから芸能界じゃなくて、音楽業界に入りたかった。
目黒:今はレコード会社もどんどん形が変わってきてるから、勤めているほうの意識の問題。だから我々の先輩がやっていたレコード会社と、我々がやっていた時代とも全然違うから、最近は<レコード会社>という名前をやめてきてて、ソニー・ミュージックエンタテイメントとかになってる。でもその中で昔のレコード会社と同じ方法でやるしかない部分もあって。だから現在<レコード会社>という枠の中に入っている十数社のどこかが変わってくれたら──と思ったんだけど、結局、手を出すところはみんな同じで。だから誰か、発想を転換するカリスマが出てくることが必要じゃないのかな。音楽業界の先端を走る人がね。
川原:ストリーミングとかYouTubeで配信する人たちの中で、ここ最近本当に優秀な人が出てきている、それが楽しみ。90年代とか2000年代の頭とかは昔の僕たちが作ってきた音楽をベースにして、ちょっと過激な表現をしたり─っていうのばかりだったけど、KING GNUの常田大希さんや藤井 風さん、最近は松木美定さんという人が凄く好きで、調べたらソニーで僕が一番最後にいたセクションの作家だった。そういった本当に自由に発想して素晴らしい楽曲を作る若い人が出てきて、従来の音楽業界とかレコード会社の価値観とかを変えたところで新しい音楽を作り出し、新たなファン層を開拓できると思う。そういうカリスマ的なアーティストが必要。
目黒:例えばモータウンやPWLみたいに、ある組織が一つの分野でこれまでとは違う新しいやり方を打ち出して、そこに賛同してくれるアーティストが集まって成功していく──。レコード会社が専門店化してその独自のカラーを出してくれるというのも、できれば楽しみですよね。
トーク・セッション②「これからの邦楽シーンに期待すること」
目黒:今は韓国が凄いじゃないですか、僕は音楽だけじゃなくて文化も全て韓国にやられたなと思ってます。2000年に『シュリ』っていう韓国のスパイ・アクション映画を観たとき、「これ、ハリウッドが作ったんだろう?」というくらいの映画で、たまげました。韓国のスタッフはハリウッドへ勉強しに行き、そこで学んだもので映画を作った。ところが日本の音楽家たちは、どうしてもローカリズムというか日本に止まって音楽をやっている。やっぱりワールドワイドで物事を考えて、世界水準を持たないとビジネスにはならないわけで。これは言い過ぎかもしれないけど、最近の若いミュージシャンは洋楽を聴いてない人が凄く多い。やっぱり洋楽の素晴らしさというのはあって、BTSとかはスタッフも含めてそれを吸収して、自分のものにして、それ以上のものにするパワーを持っている。だからそれに対抗する気概を持ったスタッフとアーティストが出てくることが、音楽でも映画でも大事ですね。
川原:この20年くらい、日本国内だけで、例えば握手会やグッズ・ビジネスで成り立ってるアーティストが続いていて、音楽でビジネスをしていないんですよ。BTSとかとは全然レベルが違う。欧米の人たちのシビアな批評眼も真摯に学ばないとね。シティ・ポップなんて欧米では絶対に流行ってないから。アジアの一部、アメリカ文化の影響力が強い国では、お金もかかって洗練された音のシティ・ポップは喜ばれているけど、欧米で日本の◎◎のコレクターがいるとかいうのは半分冗談ですよ。僕が、デタラメな日本語でずっと歌ってる日本人をトリビュートしたフランスのバンド、YAMASUKI SINGERSっていうのを好きだっていうのと多分一緒だと思う、そういうレベルだと。

続いて質問コーナーに。
Q:我が青春の一枚というアルバムを教えてください。
目黒:やっぱり『サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド』(ザ・ビートルズ)じゃないですか。僕が浪人していたくらいの時期(1967年)、あのアルバムを聴くことで相当励まされました。緻密な凄いアルバムですから、自分の人生の中では一番です。
川原:僕はその一つ前の『リボルバー』(ザ・ビートルズ)。いや、もう何でもアリなんだと思ったから。『サージェント・ペパーズ〜』はその完成形なんだけども、インド音楽がポップスのアルバムに初めて入ったり、テープの逆回転だか何だかわからない曲でジョン・レノンじゃないような声で歌ってたり、でもメロディアスだし、バンドっぽいし。ということで言うと『リボルバー』かな、高校一年の時に聴いたアルバムですけど。最近またリイシューされて新しいミックスが出て、それはそれで素晴らしくてずっと聴いてます。
目黒:すべての音楽はビートルズから派生してるって言っても過言じゃないくらいだし、川原も僕もビートルズの日本公演は観に行ったし、刺激を山ほど受けてます。
Q:ズバリ、音楽制作ディレクターに向いているのはどんな人でしょうか?
目黒:僕たちディレクターの仕事は男性・女性の気持ちが同時に分かる人間じゃないとダメ。だからディレクターになる人間は、言うならばバイセクシャルの気持ちを持っていなければダメだ──と、僕は尊敬していた大先輩のディレクター酒井政利さんの仕事ぶりを見ていて勝手に考えていました。だから異動で僕のセクションに呼んだ新人ディレクターを、新宿のそちら系の巣窟エリアの二丁目公園に連れて行ってベンチに一人で座らせるんです。僕は公園の外からこっそり見てるんですけど、座った人の傍にそちら系の人が来て、最初は距離があいてるんだけど、だんだん近づいてきて、話しかけられたらディレクターとして合格。やっぱりそういう魅力がある人間じゃないとディレクターはできないんじゃないか──という、僕の勝手なやり方でしたけど(笑)。
川原:音楽制作ディレクターは好かれないとね。それにアーティストは「才能があるから世の中から浮いてしまっている、異能の人たち」でしょ、そういう人たちを地表に引き戻す仕事だから、寄り添わないと無理があるんです。ミュータントの相手をしている感じだから、うまくコントロールしないと。
田中:それでは、そろそろお時間となってまいりましたので、最後にお二人に<2023年の抱負>をお願いします。
目黒:川原は現役でバリバリやってるからいいんですけど、僕はボランティアとして、困ってる音楽家にいろいろ提案をして、その中でも自分が助けた人が良い道に進んでくれるようになればいいなぁ、と思っています。アマチュアのアーティストでも、会うと刺激を受けるので、それによって自分も勉強することがありますね。
川原:目黒さんも自分もそうなんですけど、好きなことしかやってこなかったので、アーティストに対して良かれと思っても多少強引なところはあって。だからアフターサービスとかメンテナンスをちゃんやらないと、申し訳ないことになっちゃうな──と、ずっと思ってた。ソニー・ミュージックを退職してもう十数年経ちますけど、アフターサービスとメンテナンスをやってたような気がします。例えばコンピュータのOSでも、Windowsとか分かりやすいのならいいんだけど、僕はLinuxとかの地味なOSで勝手なことをやってた気がするんですよね。で、そのOSじゃないと動かない人たちもまだいてね。だから好きなことをやってきた分、随分無責任なこともやってきたから、それに対するアフターサービスとメンテナンスをちゃんとやって行こうと、この数年やってきたけど、そのアフターサービスもそろそろ仕上げに近づいてる感じかな、2023年は。
田中:ありがとうござました、川原伸司さんと、目黒育郎さんでした。(場内大拍手)
商品情報
ジョージ・マーティンになりたくて
~プロデューサー川原伸司、素顔の仕事録~
川原伸司 著
四六判/248頁/定価1,980円(税込)/発売中
ISBN:978-4-401-65218-1
発行:シンコーミュージック・エンタテイメント
「ビートルズだったらこういう風にやるだろうという生き方を僕も実践しよう」……高校1年生でビートルズの武道館公演を体験、社会人1年目で40万枚のヒットに携わり、様々なメディア関係者と交流しつつ大滝詠一、松本隆、筒美京平のブレーンも務めるかたわら、「少年時代」(井上陽水と共作)「瑠璃色の地球」(松田聖子)などを作曲。プロデューサーとしては中森明菜、森進一らの音源制作にも関わってきた希代のスタッフ、川原伸司の仕事録。