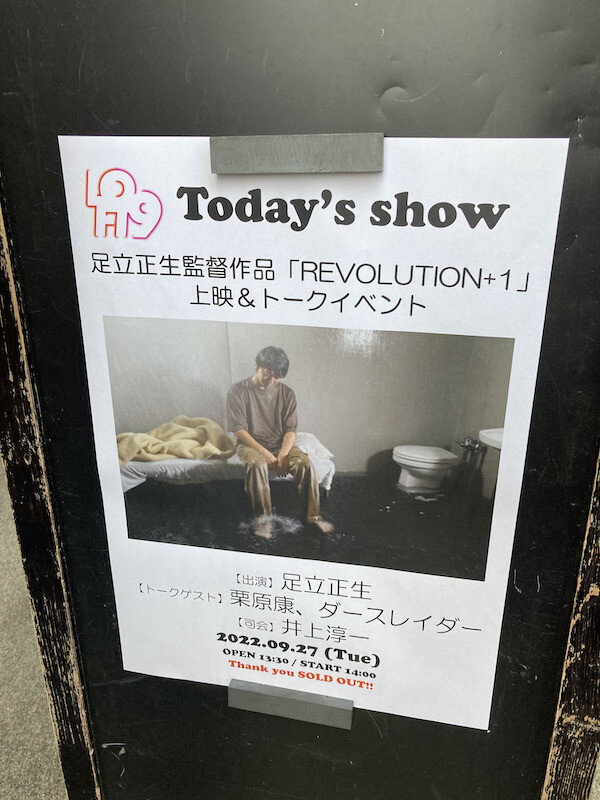どうしても国葬の日に上映したかった
故・安倍晋三元首相の国葬の日(9月27日)、東京都渋谷区円山町のLOFT9 Shibuyaにて足立正生監督の最新作『REVOLUTION+1』が上映された。
安倍晋三元首相暗殺犯の山上徹也容疑者を題材に、7月8日の事件直後から企画され、3日で脚本を書き、8月末に8日間で撮影した映像を「どうしても国葬の日に上映したい」という足立監督の強い希望で編集、緊急上映に至った。
それゆえに今回は制作途中のラッシュ版(約50分)なのだが、作品の真髄や核はしっかり凝縮しており、ジョン・レノンが楽曲制作からわずか10日後に発売に漕ぎ着けた『Instant Karma!』のように、作品の完成度よりも瞬発力と荒々しいスピードで創造することが大事であり、だからこそ足立監督は国民主権に反する国費実施の葬儀に異を唱えるため国葬粉砕の気概で9月27日に本作を上映することに拘泥したのではないか。
チケット発売後に150席が即完売、平日の昼帯にもかかわらず場内は超満員。午後2時を過ぎ、国葬が行なわれている日本武道館近くの沿道にいる足立監督の映像が生中継された後に本編上映。
上映後、本作の企画・脚本を務めた井上淳一が進行となり、キャストを壇上に上げてコメントを求めた。主人公の川上達也を演じたタモト清嵐(そらん)は、「こうした映画を公開することでいろんな人たちからいろんな思いをぶつけられると思いますが、様々な意見を受けはするけど流されない自分でありたいし、芯がぶれない覚悟を持ちたいです。これからまだ追撮もあるのでしっかりやっていきたい」と決意を語った。
その後、足立監督、アナキズムを研究する政治学者の栗原康、LOFTでは『ヒルカラナンデス』でもお馴染みのラッパー・ダースレイダーがゲストとして登壇。
引き続き進行を務める井上淳一が武道館付近にいた足立監督に武道館前の状況はどうだったか訊ねると、「中身がないから空砲を打ち続けるんだ。“空”だから」と皮肉まじりに語り、こう続けた。「武道館に爆弾を投げるような人はいなかったけど、田安門の手前で国葬反対のデモや反対の意志を示す人たちが遮断されたり、私よりちょっと若いお年寄りが国葬反対という小さなプラカードを持って静かに立っていたら、翼賛的な人たちが来て『出ていけ!』と排除していた。そういうのを見ると、日本の政治の底がいかに抜けているかを実感する。異論のある人たちに対して一方的に排除する、隠然と嫌がらせをすることでしか自分たちの心の隙間を埋めることができないのがよく分かった」
ダースレイダーは今回の国葬を“安倍さんのファンクラブの集い”だと揶揄し、実施までの手続きに対して大いに意義があるという。「民主主義という体を取るなら国会で一度も議論されないのはおかしいし、僕も一応主権者なので『やるなんて聞いてないよ』と言うだけの話。民主主義国家であるなら主権者にやるべきかやらないべきかを聞いてから判断しなきゃいけないのに、それを無視してるんだから“ファンクラブの集い”にすぎない。でもその集いに僕らが預けたお金を使っているらしいから、ちょっと待てよと。それに弔問外交なんて言うけどG7の首脳は誰も来ないし、3日間で38会談するなんて細かい話ができるはずがない。オーストラリアの首相は国葬に参加したけど、『カナダのトルドー首相が民主的プロセスを経ていない国葬よりも自国の災害対策を優先したのは正しい。豪首脳訪日は何も得るものがないだろう』とまでオーストラリアの国営放送は報じている。そこまで言われる国葬をどう取り繕うのか? と思いますね。第一、ただのファンの集いになぜ“国”という言葉を使おうとするんだろう?」と疑問を呈す。
これに対し、午前中に友人と共に武道館付近へ出向いたという栗原は「“国を葬る”という意味の国葬ならいいんですけどね」とジャブをかまし、「たとえば全国戦没者追悼式とか国を挙げて追悼する儀式なんてろくなものじゃないし、あれは他国を侵略した加害者を被害者にすり替え、正当化するものだと思います。今日の国葬も一緒ですよ。強者が弱者を支配し、虐げる格差社会を作り出したり酷い政治を安倍政権はさんざんやってきた。国家が追悼することで、安倍晋三が加害者から被害者になるんですよ」
国家や政治の暴挙を許してはいけない
映画の感想を求められた栗原は、「凄く面白かったし、テンションが上がりました。主人公の川上が決起する直前に自室で痙攣するように踊る場面が特に凄かった。人が決起する瞬間って何かが降りてきて、内なる声が聞こえるのかもしれない」と語った。
脚本には「川上の身体からほとばしり出る感情の爆発ダンス」と書かれたこの場面で足立監督は細かい演出をせず、「身体を叩きまくって何かを追い出すような踊りをしたい」というタモト清嵐の演技プランを採用したという。再び登壇したタモトはこう語る。「自分としては虫みたいなものをイメージしたんです。吸血されて身体にまとわりつくように何かが入ってくる。その自分を吸い取るものを削ぎ落としたくて、身体を叩いて追い出すと言うか」
栗原の語る“内なる声”については、安倍元首相が銃撃された奈良市内の現場を9月上旬に視察した井上がこんなエピソードを披露した。「山上の住むアパートが現場から車で7、8分の距離だったんです。前日に岡山市で狙撃しようとしたけど警備が厳しくて諦めた山上が、安倍元首相の遊説が長野から奈良に変更となり、しかも自宅から7、8分の所へやって来ると聞いたときに彼はどう思ったんだろう? と。きっとこれは運命だと、山上の中で“内なる声”が聞こえたと僕は思うんです」
足立監督は本作について、「政治的な発言はあまりしたくないし、本来は作った映画に対して『映画を見てくれ』と言うだけで済ませたいんだけど、どうしてもこの国葬だけは許せなかった。だから未完ではあるけど、ぜひ上映したかった。なぜなら国家や政治の暴挙を放っておいてはいけないから。たとえば安倍元首相の母方の祖父である岸信介元首相の時代から与党が旧統一教会と組んできたことを、国民はすぐに忘れてくれるだろうとタカを括っている。簡単に忘れてしまうわれわれも悪いけど、彼らを許しちゃいかんですよ」と意思表示する重要性を語った。
その話を受け、井上が本作の制作経緯について説明。「昔の若松プロなら、2日で脚本を書いて、1週間後に撮影して、2カ月後には上映してましたよね?」と井上が足立監督に連絡を入れる前に、共同通信社の安藤涼子記者と電話していたことが大きなきっかけだったという。シングルマザー、宗教二世、派遣労働とこの国の貧困を体現してきた山上をある種の犠牲者であると感じ、感情移入した安藤記者は、かつての若松プロならこの事件を題材にしてすぐ映画にしましたよね? と井上に問いかけたそうだ。マスディアではまだ“旧統一教会”と明記されず、“特定の宗教団体”と報道されていた時期。まともな報道ができないのならば「ここは映画の仕事じゃないですか?」と井上に焚き付けたのだという。
本作の上映決定を知らせるニュースが飛び交った直後から“元テロリストが作ったテロリズムを礼讃する映画”という未見の人たちからの批判が相次いでいるが、足立監督は「山上のやったことはテロじゃない。個人の決起をいつからテロと呼ぶようになったのか?」と話す。
その件に関して栗原も同調する。「テロリズムとはもともと国家のやる行為のこと。フランス革命がその始まりで、反逆者を見せしめのためにギロチンで処刑する。テロとはつまり国家が人民を震え上がらせる恐怖による統治です。日本で言えば大逆事件(幸徳事件)もそうだし、関東大震災の後に大杉栄や伊藤野枝といったアナキスト、当時は不逞鮮人と呼ばれた人たちを殺戮することで民衆を縮み上がらせ、権利要求を一切させないようにする。それが本来のテロリズム。テロにはテロで立ち向かおうとする個人や団体もいるけど、それはテロではなく“決起”ですよ。山上がやったことも決起です」
ダースレイダーは先述のすり替えロジックを引き合いに出し、2001年の9.11テロに直面したアメリカ国家が対テロ戦争としてアフガニスタンを侵攻、ブッシュ政権が2003年にイラク戦争を強行したのは加害者によるすり替えだと語り、そのテロのイメージが世界的に広まったことが加害者と被害者の逆転現象を生じさせたと話した。
「星になる」という台詞はどんな意味なのか?
本作への批判、外野の野次に対して足立監督は「全部引き受ける」と話す。「僕自身はテロリストじゃなく単なるシュールレアリストだと思っているけど、こうした映画を作った以上、あらゆる批評、批判はすべて引き受ける。山上は何かを引き受けるために決起したわけじゃなく、個人で決起するほどまでに追い詰められていた。そこに至る過程や彼が考え続けたことを映画の中で提示することで、今の日本が抱える問題が自ずと明らかになると思った。母親が宗教団体にのめり込むことで家庭も生活もぶっ壊された山上が感じたのは、ちょっと抽象的な言い方になるけど『愛とは何なんだろう?』ってことだったと僕は思う。愛とは何なのかと自問自答していけば良かったんだろうけど、仮に自問自答し続けてもどうしようもないんだと彼は感じていたんじゃないだろうか。独房の中で雨が降りしきるのはなぜかと言えば、彼が自分自身と向き合ったり、考えを煮詰めようとしたときにあまりにも多くのもの、重いものを引き摺っていたことを表したかったから。『お前の映画はいつも雨が降ってるな』とよく言われるけど、僕は雨が嫌いですよ(笑)」
 足立監督が脚本を務めた、若松孝二監督の『胎児が密猟する時』(1966年公開)も冒頭から雨が降るシーンだったと若松プロ出身の井上が話し、「水によって浄化されるという意味が込められているんでしょうか?」と訊くと「自分で分かれば映画なんて作らないですよ」と自嘲するように笑う。
足立監督が脚本を務めた、若松孝二監督の『胎児が密猟する時』(1966年公開)も冒頭から雨が降るシーンだったと若松プロ出身の井上が話し、「水によって浄化されるという意味が込められているんでしょうか?」と訊くと「自分で分かれば映画なんて作らないですよ」と自嘲するように笑う。
 続けて、主人公である川上の「星になる」という台詞に言及した。当初は『REVOLUTION+1』ではなく『星に・なる』というタイトルを足立監督が考えていたというだけに、“星”は本作における重要なキーワードと言えるだろう。監督は語る。「そもそも星とは何なのか? という話でね。星というのは全部過去の光であって、今この瞬間にどうするか? と立ち上がるときには最も遠い所にあるものなんだ。その最も遠いものと自分を対比したり、自分が星にならざるを得ないというところにすべてが集約されていると思う。まあ、今どきの若い子たちに『星になる』なんて言う奴はいないと言われたけどね(笑)」
続けて、主人公である川上の「星になる」という台詞に言及した。当初は『REVOLUTION+1』ではなく『星に・なる』というタイトルを足立監督が考えていたというだけに、“星”は本作における重要なキーワードと言えるだろう。監督は語る。「そもそも星とは何なのか? という話でね。星というのは全部過去の光であって、今この瞬間にどうするか? と立ち上がるときには最も遠い所にあるものなんだ。その最も遠いものと自分を対比したり、自分が星にならざるを得ないというところにすべてが集約されていると思う。まあ、今どきの若い子たちに『星になる』なんて言う奴はいないと言われたけどね(笑)」
「星になる」という台詞をアナキストはどう感じたのか? という足立監督の問いに、栗原はこう答えた。「いい台詞だなと思いました。やむを得ず、それしか道がない。そうして必然のように本気で動かなくちゃいけないとき、人はただがむしゃらで自由でいられると思うんです。たとえば幸徳秋水は死ぬ直前にずっとキリスト教批判を繰り返し、宗教も天皇制も要らない、迷信なんて信じるなと言いながら、最期は一言、『自己の良心と宇宙の理を合致させろ』と言ったんです。宗教批判から一気に神秘主義に転じてしまうという」
ダースレイダーは「川上の身体にまとわりついたものを払い落とすには、一番遠くにある星を目指すしかなかったんじゃないか?」と語る。「この映画って、いろんな登場人物がいるようで実は川上の脳内で起こっている話に過ぎないんじゃないかとも思って。つまり川上一人だけの世界。外部にいる誰かと関わっているように見えて、それが兄であろうと父であろうと本当に実在するのだろうか? という見方もできる。そういう完全に孤独な状況に置かれたとき、今の日本には救済措置がない。僕は何度も死にそうになったけど、運が良いことに周囲に他者がいてくれたし、他者と関わることによって川上のように星になるという目標設定をせずに済んだのかなと思います」
こんな時代だからこそみんなで愛について考えるべき
1時間以上に及ぶトークの後、来場者からの質問に応えるパートに。安倍元首相銃撃事件のおよそ1カ月後、港区のアメリカ大使館前で手製の火薬を持っていた大学生の男が逮捕されたという報道があったが、これは山上の起こした事件に触発されたものなのだろうか? そうした若者に何かアドバイスはあるか? という女性の問いに、足立監督はこう答えた。「鬱憤が溜まりに溜まってキレる寸前の人たちが若者に限らずいっぱいいる。そういう人たちに『心してやれよ』とけしかける映画ではない。そうではなく、今の日本の在り方に不満を抱くキレかかった人たちがこれだけ多くいるという事実がまず凄い。今や真綿にくるまれて生かされていることにも気づかない管理システムが日本中に行き届いているわけで、僕らの世代よりも今の若者たちのほうがずっと生きづらいはず。どの局面を見ても極限まで若者が追い詰められているのを僕は勝手に感じている。僕はこの状況がとても悲しいし、山上が実行したことも大きな悲しみとして受け止めています。その意味でも、若者たちと一緒に今の日本が抱える問題を真正面から捉えることをこの映画ではやりたかった」
生前、山口二矢に関心を抱き、東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所事故の後に東電前で焼身自殺する人間を題材にした映画を撮りたいと語っていたという若松孝二監督が本作を見てどう感じると思うか? という男性の問いに、井上は「若松さんには『お前らやっぱりヘタだな』と言われるでしょうね。内容的にも商売としても。『俺なら国葬の日だけじゃなく、次の日以降も通常興行するよ』と言うでしょう」と答えた。それを受け、足立監督は「若松さんほど映画が好きで、なおかつそれを商売として成立させた人は少ないからね。今まで若松さんのホン(脚本)をたくさん書いたけど、若松さんなら最後はやっぱり国葬会場を爆発させないと映画として終われないだろうと思ったわけ。そういうホンを書き続けてきた張本人として、今回の映画でああいう結末にしたのは自分のちょっと成長した側面を出せたんじゃないかな?」と笑った。
「今の時代、暴力はお呼びじゃない、連帯が必要なんだ」と語る足立監督の“連帯”についてあらためて聞きたいという女性には、「隣人あるいは家族への愛が連帯の基本だと僕は思うんです。愛があることで人間はどのように生きられるのか。そんな思春期みたいな話をこの歳になってしていますが、社会も国家も政治家も底抜けの空っぽになった今こそ、みんなで愛について考えるべきじゃないかと思う。そういう映画をこれからも作りたい」と今後の抱負を込めて語った。
完成した作品がどうなるか分からないが、川上が決起した後に彼の妹が自身の考えを話すシーンが終盤にある。あえてカメラ(鑑賞者)に向けて話をするという映画の禁じ手を使ってまで足立監督が語らせようとしたメッセージ──主人公とは違うやり方で自分自身とどう向き合い、現実とどう立ち向かい、どう社会と関わりを持つのか。それらを鑑賞するわれわれ一人ひとりが考え、行動に移していくことが大切なのだと思う。映画を武器として世界と対峙する足立監督が未完成のまま国葬の日に上映をぶつけたように、現実の理不尽や不正、主義主張を各自が絶えず訴える意思表示こそが社会を変える第一歩であり、それが本作のタイトルにもある“+1”(プラスワン)という姿勢であり思想ではないだろうか。(取材・文:椎名宗之)