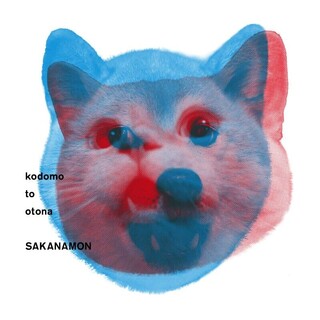2022年2月、ロシアがウクライナ東部マリウポリに侵攻開始。戦火に晒された人々の惨状をAP通信取材班が命がけで撮影を敢行、決死の脱出劇の末に世界へと発信された奇跡の記録映像をもとに制作された映画『マリウポリの20日間』が本日4月26日(金)より公開された。
このたび、映画監督/作家の森達也(『福田村事件』)、アニメーション映画監督の片渕須直(『この世界の片隅に』)、ドキュメンタリー監督の大島新(『なぜ君は総理大臣になれないのか』)、映画監督の原一男(『水俣曼荼羅』)、ジャーナリストの丸山ゴンザレスら著名人総勢11名からコメントが到着。
併せて、本作の監督・脚本・製作・撮影を務めたミスティスラフ・チェルノフ監督から、劇場公開に寄せて届いた、静けさの中に強い怒りを滲ませた、戦場の惨状を告白する<STATEMENT(声明文・5800字超)>が公開された。
* * *
2022年2月、ロシアがウクライナ東部に位置するマリウポリへの侵攻を開始。これを察知したAP通信のウクライナ人記者であるミスティスラフ・チェルノフは、仲間とともに現地に向かった。
ロシア軍の容赦のない攻撃による断水、食料供給や通信の遮断……瞬く間にマリウポリは孤立していく。海外メディアが次々と脱出していく中、彼らはロシア軍に包囲された市内に残り、死にゆく子どもたちや遺体の山、産院への爆撃など、侵攻するロシアによる残虐行為を命がけで記録、世界に発信し続けた。
取材班らも徐々に追い詰められていく中、滅びゆくマリウポリと戦争の惨状を全世界に伝えるため、チェルノフたちは辛い気持ちを抱きながらも市民を後に残し、ウクライナ軍の援護によって市内から脱出することになる。
* * *
映画監督/作家の森達也(『福田村事件』)は「戦争は僕たちが繰り返す日常の延長線上にある。家族とおしゃべりしたり友人たちと酒場に行ったり恋人と映画館に行ったり、その延長に戦争がある。切り離されていない」、映画監督の原一男(『水俣曼荼羅』)は「ウクライナと反対側の地に生きている私たちとは無縁のことなのか? マウリポリの死者たちの黙示録として、この作品を観るべきではないのか?」、アニメーション映画監督の片渕須直(『この世界の片隅に』)は「損ねられたたくさんの人生の可能性。彼らの顔がいつまでも去らない」、ドキュメンタリー監督の大島新(『なぜ君は総理大臣になれないのか』)は「報道は、世界を良き方向に変えられるのか。その葛藤に苦しみながらも、伝えなければならないとカメラを回す取材班の使命感と勇気に、うちのめされ、言葉もない」、ジャーナリストの丸山ゴンザレスは「人間の本性を引きずり出し記録した極限の戦場ドキュメンタリー作品」とそれぞれの想いを寄せた(※コメント全文は下記に掲載)。
また、本作の監督・脚本・製作・撮影を手掛けた、ミスティスラフ・チェルノフから、劇場公開に向けて寄せられた5,800字にも及ぶ<声明文>も公開。自身がなぜ、文字通り“命を懸けて”戦場での取材を敢行したのか? マウリポリでは「戦争が近づいていると確信していた人はごく僅かで、大部分の人たちが、自らの判断の誤りに気付いた時にはもう手遅れだったのです」──日常に突如入り込んできた戦争を理解する間もなく、翻弄され、人生を奪われていく多くの人々の命を前に、懸命に自らの使命を果たそうとしたチェルノフの、静けさの中に強い怒りを滲ませたテキストとなっている。
―STATEMENT(声明文)―
ウクライナのロシア国境からわずか20マイルのハルキウ市で育った私は、10代の時に、学校のカリキュラムの一環として銃の操作法を学びました。当時の私は、ウクライナは友好国に囲まれているのだから、こんなことは無駄なことだと考えていました。
その後、私は、イラクやアフガニスタンの戦争、そして、係争地ナゴルノ・カラバフの取材を行い、現地の惨状を世界に伝えようと努めてきました。しかし、アメリカ、そしてヨーロッパ諸国が大使館職員をキーウ市から退避させ始め、故郷の町から国境を挟んだ真向いで、ロシア軍部隊が増強されていることを知った時、私の心に浮かんだのは「何てことだ、祖国よ」という思いでした。
開戦当初の数日間、ロシアは、私が20代の頃まで過ごしたハルキウの非常に大きな自由広場を爆撃しました。アゾフ海に面しているという理由から、ロシア軍がウクライナ東部の港湾都市マリウポリを戦略上重要な目標と見做すはずだと、私は確信しました。そこで、2月23日の夜、AP通信での長年の同僚でウクライナ人写真家のエフゲニー・マロレトカと共に、マリウポリに向かいました。
我々がマリウポリに到着したのは午前3時30分のことでした。その1時間後に戦争が始まったのです。
最初の数日間で、マリウポリの住民43万人の約4分の1が避難しました。しかし、戦争が近づいていると確信していた人はごく僅かで、大部分の人たちが、自らの判断の誤りに気付いた時にはもう手遅れだったのです。
ロシアは電気や水、食料の供給を徐々に遮断していき、最後に、携帯電話やラジオ、テレビ塔を使用不能にしました。マリウポリ市内にいた他の数人のジャーナリストたちは、完全に封鎖されて通信が途絶する前に脱出しました。
通信を遮断することはとても重要なことで、これにより2つの目的が達成されることになります。
第1の目的は、大混乱を生じさせること。何が起きているのかを知る手段が無くなり、人々は恐慌をきたす。当初、マリウポリが何故これほど早く崩壊したのか、私には理解できませんでしたが、今では、コミュニケーションが不在となったことがその原因だったのだと思います。
第2の目的は、刑事免責です。マリウポリから情報が発信されず、破壊された建造物や瀕死の子供たちの画像が無ければ、ロシア軍は何事も意のままにできてしまう。我々がいなかったとしたら、マリウポリの情報は皆無だったはずです。
それこそが、我々が目にしたものを、危険を冒してまで世界に発信し続けた理由であり、同時に、ロシアが激怒し、我々を追跡しようとした理由なのです。
私は、沈黙を破ることがこれほど重要だと感じたことはありませんでした。
瞬く間にマリウポリ市内は死で一杯になりました。2月27日、我々は、榴散弾に当たった少女を医師が救おうとする様子を目にしました。その少女は後に死亡しました。2人目、3人目も亡くなりました。救急車は、電話が機能せず出動の要請を受けられなくなり、爆撃を受けて破壊された通りを走行することもできなくなったため、負傷者の搬送を停止せざるを得ませんでした。医師たちは、死亡した人々を運び込む家族を撮影するよう我々に懇願し、減り続ける発電機の電力を我々のカメラに使わせてくれました。我々の都市マリウポリで何が起こっているのかを世界では誰も知らないでいるのだと、医師たちは嘆きました。
病院と周囲の家屋が砲撃を受け、我々のバンも窓が割れ、側面に穴が開き、タイヤがパンクしました。時として、我々は炎上する家屋を撮影するために飛び出し、爆発の中を走って戻ることもありました。
当時のマリウポリ市内には、通信ネットワークに安定して接続できる場所がまだ1ヶ所だけ残されていました。そこはバディヴェリニキウ通りにある略奪された食料品店の外で、我々は1日1回その場所へ赴き、階段の下にしゃがんで写真や動画を世界へとアップロードしていました。階段では身を守ることはできそうにありませんでしたが、屋外にいるよりは安全に感じられたのです。
その回線も3月3日には途絶えてしまい、病院の7階の窓から動画を送信しようとしているとき、そこから、マリウポリという堅実な中産階級の都市の最後の断片が砕け散る様子を目にしました。
ポート・シティのスーパーが侵攻を受けていることを聞きつけ、砲撃や機関銃の銃声の中、我々はそこへ向かいました。数十人もの人々が、電化製品や食料、衣類を満載したショッピングカートを押して走っていました。そのスーパーの屋根で砲弾が爆発し、私は店外の地面に投げ出されました。二度目の着弾を警戒し緊張していた私は、カメラが録画状態になっていなかったことで自分をひどく呪いました。私がいた場所のすぐ隣のアパートに砲弾がヒューッという恐ろしい音を立てて命中し、私は、身体を縮めて、交差点の角の陰に隠れました。
10代の若者が、オフィスチェアに電子機器を積んで運んでいました。「友人たちとそこにいたのですが、僕たちから10mの所に着弾しました」と、その少年は私に語り、「友人たちがどうなったのか、分からないんです」と続けました。我々が病院に戻ると、20分もしない内に負傷した人々が到着し始め、その内の数人は、ショッピングカートで運ばれて来ました。
誰しもが、戦争が終わるのはいつなのかを知りたがっていましたが、私は答えを知りませんでした。
ロシア軍の包囲を打ち破ってウクライナ軍がやって来るという噂が毎日のように流れましたが、誰も来ることはありませんでした。
この頃には、病院での死や路上の死体、集団墓地に押し込まれる数十の遺体など、あまりにも多くの死を見ていたので、私は深く考えることもなく、人々の死を撮影していました。
3月9日、空爆が2回あり、産科病院から煙が上るのが見えました。我々が到着した時、救急隊員たちはまだ瓦礫の中から血まみれになった妊婦を引き出そうとしているところでした。
ある日、外出禁止の開始時刻まで残り数分というときに、バッテリー不足によって、画像を送信しようにも接続できる回線が無くなる事態に陥りました。病院への爆撃のニュースをどうやって送信するかについて我々が話し合っていたのを聞いていた1人の警察官が、電源が有ってインターネット接続が可能な場所に我々を連れて行ってくれました。「このニュースは、この戦争の流れを変えるでしょう」と、その警察官は言いました。そのときすでに我々は、非常に多くの死者、そして死んでいった子供たちを撮影していたので、これ以上の死が何かを変え得るという警察官の考えが、私には理解できませんでした。
しかし、私は間違っていたのです。
送信を早く済ませるため、暗闇の中、動画ファイルを3分割し、携帯電話を3台並べて、アップロードを行いましたが、全てを完了するのには時間がかかり、外出禁止の開始時刻をはるかに越えてしまいました。砲撃は続いていましたが、市内で我々を護衛するよう命令された警察官たちは根気よく待ってくれていました。
その後、マリウポリの外の世界との接続は再び切断されてしまいました。外界から隔絶されていた為、我々の報道の信用を失墜させようとするロシアの偽情報キャンペーンが勢いを増していたことを我々は全く知りませんでした。ロンドンのロシア大使館が、AP通信の画像は捏造であり、妊婦は偽物だったとする2つのツイートをポストし、ロシアの国連大使は、安全保障理事会の会合でその画像を印刷したものを掲げ、産科病院への攻撃についての嘘を重ね続けました。
一方、マリウポリでは、戦争についての最新情報を求めて人々が我々の所に押し寄せてきていました。数多くの人々が、マリウポリ外の家族に生きていることを知らせるために自分を撮影して欲しいと私に言ってきました。
その時点で、マリウポリでは、ウクライナのラジオやテレビの電波は停止しており、唯一聴くことが可能なラジオでは、ウクライナ人たちがマリウポリを人質化して建物に銃撃を加え化学兵器を開発しているというロシアのよこしまな嘘が放送されていました。これはプロパガンダとしては非常に効果的で、自らの目で反証を見ているにも関わらず、この嘘を信じ込んでしまった市内の人たちもいたほどでした。
「マリウポリは包囲されている。武器を放棄せよ」
ソ連風のメッセージ放送が絶えず繰り返されていました。3月11日、AP通信のエディターが、産科病院への空爆で生き残った女性たちを探し出して、彼女たちが実在していることを証明できないかと電話をかけてきました。その時私は、あの妊婦の映像は、ロシア政府が反応せざるを得ないほど強力なものだったに違いないと察しました。
空爆された産科病院の女性たちを、最前線の病院で見つけ出しました。その病院には、新生児を抱いた女性も出産中の女性もいました。また、我々が撮影した女性が新生児を失い、その後自らの生命も失ったという事実も、そこで聞きました。
我々は7階に上がり、弱々しいインターネット回線を使って動画を送信しました。その時、病院の敷地沿いに次々と戦車が集まってくるのが見えました。その戦車には、この戦争におけるロシアの標章となっている「Z」の文字が書かれていました。
私はそこで、数十人の医師たちや数百人の患者たち、そして、我々が包囲されていることを知りました。
病院を守っていたウクライナ人兵士たちは姿を消し、病院の外へ危険を冒して様子を見に行った衛生兵は狙撃により死亡しました。これによって、食料や水、撮影機材を積んだ我々のバンには近づくことができなくなってしまったのです。
夜明けに突然、十数人の兵士たちが、「ジャーナリストたちは一体どこにいるんだ?」と、押し入って来ました。兵士たちの腕章はウクライナを示す青でしたが、彼らが偽装したロシア人である可能性を疑ってから、私は、自分がジャーナリストであることを告げるために一歩前に出ると、兵士たちは私に向かって、「貴方たちを外に連れ出すために来ました」と言いました。
手術室の壁は、建物外の砲撃や機関銃の銃声で揺れており、屋内に留まった方が安全なように思われましたが、ウクライナ兵たちは私たちを連れ出すよう命令を受けていました。
私たちは、匿ってくれていた医師たちや砲撃を受けた妊娠中の女性たち、他に行く場所が無く廊下で寝ていた人たちを置き去りにして、通りに飛び出しました。彼ら全てを後に残したことで、私は酷く辛い気持ちになりました。
道路や爆撃を受けたアパートの残骸を通り抜ける9分間、あるいは10分間は、永遠のように感じました。近くに砲弾が落ちると、地面に伏せ、一回の弾着から次までの時間を計測しながら走る我々の身体は緊張し、呼吸は止まったままのようでした。次々に襲ってくる衝撃波に胸を揺さぶられて、私の手は冷たくなっていました。
やっとの思いで通用門に到着すると、装甲車で暗い地下室に運ばれました。その時になって初めて、私たちは、ウクライナ側が兵士の命を危険に晒してまで私たちを病院から連れ出した理由を一人の警察官から告げられたのです。
「もしロシア側が貴方たちを捕えれば、貴方たちは、カメラの前に立たされて、今まで撮影したものは全て嘘だと言わされます。」
「マリウポリでの貴方たちの尽力や取材の全てが無駄になってしまうのです。」
滅びゆくマリウポリを世界に見せて欲しいと以前に私たちに懇願したその警察官は、今度は私たちにマリウポリから脱出するよう要請しました。彼は、マリウポリを去る準備をしている数千台の使い古された自動車の方に私たちを連れて行きました。それが3月15日のことです。生還できるのかどうかは分かりませんでした。我々は車に3人家族と共にすし詰めになったまま、市内から5km続く渋滞に巻き込まれました。約3万人が、その日、マリウポリから脱出をしようとしていたので、車の内部をロシア兵たちがじっくり検分する時間も無いほどの台数だったのです。皆不安を感じていたのでしょう。人々は、口論し、互いに叫び合っていました。その間もずっと軍用機が飛び空爆が行われ、地面は揺れ続けていました。
我々が通過したロシアの検問所は15ヶ所で、検問所にさしかかる度に、自動車の前部座席に座っていた母親は、我々に聞こえるほどの大声で猛烈な調子で祈っていました。
3番目、10番目、15番目の検問所には、武装したロシア兵が配置されており、マリウポリが生き残るかもしれないという私の希望は、検問所を通り過ぎて行くにつれて潰えて行きました。ウクライナ軍はマリウポリに到達するのに非常に広大な地域を突破しなければならないこと、そしてそんなことは不可能であることを、私はそこで理解しました。
15番目の検問所の兵士たちは、我々の車列全体にヘッドライトを消すように命じました。それは、道路沿いに置かれた武器や装備品を見えなくするためでした。ロシアの車両に白い塗料で書かれたZという文字だけは何とか視認できました。
16番目の検問所で停車すると、ウクライナ人の声が聞こえてきました。私は溢れ出すような安堵感に包まれ、前部座席に座っていた母親は泣き崩れました。
我々は脱出したのです。我々はマリウポリを最後に離れたジャーナリストでした。現在、マリウポリにジャーナリストは残っていません。我々が写真や動画を撮った人々の安否を知りたい、というメッセージが今でも殺到しています。彼らは、まるで我々が他人ではないかのように、我々が彼らを助けることが出来るかのように、切実で親密なメッセージを送ってくれます。
我々が脱出した後、ロシア軍が数百人もの人々が避難所にしていた劇場を空爆したときに、生存者について取材し、瓦礫の山の下に何時間も閉じ込められる経験とはどのようなものかを直接尋ねるにはどこへ行けば良いのか、私は正確に指し示す事ができます。私はその劇場のことも、その周囲の破壊された家屋のことも知っています。私は、劇場の瓦礫の下に閉じ込められている人々を知っているのです。
そして日曜日、約400人が避難していたマリウポリの芸術学校をロシアが爆撃したと、ウクライナ当局が発表しました。しかし、そこに行って撮影することは、私にはもうできないのです。<※STATEMENT(声明文) ここまで※>
「おそらく私はこの壇上で、この映画が作られなければ良かった、などと言う最初の監督になるだろう」──アカデミー受賞式の壇上でコメントした、本作の監督であり、ジャーナリストのミスティスラフ・チェルノフ。AP通信社のビデオジャーナリスト、そしてウクライナ職業写真家協会の会長でもある彼は、ウクライナ東部の出身で、2014年にAP通信に入社して以来、欧州やアジア、中東の主要な紛争、社会問題、環境危機を多数取材、長年の同僚であるエフゲニー・マロレトカと、ウクライナの戦争に関連した問題を取材、報道しているワシリーサ・ステパネンコの3人の報道チームで共にマリウポリ包囲戦の取材を行ない、ロシアによるこの都市に対する攻撃の目撃者たちの証言を世界に伝えた。
なお、本報道で、ともに取材を敢行したチームとともに2023年にピューリッツァー賞公益賞を受賞した。チェルノフは現在ドイツに拠点として活動しており、過去には英国王立テレビ協会により、2016 年年間最優秀カメラマン、2015年年間最優秀若手人材にも選出されている。
コメント全文
※五十音順/敬称略
「報道は、世界を良き方向に変えられるのか。その葛藤に苦しみながらも、伝えなければならないとカメラを回す取材班の使命感と勇気に、うちのめされ、言葉もない。
この「作られなければ良かった映画」は、戦場の惨禍を決して忘れてはならないという、世界への痛切なメッセージである。」
──大島新(ドキュメンタリー監督)
「この作品は、マリウポリの街で何が起こったのか、またロシアによるウクライナ侵略の実態を永遠に目の当たりにすることができる貴重な記録である。」
──岡部芳彦(ウクライナ研究会会長/神戸学院大学教授)
「たくさんの顔が去来する。自分たちの街なのだから、と思ううちに逃げ場を失った人々。持ち場を護るしかない医療関係者、公務員たち。生命を奪われた人々。損ねられたたくさんの人生の可能性。彼らの顔がいつまでも去らない。」
──片渕須直(アニメーション映画監督)
「新たな戦争や、相次ぐ大地震などの災害報道に上書きされたが、今もウクライナでは戦争が続いている。ロシアのウクライナ侵攻直後からマリウポリを脱出するまでの、20日間に渡る決死の映像。電話やインターネットを遮断され、世界から隔離されていた内側で拡がる“終わりなき戦争”の姿を世界に伝えるドキュメンタリー。SNSから雪崩れ込むフェイクニュースを聴き流している我々に、あらためてジャーナリズムの真意と戦争の本質を問いかける。」
──小島秀夫(ゲームクリエイター)
「『フルメタル・ジャケット』『プライベート・ライアン』『ダンケルク』……。この映画は、巨匠たちの戦争映画よりも遙かにリアルで、無慈悲なまでに残酷です。何しろ、舞台の殆どが「戦場」ではなく「市街地」なのです。しかし、その光景を世界に伝えなければならないという撮影クルーの使命感には脱帽しかありません。アカデミー賞は妥当、ピュリッツァー賞も妥当。この映画が、多くの観客に届くことを祈ります。」
──駒井尚文(映画.com編集長)
「映画は最初から終わりまで、呻くような苦痛と悲哀に満ちている。それでも「これは観なければいけない」と強く説得力を持たせているのは、そこにチェルノフ監督の当事者としての視点と、自身が苦しみながら撮影している圧倒的な誠実さがあるからだろう。」
──佐々木俊尚(作家・ジャーナリスト)
「ロシアのウクライナ侵攻を記録した映像作品の中でも、この作品ほど、母親と子どもたちが殺されていく場面を多く収めたものは、ないはずだ。切なさのあまりほとんど全編を心が震えて私は泣きながら観ていた。とりわけ瀕死の妊婦が担架で運ばれている場面は、私の脳裏に焼きついて、柊生、忘れることはないだろう。今、この膨大な死者たちの映像は、たまたま生きて彼ら死者たちの映像を見ている観客の私たちに何を伝えたいのか? 理不尽、残酷、無慈悲な死。ならば、ウクライナと反対側の地に生きている私たちとは無縁のことなのか? マウリポリの死者たちの黙示録として、この作品を観るべきではないのか?」
──原一男(映画監督)
「この映画の多くの映像や写真はウクライナ戦争の報道で用いられていた。
我々は本映画のパーツを何度も見ていたはずだが、そこからは、映像がいかに過酷な戦場で撮影され、厳しいオンライン環境の中で細切れにされた状態で本社に送られ、世界に発信されたかは見えてこない。この映画はそのような戦場の現実もすべて我々に教えてくれる。」
──廣瀬陽子(慶應義塾大学 教授)
「怒り、不安、絶望、吐き気、混乱、正義、矛盾、無力……。人間の本性を引きずり出し記録した極限の戦場ドキュメンタリー作品。この作品は握る側の行動で価値が変わっていくバトンである。私たちは、それぞれが賛同する意見や己の行動がどこに向かうのか考え続けるしかないのだ。」
──丸山ゴンザレス(ジャーナリスト)
「メディアで再現される戦場は、戦場の轟音や爆発音、悲鳴や絶叫ばかりが誇張され、僕たちから切り離された異空間となる。 だからこそ本作を見ながら考える。戦争は僕たちが繰り返す日常の延長線上にある。家族とおしゃべりしたり友人たちと酒場に行ったり恋人と映画館に行ったり、その延長に戦争がある。切り離されていない。僕たちは同時代の座標軸にいる。」
──森達也(映画監督/作家)
「意味もわからぬまま、日常生活を粉々に破壊されて悲しむ人々の姿を見るのは、胸が痛む。だがそれでも、我々は事実を直視してその重さを考え、行動しなくてはならない。」
──山崎雅弘(戦史・紛争史研究)
商品情報

映画『マリウポリの20日間』
監督・脚本・製作・撮影:ミスティスラフ・チェルノフ
スチール撮影:エフゲニー・マロレトカ
フィールド・プロデューサー:ワシリーサ・ステパネンコ
プロデューサー、編集:ミッチェル・マイズナー/プロデューサー:ラニー・アロンソン=ラス、ダール・マクラッデン/音楽:ジョーダン・ディクストラ
2023年/ウクライナ、アメリカ/ウクライナ語、英語/97分/カラー/16:9/5.1ch/G
原題:20 Days in Mariupol/字幕翻訳:安本熙生
後援:在日ウクライナ大使館
配給:シンカ
©︎2023 The Associated Press and WGBH Educational Foundation
4月26日(金) TOHOシネマズ日比谷ほか全国緊急公開