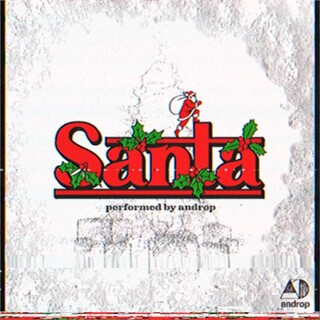平成最後となる6月23日の慰霊の日、沖縄県内では追悼行事や慰霊祭が行われ、沖縄戦で亡くなった犠牲者を追悼した。1945年3月26日から始まった沖縄戦では24万人余りが死亡し、その約半数は民間人だったという。第32軍・牛島満司令官が降伏した6月23日までが「表の戦争」だとしたら、北部ではゲリラ戦やスパイ戦など「裏の戦争」が続いていた。作戦に動員され、山中に潜んで米軍とゲリラ戦を戦った「護郷隊」と呼ばれる少年兵たち。そして、彼らを組織し、訓練したのは日本軍の特務機関「陸軍中野学校」出身のエリート青年将校たちだった。沖縄でもあまり語られることのないこの「秘密戦」で一体何が起こっていたのか?
映画『標的の村』『戦場ぬ止み』『標的の島 風かたか』で基地建設に対して徹底抗戦する人々の姿を描いた三上智恵が気鋭のジャーナリスト大矢英代とタッグを組み、沖縄戦の実態にギリギリまで迫って映画化したのが本作『沖縄スパイ戦史』だ。少年ゲリラ兵、強制移住とマラリア地獄、そして虐殺。次々と明らかになる衝撃の事実とそれらをつなぐ一本の線。沖縄ではいま、辺野古、高江での米軍基地建設に続き、宮古、石垣など西南諸島でも自衛隊のミサイル基地が建設されようとしているが、軍事要塞化する今の沖縄と過去の「秘密戦」がつながった時に見えてくるのは「次の戦争」の姿だ。
映画公開に向けて精力的に取材を受ける三上、大矢両監督にお話を伺った。(TEXT:加藤梅造)
三上:前作から一年も経たないうちにまた映画を作るとは私自身も思っていませんでした。『風かたか』で描きたかったのは、宮古、石垣に自衛隊の基地ができるのは日本がぐっと戦争に近づくということで、辺野古、高江の基地建設以上に日本国民全員にとって差し迫った問題だということ。基地問題といえば辺野古、高江っていう固定概念を打ち砕くくらいの気持ちで前作『風かたか』を世に出したんだけど、宮古、石垣の問題の切実さがほとんど全国に伝わらない。じゃあ、どうしたら次の戦争を止められるのかと考えた時に、もう沖縄戦を描くしかないと。70年以上前の沖縄と同じことが今の沖縄で起きていることに、まだ多くの人が気づいてないとしたら、それを見せるのが一番の特効薬かと思って。
「沖縄戦は過去の悲劇でも何でもない、今とシンクロしている恐怖そのものだ」と三上は言う。それは「毒をもって毒を制する」ことだとも。
三上:残酷な戦争の実態をもって次の愚かな戦争を止める。沖縄戦を経験したにもかかわらずまた同じように沖縄で戦争を始めることになったら、それは沖縄戦で亡くなった人達を二度殺すようなものですから。
今回の映画は三上監督と大矢英代監督の二人三脚で作られた。琉球朝日放送の報道記者として米軍がらみの事件事故、基地問題などの取材を担当していた大矢にとって、今作は初の映画監督作品となる。
大矢:もともと学生時代から八重山諸島の戦争被害をテーマにドキュメンタリーを作っていたので、最近の日本の状況を見るにつけて、これは今やるしかないと。昨年この企画があがった頃、ちょうどアメリカに行く予定もあったので、もしかしたら沖縄の少年兵のことや北部のゲリラ戦のことを知っている元米兵がいるんじゃないかと探してみたら、すぐに見つかったんです。それが映画にも出てくる元海兵隊員のロバート・マーティンさんなんですが、少年兵を写した写真も持っていました。彼の話を基にアメリカ側からの証言も入れたら映画にすごい厚みが出ると思いました。
三上は2017年12月に記した撮影日誌の中で「今、山を見ても、海を見ても72年前の光景がだぶる。私の魂は2017年にいないなと思う」と綴っているが、それほど沖縄戦にはまっていたのだろうか。
三上:去年の自分はまるで1945年に生きていたような感じがしています。もう他のことを何も考えたくなくて、家族にも友達にも会わずに、沖縄戦の体験者に会ってるか、内に籠もって資料を読んでるような毎日でした。沖縄戦についてはある程度知ってるつもりだったんですが、裏の戦争と言われる沖縄北部のゲリラ戦のことやスパイ虐殺のことなどの資料や証言を映画としてどうつなぎ合わせるかにすごく苦労しましたね。でも今回は一人で作ってるんじゃないというのが心強かった。英代もどこかでがんばってるんだろうなと思って(笑)。
少年ゲリラ兵部隊「護郷隊」
映画はまず沖縄本島の北部の山々で繰り広げられたゲリラ戦にクローズアップする。そこで戦っていたのは、まだ十代半ばの少年兵だった。1944年秋、陸軍中野学校で特殊なスパイ教育を受けた青年将校たちが沖縄各地に配置され、地元の少年を中心としたゲリラ部隊「護郷隊」が組織された。そして45年4月1日に米軍が沖縄本島に上陸すると、護郷隊は北部の山の中に潜み、圧倒的な武力を持つ米兵たちを相手に白兵戦に追い立てられたのだ。映画の冒頭に登場するのは、護郷隊の中で生き残ったうちの一人、当時16歳だった瑞慶山良光さん(89 歳)だ。
三上:私が良光さんを知ったのは新聞の小さな記事だったんですが、実は過去にも護郷隊を取り上げたテレビ番組で良光さんが取材されているんです。ただ彼の体験した内容があまりに凄絶過ぎて、裏を取り切れないという理由からか、結局、番組からはカットされてしまった。その話を聞いたら「これは私が撮らなければ!」と俄然思いました(笑)。
勝ち目のない絶望的な戦いは、着実に少年達の心を蝕んでいった。夥しい戦友の遺体を埋葬した良光さんは「ただおもちゃを埋めているようだった」という。戦争の狂気はやがて味方の内部へも向かい、上官に命じられ少年兵同士の処刑も行われた。映画では、生き残った護郷隊の元少年兵達から壮絶な体験が次々と語られ、それを裏付けるような当時の写真や映像(中には無残に戦死した少年兵の肉片になった写真などもある)がカットアップされていく。
三上:ただ単にひどい写真を見せたいわけではなく、なぜ少年兵の多くが戦後もPTSDで苦しんだのか、その理由の一端でも追体験するためには、ああいう残酷な写真も必要なんじゃないかと思って差し込みました。でもあれを見るのはとてもつらいと思います。私も編集しながら目をつむってましたから。沖縄戦を専門に調べている人でもめったに見たことのない写真や映像なんですが、それは元琉球大学の保坂廣志先生が戦争PTSDについての写真集を出そうと思ってアメリカの公文書館からそういった写真をたくさん集めてきたものなんです。
この映画を観る時、観客はある種の覚悟が必要なのかもしれない。映画の中には、テレビのドキュメンタリーなどではまず放送できないような悲惨な場面やエピソードが挿入されているからだ。入隊時16歳だった前原さんは、ある時、変な臭いがすると思って見たら、別の兵士が死んだ兵士の手首を「戦友の遺骨」と言って持ち歩いていたという体験談を語っている。
三上:これも究極の状況だと思いますが、大切な人を埋葬したいと思って指や手首を切る話って時々聞くエピソードなんですね。ましてや少年兵が戦友を供養したいと思い、とっさに手首を切って持って帰るというのはあったんだろうなと。