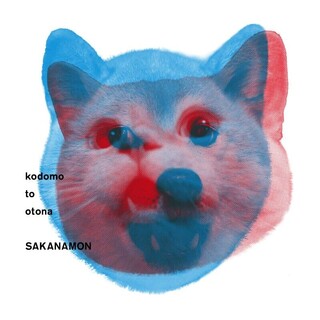お前は人の人生の一部を撮らせていただいてるねんぞ
ー大人たちが集まって「トラウマ」を勉強する会も開かれていますよね。そこで、あるお母さんの涙がとまらなくなって、退席してしまう場面がありました。それまでは子どもたちに感情移入をして観ていたのですが、あの場面で感情が一気に母親側へ動かされました。追いかけて撮影し続けるのはどんなお気持ちだったのでしょうか。
重江:…僕自身もすごく覚悟のいる場面でした。ちょうど撮影1年目の冬でしたね。あの撮影の前に、撮りためた映像を知り合いの監督さんに見てもらったんですけど、「対象との距離感がある」と言われたんです。それは、撮っている対象の人物と、僕のカメラとの現実的な距離ですね。やっぱりああいう場面になると、意識的に離れて撮っていたんです。離れているから音は録れないし、その人がどういう表情をして、どんな感情を込めているのか、というところは撮れないわけです。遠くからズームをするのではなくて、音もちゃんとおさえながら、近くで撮っている「自分」もそこに存在していなきゃだめなんだ、ということに気づかされました。「お前は人の人生の一部を撮らせていただいてるねんぞ。それを世に出そうとしているのに、なんでお前がきっちり撮れへんねん。それはすごく失礼なことやぞ」と言われて、自分の心境が変わりました。
ーその監督さんに見せていなかったら、退席したお母さんについて行かなかったかもしれないですか。
重江:間違いなく行かなかったですね。あの助言がなかったら、ついて行って撮影を続けることはしていなかったと思います。
ー「こどもの里」に娘を預けて、別々に暮らしている母親が涙を流すシーンがありますが、この複雑な涙を見てもなお、最近よく使われる「自己責任」という言葉で片付けるのか?と問われている気持ちになりました。
重江:それは、ねらったというか、意図的でした。シリアスにしようと思えば、なんぼでもシリアスになるテーマなんですよね。でも僕はそれは絶対にしたくなかった。あの子たちのいいところ…元気で明るいっていえばチープになるけど、それに僕は元気をもらってきたから。明るさとともに、その背景にあるものを撮りたかったんです。結局、子どもたちがしんどくなる理由の大半は家庭のことであり、その親御さんのことなんです。だからすごく知りたくなって、親御さんを撮れるんだったら撮りたいと思っていました。でも本当は話している最中に、泣くとは思っていなくて。お母さんと、ちょっとずつちょっとずつ関係を作っていって、やっと自宅でインタビューを撮らせてもらえるようになって、子どもの話をしたんですね、あのときはどうでした、このときはこうでした、と。お母さんのほうからたくさん話しをしてくれて、やっぱり誰かに話したかったんやろなと感じたし、子どもにすごく申し訳ないことをしたと思っているのも伝わってきました。子どものことはすごく大事に思っているんですよ、一緒には暮らせていないけれど。だから、昔のことや、自分のことを責めて流した涙だと思います。
ー子どもたちが野宿者のおっちゃんたちを見回る夜回りのあとに、「ありがとう」って言ってもらえて嬉しかったと言っていましたが、やはり、「してもらうこと」だけではなくて「してあげること」、「自分でも何かができる」ということが自信にもなっていくのでしょうか。
重江:野宿の人はすごく差別されているから、とりあえず実際に会って話そうや、ということから夜回りはスタートしているんです。喋らなわからんでしょ?冬場は寒さで亡くなるひともいるから毛布をわたそう、お腹がすいてるかもしれないからおにぎりと味噌汁を持っていこう、って。子どもたちは「支援」だとか深く考えず、夜にみんなでわーって出かけて、お泊りや! くらいの気持ちだろうけど、実際、心に残っていくものはあるんだろうな。お店で何かを買ったときの「ありがとうございます」とは違うんですよね、あの「ありがとう」は。子どもも大人も、自尊感情を高める言葉でもありますよね「ありがとう」って。
ー野宿者襲撃の事件や、差別の問題がおこるのは「自尊心」と関係があるように思えます。夜回りのように、誰かに言葉をかけることができるのは、自分自身がまわりの職員さんたちに、毎日たくさん言葉をかけてもらっていることにも関係があるのかなと思いました。
重江:そうですね、「こどもの里」は「大丈夫?」とか「どうしたん?』とか、何かあったらすぐに声かけをしてくれますね。
ー家族や学校の中でもそうですが、最近は声をかけあうということが減っているのではという危惧があります。
重江:「こどもの里」とか映画とかから離れたところ、社会の中では、なかなかないですよね。言葉をかけあうことって、やっぱり実際は少ないんですよね。
©ガーラフィルム/ノンデライコ
常に乗りかかった船状態、子どもにも大人にも、何かあったら寄り添っている
ー子どもはもちろん、親が安心して頼れる場所、言葉を発せられる場所が少ないのかな、とも思いました。
重江:映画の中にも出てくる親の学習会は、こどもの里が主催をして、専門家の人を呼んでいるんです。西成区全体にネットワークが繋がっていて、定期的にいろんなテーマで専門家を呼んで話してもらっていて、この町には支援者も当事者も一緒におるっていう。だから参加者は「こどもの里」のお母さんだけじゃないんです。
ー親に対しても子どもに対しても支援してくれる場所がある、というのはすごいことですよね。
重江:そこはね、ほんとうにもう、すごいなと思います。たとえば子どもを叩いた、仮に亡くなった、「はい、虐待!なんてひどい親!」みたいな世論。ほんまにね、そんなことじゃ良くならないですよ。子どもを中心に据えてはいるけれど、大人にも常に乗りかかった船状態というか、何かあれば寄り添い、力になれる関係性。ただそれは「こどもの里」だけでやっているわけではないんですよね。西成区のいろんなところと連携をしているんです。例えば、保育園から「こういうお母さんがいるからこどもの里を利用してもらったらどうか」って連絡がきたり、逆に、はじめて西成に行き着いて右も左も分かれへん、という人がいたら、ここにいい保育園があるからって紹介したりとか。他にもさまざまなケースがあります。
ーどうしてこれほど連携が強くなったのでしょうか。
重江:やっぱ気合い入ってんちゃいます? 情が厚いというか。この町の人は。そう思います。
ー見捨てないぞと?
重江:うん。支援する団体も個人も多いですしね。
ー楽曲提供をされているSHINGO★西成さんから、映画の感想は届きましたか。
重江:「2回連続で観たわ!」ってすぐに連絡をくれました。感想の第一声が「里のやつらすげえなあ!!!こどもの里すげえ!」って言ってくれて、すごく嬉しかったですね。SHINGOさんは、クリスマスとか夏祭りとか、ふしめふしめで歌いに来てくれていて、まったく無名なころからもラジカセを持って来てくれているんですよ。この町の子にとってはヒーローですからね。
ーメインの人物の決め手はなんだったんでしょう。
重江:高校生の女の子に関しては、不思議だったんです、最初。1年目は、彼女のお母さんと僕は接点がなかったので、月1回彼女が実家に帰ったときに「家でなにしてんの?ご飯とかどうしてんの?」って聞くと、お母さんが大好きだということをいい顔で話してくれるんですよ。でもそれって、お母さんとの関係性が分からない僕からしたら、なんで一緒に暮らせていないお母さんのことを大好きなんやろ?っていう疑問があって、それが知りたかったんです。中学生の男の子は、映画に笑いをもたらしてくれるな、って(笑)。カメラ好きやし。でもね、ふと、家族のはなしをするときとか、真面目なはなしをするときは、カッコつけちゃうんだけど、根はすごく真面目で。それがすごく面白くて。彼の心の揺れ方と明るさは魅力的でした。「こどもの里」自体が、遊び場に通いにくる子、住んでいる子、お母さんが「今日ちょっと泊めて」と泊りに来る子、その3つの柱だなと思っていて、その柱のことと、子どもたちのことを考えて撮影をしました。
ーでは最後に、これからこの映画を見る、生きづらい子どもたち、そして大人たちに声をかけるとしたらどんな言葉でしょうか。
重江:おもしろいから! とりあえず観てみて!って(笑)。さまざまな要素が盛り込まれているこの映画は、観た人に何か引っかかりや、社会全体で考える要素、を作る映画だと思うので、その引っかかりについてさまざまに考えていただければと思います。タイトルの「さとにきたらええやん」って言える場所が世の中にいっぱいあったらいいなと思いつつ、でもこういう場所が必要になっているという危機感もありますが…自分にとっての居場所は、探せばたぶんあるんだろうなっていう希望です。それは施設に限らず、何かしら居場所があるんじゃないかなって、それを見つけられるかもしれない、という希望を持ってもらいたいです。