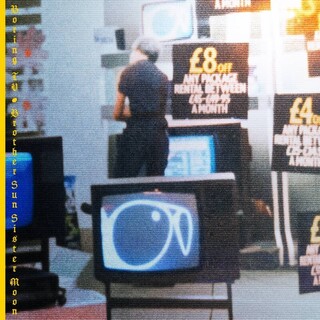先日、沖縄戦から70年目の慰霊の日を迎えた。慰霊の日の追悼式は毎年ニュースで報道されるが、この日がどんな日なのかを詳しく知る人は(沖縄県民を除くと)残念ながら日本人でも意外なほど少ない。
1945年4月1日、アメリカ軍は沖縄本島に上陸した。それから12週間に及ぶ沖縄地上戦では「鉄の暴風」とも言われたアメリカ軍の激しい砲撃により20万人以上が犠牲となり、そのうち住民の死者は9万4千人、実に沖縄に住む4人に1人が命を落とした。
戦後、アメリカの占領下となった沖縄では、住民は収容所に送られ、銃剣とブルドーザーで強制的に土地が奪われた。そして度重なる凌辱事件。米兵によるレイプの被害者は6歳の少女にまで及んだ。日本にさえ復帰できればという住民の一縷の望みは、1972年の復帰後も基地がそのまま残ったことにより失望へと変わった。沖縄の悲劇は終わらなかったのだ。
『老人と海』で与那国島の美しい自然と風土を捉え、『映画日本国憲法』で平和憲法の意義を訴えたアメリカ人映画監督ジャン・ユンカーマンは、大学を卒業した1975年に沖縄を訪れ、コザで反戦兵士の支援活動に携わって以来「アメリカをはじめ世界中の人々に沖縄の実態を伝えることが、自分の人生の仕事の一つ」と考えるようになったと言う。そのユンカーマン監督が、沖縄戦当時の米兵、日本兵、そして沖縄の住民に取材を重ね、3年以上かかって制作したのが本作『沖縄 うりずんの雨』だ。
占領期から今日に至るまで日米双方から基地負担を押しつけられてきた沖縄の「差別」と「抑圧」の歴史の中で、深い失望と激しい怒りを抱えながらも、平和を求めて不屈の闘いを続けている沖縄の人達の尊厳を描いた渾身のドキュメンタリー作品。なぜこの映画を撮るに至ったのかをユンカーマン監督に訊いてみた。(INTERVIEW:加藤梅造)
(C)2015 SIGLO
長いスパンで歴史を捉え、
問題の根っこがどこにあるかを描く必要があった
──本作は沖縄の過去・現在・未来を捉えたドキュメンタリーとして作られていますが、監督の中ではそれだけのスケールの作品にする必要があったということですか?
ジャン:沖縄の基地反対の運動が1995年の少女暴行事件から始まったのではなく、もっと前からずっと続いている運動だということを伝えるために、長いスパンで歴史を捉え、問題の根っこがどこにあるかを描く必要がありました。中でも1955年の「由美子ちゃん事件」は1つの大きな事件でした。6歳の子供がレイプされて殺されたということはものすごく象徴的な悲劇で、それに対して沖縄の「島ぐるみ闘争」と呼ばれる反基地運動がピークになったんですね。
──1つの主権国家の中に他国の軍事基地があれ程たくさんあるという状態がずっと続いているのは、普通に考えても異常ですよね。
ジャン:その理由の1つは、沖縄戦を戦った元日本軍の近藤一さんが証言している通り差別の問題ですね。沖縄戦が始まる時に本土から10万人の日本兵が沖縄に配置されたんですが、その時から日本人は沖縄の人を見下していた。「我々は大和民族で沖縄の人とは違うんだ」と。そういう意識がなければ、あんなに悲惨な沖縄戦はなかったと思います。沖縄住民の4人に1人が亡くなっているんですが、これはすごい数です。偶然巻き込まれたという数ではない。それだけの数の住民が犠牲になってもいいという、はっきりとした日本政府の判断があった。文字通り「捨て石」です。こうした差別意識は今でも続いていて、日本国内の米軍基地の75%が沖縄に集中していること、その上さらに辺野古に新しい基地を作ろうとしていることに表れています。
──本映画は、元日本兵と元米兵の両方の証言があるのが特徴ですね。当人にとってはあまりしゃべりたくないことなんでしょうけど、元陸軍軍曹のレナード・ラザリック氏が「(ある日)我々は年寄りの男と女と、赤ん坊を抱いた若い女性を殺した」と証言しています。
ジャン:特にアメリカ軍の中には、沖縄戦は米軍の勝利の戦いで、その時の軍人は英雄だったと言う人が今でもたくさんいるんですが、実際そこに参加していた兵士は自分が英雄だとは思っていない。彼等は沖縄戦がまさかあんなことになるとは思ってもいなかったし思い出したくもない記憶でしょう。勇敢に戦ったという輝かしいものではなく、まさに恐怖との戦いだった。そのトラウマを今だに抱えているのは、普通の人間なら当たり前だと思います。
──占領時代の証言も生々しく、元陸軍のブルース・リバー氏が「レイプはいつも起こっていて、大したことだと思われてなかった」と言っているのがショックでした。
ジャン:しかも彼は憲兵(軍警察、いわゆるMP)だったから、それを間近に見てきたんですね。米兵によるレイプ殺人事件があっても、仲間のMPはほとんど捜査をしないし、犯人を逮捕することもなかったと証言しています。
──沖縄占領時代はアメリカが朝鮮戦争、ベトナム戦争と次々と戦争を起こしている時期でもありましたが、特にベトナム戦争の末期は、兵士の間に厭戦気分が広がっていたと聞きます。
ジャン:アメリカはずっと戦争をしていますが、第二次大戦以降は1回も勝っていない。特にベトナム戦争は悲惨な戦争でした。兵士の被害者はすごい数です。それなのにまたアフガ二スタンやイラクで戦争をするというのは、国家としてはまだ戦争がいいことだと思っているんでしょう。国家がそういう考えだと若い兵士もそのつもりで戦いに参加する。問題はその後で、帰還してからあれは無意味な戦争だったとわかる。今、アフガ二スタンやイラクで戦っていた人を中心に米国の帰還兵がおよそ1時間に1人自殺してます(※註1)。戦闘で死んだ人の数を上回っているんです。
(※註1)2012年の推定による。
レイプ犯はモンスターではなく、ごく普通の兵士だった。
だから問題はより深刻
──『うりずんの雨』は、第1部「沖縄戦」、第2部「占領」、第3部「凌辱」、第4部「明日へ」と章立てされていますが、「凌辱」を1つの大きなテーマとした理由はなんでしょう?
ジャン:米軍が沖縄に来てからずっと性犯罪がなくならないというのもありますが、凌辱というのが性暴力に限らず、戦争という大きな暴力の問題だからです。この章で読谷村のチビチリガマで起こった集団自殺のことを取り上げたのは、戦争がそもそも命を粗末に扱うということが根本にあるから。レイプは最も象徴的なことですが、武装した特権的な軍人は、力を持っていない住民に対して必ず差別的な意識を持つし、自分達が偉く、従うべき存在だと考えるのは、権力の持つ構造的な問題だと思うんです。
──本作で驚いたのは、1995年の少女暴行事件の加害者の一人、ロドリコ・ハープがカメラの前で証言している場面です。そして彼が平凡な人間で、軽い気持ちで犯罪に加担したということに逆に暗澹とさせられました。
ジャン:そうです。ごく普通の兵士だった彼が、気楽な気持ちでレイプに加わってしまった。僕はレイプ犯はモンスターだというイメージがあったんですが、彼はそうではない。だからこそ問題は深刻です。誰でもそうなってしまう可能性がある。ハープみたいな人はアメリカ本土にいればレイプはしないでしょう。そこが沖縄だから事件を犯したんです。沖縄で起こるレイプ事件の多くは複数犯です。誰かがやろうと言って、それにNOを言えなくなる。軍隊の中にはマッチョイズムというプレッシャーがあるし、そもそも戦争がそういうものですから。イラク戦争の時もそうでしたが、戦争を始める時の高揚した雰囲気の中では、戦争をやめようとは誰も言えなくなる。今になってあれは間違いだったと言う人もいますが、その責任は誰も取っていない。それどころか一部の政治家や軍人はあの戦争はイラクにとってよかったことだとまだ言ってますから。今のイラクの現実を全くみようとしていません。
沖縄を戦利品としての運命から解放する責任をどう負っていくのか?
──印象に残ったのは、映画の冒頭に基地のフェンスにリボンを結んだりテープを張って抗議する市民団体の映像があり、最後の方で、そのテープを剥がして掃除する別の市民団体が出て来る所でした。
ジャン:あれは象徴的なシーンですよね。フェンスにテープを貼っているのは、宜野湾市の主婦のグループなんですが、それまでは基地のフェンスを触ることすらタブーだったんです。だから彼女達がフェンスに飾りを付けてグラッフィックアートのように変えるというのが、すごくおもしろい発想だと思いました。もちろん米軍にとっては、日本人がフェンスに触ることがとても気にいらない。彼等の権威を否定していることでもあり、基地の存在を拒否しているように感じるんだと思います。その一方でフェンスを掃除している日本人グループも登場するのは、基地に賛成している日本人もいることを映画の中で取り上げたかった。それも1つの事実ですから。
──元米兵の人が「人間は戦争をするものだから、戦争はなくならない」と言っていますが、今でもそういう意見は根強いんでしょうか?
ジャン:あれは彼の意見というよりは一般的にそういう意見があるということなんですが、やはりアメリカ軍の中では根強い意見なんでしょう。日本も名前こそ自衛隊ですが、24万人の隊員がいる、世界の中でも非常に強い軍隊なんです。それは根本的に人間は戦争をするものだという考えに基づいている。しかし、私はそれは古い考え方だと思います。実際、EUがまさにそうですが、19世紀・20世紀にヨーロッパ中で絶えず戦争をしてきた国々が、どうやったら戦争をしないようにできるかを考えてやっている。そうした流れに逆行するように、今、日本が戦争をできる国になろうとしているのはやはりアメリカの影響が強いと思います。アメリカがそういう指導をしなければ日本は戦争への道を選ばないのではないでしょうか。今からでも日本はもっと誇りと勇気を持って自分達の道を選んで欲しいと思います。
──そうした日本政府の方針にはっきりとNOを突きつけているのが今の沖縄の市民であり、辺野古の基地反対の運動や翁長知事の行動ですね。
ジャン:不思議な現象だと思います。基地反対がオール沖縄の運動になり、本土にもようやくその声が届くようになってきている反面、政府はますます強硬な姿勢になって、強引に辺野古の基地建設を進めようとしている。
──沖縄の人々ははっきりと意思表示をしています。いま考えなければいけないのは、日本の市民とアメリカの市民がどうするかですね。
ジャン:いまだにアメリカが沖縄を「戦利品」として扱っているのは、アメリカ市民の問題だけでなく、日本の市民がそれを許してしまっているからでもあります。沖縄を戦利品としての運命から解放する責任をどう負っていくのか? 問われているのは私達なのです。