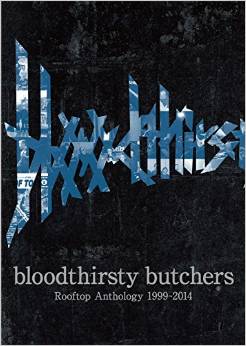逆境を撥ね除けた分だけ物語の激しさが増していった
──その思いを託す設定としてホームレスの若者が選ばれたわけですね。
石井:
──映画の冒頭はブッチャーズの楽曲が爆音で鳴り響く中で染谷さんと渋川さんが全力疾走するシーンで、いきなり息を呑む展開ですね。監督の代表作のひとつである『シャッフル』(1981年)を彷彿とさせる部分もあって。
石井:
──公開直後なのであまり多くを語れませんが、まさかの結末もあり、全体の構成自体がまさにパラレルな世界ですよね。
石井:
──その当時から色を落としたシーンを部分的に取り入れるアイディアがあったんですか。
石井:
──前2作の経験と集積の成果があって、ようやく現在進行形のデジタル映画の撮り方、見せ方の最前線が見えてきたと監督は仰っていましたよね。
石井:
──キャストの真に迫る演技とブッチャーズのヒリヒリする爆音も相まって、画はデジタル特有のつるっとした質感が少ないような気がします。
石井:
映画が完成したことで吉村君には永遠に生きて欲しい
──ブッチャーズの音楽の特性を引き出す難しさもあったんじゃないかと思うのですが。
石井:
──『ソレダケ / that's it』というタイトルにも関わらず、「ソレダケ」が劇中で一切使われていないのが「分かってたまるか!」な吉村さんイズムに溢れていていいなと思ったんですよね。
石井:
──本来なら楽曲を映画用にミックスさせてもらうのが手法としてはラクだし、そうすればもっとブッチャーズの曲を流せたのかもしれないけど、それはかなわなかった。そんな制約の中で試行錯誤の末に完成に漕ぎ着けたわけですから、真の意味で誠心誠意のコラボレーションと言えますよね 。
石井:
──吉村さんがこの『ソレダケ / that's it』を見たら、どんな感想を抱くと思いますか。
石井:
VIDEO