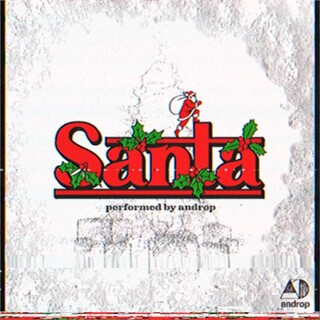自分たちが新しいと思えることをやりたい
──改めて伺いたいのですが、『Turns Red EP』以降、シンセサイザーやサンプラーを大胆に採り入れるようになったのは何がきっかけだったんですか。
武田:2年前に出した『Phantasia』というアルバムは4人だけの音を詰め込んで完成させたんですけど、出来上がったものを聴いて思ったのは、ポスト・ロックの範疇からどうしても抜け出せないサウンドでありバンドだなと。もともとバンドを始めたモチベーションは、誰もやってないことをやるというものだったんです。自分たちの中で新しいと思えることをやりたい。それが根本だったと言うか。
──『Phantasia』は大変な力作だったと思いますが、それまでの音楽性に刺激を感じなくなったということですか。
武田:新しくないなと自分たち自身が感じた時点でまた新しいことをやりたいと思ったんです。じゃあ、新しいことって何だ? と。『Phantasia』でやれるだけ音を詰め込んだから、これ以上音を詰め込むことはできない。それならここで一度音楽性をブッ壊して、新たに楽器を入れてみようと。それでシンセを入れてみたら上手いことハマったんですね。それが『Turns Red EP』という作品だったんです。ただ、『Turns Red EP』の時のシンセはまだ手探りの状態で、衝動の趣くがままに音を入れていたんですよね。それ以降、シンセの特性を活かした曲の構成も徐々に掴めてきたし、その過程で生まれてきたのが今回の『Illuminate』の収録曲なんです。音を詰め込むと言うよりはタイトにしていった感じで、初期のLITEに近くなったんですよ。シンセという手法を採り入れつつ、音数は少ないけどタイトな初期の頃に戻ってきているのが今のバンドの流れなんですよね。
──シンセを使えば同じフレーズでも音色が変わるし、劇的な変化ですよね。
武田:『Turns Red EP』に収録した『The Sun Sank』は、最初にシンセを使わずにバンドの演奏だけで成立していたんですよ。でも、今ひとつしっくり来なくて、試しにギターのメイン・フレーズを構造がシンセで弾いてみたら、全く別の曲に生まれ変わったんですよね。曲の雰囲気がガラッと変わって、これだな! と思って。
──僕も『The Sun Sank』での豹変ぶりには度肝を抜かれましたけど、それまでの音源しか聴いていなかったエンジニアのJ・ロビンスも相当びっくりしたんじゃないですか?
井澤:そうですね。ただ、レコーディングに入った初日にJと呑む機会があって、いろいろと話し込んだんですよ。「僕らは新しいことをやっていきたいんです」と話したら、「その気持ちはよく判るし、変わっていくのはいいことだよ」と言ってくれたんです。そういう話し合いができていたので、作業自体はスムーズだったんですよ。
──『Illuminate』でのシンセの使い方はまさに適材適所で、どの楽曲も端正に引き締まっているのが『Turns Red EP』との大きな違いですよね。
武田:そう言ってもらえると嬉しいです。まさにそんなふうにしていきたかったので。『Turns Red EP』のシンセはまだ使い始めでしたからね。それが逆に良かった面もあったんですけど、ずっとその状態ではいられないし、次回作も含めて本物な感じにしていきたいんですよ。もっとこだわれるところもあるだろうし。
──『100 Million Rainbows』も全面的にシンセがフィーチャーされていますが、『The Sun Sank』ほど大味じゃないし、シンセに使われるのではなく使いこなしている感じが出ていますね。
楠本:『100 Million Rainbows』は今回の5曲の中で一番最初に出来た曲なので、前作からの流れが色濃く出ているかもしれませんね。
──シンセに限らず、『On The Mountain Path』ではパーカッションを強調していたり、『Andromeda』ではコーラスを音響処理していたり、いろんなトライアルが随所に見受けられるのが本作の大きな特徴なのかなと。
武田:そうですね。シンセもそうですが、サンプラーが果たした役割も大きいんですよ。歌でも何でもサンプラーに詰め込めるし、そのことで可能性がだいぶ広がったんです。
"今"と"これから"を常に意識している
──雨の滴がリズムを刻んで連なっていく『Drops』から『Image Game』への流れもいいですよね。僅か5曲の収録曲ながら、とてつもない情報量が詰め込まれているように思います。
武田:曲作りにはかなり時間が掛かったし、構成は緻密に作り込みましたからね。『Phantasia』を作って自分の中で一区切りが付いて、それ以降はどれも同じような曲ばかりが出来ていたんです。それを解消してくれたのがシンセでありサンプラーで、新鮮味のあるフレーズがすぐに浮かぶようになったんですよ。
──ただ、ライヴではシンセを弾く楠本さんの負担が増えたことになりますよね?(笑)
楠本:サンプラーはボタンを押すだけですけど、キーボードは大変ですね。でも、負担は特に感じてませんよ。むしろ楽しいくらいです。
武田:シンセを採り入れたことで、ライヴでも音の可能性が広がった手応えはありますね。シンセはもう1台入れてやっていきたいと考えているところです。
楠本:ギターでは出せない雰囲気を出せるのがキーボードなんですよね。そこはやっぱり大きな特性だと思います。
武田:個人的には、今はギターを必要以上にこだわって弾かなくてもいいかなと思って。シンセ2台でもいいし、他の楽器をやってみてもいいし。そういう意味では凄く柔軟になれた気がしますね。ロジックっていうレコーディングのソフトがあって、それを使うとスタジオで試みたアイディアをそのまま家に持ち帰って曲を練り直すことができるんですよ。その延長で遊びみたいに作ったのが『Drops』なんです。
井澤:曲にもうちょっとスパイスが欲しい時にロジックって便利なんですよね。スタジオ内で録った音をロジックで持ち帰って、次にスタジオに入る時までに歌や他の音を乗せることもできるし。そういうのが合理的な曲作りに繋がっているんです。
──バンドという形態を取りながらも、各人がマッド・サイエンティストにもなれるという(笑)。
武田:そういう部分はもっと強化させたいし、ソフトの知識を今以上に増やしたいんですよね。
──マラカスに赤と青の信号をあしらった本作のジャケットですが、前作で"Turns Red"になったかと思いきや、早くも"Turns Blue"に変化しているというバンドの目まぐるしい進化のスピードを象徴しているかのようですね。
楠本:"Turns Red"は"紅葉"という意味で、これからバンドが面白く変わっていくぞという思いを込めたんですよ。『Illuminate』のジャケットとは直接関連性はないんです(笑)。
──ジャケットのマラカスはSOMA STUDIOにあったものだそうですね。
井澤:そうなんです。マラカスをiPhoneで撮って、それをイラストっぽく加工したんですよ。
──東名阪のリリース・ツアーでは、LITEの今までのサウンド(赤信号)と新たに進んだサウンド(青信号)のイメージをコンセプトにした2公演を行なうそうですね。"赤"は今のLITEのライヴとして下北沢SHELTER(9月15日)で、"青"はこれからのLITEをモチーフにした実験的なライヴ・イヴェントとして六本木SUPER DELUXE(10月17日)でそれぞれ開催するとのことで。
武田:今回のライヴに限らず、"今"と"これから"をいつも意識しているんですよ。常に新しいことをやっていきたいし、一度出した作品はもう過去のものになるし、すぐ次の作品に取り掛かりたくなるんです。
──『Illuminate』というタイトルには"明かりを灯す"と"人を啓蒙する"というダブル・ミーニングが込められているそうですね。従来とは異なる新たなサウンドの明かりを灯しつつ、人々を導いていくという。
武田:"LITE"(ライト)だから"Illuminate"(明かり)だろうとは全然考えてなくて、タイトルを決めた後に"ああ、やっちゃったかな..."と思ったんですよ(笑)。ただ、このタイトルに込めたいろんな意味にも気づいて欲しいなと思って。『Turns Red EP』以降、チャンレンジを重ねてきたバンドの足取りも含めて見て欲しいし、海外で育んだ交流を日本へフィードバックさせたり、客観的に見てもかなり面白いことをやっている自負があるんです。今回のアルバムだけではなく、バンドの果敢なトライアルをトータルで気づいて欲しいという願いを込めたんですよ。
次の作品を含めた3作で流れが完結する
──EPとミニ・アルバムというミニマムな形態が続いたので、そろそろフル・アルバムが聴いてみたいですね。
武田:次回はアルバムを出すつもりです。『Turns Red EP』で挑んだ試みが今回の『Illuminate』でフォーカスが絞れてきたし、今やるべきことがはっきりしてきたんですよ。スタジオで音を合わせてもアイディアが自然に生まれるようにもなったし、今はバンドとして凄く健康的な状態なんです。2枚の流れを汲んだ3作目としての位置付けで、2枚以上のクオリティの作品を作りたいですね。
──次作もアメリカでレコーディングしたいですか。
武田:2枚とも凄くいい感じで録れましたからね。ただ、どうしてもアメリカじゃなきゃダメだというほどでもないです。ジョン・マッケンタイア然り、J・ロビンス然り、録ってもらう人間が重要なんですよ。
楠本:ただ、アメリカでしか出ない空気感は絶対にありますよね。
井澤:いつも使ってる自分たちの機材とも違うし、普段から慣れた音じゃない状態で録ることになるので、その時にしか出ない音が確実にあるんですよ。達成感も毎回ありますし。
──LITEの場合、どれだけ音響的要素を加味しようとパンクの含有成分がちゃんとあるのがいいと僕は思うんですよね。決して技巧だけに走らず、肉感的なリズムとビートが基軸としてあるという。
武田:そういう部分はなくさずにいたいですね。ただ、以前のように衝動だけになりすぎないようにはしたいです。アート的な爆発と言うか、アート的に尖った作品を今は作りたいと思っているところです。
──ヨーロッパ・ツアーやアメリカの西海岸ツアーのライヴ音源を配信限定でリリースしている皆さんですが、CDパッケージの必要性を今も感じていますか。
井澤:僕はちゃんと形に残ったほうがいいですね。古い考え方かもしれませんが、配信だけでアルバムを出すのはどうもパッとしないんですよ。配信は配信でアリなんですけどね。
楠本:時代が時代ならカセット・テープでも出していただろうし、時代に即した形態を取るってことじゃないですかね。
井澤:敢えてレコードで出すのも面白いですよね。海外ではまだアナログの需要が高いし、スリーヴにあるURLからMP3をダウンロードできるようなレコードを作ってみたいです。
──活動基盤を海外に置いて、本格的に世界に打って出てやろうという気持ちはありませんか。
武田:海外での活動はもちろんやっていきたいです。国の大小に関係なく、ライヴをやることでお客さんと繋がっていけば僕らの音楽は確実に浸透していくと思ってるんですよ。
楠本:個人的には日本と海外を分け隔てて考えてないんですよ。日本も世界の中のひとつですから。
井澤:海外を拠点にするよりも、日本を大事にしながら海外でも日本と同じペースでLITEの音楽を広めていきたいですね。日本にいても海外のバンドとの繋がりでツアーも組めるし、今はかなり理想的な活動ペースだと思うので。
武田:ここ数年、日本のバンドに対する海外の評価が高くなっているのを感じますしね。toeとかmouse on the keysとか。
──今後、LITEはどんな"Illuminate"を発色していくんでしょう? 色の三原色としては黄色が残っていますけど(笑)。
武田:『Illuminate』のジャケットにある赤と青を掛け合わせた感じになるんじゃないですかね。それだと紫か(笑)。でも、まさにそうかもしれない。『Turns Red EP』と『Illuminate』があっての作品になるはずなので。その3枚でひとつの流れが完結するようにしたいですね。