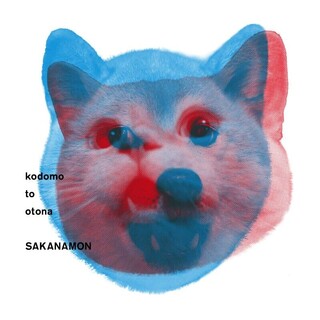昨年のRO69 JACKの投票枠にて、ROCK IN JAPAN FES.2009の出演とCDリリースを勝ち取ったthe crickets。5月12日にリリースされた作品のタイトルは『Fortune O'clock High』。"Twelve O'Clock High"(頭上の敵機)という軍事用語にちなんで名付けられたというタイトルは、幸せはすぐそこにあるという意味を表す造語。また、「まだ何色にも染まっていない」という意味を持つ、月をモチーフにしたthe cricketsのロゴが白黒の風景を照らし出すCDジャケットは、メンバーによって生み出されたもの。DIY精神を掲げ、自らの音楽でリスナーに夢や希望を届けたいという彼らに、ROCK IN JAPAN.2009に出演した際の思い、CDのレコーディングからリリースに至るまでの過程、そして今年8月20日に控えた新宿LOFTでの初のワンマンに向けての意気込みを中心に語ってもらった。(interview:松浦由香理/新宿LOFT)
リスナーとの接点を増やす
──昨年のRO69 JACKの投票枠にてROCK IN JAPAN FES.2009の出演と、5月12日に発売された『Fortune O'clock High』のリリースが決まった訳ですが、まずはROCK IN JAPAN(以下、RIJF)に出演した際のお話を聞かせてください。
轟 佑介(Guitar):RIJFに出た印象は、結論から言うと楽しかったしかありません。やっぱり日本の大きなフェスのひとつだし、楽しみにして来ている人が沢山いるわけですからね。それに参加できたというのは、すごく光栄でした。
古賀 晃英(Bass):僕は緊張しすぎて、出番の前は手がガタガタと震えていましたけどね(苦笑)。
──フェスに出演して変わった事はありますか?
山田 雄大(Vocal):知名度が上がったのはもちろんあるんですけど、一番変わったのは大勢の前で演奏した事によって、バンドのモチベーションも上がったかなと思います。最初はフェスに出演する事がゴールだと思っていたんですが、そこがスタートなんだと切り替えられたのが一番の収穫でした。ミュージシャンとしての自覚を持とうとか、そういう意識が高まりましたね。
──『Fortune O'clock High』のレコーディングに入ったのは、フェスの出演を終えてからだったんですか?
轟:RIJFの出演が終わって年内は大きいイベントがあったので、その間は曲のクオリティを高めたり新曲を作ったりして、完成度をそのままに今年の1月から短期集中でレコーディングに入りました。
林 弘樹(Guitar):フェスに出る前と出た後では、バンドで鳴らした音が全然違いましたよ。伝えたいという思いが強まったのはもちろんあるし、単純に度胸が付いたのもあるかもしれないし、トータル的に目に見えない経験値が身に付いて出す音が変わったのかなと思います。
──たくさんの人の前でライブをやってからレコーディングに入ったとなると、「ここでこう盛り上がるからこうしたい」という意識が高まったりしたんですか?
林:もともとそういう意識を持って曲作りをしているのですが、出演した事によってより高い次元で考えられているのかなと思います。
山田:音源と同じようにライブも、僕らのことを知らない不特定多数のお客さんを前に演奏をするわけじゃないですか。普段のイベントでも、どうやったら僕らの音楽を伝えられるかをより深く考えるきっかけになりました。
──初めて見てくれるお客さんを前にしてステージに立つ時って、どんな思いで立っているんですか?
古賀:やっぱり自己満足だけでは終わりたくないので、自分たちのやりたいことをやりつつ、お客さんも楽しめることを意識しながら曲作りもしています。
林:単純に限られた時間の中のセットリストで、ジャムっぽいアレンジを加えたりしています。毎回同じライブをやってもつまらないですからね。
轟:基本的にサウンドで圧倒するというより、お客さんとの一体感を求めたい曲が多いんですよね。なのでイントロだったり繋ぎだったりにこだわっている中で、どうやったら楽しんでもらえるかを考えて、ハンドクラップを求めるポイントを作ったりするようになりました。
山田:そうすることによって、ただ曲をやるよりは自分たちの気持ちも上がりやすくなりますし、僕たちが楽しんでいれば、見ている側にも徐々に伝わっていくんじゃないかと思います。
古賀:初見の人を引き込んだ上で曲を聴いて欲しいと思っているので、そういったいろんな形でイントロダクションをつけて曲を繋いでくという感じですね。一歩踏み込んでいくところを狙っています。
曲を聴いて力が沸いてくるようなイメージ
──今までにも何枚か作品をリリースしていますが、過去のレコーディングと今回で何か変わった点はありますか?
轟:根本的にドラマーが違いますね。
林:ドラマーはリリースするたびに違うので。たぶん次回も変わると思います(笑)。
伊達 慧介(Drum):そんな話、聞いてないよ(笑)!
古賀:自分のパートに関しては、前よりは出す音の入魂具合が違います。
轟:バンド的には歌詞の追求だったり、細かいアレンジの詰め方だったりリズムの使い方に、よりこだわるようになりました。
古賀:あとはフェスに出て、沢山の人の前で演奏が出来て、お客さんの顔とかを想像しながら曲作りが出来るようになってきている気がします。
山田:前はレコーディングで、ベストが出るまで何回も録り直したりしていたんです。それこそ部分的に気に入らなかったらそこだけ録り直して、良いものを良いものをって背伸びしている感じだったんですけど、今回は今を見せようっていう意識が初めて強く出ましたね。これ以上録っても良くはならないし、これ以上はやる必要がないんじゃないかなって場面が多々ありました。歌もそうですけど、ドラムも一発で終わった曲がたくさんありますから。
林:結局、一番最初が一番良かったりするんですよね。その辺の見極めが昔より上手くなったと思います。まだまだではありますが、昔よりは技術的にも向上していると思いますし、それでちゃんとやればちゃんとしたものが作れるっていう自信もついたので。
古賀:考えすぎるのも良くないですからね。気持ちを込めたワンプレーが一番きれいに出たというのが、メンバーそれぞれ多かったのかなと思います。ガチガチに固めたものより、ナマっぽさがあったほうがいいかなと思ったので。
林:あとはちょっとくらいミスがあったほうが、聴いていて逆に面白いんじゃないかと思います。
山田:ミックスが終わってマスタリングが終わって、出来た音そのものもナマに近いというか。加工しすぎていない音源になりました。こんなにナマで混ぜているバンドは、最近の日本のシーンにはいないんじゃないかなと思いますね。
古賀:ドラムとか、全然加工してないもんね。ほぼナマ。
林:あとはエンジニアの人とも話して、そういう方向になったんです。
──出来上がりは何点だと思いますか?
古賀:そのときに一番良いと思ったものを録ったので、100点だと思います。プレーに関しては、そのときのメンバーの気持ちの集約的なものが入っているから、今録ったら違う音になるんじゃないかなとは思いますけど、良いものができたと思っています。
山田:改めて聴いてみても、減点じゃなくて加点されていってますね。その時が100点だとしたら、今は120点ですよ。
──では、歌詞を書く上で大切にしていることってどんなことですか?
山田:曲によって、この曲はこういうことを歌ってますというよりも、バンドのテーマみたいなものを頭に入れて、そこにエッセンスを加えて、最近では伝わりやすい言葉や、自己満足では終わらない言葉を選んで歌詞を書こうというのはあります。
──歌詞は、メンバーの皆さんで話し合うこともあるんですか?
山田:特に最近はそういうことで話し合う機会が多いんです。リスナーの人には、聴いて、夢や理想を追いかける原動力になってもらえたら良いなと思っています。一曲を通してでも、全体を通してでも、聴いたあとに「よし!」と思って力が沸いてくるような歌詞を常に考えています。
──英語の歌詞と、日本語の歌詞がありますが、歌詞を書く上で何かが違ったりするのですか?
山田:曲によってはノリやすさだとか、メロディを上手く表現できるということで英語を使うこともあります。あとは英語を使うことで、日本語では直接言えないようなことや、表現しにくいことも表現できるので。英語は気持ちをストレートに表現出来るひとつのツールとして考えています。
──2曲目の『owe』は唯一の英詞ですけど、それも言いづらい気持ちを英語にした、と?
山田:そうです。自分の中にある葛藤だとか、他者への喪失感だとかそういうことを表したくて書きました。
──英語も気持ち良く乗っている曲ですよね。
山田:英詞だとノリ重視というか、サビの頭をわかりやすくしようとか、聴きやすいように単語の位置を考えるのがポイントだと思っているので、韻を踏んだりとか、そういう計算は英語の歌詞のほうが多いです。全部は聴き取れないけど覚えちゃった、みたいのがあったほうがいいと思うので、その辺を気にしていますね。