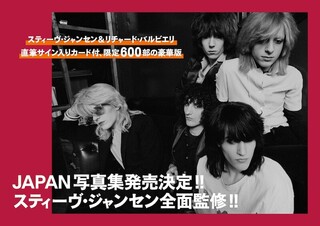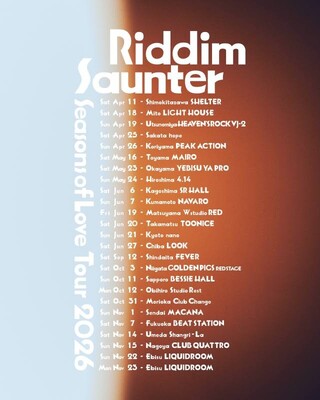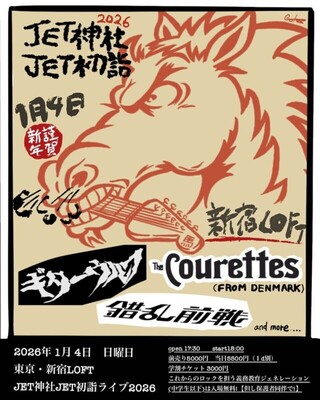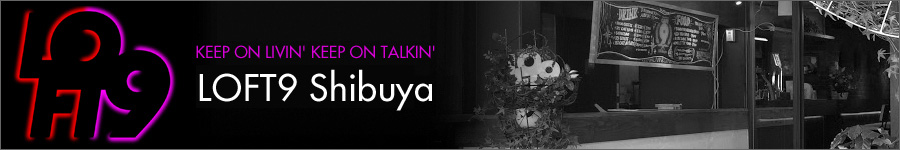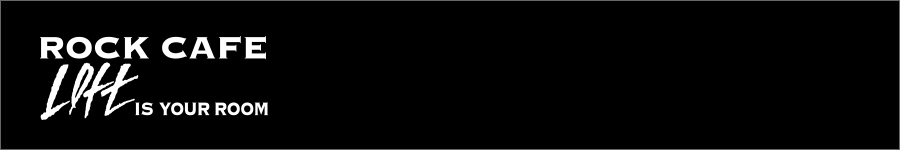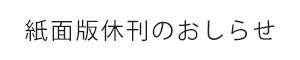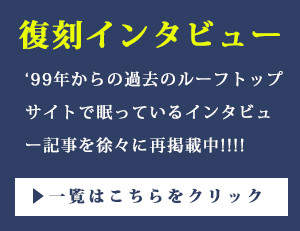紛うことなきバンド史上最高傑作である。トライバル・チェアーにとって通算3作目となる渾身のフル・アルバム。自身のバンド名を堂々とアルバム・タイトルに冠していることからも、メンバーが過去随一の確かな手応えを感じていることがわかるだろう。前作『Accept the world』の発表から2年という長いインターバルを置いただけあって、楽曲のクオリティの高さと微に入り細を穿つアレンジの妙、胸を締め付ける哀愁と激情が交錯した有機的なアンサンブル、静と動のコントラストを巧みに配した構成がどれもとにかく素晴らしい。エモーショナル・ハードコアやスクリーモ、ヘヴィ・メタルといったメンバー各自のルーツ・ミュージックを混在させた上で今日性を加味した彼らの音楽には、日本人の琴線に触れる美麗で儚い旋律が通底している。その旋律は"日本人が作る本物の音楽を奏でたい"という彼らの揺るぎない志の表れであり、その志がいよいよ肝の据わったものになったことが本作を聴けばよくわかる。また、金や権力が人間の価値を計る物差しであると言わんばかりの日本の現状を憂い、欺瞞に満ちた日本のロック・シーンに容赦なく牙を剥くなど、ロックが本来内包する鋭利な批評精神が歌詞に盛り込まれていることも注目すべき点だ。何故これだけ完成度の高い作品を生み出し得たのか、ヴォーカルのHIROKI、ギター&ヴォーカルのSEKINEのふたりに話を訊いた。(interview:椎名宗之)
持ち得る力を全部注ぎ込んだ自負がある
──前作『Accept the world』から本作に至るこの2年は、トライバル・チェアーにとってどんな期間でしたか。
HIROKI(以下、H):単刀直入に言えば、経験値が上がりましたね。『Between Hope and Despair』、『From the bottom of this town』という2枚のシングルを出して、FACT企画のコンピレーションとゲット・アップ・キッズのトリビュートに参加してレコーディングする機会は多かったんですけど、その間にSEKINEが事故って活動が3ヶ月くらい止まったりもしたんですよ。
SEKINE(以下、S):そう、背骨を骨折して麻痺寸前で、2ヶ月間はずっと寝たきりだったんです。それでシェルターの自主企画をキャンセルすることになって、シェルターへお詫びに行ったんですよ。
H:心配してお見舞いに行ったら、動けないだけでまるで元気だったんですよね。それがまたムカついちゃって(笑)。自分としては『Between〜』を出して間髪入れずにアルバムまで行きたかったんですけど、こいつの事故もあって、気がついたら2年経ってたっていう。ただ、アルバムを念頭に置きながらシングルなりコンピなりのコンセプトを設けてレコーディングを突き詰めていったので、時間が掛かったぶん、いい経験をしながら過ごせた2年間ではありました。今までは作品を作り終えた後にいろいろと反省点が出てきたんですけど、まずはそういった至らない部分を正していこうと考えたんです。シングルも実験するにはちょうどいいサイズだったし、1枚1枚実験しながら成長していく手応えはこの2年間で格段に強まったと思いますね。
──『Accept the world』は前任のベースが脱退してバンドを再構築した直後に制作したアルバムだったし、この2年間は今の編成となって改めて基礎固めをする時期だったとも言えませんか。
H:そうですね。レーベルが変わって板に付いた活動がちゃんとできるようになったし、改めて地盤固めをするべき時期だったんですよね。いろんなフェスに出させてもらったり、新しい出来事の連続でしたしね。
S:ライヴを重ねることで、ベースのK2Oのプレイもちょっとずつ見極められるようになったんですよ。ライヴでヤツが隣りで弾いてるのを見て、どんな働きをするのか目を光らせてみたり(笑)。
H:監視役だ(笑)。
S:ヤツのほうが年上なんだけどね(笑)。
──今回、自身のバンド名をアルバム・タイトルに冠したことからも相当な自信作であることが窺えますね。
S:HIROKIが突然言い出したタイトルなんですけどね。
H:もういいかなと思ったんですよ。サード・アルバムだし、これが3度目の正直だなって言うか。バンド的にも今が一番仲が親密な時期だし、これからもっといい時期に入っていくだろうなっていう実感もあって、自分たちの持ち得る力を全部注ぎ込んだ自負もあったから、ここはバンド名がタイトルでもいいだろうと。そこまでやり切った感のある作品は今回が初めてでしたからね。
──楽曲作りの精度の高さとバンドの芯の強さが一段と増した気がしますね。1曲の中にアレンジのアイディアが豊富に盛り込まれていて、構成が練りに練られているのを感じるし、音楽的には節操のないくらいに幅広い楽曲が揃っているけれども、1本の太い芯が貫かれているブレのなさもちゃんとあるという。
H:レコーディングにあたって、事前にメンバー同士でよく話し合ったことも大きいと思います。今までは付き合いが長いぶん、推して知るべしみたいな部分があったんですよ。悪く言えばナァナァになっていた部分も多少あったし。それが今回はメロディやバッキングのお互いのツボを改めてちゃんと話し合って、それぞれの音楽的なルーツを言葉にして明確にしたんです。5人の持ち場がそれぞれあるっていう意識じゃなく、それぞれ持ち場はありつつ他の4人の立場を考えられるようになったんですよね。そういう5人のツボの摺り合わせ作業を経て、客観視した上で楽曲作りに入れたのが功を奏したんじゃないかなと思いますね。
日本人が作る本物の音楽を奏でたい
──『Third eye creation』や『Utagai Future』といった恐ろしく凶暴なデス・メタル的要素の色濃い楽曲が際立っているのはそのせいですか(笑)。
S:その辺のルーツが好きなのは限られていて、一番ツボなのはK2Oで、それよりもちょっとソフトなのが俺だったりするんですよ。俺はHIROKIのルーツを余り通ってないから、打ち込みを使った『Midnight Beating』みたいな曲は凄く新鮮で面白かったんですよね。
H:『Midnight Beating』は、もうひとりのギターのKEITAが泣けるアルペジオのフレーズを持ってきたので、このまま踊れる曲にしてみようと思ったんですよ。完全に趣味の世界で、楽曲ごとに各人の趣味がよく出てるんですよね。僕は洋楽育ちで、オルタナティヴ・ロックやグランジのメロディが凄く好きなんです。だから邦楽のメロディのツボが他の4人とは微妙にズレていたりする。そこを徹底的に話し合って、摺り合わせをしたわけですよ。やっぱり、メロディの在り方が特に激変したと思いますね。
──『My world is not over』は僕らが慣れ親しんできたエモーショナルで瑞々しいトライバル・チェアー節を堪能できる楽曲ですけど、オルゴールを思わせる穏やかなイントロダクションの『Enter the story』からデス声の大絶叫が始まる『Third eye creation』で本格的にアルバムが幕を明けるわけだから、いきなり胸倉を掴まれる感覚がありますよね(笑)。
H:ハードコアやエモといったラウドな部分はもともとあった要素なんですけど、しっとりした曲をやるにしてもハードな曲をやるにしても、とにかく振り切っちまおうっていう意識が強くあったんですよ。デモの段階だと「やりすぎかな?」って客観視できない部分も正直あったんですけど、ある程度までプリプロをやっていくと自分たちらしさをちゃんと感じられるようにもなったし、これなら振り切ろうと腹を決めて出来上がったのが今回の15曲なんです。
──どれだけ荒々しく性急な楽曲でも、メロディの中にバンドの持ち味がしっかりと息づいていますね。
H:それは日本語詞っていうのもあるし、僕が唄っているのもあると思うんですけど、5人ともこじゃれたことをいくらやってもこじゃれ切れないところがあるんですよ(笑)。
S:でも、ダサくはなってないんだよね。今回初めて全部日本語詞で唄ってるにも関わらず。
──そう、今までのアルバムには数曲必ず英詞の楽曲が入っていましたけど、今回全曲日本語詞にしたのはどんな意図があるんですか。
H:今回も英詞の楽曲を入れようと考えてたんですけど、周りから「別にいいんじゃない?」って言われたこともあって。それと、活動の幅が広がっていくにつれて、英詞で唄う必然性も感じなくなってきたんですよ。結局はネイティヴ・スピーカーにはかなわないわけだし、自分が日本人たる中でどこまでベタッとしない日本語詞を書けるかが今回の課題のひとつでもあったんですよね。"日本人が作る本物の音楽を奏でたい"という欲求が以前からずっと意識としてあったんですけど、それがどんどん強まってきたんです。
──HIROKIさんのオルタナ的ルーツとSEKINEさんのメタル的ルーツが絶妙なバランスで融合しているのが先行シングルにもなった『The theory of evolution』なのでは?
S:確かにそうですね。あの曲、Aメロはラップみたいだなと思いましたけど。俺の通ってないラップまで遂に来たか! って(笑)。
H:あの曲はデモの段階で「ダサいよね、これ!」って笑ってたんですよ(笑)。でも、微妙な不快感がありつつも何故か口ずさんじゃうって言うか、ダサ格好良さみたいなものがあるなと思って。それも各人のツボの摺り合わせがあったからこそだし、今時あんなに古くてダサいギター・ソロを弾いてるヤツもいないだろうから、それもアリかなと(笑)。僕らの中では、今のパンク・キッズやギター・ロックを聴いてる若い子たちに対してリプレゼントしてる感覚ですよね。

一切妥協をせずにクオリティを突き詰めた
──『train and boat』は冒頭から全員の合唱で始まったり、途中で入るギターのエフェクトが効果を上げていたり、アレンジを凝りに凝った後が窺えますね。それは本作に収録された楽曲全般に言えることですけれど。
S:ギターもプリプロの段階でだいぶ時間を掛けたし、メロディもかなり凝ったよね?
H:メロディもコーラスも何でもそうですね。そこに費やすペースが客観視できないんですよ(笑)。
S:録りの当日までアレンジを詰めてたしね(笑)。
H:『Utagai Future』もギリギリまで「このメロディは違うだろ!?」って迷ってたし、ブッ壊してはまた作っての繰り返しだったんですよね。スパッと行ける時もあるんですけど。
S:スパッと行けない時は全然行けないよね。録りの寸前まで詰めないと気が済まないとか思っても、結局終わらなかったりして(笑)。
──5人のルーツを事前に確認し合って制作に臨んだ以上、一切妥協せずに5人全員が納得できるクオリティまで突き詰める難しさもあったんじゃないですか。
H:ありましたね。そのお陰でレコーディングが10日ほど延びましたから。メロディで一番手こずったのは『Utagai Future』なんだけど、プレイ的にはどれ?
S:ほとんど全曲だね(笑)。どれも凄く時間が掛かった。
H:楽曲の持つニュアンスを出すのにかなりこだわりましたからね。最後の『Over the river』はコーラスのほとんどをSEKINEが考えたんですけど、そのコーラスの厚みを出すのに何パターンも考えて実際に録ってみたんですよ。どの曲も思い付いたアイディアは全部録って、そこから引き算をしたり足し算をするやり方だったんです。ヴォーカルで死にそうだったのは『Aquarium』ですね。
──『Aquarium』は極々シンプルな演奏でじっくりと聴かせるミディアム・テンポの傑作だと思いますよ。
H:あんなにメロウで甘い響きのある楽曲は今まで唄ったことがなかったんですよ。あのニュアンスを出すのにムチャクチャ苦労しましたね。
──あそこまで切なくロマンティックなラヴ・ソングも新機軸ですよね。
S:あの歌詞は俺も驚きましたけどね(笑)。
H:僕も驚きました(笑)。自分でもあんなことを言えるんだなと思って。そういう作風もひとつの挑戦と言うか、「これをやったら格好悪いかな?」っていう足枷を作りたくなかったんです。「こんなに甘酸っぱい歌も唄えるようになりました」くらいのほうが胸は張れるかなと。まぁ、それでもメンバーにあの歌詞を持っていった時は凄く恥ずかしかったんですけどね(笑)。
S:こいつの書く歌詞のダメな一線っていうのが俺の中には勝手にあるんですよ。でも、単刀直入に「I love you」を言うような歌詞じゃなかったから、全然OKだなと思って。
H:でも、「I love you」をストレートに唄えるようになったら凄いと思うよ。
S:じゃあ、唄ってみてよ。
H:いや、まだムリだな(笑)。『Aquarium』は確かにラヴ・ソングですけど、この歌詞でもまだ無意識の壁が多分あると思うんですよ。もっとストレートなことを唄えるようになったら...とか思いつつ、唄ってる自分をまだ想像できませんね(笑)。
──『Enter the story』に導かれて『Third eye creation』が始まったり、中盤に『Time again』というインストを配してみたり、『909』と『Joint your black』に繋がりを持たせてみたりと、全体的にコンセプチュアルな構成になっているのが本作の特徴のひとつですね。
H:そういう部分は以前からライヴで試していて、曲に対するインタールードを作ったりしてたんです。僕らの曲は良くも悪くも対比が激しくて、100行ってる曲もあれば、逆の方向に100行ってる曲もあるので、それらを繋げる世界観みたいなものを作ろうと思ったんですよ。それがあることによって、切ない曲を聴いていたはずがいつの間にか頭を振るような激しい曲になっているみたいな効果が出せるなと思って。聴く人を別世界へと連れ去るって言うか、びっくりさせたいと思ったんですよね。
道を踏み外すきっかけとしての音楽
──重厚なギター・リフが掻き鳴らされる『909』と『Joint your black』から一転して爽快感に溢れる『Midnight Beating』が来るわけですから、充分びっくりしましたよ(笑)。
H:『Midnight Beating』は真夜中の心情なんです。意識したわけじゃないんですけど、アルバムを通じて1日の時間の流れが歌詞の中に潜んでいるのかもしれない。最後の『Over the river』は朝を迎えて終わりますからね。1日のバイオリズムを感じるようなアルバムを作りたいとずっと思ってたんですよね。同じ夜でも、平日の夜と週末の夜とでは表情が違いますよね? そんなニュアンスを踏まえつつ、1日の時間の流れを感じさせる歌詞作りなり曲の雰囲気作りなりをしたかったんです。僕らはエンターテイメント型のロックじゃなく、日常生活の中に溶け込んだロックを志向する意識もありますからね。
──"哀愁"もトライバル・チェアーにとっては重要なキーワードのひとつとしてありますよね。
H:大きなテーマのひとつですね。楽曲の振り幅は大きいけど、どの曲にも"哀愁"と"グッド・メロディ"が根底にはあるんですよ。そのこだわりは凄くあるし、味付けが甘かろうが辛かろうが元の素材はずっと同じなんですよね。(SEKINEに)オマエなんてメタルしか弾けないしな?(笑)
S:そうだな(笑)。でも、最近は自分のルーツもちゃんと出せるようになってきたよ。
H:僕はハード・ロックやメタルを全然通ってこなかったので、「なんでこんなにギター・ソロが長いんだ?」とか思うこともあるんですけど(笑)、惹かれる人の気持ちもわかるんですよ。SEKINEが言うには、ハード・ロックやメタルっていうのはプロレスを楽しむ感覚に近いと。プロレスって、相手の技を避けられるのに絶対に避けない潔さがあるじゃないですか。ただ、プロレスをそのままやっても意味がないから、それを認めつつ僕やK2Oが持ってるハードコアやエモの要素を加味して新しい音楽を提示していきたいんですよね。ホントは、もっと頭の悪いことをやりたいんですよ。
──頭の悪いこと?
H:音楽に強い衝撃を受けるのは中高生の頃だと思うんですけど、今の中高生はロックよりもダンス・ミュージックに惹かれる傾向にあるじゃないですか。ロック好きな中高生はどこかで道を踏み外してロックへ辿り着いてると思うんですよ。そんな子たちにもっともっと僕らのライヴを見て欲しいし、あわよくば僕らの音楽が道を踏み外すきっかけであって欲しいんです。
──『Transparent Imagination』には、「ロックオブしがらみジャパン 走り抜ける術/偽り見破れ」という今の日本のロック・シーンに対するアンチテーゼとも受け取れる一節がありますね。
H:今の時代、いい音楽が自由に手に取れるようで、その裏で実はいろんな罠が仕掛けてあるじゃないですか。いい音楽をやってるだけじゃダメで、+αが必要な部分ってありますよね。大きなイベントに出るのもそうだし、版権や利権の問題もあったりして。僕らみたいなペェペェですら政治的な匂いを感じることがあるので、知名度のある人たちはもっと大変だろうし、大人も大人側でいろいろ大変だとは思うんだけど、僕らはそこをちゃんと闘っていきたいんですよ。誰が悪い訳とかじゃなく、開かれたものにしたいっていう。今のロック・バンドはそういうことを正面から言うことがないから、余計にそう感じてますね。『Transparent Imagination』の一節は僕の中では序の口で、書きたいことはまだまだ一杯あるんですよ。
──今のロック・シーンに限らず、付和雷同することなく自分だけの見識を持つことは生きる上で基本中の基本ですよね。
H:そうじゃないと、偽りを見破れませんからね。たとえば、お客さんがたくさん入って盛り上がってるライヴがいいライヴかと言えば、必ずしも一致するものじゃないですよね。一見その華やかさに惑わされるけれど、よく見ればおかしなことって結構あるぜ、ってことを唄いたかったんです。『Transparent Imagination』は"透明な想像"っていう意味なんですよ。僕自身、満杯のライヴハウスで演奏したいっていうバンドを始めた時の初期衝動を今までずっと大事にしてきましたけど、その中でしがらみや損得の部分で打算的になって自分の方向を見失っていくバンドって多いじゃないですか。それは論外だと思うし、今回のアルバムで一番訴えかけたいことは実はその部分なんです。
 |
 |
ライヴは意地の張り合いで馴れ合いじゃない
──「二進法で刻む名無しの本音が浮き世を物語る」という歌詞も辛辣ですけど、インターネットに依存したコミュニケーション不全の現代を的確に言い表していますね。
H:ネットがすべてじゃないってことですよね。ライヴがその最たる例ですけど、自分からその場に足を運んでステージを自分の目で見て心に刻む行為は絶対にネットじゃ体感できないですから。僕らみたいにライヴハウスと身近な人間がどんどんライヴハウスへ足を運ばないと今のキッズは足を踏み外してロックに辿り着いてくれないし、もっともっとライヴハウスを面白い場所にしたいですよね。今の若い世代はライヴハウスが身近なようで身近じゃない気もするんですよ。僕らの世代はネットがなかったから、情報を得るためにはライヴハウスへ足を運ぶしかなかった。そこが一番の大きな違いだと思いますね。
S:今はバンドマンもヒリヒリする感覚が減ったと思うんですよ。バンドマンがマイナスの意味で身近になりすぎている気がするし、もっと近寄り難い感じが俺としては欲しいですね。埼玉でZIGGYを見た時にそういう近寄り難いオーラを感じたんですよね。楽屋とかへ行った日にゃブン殴られるんじゃねぇかと思って(笑)。俺はそんなヒリヒリ感をもっと味わいたいんですよ。
H:ヒリヒリ感があるのに、行ってみたいと思わせる身近さもある...そのバランスが大事なんでしょうね。
S:ライヴハウスで憧れのバンドマンと握手ができるかもしれないけど、行ってみなければ握手はできないわけじゃないですか。だけど、握手を求めたら怒られるんじゃねぇかっていうドキドキ感もあるっていう(笑)。
──バンド間の仲が馴れ合いすぎるのもどうかと思いますよね。ステージに立つ以上はライヴァルだという意識は当然あるんでしょうけど。
H:みんなで頑張っていこうとする意識がちょっと強すぎるのかもしれませんね。僕らはジャンルの狭間の対バンが多いんですよ。ハードコア・バンドの中にポツンと1バンドだけでいたり、ギター・ロック・バンドの中にパワー・ポップ的なポジションの延長線上で置かれてみたり。
──多彩な音楽性ゆえに何処にも属せない空集合的な佇まいがトライバル・チェアーにはありますよね。その立脚点だからこそ見える景色もあると思いますけど。
H:特定のジャンルでヌルいなと思うことはありますね。いいバンドはもちろんいるんですけど。あと、ツアー先で地元のバンドと対バンする時に、地元を盛り上げていこうぜ、みんなで頑張っていこうぜ、みたいな過剰な仲良し空気になると興醒めするところがあるんです。打ち上げはともかく(笑)、ライヴ中だったら特に。地元シーンの底上げは当然のことであって、その前にまず自分たちが大きくならなくちゃいけない。動員を増やしたいから団結したくなるんでしょうけど、僕はそうじゃねぇだろって思うんですよ。上辺だけの馴れ合いなんて要らない。この間、自主企画をERAでやったんですけど、それがエンバークっていう若手のバンドとココバットとの3マンだったんです。ココバットのメンバーがステージ脇で見てる前で唄うプレッシャーはハンパじゃなかったし、ココバットのグルーヴの説得力たるや凄まじいものだったんですよ。でも、演奏力や自分たちの見せ方っていう意味では到底及ばないかもしれないけど、そこは意地の張り合いなんです。お客さんに何かを残せた者が勝ちだと思うし、バトルロイヤル的な対バンをしてないバンドにはその感覚をもっと理解して欲しいんですよね。
──アレンジとコーラスが妙がとりわけ光る『Last wish』ですが、「目を凝らせ 見届けて この腐りかけの日の本で」という重いテーマを孕んだ一節で終わるのが印象に残りますね。
H:歌詞が重いテーマだからこそ、サウンドは浮遊感を持たせたかったんです。『Last wish』は僕自身凄く思い入れの強い曲なので、アレンジはムチャクチャ凝りましたね。プレイヤーもリスナーも、意識が変わらないことには何も変わらないじゃないですか。何かが劇的に変わることがなくても、この曲を聴くことによってちょっとでもいいから考えるきっかけになれば凄く嬉しいんですよ。
──今の日本に対して憂いを抱く最たるものは何ですか。
H:利益や損得勘定ばかりが最優先されることですね。それによって人と人の触れ合いがないがしろになるのも耐え難い。ウチの実家は床屋で、僕は町の商店街の中で生まれ育ったんですよ。商店街は小さい世界だから相互扶助の意識が強くて、俺が悪さをすると隣のトンカツ屋のオヤジさんが出前の時とかに叱ってくれたりするんです。そういう古き良き繋がりって悪くないなと思うんですよね。そのトンカツ屋のオヤジさんみたいに、自分の子供でもないのに親身になって気に掛けてくれる人が今はどれくらいいるんだろうなと思って。何から何まで利益や損得勘定に走りすぎるこんな時代だからこそ、相互扶助の意識が必要なんですよ。身近なところでちょっと意識を変えれば状況が変わることってたくさんあるはずなんです。僕らはそんなことを歌を通じて促したいんですよね。