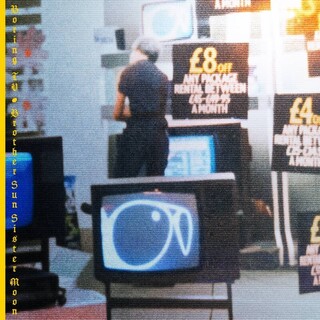昨年5月に発表した『泥水のメロディー』で普遍的なポピュラリティと不変的なブルースの理想的な融合を具現化したア・フラッド・オブ・サークルが10月から3ヶ月連続で発表し続けたライヴ音源のタイトルは『Before the flood』というものだった。"怒濤の濁流の前に"あるもの──それは、2006年の結成以来一歩ずつ着実に積み上げてきた自らの音楽性、そして彼らが本懐を遂げる場であるライヴの在り方の集大成に他ならない。ブルース・ロックを分母に置いた処女作、そのツアーでの教訓から大衆性が高まったことで生まれ得た『泥水のメロディー』、日本全国にその名を知らしめた精力的なツアーの日々、そこで培ったライヴ・バンドとしての経験値とポテンシャルの高さをしかと刻み込んだ『Before the flood』。すべては海原に連なる波の列のようであり、あらゆる帰結は"怒濤の濁流の先に"あるのだろう。輝ける新章の扉を開けるその前に、彼らは自身初となるワンマン・ライヴを新宿ロフトで執り行なう。その市松模様のステージの上に、ロックの過去と未来を繋ぐ奇跡の一瞬がある。その歴史的瞬間を是非刮目して頂きたい。(interview:椎名宗之)
総決算となるライヴの記録を残したかった
──この時期にライヴ音源を立て続けに発表した意図というのは?
佐々木亮介(vo, g):2008年は『泥水のメロディー』を出してツアーをやって、8月に総決算となるイヴェントをロフトでやれたので、その記録を音源として残しておきたかったんですよ。『Before the flood』、つまり"嵐の前に"という意味なんですけど、次なる動きの前の助走的な意味も込めてあるんですよね。
──ライヴ盤はごまかしが利かないし、ある意味スタジオ盤よりもハードルが高い部分があったりしませんか。
佐々木:そうですね。録るのを前提にしたライヴは経験したことがなかったので、凄く緊張感がありましたね。新曲を披露するのもあったし。
──『シーガル』や『エレクトリック ストーン』といった新曲は、『泥水のメロディー』に収録されていた楽曲の延長線上にあるように思えますね。ポップさとロックの武骨さがギリギリのところでせめぎ合っている絶妙なバランスで。
佐々木:かもしれません。新曲はどれも、『泥水のメロディー』のリリース・ツアーの中で生まれてきた曲ですから。ライヴのために作った曲だったし、そういうモードだったんでしょうね。スタジオ盤を作ることになれば、また違ったモードになると思うんですけど。
──ツアー中のタイトなスケジュールでも、コンスタントに新曲を作れるものなんですか。
佐々木:毎月3曲ずつ必ず作ることを自分たちで決めていたんですよ。その中からいい曲を厳選した感じです。ツアーがあってもなくても新曲を定期的に作っていたので、自分たちなりのペースが掴めた気はしますね。
──ロフトでのライヴというのは、やはり特別な思いがあるものですか。
佐々木:特別ですね。シェルターでライヴをやるようになった頃から憧れがずっとあったし、その昔、スピッツもロフトで自主企画をやってましたからね。
──ライヴ音源と言えどもひとつの作品なわけで、完成に漕ぎ着けるまでに気を留めたのはどんな点ですか。
石井康崇(b):勢いを出すのがテーマでしたね。自分の好きなライヴ盤も、スタジオ盤にはない勢いと激しさがあるから、そこは今回強く意識しました。
──なるほど。だから『308』のようなスローな曲がないわけですか。
佐々木:実際のライヴではそういう曲もやったんですけど、作品にはそういう曲を意識して残さなかったんですよ。それも勢いを意識してのことなんです。
──『ロシナンテ』から『Red Dirt Boogie』への流れが非常にスリリングで、これはやはりライヴ盤ならではの醍醐味ですよね。あと、『プシケ』のメンバー紹介も大きな聴き所のひとつなのかなと(笑)。
佐々木:メンバー紹介がそのまま入ってるライヴ盤もなかなかないですよね(笑)。『プシケ』はなかなか録るチャンスに恵まれなかった曲で、やっと作品にすることができたんですよ。凄く昔の曲で、ファーストを出す前からあったんです。最初はコードもなかったし、panicsmileみたいな変拍子のアレンジだったんですよ。『プシケ』っていうのはギリシャ神話に出てくる神様の名前で、ジェフ・バックリーが精神世界を意味する言葉として『プシケ』を使ってたんですよね。
──「人の心には"プシケ"と呼ばれる喜怒哀楽のコアになる領域がある」っていうやつですね。
佐々木:そう、その意味を自分に置き換えて作った曲なんですよ。
──『シーガル』っていうのは?
佐々木:カモメですね。
──『象のブルース』や『ロシナンテ』に続くフラッドお得意の動物シリーズですか(笑)。
佐々木:『ブラックバード』は鳥だし、『ガラパゴス』はゾウガメだし、確かに動物ネタは多いですね(笑)。


今取り組んでいる新曲が"After the flood"
──『エレクトリック ストーン』は、僕らの世代だとタイトルから何となくストーン・ローゼズを連想してしまうんですけど(笑)。
佐々木:ははは。『エレクトリック ストーン』は、自分たちなりのロックンロール賛歌みたいなものを作ろうと思ったんです。リフが出来るまでに一番時間の掛かった曲で、難産だったんですよ。
岡庭匡志(g):本リフの前の溜めの部分をどういうテンションで行けばいいのか悩んだんですよね。メロディじゃなくバックで鳴ってる感じをどうすればいいのかっていう。
──ああいうブルージーな曲調にポップなテイストをブレンドするのが今のフラッドのモードなんですか。
佐々木:だと思いますね。そのバランス加減が見えてきたところもあるし、今はそれをこれからどう広げていくかの段階に来てるんですよ。ちょうど今、次のアルバムのレコーディングをしていて、録ってる曲がまたかなりユニークなんですよね。それが自分たちにとってのネクスト・ステージって言うか、"After the flood"になっていると思います。
──各人の好きな古今東西のライヴ・アルバムを挙げると、どんなラインナップになるでしょう?
石井:俺はツェッペリンの『How The West Was Won』ですね。1曲目の『Immigrant Song』からいきなりトップ・スピードで行く感じが堪らない。
──映画にもなった『The Song Remains the Same』とかは?
石井:それよりも、砂漠がジャケットの『Led Zeppelin』のほうが俺は好きですね。
──『The Song〜』はジミー・ペイジの顔が老人になっていく妙な幻想シーンも入っていて、何かまとまりに欠ける映画でしたよね。
佐々木:ああ、あれは何をやりたかったのか終始意味が判りませんよね(笑)。
石井:でも、あれに入ってる『Since I've Been Loving You』は凄い名演ですよ。音と映像が全然噛み合ってないんだけど(笑)。
岡庭:俺は断然、オールマン・ブラザーズ・バンドの『At Fillmore East』ですね。好きなライヴ盤はたくさんあるけど、あれはちょっと飛び抜けてる。曲の中で一番グッと来るのは、やっぱり『In Memory of Elizabeth Reed』かな。
──岡庭さんは、てっきりフリーの『Free Live!』かと思いましたけど。
岡庭:あのアルバムは正直、余りグッと来ないんですよ。
渡邊一丘(ds):ヘタだもんね(笑)。音がペラペラだしさ。俺は何が好きだろう...。
──フーの『Live At Leeds』とかは?
渡邊:ああ、あれは最高ですね。最後に入ってる『Magic Bus』とかヤバイですよ。挙げていくと他にもいろいろとありそうだなぁ。
石井:俺はあと、レッチリの『Live In Hyde Park』が好きだな。2枚組のやつ。
渡邊:俺、あったわ。チープ・トリックの『At Budokan』。世界に武道館の名を知らしめたアルバムだし。
佐々木:俺はストーンズの『Get Yer Ya-Ya's Out』を挙げたいところなんだけど、何かありきたりでつまらないでしょ?
──あのアルバム、『Midnight Rambler』のブレイク部分で「カッチョイイ!」っていう日本人の声が入ってるでしょう? 確かに恐ろしくカッチョイイんだけど(笑)。
佐々木:そうそう。あの声の主が村八分のチャー坊さんだっていう噂がありますよね。
渡邊:でも、本人は違うって言ってたらしいよ。
石井:ストーンズは『Shine A Light』のサントラも凄く格好良かったですよ。
──ライヴ盤の魅力はどんなところにあると思いますか。
佐々木:ライヴ盤特有のヴォーカリゼイションってありますよね。音源でも"イェイ!"って叫んでるんだけど、ライヴ盤の"イェイ!"のほうが堪らないっていうのがあるんですよ。
渡邊:うん、判る。やっぱりその場の空気感だよね。

ブルース・ロックというキーワードから脱却したい
──スタジオ盤の枠に収まらないギターのフレーズとかもあるのでは?
岡庭:でも、俺の場合は全部スタジオ盤と同じように弾いてるんですよ。スタジオ盤では出せない勢いをライヴで出せればいいなとは思ってるんですけど。オールマンも、ライヴではスタジオ盤と同じソロが多いんですよ。あんなにインプロヴィゼーションの印象が強いのに。
佐々木:ブッチャーズの田渕(ひさ子)さんもナンバーガールの時は音源に近いソロでしたよね。そうだ、ナンバーガールの『シブヤROCKTRANSFORMED状態』も挙げたいですね。あれは最高ですよ。
渡邊:日本のバンドで言えば、ブランキーの『Last Dance』も格好いいですね。真っ赤なジャケットのやつ。
佐々木:あと、クラムボンの『3 Peace〜Live At 百年蔵〜』。挙げていくとキリがないですね。
──去年共演したバンドの中で、とりわけ刺激を受けたのは?
石井:my way may loveですかね。とにかくあのテンションが凄まじかったので。
岡庭:俺もmy way may loveかな。外タレみたいに思えたし(笑)。
渡邊:俺はSTANですね。神戸でライヴを一緒にやった時に観て、恰好悪い瞬間が1ミリたりともなかったから。外タレみたいではなかったけど(笑)。
佐々木:去年じゃないですけど、フラカンは凄かったですね。歌を突き刺すように伝える(鈴木)圭介さんがとにかく凄くて。
──今月末にはバンド史上初となるワンマン・ライヴが開催されますね。しかも、シェルターではなくロフトという大舞台で。
佐々木:そうなんですよ。バンドにとっては大挑戦なんで、今はそれに向けて気合いを入れて準備を整えてます。今録ってる新曲も披露したいし、ライヴ・バンドとしてずっとやってきて初めてのワンマンだから、モチベーションの高いライヴをやりたいですね。
──いつも『What's Going On』をやっているシェルターの倍のキャパシティっていうのも大きなプレッシャーですよね。
佐々木:しかも、全員がフラッド・オブ・サークルを観に来てくれるわけですからね。それはプレッシャーでもあり、喜びでもありますけど。
──セットリストの構成も試行錯誤しそうですね。
佐々木:選曲にも迷うだろうし、アレンジや曲の繋ぎ方も変えたりしますからね。
──ワンマンならではの趣向を凝らす予定はありますか。たとえば、アコースティック・セットを挟んでみたりとか。
佐々木:個人的には普段よくやってるんですけどね。まぁ、検討してみます(笑)。
岡庭:アコギは普段弾き慣れてないし、エレキに逃げたいくらいですよ(笑)。全然違う楽器みたいに感じるし。
渡邊:まぁ、せっかくのワンマンだから何か面白いことはやってみたいよね。
佐々木:石井のフリー・トークとか?(笑)
石井:全然締まらないし、次に繋げられないよ(笑)。ロフトは魔物が棲んでる印象があるんですよね。あのステージに呑まれる感じがあるから。そこをどう正気を保つかが課題だと思ってます。
──月並みですけど、2009年はどんな1年にしたいですか。
石井:ライヴ盤も出たことだし、ライヴを去年以上に盛り上げたいですね。まずはワンマンを成功させないと。
岡庭:いろんな面で一皮剥けていきたいですよね。ライヴも、曲作りも、個人的なスキルも。特に曲作りは頑張ってみたいですね、個人的には。
渡邊:全然バンドとは関係ないですけど、今年はもっと自然と触れ合いたいなと思いますね。バーベキューをしたり、釣りをしてみたり。夏場には苗場辺りでキャンプを張りたいじゃないですか?(笑)
石井:遠回しでいやらしい言い方だなぁ(笑)。
佐々木:俺は、ブルース・ロックをキーワードとしてやってきたところから脱皮したいですね。ブルースが心底好きな人たちが俺たちの音楽を聴いたら、"全然ブルースじゃないじゃん"って感じると思うんですよ。でも、それでいいんだと思う。ツェッペリンが出てきた時もきっとそう思われたんだろうし。それでも自分はやっぱりブルースが好きで、それに影響を受けて今の音楽をやっているから、その魂は捨てずに新しいことをやっていきたい。3コードのブルースを弾かなくてもブルースが鳴っているような音楽をやりたいんですよ。それが今作ってる新曲でだいぶ焦点が絞れてきたので、楽しみにしていて欲しいですね。
pix by h.o-mi