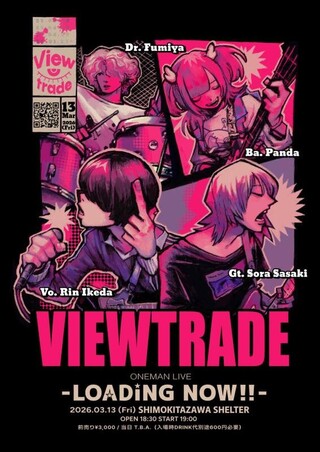自らのバンド名をタイトルに冠したファースト・ミニ・アルバムの発表から僅か10ヶ月。a flood of circleが放つ最新作『泥水のメロディー』は、前作で顕著だったブルース・ロックを分母に置いたスケールの大きい音像と聴き手を選ばぬ群を抜いたポピュラリティとが絶妙のバランスで溶け合った会心の作だ。大衆に媚びへつらわないギリギリのところでエッジの立ったロックを打ち鳴らすという至難の業を、彼らは肉感的なダイナミズムと躍動に溢れたグルーヴ、そして極上のメロディーを武器にして見事に成し遂げている。普遍的なポピュラリティの獲得という嬉しい誤算を我々に提示してくれた佐々木亮介(vo, g)と岡庭匡志(g)の2人に、本作完成に至るまでの試行錯誤と2008年に在るべきブルースの本質について訊いた。(interview:椎名宗之)
ブルースを如何に王道へ引っ張っていくか
──今振り返って、昨年7月に発表した処女作をどう捉えていますか。
佐々木:あの時は演奏も全力でやっていたつもりなんですが、端的に言えばヘタだなと(笑)。ただ、曲のクオリティや構成自体は今も素直にいいと思えますね。まとまりもちゃんとあるし、今回のアルバムに繋がる雛型みたいなものもあるんです。あのアルバムに確信があったからこそ、それを広げて今もやれている感はありますね。
──ライヴを重ねることでだいぶ収録曲も成熟してきたのでは?
佐々木:そうですね。ライヴでやればやるほど曲の新たな側面に気付かされたりもするし。
岡庭:ギターの絡み方やアレンジも、音源からどんどん変わってきてますからね。
佐々木:僕のギターがシンプルになって歌に専念するぶん、岡庭のギターの比重がより強まったんですよ。そのバランスが日増しに良くなってきている気はしますね。
──前作での反省点を踏まえて本作の制作に臨んだ点はありますか。
佐々木:タイトル・トラックの「泥水のメロディー」然り、「ロシナンテ」然り、今回はスピード感のある曲を意識的に増やしたんですよ。ポップで疾走感のある「世界は君のもの」はこのアルバムに入れる発想が最初はなかったんですけどね。
──「世界は君のもの」は、バンドにこんな引き出しがあったのかと思うほどのポップさがありますね。今回の『泥水のメロディー』は、全体的にフラッド流のポップ感覚に彩られた作品だと言えると思うんですよ。
佐々木:そういうところは前作より念頭に置いていましたね。タイトルに"メロディー"という言葉を使っているくらいなので、メロディーに対する自分達なりのこだわりを全面に押し出そうと思ったんですよ。それを突き詰めた結果、メロディーの良さがポップさに繋がっているんじゃないですかね。
──ただ、前作にも「ブラックバード」や「夜はけむり」のようなポップの純度の高い楽曲が揃っていましたよね。
佐々木:確かに。自分達の中にあるブルースというキーワードを前作では1本の太い軸として置いていたんですけど、今の時代にブルースが王道ではないことはよく理解しているつもりなんです。それをどうやって王道へ引っ張っていくかがテーマだった気がします。ポピュラリティがあって初めて王道となり得るわけで、そのポピュラリティを獲得できるようにどう曲作りをするかに一番腐心したんですよ。
岡庭:そうだね。そこが前作と比べて最も大きな違いだよね。今ファーストを聴くと、全力で格好付けてるように思えるんですよ(笑)。もちろん今も格好は付けてるけど、もっと違う種類って言うのかな。ギターも以前の格好付け方を忘れずにポップなアプローチで弾いていますし。
佐々木:「Red Dirt Boogie」みたいな典型的なブルース・ロックでもリフはキャッチーだし、「ビスケット」もブルースの定型だけど、どこかハッピーな感じを出したくてシャッフル調にしたんですよ。それと「世界は君のもの」のリフは、岡庭がよくあのコード進行であれだけポップなものにしたなと思うし。だから今回、岡庭のギタリストとしての視野がだいぶ広がったと僕は思うんですけど。
岡庭:そこは自分でも強く感じてますね。曲作りに悩んだぶんだけ視野が広がって、自分でも驚いてるところはあるんですよ。リフ以外のバッキングが特にてこずったんです。ギター・ロック然とした「世界は君のもの」のような曲は今まで余り弾いたことがなかったですから。
佐々木:僕が綴る内省的な言葉と岡庭の粘着質なギターが自分達の大きな強みのひとつだと思っているので、そこは今回も活かしたいと思っていたんですよね。ただ、僕らはコアなブルースを追求していくバンドではないし、もともとポップなサジ加減を加味した方向性に行きたかったんですよ。この『泥水のメロディー』はその理想的なバランスを具現化できていると思うんです。
4人で曲の世界観を共有できた強み
──タイトルにもありますけど、"泥"や"水"が象徴的な言葉として作品全体に通底していますよね。「Red Dirt Boogie」にも"Dirt"という単語が使われているし、「SWIMMING SONG」には"深い川を渡る"というフレーズが出てきますし。
佐々木:何と言うか、ドロドロ感みたいなものがキーワードとしてあったんですよ。自分達の音楽性を客観視すると、ドロドロしているのにキラキラした部分もあるように感じるんです。
岡庭:そのキラキラしたところから発展させて、"宇宙"っていうテーマも今回のアルバムにはあったので、ジャケットも銀河系のイメージにしてみたんですよ。
──"泥水"=マディ・ウォーターだから、偉大なるブルースの巨人に対するオマージュの意も込められているんじゃないですか。
佐々木:そこはもちろん。ちょっとした言葉遊びですけどね。「泥水のメロディー」のリフと歌が交互に折り重なる部分は、マディ・ウォーターズの「I'm Your Hoochie Coochie Man」にインスパイアされたものなんですよ。
──マディ・ウォーターズこそマイナーな存在だったブルースを極めてポップな解釈で世に広めた立役者だし、フラッドの志向性とも合致しますよね。
佐々木:そうですよね。マディ・ウォーターズは、ブルースマンの中でもロックやポップスとの異種交配が活発な人でしたからね。
──最初に「泥水のメロディー」が出来て、枝葉が分かれていくように収録曲を決めていったんですか。
佐々木:「ロシナンテ」や「Red Dirt Boogie」といったブルース色の強い曲は「泥水のメロディー」の後に出来ましたね。「泥水のメロディー」よりも歌モノっぽくとか、もっとブルースっぽくとか、そういう発想で曲を固めていきました。
──珠玉のスロー・ナンバー「SWIMMING SONG」は、岡庭さんの名前が作曲者として初めてクレジットされていますね。
岡庭:そうなんです。今までもアレンジやリフに自分のアイディアを持ち込むことはあったんですけどね。
佐々木:この曲の雰囲気を決めたのは岡庭だったんですよ。最初にAメロを岡庭が持ってきたんですけど、今ひとつパッとしなかったんです(笑)。
岡庭:サビが地味だったんだよね。そこで亮介が別のサビを持ってきて、ひとつの曲として完成させたんですよ。
──「SWIMMING SONG」は愁いを帯びながらも透明感があって、こうしたタイプの曲は今までになかったですよね。
佐々木:なかったですね。「308」と比べても圧倒的に暗いし(笑)。岡庭が持ってきたのはコードが深く沈み込んでいく感じで、そこを僕がポップに上げていく進行にしてみたんです。それが凄くいいバランスになったんですね。
岡庭:僕が持っていくフレーズは基本的に暗いんですよ(笑)。
佐々木:岡庭が「新曲だよ」って持ってきた曲でマイナー・キーじゃなかったことは一度もないですからね(笑)。でも、お互い持っていない部分に惹かれ合っているところもあるんですよ。
──本作も前作同様、サンボマスターや音速ラインなどを手掛ける杉山オサムさんをエンジニアに起用していますが、2作目ともなればやり取りもスムーズだったんじゃないですか。
佐々木:そうですね。頭の3曲は特に勢いを大事に持っていきたいとリクエストもできたし。
岡庭:そこはオサムさんも直感で理解してくれたみたいで。「Red Dirt Boogie」までの3曲は音が歪みまくってますけど、それが気持ちいいと言うか。オサムさんの作る音は塊が真っ直ぐに飛んでくるような感じで、バンドとの相性が凄くいいんですよ。
佐々木:そのオサムさんの音が随分と手助けをしてくれたんです。それは前作も同じで、僕らのモチベーションを上げるような雰囲気作りをしてくれたのが有り難かったですね。
──本作を完成させたことで、自分達が理想とするサウンドを形にすることには自信が付きましたか。
岡庭:自分の出したい音のニュアンスが、前作よりも忠実になった気はしますね。
佐々木:それと、曲の世界観を4人で共有する時間を事前に持てたことが功を奏していると思うんですよ。曲に対して同じイメージを共有したからこそ、各々のプレイが有機的に絡み合えているんじゃないかなと。
ポップなブルースこそが自分達のスタンダード
──そういった有機的なサウンドが余計に"開かれた"印象を与えるのかもしれませんね。決してマニアックに走ることのない音作りだから、コアなロック・ファン以外にも受け容れられるポテンシャルが高いと思うんですよ。
佐々木:ブルースって本来は凄くポップなものだったはずだし、ポップなブルースこそが僕らのスタンダードであり王道なんですよ。
岡庭:そう、だから本当の意味でのポップをこのアルバムで追求したかったんです。
──2人にとってポップの定義とは?
岡庭:僕にとってポップとは、判りやすいという意味ではなくて、直感的にいいと思えるものですね。フィーリングで楽しめるものと言うか。
佐々木:僕の中ではポピュラリティという言葉と直結したものですね。万人に受け容れられることを意識した音楽がポップなんだと思います。日本で大衆的な音楽のことを便宜的にJ-POPと呼ぶのなら、僕らは喜んでJ-POPと呼ばれたいくらいなんですよ。
──不特定多数のリスナーを意識するようになったのは、ライヴを重ねるごとにオーディエンスの反応に重きを置くようになったのも関係しているのでは?
佐々木:それは大きいですね。前作を発表した後のツアーで、ライヴの在り方についていろいろと考えるようになりましたから。
岡庭:要するに、オーディエンスがノリ切れていないのを目の当たりにしたんですよ。それは前作の収録曲のテンポもあったのかもしれないですけど。その反動からか「泥水のメロディー」のようにノリの良い曲が出来て、自分達も演奏がより楽しめるようになったんです。その流れで「ロシナンテ」が出来て、本作の方向性が明確になった部分はありますね。
──と言うことは、この『泥水のメロディー』はライヴが生んだ賜物であるとも言えそうですね。
佐々木:全くその通りですね。今のライヴがベストな形なのかは判らないですけど、自分達の理想に向けて一歩ずつ登っている手応えはありますね。その手応えが今回のアルバムに着実にフィードバックしているとも思うし。ライヴでの経験値が上がったせいか、石井(康崇)のベースと渡邊(一丘)のドラムが格段に伸びたと思うんですよ。ボトムがしっかりしてきたので、曲作りのペースが早くなってきたんですよね。彼らは彼らでアレンジのアイディアがあって、いろんな意見が出てくるようにもなったし。だからバンドがより民主的になってきた気がしますね。
──2人はどうですか? 佐々木さんから見た岡庭さんの変化、岡庭さんから見た佐々木さんの変化というのは。
岡庭:僕は前作よりも亮介への信頼度がグッと上がりましたね。バンド全体を俯瞰して、その中で僕のギターがどう活きるかを考えながら曲作りをしてくれるようになったので。こんな面と向かって言うのは恥ずかしいですけど(笑)。
佐々木:前作での岡庭は天然の極みで(笑)、そこが彼の大きな魅力でもあったんですけど、本作を作る前に凄く悩んでいた時期が4人ともあったんですよ。バンドの在り方や音楽の方向性を見つめ直すいい機会にはなったんですけど。そこを乗り越えて『泥水のメロディー』が出来て、岡庭のギターは今までと違うものに生まれ変わったと思うんです。ただのブルース好きではなく、器用に何でもトライできるようになったと言うか。
岡庭:自分の引き出しにないフレーズでもいいと思えるようになったことが一番の変化だと思うんですよ。あと、亮介の歌をちゃんと活かしながら自分のギターを殺さないで弾くことができるようになったんです。
佐々木:今まではブルース特有のコードを忠実になぞらえていたのが岡庭にとっての王道だったんですけど、それを携えたまま自分の新しいスタンダードを作れるようになったんですね。4人それぞれそういう変化はあったと思うし、岡庭が言うようにメンバーに対する信頼度が以前に比べて増したことは確かですね。だからこそこの『泥水のメロディー』は前作に比べて格段にビルド・アップしていると思うんです。
──2008年の今現在に在るべきブルースの姿とは、一体どんなものだと思いますか。
佐々木:ブルースはリアルな音楽だし、人間が社会や生活と絡まっていかないと生まれないものだと思いますね。
岡庭:ポップじゃないとダメでしょうね。2008年の今日に至るまでに生まれてきたあらゆる音楽的要素を踏まえてのものじゃないとリアルじゃない気がする。
佐々木:各時代でブルースを分母に置いた音楽はどれも皆ポップになり得ていますからね。僕らの目指す場所も結局はそこなんだと思います。