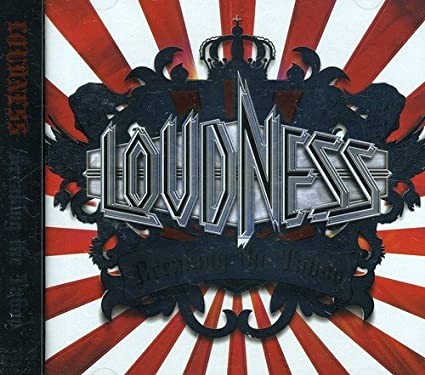昨年3月には14ヵ所に及ぶアメリカ・ツアーを敢行、現在もなお、世界基準のロック・ミュージックを体現させていることを証明したLOUDNESSが通算20枚目となるオリジナル・アルバム『BREAKING THE TABOO』を発表した。二井原実のメロディックかつパワフルなヴォーカリゼーション、さまざまなテクニックを駆使しながら構築される高崎晃のギター・ワーク、さらなるダイナミズムを獲得した樋口宗孝/山下昌良によるリズム・セクションがひとつになった本作は、ヘヴィ・メタルの真髄を伝える世界観と、'00年代のロックとしての強度を両立したアルバム。常に前進を続けるLOUDNESの現状について、リーダーの樋口に訊いた。(interview:森 朋之)
25周年を記念した20枚目のオリジナル・アルバム
──まずは、昨年の12月にリリースされた最新アルバム『BREAKING THE TABOO』のことを聞きたいんですが。
樋口:はい。
──'90年代以降のラウド・ロック、ヘヴィ・ロックの流れを汲みつつ、我々がイメージするラウドネスらしさもガツンと感じられる、素晴らしいアルバムですよね。
樋口:あのね、かつてアメリカに行ってプロデューサーがついてからは、サウンドが変わって、どんどんハードになっていったんですよ。攻撃的な音っていうのかな。そこをひとしきりやって、またちょっと変わってきたのかもれないですね。日本のラウドネスのファンっていうのは、3枚目の“魔界典章”('83年1月にリリースされた『THE LAW OF DEVIL'S LAND』)とか“DISILLUSION”('84年1月にリリースされた『DISILLUSION 〜撃剣霊化』)辺りが一番好きだと思うんですけど、今回のアルバムはその次に来るようなものだと思います。もちろん、かなりハードな音にはなってるんですけどね。ポップの“ポ”の字もない(笑)。
──確かに。
樋口:ラウドネスはデビューした時から常にポジティヴで、後ろに下がらないバンドなんですよ。その結果、ファンの期待を裏切るようなことも多々あったんですけど、このアルバムに関しては大丈夫じゃない? 最近のハードなサウンドと初期の頃のテイストがうまいこと混じり合ってるというか。ただ、今までのアルバムのなかでも、1、2を争うくらい短期間でレコーディングしたんだけどね。ドラムは20時間で全部録ったし、ギターも2日間くらいで録ったと思う。
──凄いですね。どうしてそんなことに…。
樋口:最初はね、エディ・クレイマー('60年代から活躍するサウンド・プロデューサー/レコーディング・エンジニア。ジミ・ヘンドリックス、レッド・ツェッペリン、ローリング・ストーンズ、キッスといったロック・ジャイアンツの作品を数多く手掛ける、伝説的なクリエイター)とやろうと思ってたんですよ。でも、なかなかスケジュールが合わなくて、ズルズルしてるうちに“間に合わないな”ってことになって。で、今回は野村昌之っていうエンジニア──もともとはラウドネスのライヴ・エンジニアなんだけど──がスタジオを作ったって聞いてたから、そこで録ることにしたんです。彼と一緒に音を作るのは久々やったんやけど、もの凄く強力な音になったから、結果的には良かったかな、と。ただ、大変だったけどね。11月25日に国際フォーラムでライヴ(25周年のスペシャル・ライヴ『thanks 25th anniversary LOUDNESS LIVESHOCKS 2006』)があって、27日からレコーディングに入って、12月27日にはリリースだから。
──壮絶ですね、それは。レコーディングに入る前には、何かテーマはあったんですか?
樋口:うーん、さっきは“めちゃめちゃハードな音になった”って言ったけど、一番気にしてたんは、実はメロディなんですよね。ここ最近のアルバムって、(ヴォーカルが)叫んでばっかりだったんですよ。楽曲がどんどんハードになっていくものだから、“これに対抗するためには、叫ぶしかないだろ”っていう感じになってて。でも、今回はメロディもかなりいいと思う。個人的には6曲目の「THE LOVE OF MY LIFE」(壮大かつダイナミックなロック・バラード)が凄く気に入ってます。
──いいですよね、この曲のメロディ。
樋口:かなり口出しもしたからね、今回は。いつもは(ヴォーカルの二井原実に)任せてる部分が多いんだけど、メンバー全員で「もっとこうしたほうがいいんじゃないかな?」とか「そのメロディは変えてくれ」とか、いろいろ言いました。メロディって、メンバーみんなで考えたほうがいいと思ってるので。
──他のパートについてはどうですか? たとえば高崎さんのギター・ソロに注文をつける、なんてことも…。
樋口:たまにはありますよ。といっても、「もっと速よう弾いてくれ」とか、そんなことですけど(笑)。ウォーッ!って感動できるようなやつが。2曲目(「BRUTAL TORTURE」)のギター・ソロなんて、かなり強烈だし。もちろん、俺も根性入れてやりましたよ。今までで一番強く叩いてるんじゃないかな。
──「DAMNATION」に代表される、キャッチーなリフを軸にしたナンバーも印象的でした。ライヴで大合唱してるオーディエンスがはっきりと目に浮かびますよね。
樋口:もちろん、それを狙って作ってますから(笑)。こういうシンプルなビートっていうのは、凄く難しいんですよ、実は。あえて複雑なことをしないで、ぶ厚いグルーヴを出すっていう。
──パワーと技術の両方を、高いレヴェルで求められるというか。
樋口:うん。そこもやっぱり、アメリカに行ったことが大きいんですよね。最初にアメリカでライヴをやったのは'83年なんだけど、ハンマーでガツンと殴られたようなショックを受けたから。
次のアルバムをもっといいものにすることしか考えていない
──どういう部分で、ですか?
樋口:とにかくね、「ノリが軽過ぎる」って言われるんですよ。エディ・クレイマーからもマックス・ノーマン(オジー・オズボーンなどを手掛けたことで知られる名プロデューサー)からもいろいろ言われたけど、一番うるさいのはグルーヴなんですよ。「ダメだ、コレじゃあ乗れない」って。こっちにも“俺達は日本で一番”っていう思いがあるから、思い切りケンカしてたけどね。「何言ってるんだ!」って。
──まぁ、カチンときますよね。
樋口:一応、日本ではナンバーワン・ドラマーって言われてましたからね、当時すでに。俺が自分の好きなフィルを叩くと、「そんなフィルは必要ない。もっとシンプルにやってくれ」とかね。でも、自分でもいろいろと試したり、練習方法を変えたりしてるうちに、ちょっとずつ判ってくるんですよ。“そうか、外人はこういうリズムにシビれるんだな”って。あと、結果がついてきたことも大きいよね。ビルボードで64位になったり('86年に全米でリリースされた『LIGHTNING STRIKES』[『SHADOW OF WAR』のアメリカ盤]がビルボード誌のチャートで64位を記録)。
──やっぱり、ハードな努力をされてきたわけですね。
樋口:そうですね。昔はね、“30くらいになったら、そんなに練習しなくなるんだろうな”って思ってたんやけど、全然違ってた。今のほうが練習してるくらいだから(笑)。今日もスタジオ入って、個人練習ですよ。3時間、あえてデッドなスタジオを選んで。響きのあるスタジオだと上手く聴こえちゃうから、ダメなんですよね。
──海外で本格的にやろうと思ったら、それくらいやらないといけない、と。
樋口:もともと俺達は日本のマーケットだけを見てるバンドではなくて、最初からワールド・ワイドな活動をしたいと思ってから。“こんなふうにやったら、日本でウケるやろう”なんて考えてるようなポップ・バンドとは全然違う。今のポップ・バンドって、向こうの売れてるやつ──U2とかオアシスとか──をパクって、日本語を乗せてるだけじゃないですか。そんなダサいことは絶対にしないから、俺達は。日本のバンドとしてのオリジナリティを持って、世界に通用するような音をやってるわけだから。
──去年もアメリカでツアーをやってますよね(2006年3月に行われた全米ライヴ『LOUDNESS LIVESHOCKS 2006 chapter1 〜NORTH AMERICA〜』全14ヵ所をソールド・アウトさせた)。
樋口:ニューヨークのど真ん中で、3,000人規模のライヴをやったり、楽しかったよ。モトリー(・クルー)、AC/DCと一緒にツアーを回った時のファンが、ちゃんと来てくれるんですよね。どこに行っても大盛況だから、ちょっとビックリしたよ。会場に入ろうとしたら、500人くらいのファンが待ってて、サインを求められたりするし。CDとかレコードを30枚くらい持ってて、「これに全部サインしてくれ」とか言われるから、時間が掛かってしょうがない。
──(笑)客層はどんな感じなんですか?
樋口:いろんな人がいるね。14歳くらいから、50歳くらいまで。'80年代に俺達のライヴを観てファンになってくれた人が、子供を連れて来てくれたりね。嬉しいよね、そういうのは。
──待ち望んでたんでしょうね、ラウドネスのアメリカ・ツアーを。
樋口:そうですね。俺らの後に続いて、日本人のバンドがどんどん海外に出ていくと思ってたんだけど、結局、誰も行ってないっていうのは残念だけど。あっちで日本のバンドに会ったり、“あいつらもツアー回ってんのか”ってことがあったり、そういう状況になることを想像してたんですけど、全然違ってましたね。まぁ、システムもルーツも違うから、難しい面があるんだろうけど。テクニックもグルーヴも比べ物にならないですからね。
──残念ですけど、事実かもしれないですね。
樋口:あと、精神的な強さもあるよ。日本ではちょっと売れると、新幹線とか飛行機で移動できるけど、向こうはほとんどバスだから。去年のツアーなんて、今まで一番ハードだったよ。20日で14本ですから。
──うわっ! 凄いですね。
樋口:4日続けてやって、1日休んで、また5日続けてやって。しんどい。何歳だと思ってんだよ、本当に。
──それでもやっぱり、海外で活動し続ける。
樋口:そうね。シブくなるとかレイドバックするとか、全然興味ないから。さっきも言ったけど、常に前に前に進んでいくバンドやから、ラウドネスは。もちろん、新しいテイストもどんどん取り入れてるし、音も変わってきてる。そこをがっちり追求してるから、今もこうやって生き残っていると思うしね。
──25周年については?
樋口:何もないですね。“あ、もうそんなに経ってたの?”ってくらい。俺は業界30年だけど、そのことについては、全然何も思わないし。いつも満足してなくて、“次のアルバムは、もっといいものにする”っていうことしか考えてないから。今回のアルバムを超えるのは大変だと思うけど(笑)、まぁ、やりますよ。