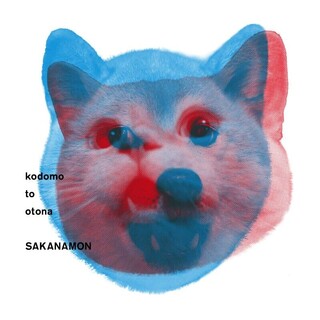「育ててくれてありがとう」「ニッポンには夢の力が必要だ」「全米が泣いた」──今の社会でよく聞く決まりきったフレーズ。その言葉の裏に潜んでいる"紋切り型の思考"が、私たちの社会を硬直化させているんじゃないのか? そんな斬新な視点で書かれたデビュー作『紋切型社会──言葉で固まる現代を解きほぐす』が話題沸騰中のライター、武田砂鉄。6月28日にはNAKED LOFTで新刊出版記念イベントも開催決定している彼に、いろいろとお話を伺ってみた!![interview:小柳 元(NAKED LOFT)]
撮影:宇佐巴
あらゆるジャンルを全部ひっくるめて書く理由
──武田さんはフリーのライターとして独立される前は、出版社で編集のお仕事をされていたんですよね。
武田:そうですね。会社に在籍していたのは9年半ほどで、最初の2年間は営業をやり、その後7年ほど編集をやっていました。
──最初は営業をされていたんですね。
武田:はい、さまざまな書店さんを回っていましたね。
──会社を辞めようと思われたきっかけって何ですか。
武田:大学時代から音楽雑誌などでコラム原稿を書く仕事をやっていましたし、書きたいという願望は昔から強いままだったんです。編集者としてさまざまな本を手掛けながらも、原稿を書く仕事を続けていました。その2つを天秤に掛けた時に、書くことに専念してみようという思いが強くなり、このド不景気の中ですが、フリーのライターとしてやっていこうと決意しました。
──武田さんは芸能人の話題や時事問題等、いろいろなジャンルのことをテーマに記事を書かれていますよね。ご自分では何かの特定のジャンルに比重を置いて書かれているという意識はありますか?
武田:このジャンルで書いていこう、という意識はありません。むしろ、全部ひっくるめて、くらいに思って書いています。今、芸能人について書く人は芸能人のことだけを書き、ジャーナリズムを突き詰める人はジャーナリズムだけを書き、アイドルに詳しい人はひたすらアイドルについて書く。だけど、そもそもひとつのことだけを考えている人なんていないはずです。24時間アイドルのことを考えている人はいない。ほとんどの時間、アイドルのことを考えていたとしても、2時間くらいは政治のことを考えているかもしれないし、これからの日本のことを考えたりしているはず。ならば、そのそれぞれを原稿にしていくのが、ライターとして至って普通の態度かなと思っています。
確かリリー・フランキーさんが話していたと思うんですけど、自分の最寄り駅から家まで歩いて帰る時に、ずっと同じことを考えている奴はいない、と。「今日の仕事は面倒くさかったなー」って思った次の瞬間に、「あ、こんなところに花が咲いているな」と思ったり、すれ違った女の人を見て「キレイな人だな」と思ったり、頭の中でいろいろなことを混ぜながら家まで帰るわけじゃないですか。原稿を書くというのも、そうであって構わないと思っています。最寄り駅から家まで一直線、ひとつのことしか考えちゃいけないというレッテル貼りがされているような気がするんですが、ひとつの原稿にしても、いろいろなことを考えながら家の玄関まで辿り着くべきだと思うんです。道草食ってはいるけど、道草食うのが普通だろう、と。
だから、今回の『紋切型社会』の原稿を書く時も、真面目に日本社会のことを捉えたかと思えば、それをわざと外すように、どうでも良さそうな小ネタを柔軟に織り交ぜていって、全部一緒くたにしていくやり方を心懸けたんです。偏屈な文体と感じるかもしれませんが、自分にとっては素直な文体です。
──確かに、『紋切型社会』はエッセイでもなく評論でもなく、独特なジャンルの本になっています。
武田:書店さんは売り場選びに困っているかもしれませんね(笑)。時事評論っぽくもあるし、サブカルっぽくもあるし、人文っぽさがないわけでもない。だけど、そういう色が混在したものがあってもいいんじゃないかと。
紋切型の言葉に「ちょっと待って」とケチを付ける大切さ
──武田さんはこの本の中で、結婚式の挨拶だったり、選挙のポスターだったり、電車の中の広告だったり、ありとあらゆるものから言葉を拾って、それについて丁寧に考えられていますよね。どういう意図でそういうことをされているのでしょうか。
武田:今の社会って、さまざまなことが空気で決まってしまいます。国の中枢にいる人たちが世の中の空気を司ろうとしている時に、個々人がその空気を平然と黙認してしまうんですね。確かに個人ではなかなか空気は動かせないから、すぐに諦めてしまう。でも、その空気を作っている言葉を捕まえて「こんな言葉が平然と流れてくる世の中ってどうなんだ?」と疑っていくアプローチは有効だと思ったんです。安倍首相にしても橋下徹氏にしても、彼らの発言を捕まえるように指摘すると、「言葉尻を捉えただけ」だとか、「失言を拾っているだけじゃ世の中は良くならない」なんてツッコミが入るわけですが、そういう言葉を一個一個拾わないからこそ、空気がどんどん強まってしまう。先日、今回の本を改めて読み直してみたんですが、「こいつ、嫌な奴だな」としか思えない(笑)。でもやっぱり、世に流れる紋切型の言葉に「ちょっと待って」と、いちいちケチを付けていかなきゃいけないと感じているんです。それは小さい試みかもしれないけど、それぞれが試みればジワジワ効果が出るはずです。
──今、橋下さんや安倍さんが発言する言葉に対抗するのって凄く難しかったりしますよね。
武田:たとえば首相の演説などでは優秀なスピーチライターがついており、国民にもっとも伝わりやすい言葉が慎重に選ばれています。その言葉に対抗していくためには、ただの嫌な奴になるしかないのだけれど、それを引き受けて、一旦彼らの仕組みにハマりながら、その仕組みにある軽薄さなりを執拗に掴まえていく。それこそ、ロフトに出てくるような論客の人たちって面倒くさそうな人たちが多いじゃないですか(笑)。面倒くさいと言うか、いちいちうるさい人たちが多い。でも、いちいちうるさくないと、限られた言葉が作り出す空気がどんどん稼働してしまいます。ならば、言い続けるしかない。
──武田さんが『紋切型社会』のような本を書くにあたって、一番影響を受けた方っていますか。
武田:長い間影響を受けてきたのは本田靖春さんというジャーナリストです。彼が著作の中で心懸けてきたのは「複眼」の姿勢。ある物事が起きた時に、ひとつの方向からではなく両面から見ることを心懸けていた。彼の代表作に『誘拐』という作品があります。東京オリンピック前に起きた誘拐殺人事件を追った本ですが、彼はその本の中で、被害者家族を見つめながらも、それと同様に、小原保という犯人にも寄り添っていく。その上で「きわめて不幸なかたちで人生を終わった二人の冥福を改めて祈りたい」と書いた。先日の、川崎リンチ殺人事件の時もそうですが、事件報道を見ていると「とにかく酷い犯人だ」と一斉に走るパターンもあれば、或いは「被害者のお母さんはシングルマザーで男と付き合っていたらしい」と別の理由を見つけたりする。いずれにせよ、ひとつの理由に集約させたがる傾向があります。その傾向の前では、「ちょっと待てよ、別の視点はないだろうか」と意識しておかなければ流されてしまう。大きな事件ではなく、ちょっとしたやり取りであっても、その状況を把握することはできないのではと思っています。その「複眼」を意識的に書いたつもりです。
──最後になりましたが、武田さんの今後の展望というのはありますか。
武田:最初に言ったように、ある書き手が出てくると、この人はこういうことを書く人だ、こういう専門家だと決めつけられてしまうので、そういう働きかけを外していくような仕事をしたいと思います。ジャンルを固めてくる流れからすべて逃げていって、いろいろなジャンルの原稿を書いていければと思っています。論客の人たちの中には、なんとなく群れを作って、その中で活動していくというような流れもあるようです。でも、その手のものには所属したくない。サークルの中にいると気持ちは良いのでしょうけど、そうすると聞こえてくる言葉が限られるのではないかと思っている。大学教授の話だって、ミュージシャンの話だって、喫茶店でだべるオバちゃんだって、そこら辺で歩いている幼稚園生だって、いろいろな言葉を聞きたい。それらの人が持っている言葉ってそれぞれ違います。カテゴリーに収まりそうになったら抜け出て、いろいろな言葉を吸収できればと思っています。